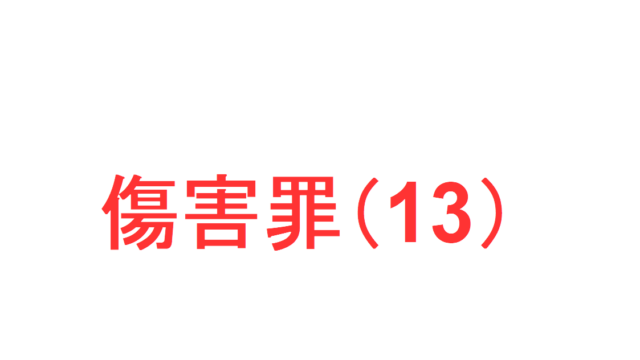- 逮捕監禁罪・逮捕監禁致傷罪
との関係について説明しました。
今回の記事では、傷害罪と
- 強盗罪・強盗致傷罪
との関係について説明します。
傷害罪と強盗罪・強盗致傷罪の関係の説明テーマは、以下の①~⑦があり、長くなるので、【その1】と【その2】の2回にわけて説明します。
今回の記事である【その1】では、①~④のテーマについて説明します。
- 強盗致傷罪は、「傷害罪」と「窃盗罪や恐喝罪」などとの併合罪として処理される場合が多い
- 暴行の程度が被害者の犯行を抑圧するに足る程度のものと認められない場合は、強盗致傷罪ではなく、恐喝罪と傷害罪との観念的競合になる
- 傷害が、財物奪取の犯意を生ずる前の暴行による場合、強盗致傷罪ではなく、傷害罪と窃盗罪との併合罪になる
- 傷害が、財物奪取の犯意を生ずる前の暴行による場合、強盗致傷罪ではなく、傷害罪と恐喝罪との併合罪になる
- 窃盗行為の着手がないとして、被害者に対する傷害罪・暴行罪を認定した事例
- 強盗の犯意発生の前後いずれの暴行による傷害であるか認定できないとして、強盗罪と傷害罪の包括ー罪を認めた事例
- 窃盗行為後に逮捕を免れるため、私人の逮捕者に暴行を加えた事案で、有効な逮捕行為を認定せず、強盗致傷罪ではなく、窃盗罪と傷害罪の併合罪とした事例
強盗罪・強盗致傷罪との関係【その1】
傷害罪と強盗罪(刑法236条)、強盗致傷罪(刑法240条)との関係について説明します。
① 強盗致傷罪は、「傷害罪」と「窃盗罪や恐喝罪」などとの併合罪として処理される場合が多い
強盗致傷罪は、事実認定の問題として、強盗致傷罪の成立を認めず、「傷害罪」と「窃盗罪や恐喝罪」などとの併合罪として処理される事例は多いです。
この点について、以下の判例があります。
大阪地裁判決(昭和47年3月22日)
強盗致傷の訴因(公訴事実)を排斥して傷害と窃盗の成立を認めた事例です。
ひったくりをして被害者を転倒させて負傷させ、ハンドバッグを奪取した強盗の犯意を否定し、強盗致傷罪ではなく、傷害罪と窃盗罪にニ罪が成立し、両罪は併合罪になるとしました。
裁判官は、
- 被告人が、帰宅のため一人で通行中のK子からその所持するハンドバック1個を奪取しようとした際、K子をして道路脇の測溝にその足をつつこませるとともに道路脇の板塀にその顔面部を突き当らせたうえ、同所に両膝をつくようにして転倒させ、よって、K子に対し傷害を負わせたこと、ならびにその直後、被告人がK子から右ハンドバック1個を奪取して逃げ去ったことは証拠によって明らかであるから、以下においては、被告人がいかなる犯意のもとにハンドバック取得のための手段としていかなる行動に出で、被害者がそれに呼応していかなる行動をとり、さらに被害者がどのような経緯、原因で転倒するに至ったかなどについて順次検討を加えたうえ、強盗傷人罪の成否につき判断することにする
- 【被告人は当初いかなる犯意を有していたか】被告人は、一人で通行中の被害者K子を見かけるや、酒気を帯びていたことも手伝い、K子をひやかそうと考え、K子を尾行して行ったが、本件現場から南方約10メートル付近の地点に差しかかつた際、同女の左腕に通して所持するハンドバックを認め、突発的に右ハンドバックをひったくって奪取しようと考えるに至ったが、未だ暴行、脅迫を右財物奪取の手段とする気持ちを抱いていなかったことが認められる
- 右認定事実に徴すると、被告人は当初、窃盗の犯意のみを有していたにすぎないと認めるのが相当である
- もっとも、検察官は、「被告人は被害者を見かけるや、K子から金員を強取しようと企てた」旨主張が、もし、被告人が当初より強盗の犯意を有していたとすれば、同犯意の外部的発現行為として、被告人において被害者に対し「金を出せ」と申し向けるなど、何らかの脅迫的言辞を弄しているはずであるのに、被告人は本件財物奪取に至るまで終始無言で右のような脅迫行為に及んでいないところからみて、強盗の犯意を生じたする各供述記載は、いずれも被告人の当時の心理状態を正確に表現したものかどうかすこぶる疑わしいばかりではなく、被告人の当公判廷における供述内容第10回公判調書中の被告人の供述部分、前段認定の被告人が本件犯行に着手するまでの経緯、心理の推移ないしはハンドバック取得の動機に照らしてもにわかに措信できないし、他に検察官主張のように被告人が当初から強盗の犯意を有していたことを認めるに足りる証拠はない
- 【被害者が転倒するに至った経緯、原因】被害者は被告人からいきなり自己の左肩に左手をかけられたため、逃避しようとして道路の窪に足をとられて右前方によろけたのであるが、その際、ちょうど被告人においてK子に逃避されまいとして、右手をK子の頸部に巻くようにしてかけ制止したため、そのままの態勢で背後からK子に抱きつくような恰好になり、自己の体重をK子にかけたので、K子をして道路脇の側溝にその足をつっこませるとともに道路脇の板塀にその顔面部を突き当らせたうえ、同所に両膝つくようにして転倒させる結果となったこと、被告人がK子の左肩に左手をかけてから右転倒までの時間は瞬時であったこと(証拠上何分、あるいは何秒と認定することはできないが極く短時間であったことは十分推測できる)がそれぞれ認められる
- 叙上の事実に徴すると、被害者は被告人の右一連の暴行と逃避しようとした地点の道路状況が悪かったこととが相俟って転倒するに至ったものと認めるのが相当である
- 逃避制止行為はK子に逃げられそうになり、当初の目的であるひったくりが失敗しそうになったから行なったものであり、その意味においては、奪取の目的を達成するために行なわれたという側面をもっているというべく、このような場合、奪取のため客観的に被害者の反抗を抑圧する程度の暴行が加えられたときは、当初において強盗の犯意がなくとも、その過程において強盗の犯意が生じたと認められる場合も考えられるけれども、前掲各証拠によると、被害者はハンドバックを奪われまいとして終始抵抗していたものであって、そのためハンドバックのさげ紐がその中央部からちぎれたものであると推認されること、頸部に右手を巻くようにしてかけられていた時間は極く短時間であり、前認定のとおり被告人において意識して同女の頸部を締めつけたものではないから、同女に対し、失神ないしは気力を失わせるほど強度な肉体的影響を与えたものでないことが認められ、右認定事実に徴すると、被害者の年令、犯行現場の状況、時刻などを考慮に入れても、右逃避制止にともなう前記暴行の程度は未だ被害者の反抗を抑圧するに足りるものであったということはできないから、右のような観点からしても、前記暴行時において被告人に強盗の犯意が生じたということはできない
- 従って、被告人の前記認定の各暴行(傷害)は、強盗の犯意にもとづきなされたものではなく、いわゆるひつたくり(窃盗)の手段としてそれに付随してなされたものであり、事後の財物奪取行為は窃盗罪を構成するものと解するのが相当であるから、本訴因である強盗傷人罪の成立を否定し、その訴因の範囲内で傷害罪と窃盗罪の成立を認めて認定した次第である
と判示し、強盗の故意がないとして、傷害致傷罪ではなく、傷害罪と窃盗罪のニ罪が成立するとしました。
東京高裁判決(平成15年3月20日)
暴行を加えて傷害を負わせ、被害者が昏睡したのに乗じ、被害者の財布の領得の意思を生じ、被害者と同行していた女性に強迫的言辞を申し向けてその反抗を抑圧して、被害者所有の現金在中の財布を強取した事案で、強盗致傷罪ではなく、傷害罪と強盗罪のニ罪が成立し、両罪は併合罪になるとしました。
裁判官は、
- 被告人両名は、気絶したCから財布を奪っているが、その領得の意思が生じたのは、A・Bのいずれについても、Cが気絶した後であると見るのが合理的であり、その段階では、Cに対する暴行は既に終了しており、Cの原判示の傷害は、この既に終了している暴行の結果であることが明らかである
- そうすると、Cの傷害は、被告人両名がCから財布を奪った機会に生じたものと認めることはできず、この点については、被告人両名による傷害罪の共同正犯が成立するにとどまる
- そうすると、この傷害が強取の機会に生じたものとして被告人両名に強盗致傷の共同正犯が成立する旨認定した原判決には、事実誤認があるといわざるを得えない
- なお、強盗罪が成立する理由について補足説明するに、被告人両名が、Cの着衣から現金等が在中する財布を取り出した時点において、既にCは被告人両名の暴行により気絶しており、同人に対して新たに財物奪取の手段となる暴行・脅迫は認められない
- しかしながら、本件においては、当時交際中のCとが行動をともにしていたD子は、本件の際、終始傍にいて、被告人両名がCに加えた激しい暴行を目の当たりにし、Aから「犯すよ。」などと脅かされたり、Bから股間や胸を触られるなどして、次には自分が強姦等されるのてはないかと激しく畏怖していたこと、D子は、被告人両名がCの着衣から財布を取り出し、中味を改める際には、放り出したカード類を拾い集めていたこと、被告人両名は、指紋が付いたなどと言って、財布だけでなく、D子が拾い集めたカード類も強引に取り上げて持ち去ろうとしていること、D子は、Bの服をつかむなどして、布やカード類の返却を強く求めたのに対し、Bは、全く応じる素振りを見せず、Aに至っては、「中出しさせてくれたら、返してやる。」「やらせてくれたら、返してやる。」などと言って、D子の要求を拒絶し、財布等を持ち去っていること、被告人両名は、その後、在中の金品を山分けしていることが認められる
- これらによれは、被告人両名が、財布及びその在中物の占有をCから奪って、その確保をするためには、D子の抵抗を排除する必要があったことは明らかである
- そして、そのために、Aが、「中出しさせてくれたら、返してやる。」などと激烈な脅迫言上を述べ、D子の要求を拒絶したものであり かつ、D子は、それまでに被告人両名に対して著しい畏怖の念を抱いているのであるから、被告人の言辞、態度は、D子の反抗を抑圧するに十分な脅迫であると優に認められる
- 被告人両名が、Cが昏睡状態にあるのに乗じ、かつ、行動をともにしていたD子に対して脅迫言辞を申し向けるなどして、その反抗を抑圧した上で、C所有の現金等在中の財布の占有を奪い、これを確保したものであるから、被告人両名のこの一連の行為が、強盗罪を構成することは明らかというべきであり、被告人両名の間にそのような犯行を共同して実行する意思の連絡があったことも疑いなく認められる
と判示し、傷害が終わった後に財布を強取しており、財布を強取するために傷害を加えたものではないため、強盗致傷罪ではなく、傷害罪と強盗罪のニ罪が成立するとしました。
大阪地裁判決(昭和34年11月30日)
この判例は、強盗致傷罪の公訴事実につき、強盗の着手前の別の動機目的による暴行であるとして、強盗致傷罪ではなく、強盗予備罪と傷害罪との併合罪を認めた事例です。
タクシー強盗の目的でレンガを新聞紙に包んで携帯してタクシーに乗車したものの、運転手に強盗目的を察知されたと思い、逃走しようと運転手を殴って傷害を負わせた事案で、裁判官は、
- 本件公訴事実は、被告人は被害者Nに対し、タクシー売上金を強奪する目的で判示暴行を加えたもので、強盗傷人罪にあたるというのであり、前示被告人の検察官並びに司法巡査に対する各供述調書によると、右公訴事実にそう自白がなされている
- しかし、被告人は第一回公判調書及び当公判廷において右自白をひるがえし、判示N運転手のタクシーに乗り込む前から既にタクシー売上金強奪の決行をためらっていたところ、判示第二の暴行の場所に至るまでに、もはや同運転手に売上金強奪の意図を察知されたものと思い、右強奪を決行するどころではなく、その場からのがれたいと焦っていたと供述しているのである
- 前掲各証拠によつて認められる、(一)被告人が数回にわたって行先を変更したため、N運転手は被告人が強盗の目的で乗車したことを察知して、被告人に何度も降車してくれるように懇願していたところ、被告人は当時乗車賃の持ち合わせがなく、運転手にとがめられることをおそれ進退に窮していた事情が窺われること、(二)本件暴行は傷害の程度等からして、いわゆる自動車強盗としてそれ程強度のものでなかったこと、(三)被告人はその行為においても、暴行に際し、何ら売上金強奪のための言動に出ることなく、かろうじて車外に脱出していること等を総合すると、被告人の右供述はあながち、単なる罪責を免れるための弁解とも認め難く、結局、売上金強奪のための暴行であるとの証明は十分でないといわなければならない
- しかし、判示のような強盗予備及び傷害の各罪が成立することは各証拠に照して明らかなところである
と判示し、強盗の機会に傷害を行ったものではなく、その場から逃げるために傷害を行ったと認定し、強盗致傷罪ではなく、強盗予備罪と傷害罪のニ罪が成立するとしました。
【参考】裁判において、強盗致傷罪を傷害罪と窃盗罪の併合罪として認定するに当たり、訴因変更は不要
裁判において、強盗致傷罪を傷害罪と窃盗罪の併合罪として認定するに当たり、訴因変更手続は不要であることを明示した判例があるので紹介します。
なお、訴因変更手続とは、検察官が既に起訴した公訴事実を変更する請求をし、裁判所が検察官の訴因変更請求を認める手続きをいいます。
たとえば、検察官が強盗致傷罪で起訴した事件について、検察官が強盗致傷罪ではなく、窃盗罪と傷害罪の併合罪となると考え直し、裁判官に対し、その旨訴因変更請求を行い、裁判官が検察官の請求どおり、強盗致傷罪の公訴事実から、傷害罪と窃盗罪の公訴事実への変更を認める場合が当てはまります。
この判例は、
- 検察官の強盗致傷罪の起訴に対し、判決で強盗罪・窃盗罪と傷害の併合罪であると認定するについては、被告人の防御に実質的不利益が認められない以上、訴因変更手続を要しないことは当然である
旨判示し、訴因変更手続を行うことなく、傷害罪及び強盗罪の併合罪を認定したことの適法性を認めました。
② 暴行の程度が被害者の犯行を抑圧するに足る程度のものと認められない場合は、強盗致傷罪ではなく、恐喝罪と傷害罪との観念的競合になる
暴行の程度が被害者の犯行を抑圧するに足る程度のものと認められない場合は、強盗致傷罪ではなく、恐喝罪と傷害罪の観念的競合になります。
岡山地裁判決(昭和44年8月1日)
この判例は、強盗致傷罪の起訴に対し、その手段たる暴行脅迫が被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものとは認められないとして、恐喝罪ならびに傷害罪を認定した事例です。
裁判官は、
- 強盗罪が成立するためには、財物奪取の手段として被害者に加えられた暴行、脅迫が、その反抗を抑圧するに足るものでなければならず、反抗を抑圧する程度に至らず、被害者を畏怖させたにすぎない場合は、恐喝罪が成立するにすぎないことはいうまでもないところであり、反抗を抑圧するに足る程度の暴行、脅迫であるかは、結局、暴行、脅迫の方法、程度、被害者の男女の性別、年令、時刻、場所、その他犯行の具体的附随事情を考慮して客観的に判断しなければならない
- そこでこれを本件について検討する
- 判示日時、場所において被害者Kの運転する大型貨物自動車を停車させた後、Tら数名が共謀の上、被害者両名(K、M)に対し暴行を加え、更に空地に連行して被告人W、O及びTにおいて、それぞれ脅迫を加えたこと及び暴行は被害者両名に対し、いずれも加療5日間を要する傷害を負わせるに足るもので、必ずしも軽微なものとはいえないことは判示認定の通りであるけれども、右事実からは、判示暴行、脅迫が被害者両名の反抗を抑圧するに足るものであるとはにわかに断定し難いところ、前掲関係各証拠によれば、被告人Wらが、判示大型貨物自動車を停車させ、被害者両名に対し暴行を加えた国道二号線は、既に午後10時30分を過ぎていたとはいえ、比較的交通量も多く、近くには人家もあって、必ずしも救助の求められない所ではなかったこと、しかも被告人Wは、Tが助手Mに対する暴行を続けることを制止し、被告人Nは、鼻血を出して倒れていた助手のMにハンカチを与えて鼻血を拭くよう勧めていること、その後、大ケ池に連行し、当て逃げをしたと因縁をつけ、古傷を見せてその修理代を要求した際、被害者において、修理代は岡山の営業所に行ってくれれば払う旨を答えると、6人分の日当や岡山までのガソリン代を出せ等と嫌がらせを言い、金を出しそうもないとみるや、更に「スペアタイヤを出せ」「荷物を置いておけ。」等と要求し、その結果、被害者両名は所持金を交付したものであることは判示のとおりであって、被告人らは被害者両名の意思を全く無視する態度を示していないこと、犯行直後、大ケ池付近の食堂で飲酒した際、Tから、被害者に示した自動車の傷が古傷であった旨を知らされた被告人O、Wにおいて、被害者に謝罪に行っていること等の事実が認められ、判示暴行及び脅迫の態様、程度に右認定の犯行現場の状況、金員の交付を受けるに至るまでの被告人らと被害者とのやりとりの経過及び模様、被告人W、O、Nの犯行当時及び直後における行動、被害者両名の性別、年令等諸般の事情を比較検討すると、判示暴行、脅迫をもって被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものとは断じ難く、しかも被告人W、Oは捜査官に対しても、車が当ったと因縁をつけて修理代を出させる意思であった旨の供述をしており、かかる供述内容からしても、被害者の犯行を抑圧したうえ金員を強取する意思があったと認めるよりも、むしろ、車が接触して傷がついたと因縁をつけ、修理代名下に金員を喝取する意思であったと認めるのが相当である。
と判示し、強盗致傷罪ではなく、恐喝罪と傷害罪を認定しました。
大阪地裁判決(昭和43年12月23日)
この判例は、強盗致傷罪の訴因について傷害罪と恐喝(未遂)罪の成立を認めた判例です。
この判例は、強盗致傷罪の訴因で起訴されましたが、裁判官において、恐喝罪と傷害罪の両罪が観念的競合の関係で成立すると認定しました。
被告人とMが別れ話の際にののしり合いのけんかになり、被告人がMから1万円をおどしとっていこうと考え、Mに対し、「金を出せ」と要求し、暴行を加えて1万円を奪い取ろうとしたがMの抵抗により奪い取れなかったが、代わりに衣類など喝取し、その際、Mに約1か月の加療を要する傷害を負わせたという事実により、強盗致傷罪で起訴された事案です。
裁判官は、
- Mは、被告人に非常に立腹し、自分を馬鹿にしたということで、繰り返し被告人を強く罵倒したこと、Mの応接ぶりをみても、一万円札を自分の靴下の中に隠したり、被告人の「金が欲しいか、命が欲しいか」との趣旨の脅迫に対して、「どちらも欲しい」と応じるなど、9歳年下の被告人に対して相当の余裕がみられること、被告人においても、脅しが功を奏しないため「荷物を置いていくから金を貸してくれ」と哀願するなど、なんとかMを言いくるめて一万円を出させようとしていること、頑強に拒むMに結局根負けして一万円を諦めてしまっていること、被告人とMは1年3か月前から同棲していたのであって、両者の間には相応の一種の信頼関係が存し、そのために被告人の暴行脅迫がかなりの程度のものであるのに、に対し、さほど大きな影響を与えるに至らなかったことがうかがえること、等の諸事実を総合すれば、結局、被告人のMに対する暴行脅迫は相当程度のもではあったけれども、被告人とMとの関係等からみて、なおいまだMの反抗を抑圧するに足る程度のものであったと認める十分な証拠はないというべきである
- また、被告人において、金品強取すなわちMの反抗を抑圧してまで金員を奪取するというほどの故意の存したことについても相当の疑いが残るのであって、被告人の所為について強盗致傷罪の成立を認めることはできない
- また、弁護人は、本件被告人の所為は夫婦間の痴話喧嘩のこうじたものであり、かつMは一万円はもとより衣類についても頑強にその提供を拒んでいたのであるから、たとえその拒絶がなかば嫉妬によるものであったにせよ、暴行脅迫を加えて金品の交付を受けようとした被告人の所為は財産罪を構成するものといわなければならない
- 以上の次第であるから、被告人の衣類等領得の点については恐喝罪の成立を認めるのが相当であり、なお一連の暴行は主として金品の喝取に向けられたものであるから、これによる傷害罪の点については、右恐喝罪と観念的競合の関係にあるのと解するのが相当である
と判示し、強盗致傷罪ではなく、恐喝罪と傷害罪が成立し、両罪は観念的競合になるとしました。
東京高裁判決(平成13年9月12日)
この判例は、被告人らが加えた暴行脅迫は被害者の反抗を抑圧するに足りる程度であったとは認め難いとして、恐喝未遂罪と傷害罪が成立するにとどまるとした事例です。
裁判官は、
- 関係証拠によれば、被害者は本件当時21歳の男性であったこと、本件犯行の継続時間は5、6分間の比較的短時間であること、被告人らは、刃物等それ自体殺傷能力の高い凶器を使用していないこと、また事前に凶器を準備して本件店舗に赴いてもいないこと、被害者の顔面等を手拳で殴打した暴行も散発的であること、被害者の左腕をねじり上げ、喉輪の形にした手を被害者の首に押し付けるなどしているが、いずれもすぐにやめていること、さらに、本件犯行場所は店舗内であるが、同店舖内には被害者のほかに女性従業員のT(当時33歳)がいたほか、被告人らが本件店舗に入った直後、同店の女性従業員4名が本件店舗に入ってきたこと、被告人らは同女らを拘束しておらず、同女らは本件店舗の店長に携帯電話で連絡をとったりしていること、Tは本件犯行の開始後間もなくして被害者のすぐ左隣にきて、「やめてください。」などと被告人らの本件犯行を制止する発言をするとともに、Xが灰皿で被害者を殴打しようとしたのを、その灰皿をつかむなどして防いでいたこと、さらに、別の女子従業員も被告人らに対し、「それは駄目。それは駄目。」などと制止しようとする発言を繰り返していたこと、被害者は本件被害を受けている間に携帯電話で店長に連絡しようとしていたこと、被害者には所持金があり、本件店舗内には予備の金員が若干あったが、被害者はそれらを被告人らには渡さず、「お金がないんです。お客さんいないんです。」と何回も返答していること、金員の入っていない引き出しをカウンターの上に出して見せ、「今本当にお金がないので、あしたお金を払いますから、あした取りに来て下さい。」と述べて、本件店舗から出て行くように被告人らを仕向けたこと、被告人らもそれを了承して、明日金員を取りに来る旨言い残して本件店舗から出て行ったことが認められ、これらの認定事実のうち、特に、被告人らが被害者に加えた暴行の態様、被告人らは「殴り殺す。」などと被害者を脅迫してはいるが、それに見合うような強烈な暴行は加えていないこと、複数の女性従業員が被告人らの本件犯行を言葉や行動で制止しようとしていたこと、被害者は被告人らにうそを言って金員を渡さず、本件店舗から出て行くように被告人らを仕向けるなど、全般的に緊迫性に欠けており、被害者はある程度の余裕をもって行動していたことなどの事情を考慮すると、被告人らが被害者に対して加えた暴行及び脅迫が被害者の反抗を抑圧するに足りる程度であったとは認め難く、結局本件については、恐喝未遂罪と傷害罪が成立するにとどまるというべきである
- そうすると、被告人らの前記暴行及び脅迫が被害者の反抗を抑圧する程度に至っていたと認定し、強盗致傷罪の共同正犯の成立を認めた原判決には事実の誤認があり、ひいては法令の適用を誤ったものであって、それらの誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、原判決は破棄を免れない
と判示し、被告人らが被害者に対して加えた暴行及び脅迫が被害者の反抗を抑圧するに足りる程度であったとは認め難いとして、強盗致傷罪ではなく、恐喝未遂罪と傷害罪のニ罪が成立するとしました。
③ 傷害が、財物奪取の犯意を生ずる前の暴行による場合、強盗致傷罪ではなく、傷害罪と窃盗罪との併合罪になる
財物奪取の犯意を生ずる前の暴行による傷害であると認定して、強盗致傷罪ではなく、傷害罪と窃盗罪の併合罪になるとした以下の判例があります。
仙台高裁秋田支部判決(昭和33年4月9日)
この判例は、強盗致傷罪ではなく、傷害罪と強盗罪の併合罪が成立すると認めた判例です。
裁判官は、
- 原判決における事実認定によると、被告人らは賭博に負けた損失金を取り戻すべく共謀の上、Tに対し暴行を加え、その反抗を抑圧してTより金品を強取し、その際、Tに対し傷害を負わしめたというにあるが、被告人らは前認定のように、Tがいかさま師の手引をなしたことを憤慨して暴行を加え、傷害を負わしめたものであり、被告人K、Sの両名は、更にその後犯意を新にしてTより金品を強取したものであって、強盗の犯意はTに対する暴行を当初より存したものでなく、また被告人Mが右強盗の犯行に加担したと認めることはできないのである
- してみれば、被告人らに係る前記認定の所為は、被告人ら3名共謀による傷害罪及び被告人K、Sの共謀による強盗罪と2個の訴因事実を認定するを相当とすべく、従って原判決はこの点において判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認の違法を冒したものといわなければならない
と判示し、暴行は財物を奪取する前の被害者のいかさまの手引行為に憤慨して行ったものであるから、強盗致傷罪ではなく、傷害罪と強盗罪のニ罪が成立するとしました。
仙台高裁判決(昭和34年1月13日)
酔って口論の上、相手を殴打し、足蹴にする暴行を加え、相手の所持していた洋傘1本を持ち去ったという事案で、相手を殴る道具として傘を取り上げたものの、その場を立ち去る際、洋傘をそのまま持ち去ったものであるとして、強盗致傷罪を否定し、傷害罪と窃盗罪が成立し、両罪は併合罪になるとしました。
裁判官は、
- 問題は、被告人がYから洋傘を強取する意思を有し、その目的を遂げる手段として同人に暴行を加え、同人からこれを強取したものであるかどうかの点である
- 原判決は、被告人が、最初、Yの胸倉をつかみ、手拳で同人の顔面を一回殴打してから、同人が洋傘を所持しているのを目撃するに及んで、同人からそれを強取しようと決意したとし、その後、被告人がYに加えた暴行をもって、洋傘を強取するため、同人を制圧する手段としての暴行と見て、右暴行によって同人の反抗を抑圧したうえ、同人から洋傘を強取した旨判示した
- 被告人は、司法警察員及び検察官の各取調において、当時、強盗の意思を有していたとは述べておらず、原審ではこの点を明らかに否認している
- 原判決は、被告人がYから洋傘を取り上げ、同人に暴行を加え、そのまま洋傘を持ち去った事実に、被告人が2、3日前、パチンコ店で自分の洋傘を他の悪い洋傘と取り替えられたという事情を総合すれば、被告人に強盗の意思のあったことの認定が可能であると判断したものと認められる
- しかし、この判断には疑問がある
- 被告人は、原審公廷で、Yから洋傘を取り上げたのは、それで同人を殴るためであったと述べているが、Y証人及び被告人の原審公廷における各供述によれば、被告人は現にYの頭部等を洋傘で2、12回殴っているのである
- のみならず、Yの証言に被告人の司法警察員に対する供述調書及び被告人の検察官に対する供述調書(二通)を総合すると、Yは、当時、相当酩酊していて、被告人から最初の一撃を受けてその場にしゃがんでしまい、「たたきたいならいくらでもたたけ」といって無抵抗の意思を表示し、終始殴られどうしでいたのである
- すなわち、被告人がYから洋傘を奪取しようと思えば、その目的を遂げる手段として手拳、革バンド、ゴム長靴ばきの足等で同人に殴る蹴るの暴行を加えないでも容易に奪取することのできる状況にあったものと認められる
- したがって、被告人がYから傘を取り上げたのは、被告人の弁解するとおり、それで同人を殴る目的から出たものであって、それで同人を殴った行為も、手拳、革バンド、ゴム長靴ばきの足で同人を殴ったり蹴ったりした行為も、洋傘を奪取し、あるいはその奪取を確保する手段たる暴行と見るよりは、最初の一撃と同様、口論の末の腹立ちまぎれに加えた暴行と見る方が、むしろ事態に即するものと認められるのである
- 以上の次第で、被告人がYに暴行を加えている間に、強盗の意思を生じて同人から洋傘を強取したとの点は、証拠上必ずしも明らかではないというべきである
- しかし、さきに触れたとおり、被告人がYに暴行を加えた後、そこを立ち去る際に洋傘を不法に領得する意思を有していたことは疑がない
- また、被告人がYに暴行を加えている間に、同人の洋傘を取ってそのままそれを手中に収めてはいたが、被告人がその場を立ち去るまでは、同所にいるYの洋傘に対する占有は依然存続していたもので、被告人がその場を立ち去るに及んで始めて洋傘はYの占有を離れて被告人の占有に完全に移ったものと解するのを相当とする
- したがって、Yの洋傘を持ち去った被告人の所為は、窃盗罪を構成するものといわなければならない
- 結局、被告人の本件所為は、Yに原判示暴行を加えて前記傷害を与えた点において傷害罪を構成し、右のごとく同人の洋傘を持ち去った点において窃盗罪を構成し、以上の二罪は併合罪をもって論ぜらるべきものといわなければならない
- したがって、原判決が、被告人に対し、強盗傷人の結合犯を認定し、刑法240条前段を適用処断したのは、事実を誤認し、ひいて法令の適用を誤ったもので、以上の誤は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は破棄を免れない
と判示し、暴行は、被告人がYから洋傘を強取する意思を有し、その目的を遂げる手段として加えたものではないとして、強盗致傷罪の成立を否定し、傷害罪と窃盗罪の二罪が成立するとしました。
東京地裁判決(昭和46年7月6日)
この判例は、酔った勢いで通りがかりの女性をからかおうとして抱き付くなどの暴行に及び、倒れた被害者が落としたバッグを持逃げした事案で、強盗致傷罪の起訴に対し、傷害罪と窃盗罪を認定した事例です。
裁判官は、
- 被告人が本件暴行を行なった事実、およびハンドバッグを持ち去った事実は明瞭であり、ハンドバッグの奪取が、右暴行と接着した時間に敢行されたことにかんがみると、本件暴行が財物を奪取する手段として行なわれたかの観があり、取調べに当たった捜査官が、その間の事情を追及したのはもとより首肯できるところであり、他方、被告人が説明に窮したのも無理からぬことといわねばならない
- さらに、証人Y、Kの各供述その他の関係証拠を子細に検討すると、本件において、司法警察員、検察官が強制、拷問、脅迫その他これに類する手段を用いて取調べを行なった事実はうかがわれず、また前記のような取調に対して、前記のような供述をしたからといって、ただちに右供述の任意性に疑があるものとは解されない
- けれども、被告人としては、理詰めの質問に対し説明に窮したため、あるいはそのことによる心理的動揺から、深く考えもせず、捜査官に迎合し、真実に反する供述をしたものと認められる
- よって、右各供述調書の前記記載部分はたやすく信用することができない
- 以上を要するに、本件公訴事実中、被告人に金品を強取する意思があったとの点は、これを認めるに足りる証拠がなく、被告人は、判示認定のとおり傷害と窃盗の限度において責任を負うものと解するのが相当である
と判示し、バッグ窃取のついて強盗の意思はないとして、強盗致傷罪ではなく、傷害罪と窃盗罪のニ罪が成立するとしました。
東京地裁判決(昭和46年9月29日)
この判例は、遺恨を晴らす目的で暴行を加え、その後、被害者がふらふらしているが、反抗を抑圧された状態には至っていなかったときに財布を抜き取ったものであることを認め、強盗致傷罪の訴因につき、傷害罪と窃盗罪の併合罪を認定した事例です。
裁判官は、
- 被告人らが、Vに対する暴行を加え終った後、転倒していたVがSに助け起され、そば店の方向に歩きかけた際に、被告人Kが、被告人NおよびSに対し、ことさら「いい財布だなあ。このままで帰えすほうはない。」とVが先に差し出した財布をVから奪取すべき旨の言辞を口外していることが認められるのであって、このことをも合わせて考察すると、被告人らが判示暴行を加える際に、財物奪取の故意を有し、右財物奪取の手段として右暴行を加えたものであるとは断じ難いところである
と判示し、暴行は、財物奪取の犯意を生ずる前に行われており、暴行は強盗の手段として行われていないから、強盗致傷罪ではなく、傷害罪と窃盗罪のニ罪が成立するとしました。
岡山地裁判決(昭和47年2月9日)
この判例は、強盗致傷の訴因につき、傷害罪と窃盗罪の成立を認めた事例です。
裁判官は、
- 被告人の捜査段階の供述について見るに、司法警察職員に対する第一回供述調書によれば、くわしいことは覚えておらないが、その男を引倒し、店の前道路脇にある小さい溝に首をつかんで泥水に顔をつけたりした後、その男のはめていた腕時計をとった旨概括的に供述するにすぎないが、同第二回供述調書によれば、相手が帰りぎわに「出てこい」などというので、腹が立ち、生意気なことをいうやつだという気持になり、時計でも盗ってやろうと思って店外へ出、当公判廷でも認めるような乱暴をした後、相手が立ち上ろうとして下水道の端のところへ手をかけて来たので、引上げてやろうと思って手首をつかんだところ、はめていた時計が手からはずれて道路に落ちたので、これをズボンのボケットにねじ込んでとんで逃げた旨供述し、相手の腕から奪いとったものではないことをうかがわせるような供述になっているのである
- 検討したところによれば、被告人による右時計を拾い取る行為が強盗致傷罪を構成しないことは明らかである
と判示し、強盗致傷罪でなく、傷害罪と窃盗罪の二罪が成立するとしました。
④ 傷害が、財物奪取の犯意を生ずる前の暴行による場合、強盗致傷罪ではなく、傷害罪と恐喝罪との併合罪になる
上記と同様、傷害が財物奪取の犯意を生ずる前の暴行による場合において、強盗致傷罪ではなく、傷害罪と恐喝罪との併合罪になると認定した事例として、以下の判例があります。
広島地裁判決(昭和44年3月19日)
この判例は、タクシーの運転手に対し、暴行脅迫を加えて所持金を奪取した事案につき、その暴行・脅迫の程度は相手方の反抗をかなり困難にさせるものであつたと認められるが、さらに進んでその反抗を抑圧するに足りるものであつたとは認めがたいとして、傷害罪と恐喝罪の併合罪を認定した事例です。
裁判官は、
- 本件犯行の経緯と状況をつぶさに検討してみると、右暴行、脅迫の程度は、未だ相手方の反抗を抑圧するまでにはいたつていなかったと認めざるをえないのである
- すなわち、被告人らは判示のとおり、タクシーに乗車したところ、S運転手の態度が横柄であったため憤激し、まず被告人が、Sの顔を殴ったが、次いでAが100メーター道路でSを車外にひきずり出そうとした際には、被告人がAに対し、「すな、すな」と言って、あまり手荒なことをしないように制止し、そのためにSも車外に出なかったこと、またTにおいても、被告人は小用のため等で再三車を離れ、しかも、売上金のことに話がおよんだ際にも、被告人は「ようもうけたんじゃのお」などといい、Aも「兄貴、それだけは手をつけな」などと言っており、また被告人がSに対し「お前時計をちよっと見せてみい」と言って時計を呈示させた際にも、被告人が「メーカーは」ときいたのに対し、Sは「セイコー」と言ってこれに答え、さらに被告人は右時計を「曇っているじやないか」と言ってSに返していること加えて、本件の5000円はSが「これでかっこうをつけてつかあさい」と言って座席の上に置いたものを、被告人が受けとったのであり、しかも、そのあとでAにおいてSから紙片とボールペンを借り受け「酒代により、金五千円也おかしします」などと記載してSに指印させ、さらに、タオルを出させて「わしらのことを今言うて行ったら東署にいってもすぐわかるんじやけんのお」などと言いながら車についている被告人らの指紋をふきとるなどしているのである
- このような本件犯行の経緯や状況にかんがみると、被告人らが被害者Sに対して加えた暴行、脅迫をもつてその反抗を抑圧するに足りるものであつたと認めるには、あまりにも緊迫感を欠くものであるといわざるをえない
- しかも、被告人らは、別段凶器を使用しているわけでもなく、また被害者をその場にとり押えて動けないようにしたわけでもないのであるから、被害者がその場から逃げ出そうとすれば、決して不可能ではなかったと考えられる
- 要するに、被告人らの加えた暴行、脅迫の程度は、相手方の反抗をかなり困難にさせるものであったと認められるが、さらに進んで、その反抗を抑圧するに足りるものであったとは認めがたい
- また、被告人らが当初から、Sより余負を奪取しようと企てたものでなく、同人の態度に憤慨して暴行を加えたため、判示傷害を生ぜしめたのち、判示のように金員喝取(かっしゅ)の犯意を生じたものと認められるから、結局本件については、傷害罪と恐喝罪が成立するにとどまるというべきである
と判示しました。
次回記事に続く
次回記事では、傷害罪と強盗罪・強盗致傷罪の関係【その2】について説明します。