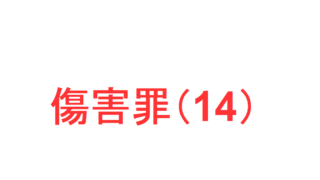傷害罪(15) ~傷害罪における違法性阻却⑥「暴行・傷害罪における正当防衛」「成立要件(侵害の危険の緊迫)」「憤激により反撃した場合・防衛行為で生じた結果が大きい場合・反撃の準備をした場合の正当防衛の成否」を判例で解説~
前回記事では、傷害罪において違法性阻却事由となりうる「現行犯逮捕の際の傷害」「スポーツにおける傷害」について説明しました。
今回の記事では、傷害罪における違法性阻却事由となりうる正当防衛に関し、「正当防衛の成立要件」などについて説明します。
暴行・傷害罪における正当防衛
正当防衛(刑法36条)とは、
急迫不正の侵害に対して、自分または他人を守るために、やむを得ずにした反撃行為
をいいます。
刑法には、『自分に危険が迫っているときは、反撃して自分の身を守ることができる』ことが明確に規定されているのです。
正当防衛が成立すれば、反撃行為が殺人罪や傷害罪を構成しても、違法性が阻却され、犯罪を構成せず、処罰されずに済みます(正当防衛についての詳しい説明は前の記事参照)。
暴行・傷害罪において、正当防衛が問題となる事例は多いです。
これは、たとえば、けんか事案の場合、「相手に殴られそうだったから、正当防衛のため相手を殴ったんだ」などと言って自己の正当性を主張すれば、正当防衛により違法性が阻却され、傷害罪の罪を免れることができるかもしれないと考える者が多いからです。
暴行・傷害罪において正当防衛が成立するためには、侵害の危険が間近に緊迫していることが必要となる
暴行・傷害罪において、正当防衛が成立するためには、暴行・傷害を受ける危険が予想されるというだけではなく、
侵害の危険が間近に緊迫している状況
が必要になります(最高裁判例 昭和24年8月18日)。
暴行・傷害行為が終わった後に反撃する行為は正当防衛にはなりません。
たとえば、暴行を受けた被害者が逃げ出すなどして一旦難を避けた場合、その後に反撃しても、侵害が存在しないため、正当防衛は成立しません。
また、被害者が反撃することにより、暴行・傷害犯人が逃げ出し、あるいは無抵抗になった場合は、その後、更に被害者が反撃しても、侵害が現在しないため、正当は成立しません。
しかし、暴行・傷害犯人が、なお侵害行為を反復する危険が現存すれば、侵害の急迫性は消滅しません。
なので、侵害行為を再び行うおそれがある犯人に対し、被害者が反撃行為に出た場合は、正当防衛が成立する可能性があります。
たとえば、被害者が犯人から凶器を取り上げ、犯人がひるめば、急迫性はなくなりますが、なお犯人が素手でも襲いかかってきた場合は急迫性が認められるため、なお襲いかかってきた犯人にに対して反撃行為に出ても相当防衛が成立する可能性があります。
この点については、以下の判例があります。
暴行犯人から鉄パイプで頭を殴られた被害者が、暴行犯人を追いかけた後、勢い余って2階通路から上半身を乗り出すようにしていた暴行犯人の足を持ち上げて転落させ、暴行犯人に腰椎骨折などの3か月間の傷害を負わせた事案です。
裁判官は、暴行犯人がなお鉄パイプを握り続けるなど再度の攻撃に及ぶことが可能であったとして、急迫性の侵害の継続を認めました。
ちなみに、この判例の事案では、結果として、被害者の正当防衛ではなく、過剰防衛(刑法36条)を認定しました。
加害行為に対し、憤激して反撃を加えたからといって、防衛の意思を欠くとされるものではない
相手の加害行為に対し、憤激または逆上して反撃を加えたからといって、ただちに防衛の意思を欠くものではありません。
この点について、以下の判例があります。
この判例で、裁判官は、
- 刑法36条の防衛行為は、防衛の意思をもってなされることが必要であるが、相手の加害行為に対し、憤激または逆上して反撃を加えたからといって、ただちに防衛の意思を欠くものと解すべきではない
- これを本件についてみると、被告人は旅館に戻ってくるや、Cから一方的に手拳(しゅけん)で顔面を殴打され、加療10日間を要する傷害を負わされたうえ、更に本件広間西側に追いつめられて殴打されようとしたのに対し、小刀をもって同人の左胸部を突き刺したものである
- そうであるとすれば、かねてから被告人がCに対し憎悪の念をもち、攻撃を受けたのに乗じ積極的な加害行為に出たなどの特別な事情が認められないかぎり、被告人の反撃行為は防衛の意思をもってなされたものと認めるのが相当である
と判示しました。
予期せぬ侵害に直面した際に、とっさに加害意思で対抗しようとした場合は、侵害の急迫性を失うものではありません。
この判例で、裁判官は、
- Aの木刀による攻撃は被告人の予期しなかったことであって、それは被告人に対する急迫不正の侵害というべきである
- この点において、原判決が、被告人はAの攻撃を予期しており、その機会に積極的に同人を加害する意思であったもので、Aの攻撃は侵害の急迫性に欠けるとしたのは、事実を誤認したものといわざるをえない
と判示し、予期せぬ攻撃に対し、加害の意思で攻撃したからといって、侵害の急迫性に欠けることにならないとしました。
防衛行為で生じた結果が侵害されようとした法益より大きくても、正当防衛でなくなるものではない
防衛行為で生じた結果が、たまたま侵害されようとした法益より大きくても、正当防衛が否定されるものではありません。
この点について、以下の判例があります。
突然指をつかんでねじ上げられ、痛さの余り相手の胸を突いて転倒させて軽傷を負わせた事案で、裁判官は、
- 刑法36条1項にいう「やむことを得ざるに出たる行為」とは、反撃行為が急追不正の侵害に対する防衛手段として相当性を有することを意味し、右行為によって生じた結果がたまたま侵害されようとした法益より大であっても、正当防衛行為でなくなるものではない
と判示しました。
侵害を予期して反撃の準備をする場合は、急迫性を欠くため正当防衛を成立させない
侵害が予期されるものであるからといって、直ちに急迫性が否定されるものではありません。
しかし、侵害を予期して、
反撃の準備をする場合
は、侵害の急迫性を欠き、正当防衛を成立させません。
この点について、以下の判例があります。
この判例で、裁判官は、
- 刑法36条が正当防衛について侵害の急迫性を要件としているのは、予期された侵害を避けるべき義務を課する趣旨ではないから、当然又はほとんど確実に侵害が予期されるとしても、そのことから、ただちに侵害の急迫性が失われるわけではない
- 予期された侵害の機会を利用して積極的に相手に対し、加害行為をする意思で侵害に臨んだときは、侵害の急迫性を欠く
と判示しました。
防衛に名を借りて侵害者に攻撃を加える場合は、正当防衛は成立しない
防衛の意思に付随し、攻撃的意思が併存しても、防衛意思を欠くものではありません。
しかし、防衛に名を借り、侵害者に対し、積極的に攻撃を加える行為は、防衛の意思を欠き、正当防衛を成立させません。
この点にについて、以下の判例があります。
最高裁判決(昭和50年11月28日)
この判例では、防衛の意思と攻撃の意思とが併存している場合に、刑法36条の正当防衛が成立するか否かが争われました。
裁判官は、
- 急迫不正の侵害に対し、自己又は他人の権利を防衛するためにした行為と認められる限り、その行為は、同時に侵害者に対する攻撃的な意思に出たものであっても、正当防衛のためにした行為にあたると判断するのが、相当である
- すなわち、防衛に名を借りて侵害者に対し積極的に攻撃を加える行為は、防衛の意思を欠く結果、正当防衛のための行為と認めることはできないが、防衛の意思と攻撃の意思とが併存している場合の行為は、防衛の意思を欠くものではないので、これを正当防衛のための行為と評価することができるからである
と判示しました。
東京高裁判決(昭和60年6月26日)
この判例で、裁判官は、
- 被告人が相手に喧嘩を挑み、相手がこれに挑発されて攻撃してくるであろうことを予期し、その機会を利用して、被告人自身も積極的に相手に対して加害する意思で暴行を加えた場合には、正当防衛における侵害の急迫性に欠けるというべきである
と判示しました。
次回記事に続く
次回記事では、「けんかと正当防衛」について書きます。