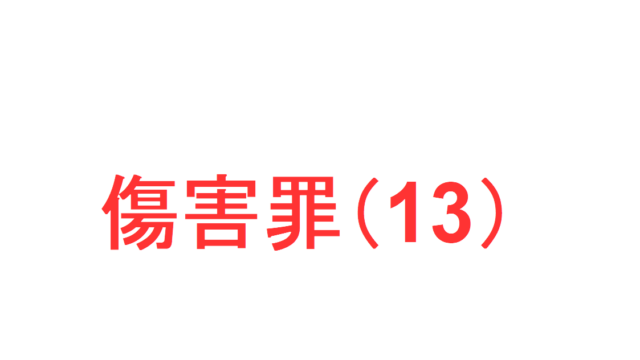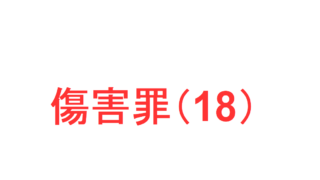傷害罪(19) ~「傷害罪における責任能力(心神喪失・心神耗弱)」「責任能力が争われた判例」を解説~
責任能力とは?
まず、責任能力について説明します。
責任能力とは、
犯罪の行為時において、自分が実行した犯罪行為の是非善悪を弁別し、かつ、その是非善悪の弁別に従って行動し得る能力
をいいます。
責任能力がない人は、たとえ殺人罪などの凶悪犯罪を行ったとしても、処罰されません。
ニュースで、犯人の弁護士が「犯人は犯行当時、責任能力がなかった」と主張しているのが報道されることがあります。
これは、『犯人に責任能力はない→だから犯人は無罪である』という判決になることをねらっているのです。
ちなみに、責任能力がない人を「心神喪失者」といいます。
責任能力がない状態とは、心身喪失の状態であると考えればOKです。
高度の精神病者や知的障害者は、心神喪失者になり得ます。
たとえば、高度の知的障害者が、混乱してわけが分からなくなっている状態で人を殺したとします。
そのような知的障害者を殺人罪で有罪にして、懲役20年の刑罰を科したとしても、知的障害者は知能が低く、「ここはどこ?わたしは誰?」といった感じでわけが分からない状態なので、反省も更生もできないわけです。
法は、そのような責任能力がない人に対し、刑罰を科して刑務所に入れても意味がないと考えるため、責任能力がない人が犯罪を犯しても、無罪とするのです。
このような状況は、『行為者に責任能力がない場合、たとえ違法行為を行っても、そのことについて行為者を非難する前提を欠き、犯罪は成立しない』という言葉で表現されます。
次に、責任能力が著しく減退している人(責任能力が全くないわけではない人)を「心神耗弱者」といいます。
裁判で心神耗弱者の認定をされると、刑罰が減軽されます(刑法39条)。
(責任能力については、前の記事でより詳しく説明しています)
責任能力の有無は、医学ではなく法的判断により決定される
心神喪失・心神耗弱の判断は、法律的判断であって、精神医学的鑑定のみによって判断されるものではありません。
つまり、精神科の医師が、傷害犯人の犯行時の精神状態を鑑定して、心神喪失又は心神耗弱の診断をしたとしても、裁判官は、精神科医師の診断が記載された鑑定書の内容に縛られ、心神喪失又は心神耗弱の判決を言い渡さなければならいというわけではありません。
裁判官は、精神科医師の鑑定書のほか、傷害犯人の言動や様子、その他の犯行時に存在した事情を総合的に考慮して、裁判官の判断として(医学的な判断ではなく、法的な判断として)、傷害犯人が犯行時に心神喪失又は心神耗弱であったかどうかを決めることになります。
この点について、以下の判例があります。
仙台高裁判決(昭和26年8月24日)
睡眠薬の服用と飲酒による病的酩酊にあった旨の鑑定のある事案で、裁判官は
- 犯行当時、被告人は飲酒していたことは認めうるが、当時の状況につき整然たる供述をしている等の事実より、精神障害があったことは是認することはできない
として、心神喪失を認定せず、心神耗弱を認定しました。
東京高裁判決(昭和38年11月25日)
この判例は、傷害事案について、被告人が、犯行当時、病的酩酊の状態にあったとの鑑定結果があったにもかかわらず、心神喪失を認定せず、心神耗弱を認定した事例です。
裁判官は、病的酩酊の鑑定結果があったが、精神医学上の鑑定と、心神喪失・心神耗弱の判断とは別個のものであることを明言し、被告人が犯行当時、心神耗弱であったと認定し、傷害罪の成立を認めました。
具体的な判決内容は以下のとおりです。
裁判官は、
- 原判決は、鑑定人Mの作成にかかる鑑定書、とくに、被告人の本件犯行当時の精神状態は、「気分昂揚的異常性格傾向に、軽い知能障害の加重された人格面全般の水準低下の状態において飲酒し、その酩酊状態は、飲食前に服用したハイミナールの作用によって増強され、高度の意識混濁と不気嫌状態を伴う強い運動性興奮を呈し、定型的な病的酩酊といいうる状態にあったと考えられる。従って、この範囲では、是非を弁別し、それに従って行動する能力は、著しく障害されていたと考えられ、その責任能力は、高度に限定されていたものと考える。」旨の記載、原審第三回公判調書中証人Iの供述記載、被告人の司法警察員および検察官に対する各供述調書などを総合して、被告人は、本件犯行当時、心神喪失の状態にあったものと認定していることは、その判文にてらし明らかである
- しかし、当審証人Mの当公判廷における供述によれば、右鑑定書は、精神医学上の見地から、被告人の本件犯行当時の精神状態を前記のように鑑定したまでのことであって、それが刑法上にいわゆる心神喪失にあたるか、心神耗弱にあたるにすぎないかをまで鑑定したものではないことを看取することができる
- また、ある人の常日頃の酒量、犯行当時におけるその人の飲酒量がどの位であったかに関する当該本人の供述、または当時一緒に飲酒をした人の供述のごときは、飲酒の結果、心神喪失の状態にあったか、または心神耗弱の程度にあったかというような微妙な差を判定する資料としては、大した価値を有するものではない
- そして、各供述調書によれば、被告人の本件犯行は、被告人が料理店において、酔余、同店の女中らに乱暴をしたことについて、被害者から強くたしなめられたことに憤慨してなされたものであることが明らかであり、また、本件犯行当時、被告人はある程度において、その状況を察知しながら行動をしていたことが十分認められ、是非善悪を弁別する能力を失っていたものとは、とうてい認めることができない
- したがって、右各供述調書と前記鑑定書の記載と当審証人Mの当公判廷における供述を総合して考察すると、被告人は本件犯行当時、ハイミナール約6錠を服用したのち、飲酒をした結果、心神耗弱の状態にあったものであって、原判決のいうような心神喪失の程度には至っていなかったものと認定するのを相当とする
- 本件犯行当時、心神耗弱の状態にあったので、刑法第39条第2項により法定の減軽をした刑期範囲内において、被告人を懲役6月に処す
と判示し、傷害罪の成立を認めました。
傷害罪に関して責任能力が争われた判例
傷害罪に関して責任能力が争われた参考となる判例として、以下の判例を紹介します。
飲酒により自ら精神障害を招いた上で傷害に及んだ事案
長崎地裁大村支部判決(昭和43年11月5日)
この判例は、飲酒酩酊による心神耗弱の状態における傷害につき、心神耗弱の状態がいわゆる自招精神障害にあたるとして、心神耗弱による減刑規定の適用を否定した事例です。
裁判官は、飲酒酩酊して他人に暴行傷害を加える酒癖のある者が、自己の酒癖を知悉し、飲酒酩酊の末に暴行傷害の結果を惹起すべきことを意識しながらこれを認容して敢えて飲酒酩酊の上、 傷害を負わせた旨認定し、 自招精神障害として心神耗弱を認めず、傷害罪が成立するとしました。
具体的な判決内容は以下のとおりです。
裁判官は、
- 弁護人は、被告人は当時酒に酔い、心神耗弱状況にあったと主張し、被告人が犯行当時、酒に酔い酩酊していたこと判示のとおりであるけれども、判示証拠によれば、被告人はこれまでも何回となく酒に酔って他人に暴行・傷害を加えており、時には刑事事件として罰金刑に処せられたことも一再ならずあること及び被告人自身も自己がかかる酒癖を有することを知悉していたことが認められるので、被告人が真に他人に暴行傷害を与えまいと思うならば、当然に飲酒を慎しむべきであり、これを慎しまないで敢えて飲酒し、その結果、犯行に至るときは、その犯行の結果はその飲酒に当たり、被告人が当然予見していたところというべく、右結果発生当時の被告人の心神の状態が、たとえ医学的に心神耗弱というべき状況にあったとしても、被告人の刑事責任能力を考える上においては、たんに被告人の右医学的心理状況のみに局限せず、右飲酒に当たり、被告人が予見したところをも包括して判定すべきものと考えるので、結局、本件被告人の行為は刑法にいわゆる心神耗弱者の行為に当たらないものと考える
- それ故弁護人の主張は採用しない
と判示しました。
薬物使用により自ら精神障害を招いた上で傷害に及んだ事案
薬物を摂取して悲観的思考になり、愛する姉を殺害して自殺しようと決意し、姉を短刀を使って殺害した事案です。
まず、被告人の弁護人は、
- 被告人は、本件犯行当時、心神喪失の状態にあったから、本件は心神喪失者の行為として無罪である
と主張しました。
この主張に対し、裁判官は、
- 被告人は、生来異常性格者で、ヒロポン中毒のため、その変質の度を増し、本件行為当時は薬剤注射により、症候性精神病を発しおり、本件犯行は該病の部分現象である妄想の推進下に遂行されたものであって、通常人としての自由なる意思決定をすることが全く不能であったことを認めることができるので、被告人の本件犯行の殺意の点については、法律上、心神喪失の状態において決意されたものと認めざるを得ない
- 果たして、然らば、本件犯行を心神喪失者の行為として、刑法第39条第1項により無罪の言渡しを為すべきか否かにつき更に審究するに、薬物注射により症候性精神病を発し、それに基く妄想を起こし、心神喪失の状態に陥り、他人に対し、暴行傷害を加え、死に至らしめた場合において、注射をなすに先だち、薬物注射をすれば、精神異常を招来して、幻覚妄想を起こし、あるいは他人に暴行を加えることがあるかも知れないことを予想しながら、敢えてこれを容認して薬物注射をなした時は、暴行の未必の故意が成立するものと解するを相当とする
- 被告人は、薬剤エフェドリンを買い受け、この水溶液を自己の身体に注射したのであるが、その際、該薬物を注射するときは、精神上の不安と妄想を招来し、所携の短刀をもって他人に暴行等如何なる危害を加えるかも知れなかったので、これを懸念しながら、敢えてこれを容認して右薬剤を自己の身体に注射し、その結果、幻覚妄想に捉われて、短刀をもって姉を突刺し、よって同女を死亡するに至らしめた事実を認めることができるから、被告人は、本件につき、暴行の未必の故意をもって姉を短刀で突刺し、死に至らしめたものというべく、従って傷害致死の罪責を免れ得ないものといわなければならない
と判示し、傷害致死罪の成立を認めました。
東京地裁判決(昭和53年11月22日)
この判例は、被告人による妻に対する傷害、殺人事案(妻に対する傷害罪を犯し、その4か月後に妻を殺害した事案)であり、覚せい剤を反復使用した結果、犯行時、精神障害に陥っていたとして、心神耗弱が認められた事例です。
裁判官は、
- 覚せい剤中毒による精神障害は、人格が破壊し、病的体験が全人格を支配するとされる精神分裂病などとは異り、妄想というような病的体験は人格全体を支配せず、病的体験の関与には濃淡、強弱があつて、病的体験を有しながら知情意の面には、なお健康な部分が残存し、疏通性を保持したり、通常の生活活動をするなど生活能力の点ではほとんど正常である場合も少なくないとされているのであるが、既に見て来たとおり、被告人の場合は、妄想を主体とする異常体験に捉われることもあったが、通常は、生活能力に格別の低下はなく、意識も概ね清明であり、覚せい剤使用の違法性や薬害も認識して、その中止を考慮しており、通常における異常体験の関与は必ずしも強くはなかったと認められる
- そして、本件傷害については、妄想等の異常体験の関与が薄く、これに支配されてなされた犯行とは到底認められず、また、本件殺人については、本件傷害の場合に比し、妄想等の異常体験の関与が強かったとはいえ、それが直接動機とはなつていないと認められるうえ、被告人の本件犯行当時の記憶はかなり詳細、正確であって、意識の清明であったことが認められるし、犯行前後の被告人の理に適った言動に照らせば、被告人がある程度の規範意識を保持していたことも認められるから、本件殺人もまた、妄想等に全人格を支配されてなされた犯行とは認められず、被告人は、本件各犯行当時、是非善悪を弁識する能力及びこれに従って行動する能力をいまだ欠くには至っていなかつたものと認められる
- しかしながら、被告人の爆発的で情緒不安定な性格は、覚せい剤の常用によりかなり先鋭化し、精神の荒廃もある程度進行していたことは証拠上否定し難く、しかもその尖鋭化した爆発的性格が本件各犯行において重要な役割を果していることも明らかであって、本件各犯行当時、被告人は是非善悪を弁別し、これに従って行動する能力を著しく減弱した状態にあったと認められる
- 従って、弁護人の主張は、この限度で理由があると認め、心神耗弱を認定した
と判示しました。
犯行の途中で意識がなくなった事案
東京地裁判決(平成9年7月15日)
この判例は、傷害事件の被告人が、実行行為たる傷害行為の時点において外傷性てんかん発作を起こし、意識がない状態にあったとしても、発作中の行為がその直前の被告人の意思に従ったものである以上、完全責任能力が認められるとした事例です。
裁判官は、外傷性てんかんを患っていた被告人の傷害事件において、実行行為の着手後発作を起こし、意識がない状態にあったとしても、発作中の行為がその直前の被告人の意思に従ったものである以上、完全責任能力が認められるとして、傷害罪の成立を認めました。
具体的な判決内容は以下のとおりです。
裁判官は、
- まず、被告人の捜査段階の供述によれば、被告人に傷害の故意及び責任能力が存することは明らかである
- 次に、被告人の公判供述によっても、包丁で刺したこととベランダでの暴行との継続性を否定する事情はなく、それらは一連の行動であると認められ、台所でB子を捕まえて刃先の鋭利な包丁を手に取ったことまでは認識していたというのであるから、遅くとも包丁を手にした時点までに傷害の故意を生じたと認められる
- そうすると、仮にB子を刺した時点で発作が起きていたとしても、発作中の行為はその直前の意思に従ったものであって故意に欠けるところはない
- 捜査報告書によれば、被告人は交通事故による外傷性のてんかんを患い、医師の投与する薬を服用していたところ、時々発作を起こし、発作を起こしている間は意識がなくなるものの、発作を起こす前及び意識が戻った後は通常の者と同様に意識があり、物事の善悪も分別できることが認められる
- そうすると、B子を刺した時点で発作が起きていたとしても、発作中の行為がその直前の被告人の意思に従ったものである以上、被告人は自己の行為を認識して善悪の判断をしそれに従って行動する能力を有しつつ実行したものといえ、完全な責任能力が認められる
と判示しました。
精神病者による傷害の事案
東京高裁判決(昭和53年9月19日)
この判例は、犯行の動機及び態様がほぼ同一の2個の傷害の事実で、被告人は、その1つにつき心神耗弱の状態、他の1つにつき心神喪失の状態であったとした原判決が破棄され、いずれも心神喪失の状態にあったと認められた事例です。
裁判官は、統合失調症等の精神疾患の場合は、判断が困難であるが、駅又は電車内で特段の理由なく突如女性に暴行を加えたもので、犯行時点が約3か月離れている2件の傷害事案について、精神分裂症の病的過程の進行中のうえ、過度の飲酒による複雑酩酊の状態にあったとして心神喪失を認定しました。
具体的な判決内容は以下のとおりです。
裁判官は、
- 本件第一の犯行の際も、第二の犯行時と同様、被告人は平素の酒量を上回る飲酒をし、相当な酩酊状態にあったこと、そのため、ことに第一の犯行の際には、被告人は、前を降りて行く女性を見て、その女性が自分の進路を邪魔しているように思い、だれかが「この女は悪いやつだ」とささやいているような声が聞えたとしていること、A医師は、被告人の右の入院歴・行動歴ののみならず、家族歴・生活歴・病状経過・本件各犯行の経過及び態様・身体的所見・精神医学的所見・鑑定時現在の精神状態等を詳細に総合検討したうえ、前記鑑定結果のとおり鑑定したものであること、したがって、事実はおおむね前記鑑定結果のとおり、すなわち、被告人は本件各犯行当時、精神分裂症の病的過程の進行中のうえ、過度の飲酒による複雑酩酊の状態にあったものであることが認められる
- 右認定の事実によれば、被告人は本件第二の犯行当時だけでなく第一の犯行当時も、自己の行為の是非善悪を弁識し、かつ、これに従って行動する能力を失っていた、すなわち、心神喪失の状態にあったものと認めるのが相当である
と判示しました。
神戸地裁判決(平成6年5月10日)
この判例は、パラノイアに羅患していた被告人によるAに対する殺人・Bに対する傷害事件について、当時被告人は妄想に支配されており、心神喪失の状態にあったことから、責任能力がないとして無罪が言い渡された事例です。
裁判官は、
- 精神科医師Sの鑑定は、「本件犯行は、明らかに被告人の被害妄想ないし関係妄想に根ざしたものであると認められる。」とし、「本件犯行当時の被告人は、被害者に対する一次的な被害妄想の支配下にあり、被害者達に対し強い被害的な内容の妄想を有し、自己統制力、行動抑止力に著しい欠陥があったため、無思慮かつ衝動的・短絡的に犯行に及んだものと認められる。したがって、当時被告人は、このA母子との問題に関係のない事柄については是非善悪を弁識する能力を欠いてはいなかったが、これに関係する事柄については、弁識能力を欠如していたと認められる。」と結論付けている
- また、精神科医師Mの意見は、被告人は、妄想知覚を一次的妄想体験として被害妄想、迫害妄想が生じてきていたとしたうえ、「本件犯行は、被疑者の罹患していた妄想性障害に基づいており、直接妄想に支配されてなされたものと考えられる。被疑者の犯行の原因が真性妄想に基づいている以上、犯意を持って計画的になされた犯行であっても、被疑者は犯行の動機においてその現実検討能力を失っており、理非善悪を判断する能力とこれに従って行動する能力を喪失していたと考えるのが妥当であろう。」としている
- 被告人の被害妄想、迫害妄想、関係妄想は、妄想知覚によってますます強化され、被告人の精神生活を大きく支配していたので、被告人は、犯行直前、錠の留め金を直している時、たまたまAが通りかかったのを見て、Aが留め金を修理しているのを知り、酒に酔って冷かしに来たと直観して激怒し、本件犯行に及んだのであって、犯行当時、被告人は、右の妄想に直接支配されていたと認めるのが相当である
- Aに対する犯行について、被告人は、右犯行当時、妄想に直接支配されていたため、右犯行に関し事の理非善悪を弁識し、これに従って行動する能力を欠如していたから、被告人は、犯行当時、心神喪失の状態にあったと認められる
- Bに対する犯行について、被告人のBに対する犯行は、まさに、被告人の妄想に基づく、Aに対する報復行動(犯行)の直前またはその最中に付随してなされたものであって、右行動と一環をなしているから、主たる犯行について、妄想に支配された行為として責任能力がないとする以上、その延長線上のBに対する犯行についても、妄想に支配された中での行為として、責任能力がないと認めるのが相当である
- 以上のとおり、被告人の本件各行為は、心神喪失者の行為として罪とならないから、刑事訴訟法336条前段により被告人に対し無罪の言渡しをする
と判示しました。