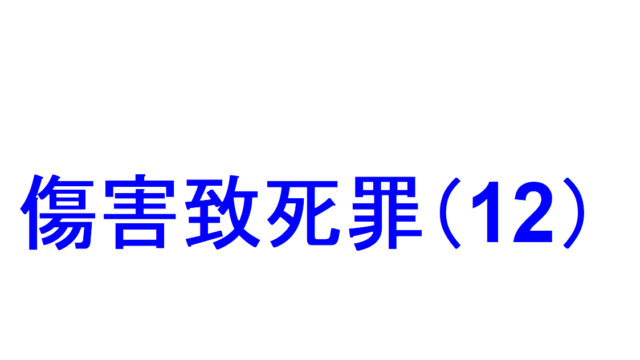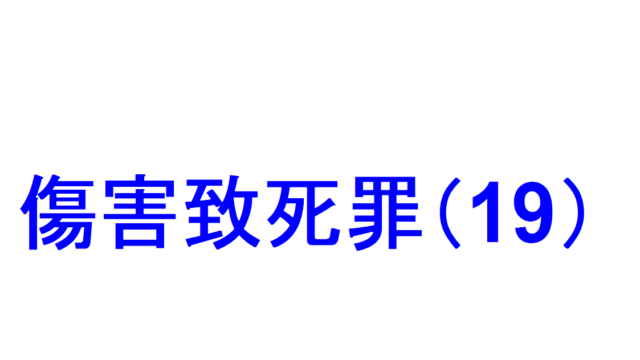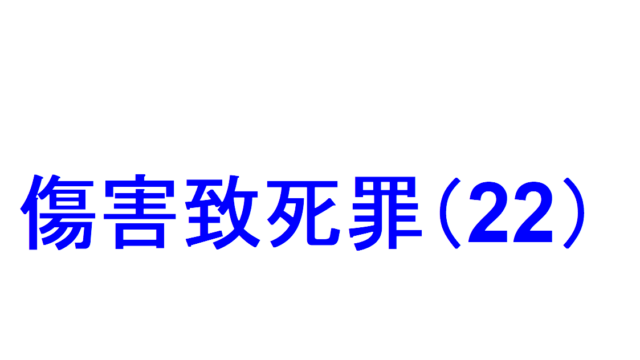傷害致死罪(11) ~暴行・傷害と死の結果の因果関係⑤「暴行と死亡の間に時間的経過がある場合、死体の発見されない場合の因果関係の認定」「因果関係の認定に結果の予見可能性は必要ない」を判例で解説~
前回の記事では、暴行・傷害と死の結果の因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとした下級審判例を紹介しました。
今回の記事では、暴行・傷害と死の結果の因果関係について、
- 暴行と死亡の間に時間的経過がある場合の因果関係の認定
- 死体の発見されない場合の因果関係の認定
- 因果関係の認定に「結果の予見可能性」は必要ない
について説明します。
暴行と死亡の間に時間的経過がある場合、死体の発見されない場合の因果関係の認定
暴行と死亡の間に
- 時間的経過がある場合
- 死体の発見されない場合
は、暴行と死亡との因果関係を認定するには、医学的な検討・判断を要します。
この点については判示した事例として、以下の判例があります。
①暴行と死亡の間に時間的経過がある場合の因果関係の認定
名古屋高裁判決(昭和54年2月14日)
2歳7か月の幼児に対し、その前頭部を手拳で1回強打した暴行と、その9日位後に幼児が脳機能障害によって死亡した傷害致死事件で、医学的判断に基づいて、結果との間に因果関係を認めた事例です。
裁判官は、
- 医師の鑑定によれば、(1)被害者Wの死亡の直接の原因は、硬膜下出血による脳圧迫によって惹起された脳機能障害であること、(2)Wの死体の前頭部には、その髪際を中心として、手掌面大の皮下出血が存し、硬膜下出血は、皮下出血を生ぜしめた外力の作用によるものと考えられること、(3)皮下出血を生ぜしめた外力は、作用部位に角のない鈍体によるものと推定され、右出血が手拳によって生じたと考えて矛盾はないこと、(4)右外力の作用した時期は、6月23日の第一回ひきつけより以前、長くても1週間以内と推定されること、などの事実が認められる
- また、証拠を総合すると、(5)第一の暴行は、正座するWの前頭部髪の生えぎわあたりを手拳で強打したもので、被告人がWに加えた一連の暴行の中では、第二の暴行と並んで、もっとも強烈なものであったうえ、打撃の位置、方向が、同人の死体の頭部皮下出血の位置から推定されるそれと、おおむね一致すること(6)前記(4)記載の外力が作用したと推定される6月23日以前の1週間以内には、Wの頭部に対し、他に、右受傷の原因となり得るような外力が加えられた形跡がなく、被告人自身も、原審及び当審公判廷において、Wの死が、自己の右殴打行為により惹起されたとしか考えられない旨供述していること、などの事実が明らかである
- しかして、右(1)ないし(6)の各事実に、原判決が認定し、当裁判所がこれを是認する前記の諸事実をも綜合して考察すると、同人の死を惹起した前記硬膜下出血の少なくとも有力な一因は、被告人の第一の暴行にあったと断ぜざるを得ない
と判示し、医学的判断に基づいて、暴行と死の結果との因果関係を認め、傷害致死罪の成立を認めました。
福岡高裁判決(昭和58年4月25日)
被害者の襟首をつかんで押し倒して路面に後頭部を強打させた比較的軽微な暴行により、1か月余を経て発生した死亡に、医学的判断に基づいて因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとしました。
裁判官は、
- 医学部教授Hが、被害者Mの死体を解剖したところ、その右後頭葉右後面に縦約6cm、横約5cm大の範囲にわたりわずかながら圧平化が存し、かつ、その左前頭・頭頂部の硬膜下に血腫が存し、血腫直下の脳に縦約11cm、横約8cm大の範囲にわたり軽度の圧平化が存し、右血腫は既に一部硬膜と癒着、器質化していたこと、右硬膜下血腫は右解剖時よりも2週間ないし2か月位以前に発生したものであり、Mの死因は硬膜下血腫であること、これらの圧平化及び血腫の状態からすれば、Mの左前頭部か右後頭部のいずれかに転倒や鈍器による殴打などの外力が作用した蓋然性が大きいが、統計的には後頭部に外力が作用して前頭部を損傷する場合の方が、その逆の場合に比べて圧倒的に多いこと、硬膜下血腫には外傷性のものとそれ以外のものとが存するが、両者の差異は法医学者には歴然としていること、Mが右硬膜下血腫を受けた後、死亡するまでの間、受傷前と大差ない日常生活を送ったとしても、それは硬膜下血腫の症状と矛盾しないことを推認することができる
- 被告人は、路上約8メートルの間を、左手で空瓶を持ったMの右手首をつかまえ、右腕をMの首に巻きつけたり、右手でMのコートの襟首をつかまえたりしながら押し進んだため、Mが路上に仰向に転倒したことを推認することができる
- 事実関係を総合すると、被告人は、上記の態様でその間の約8メートルを押し進んだため、Mを路上に仰向けに転倒させて、路面でその後頭部を強打させ、自らも転倒したMの身体の上に重なり合うように倒れ込んだうえ、数分間右腕をMの首に巻きつけ、自己の上体をMの上体に乗せるなどしてMを押えつけ、Mに硬膜下血腫の傷害を負わせ、よってMを右傷害により死亡するに至らせたものであることを優に肯認することができる
と判示し、被害者が暴行を受けた後、1か月余を経て死亡した点について、医学的判断に基づいて因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとしました。
②死体の発見されない場合の因果関係の認定
東京高裁判決(昭和59年9月21日)
死体なき傷害致死事件において、関係者の供述や、専門家の鑑定などの医学的判断から、暴行と死亡との因果関係(外傷性ショック死)を認め、傷害致死罪が成立するとしました。
裁判官は、
- 本件は、死体が確保されていないため、死体が確保されていないため、死体の解剖検査による法医学上の精細なる鑑定を経ていない事件であることに留意を要し、事実認定は慎重であることを要するのはもとよりである
- しかし、M鑑定人は、「被害者Bは、殴打などの外力を受けるまでは、通常の生活をしており、特に身体に異常はなかったものと推定される。以前に胃潰瘍の手術を受けているらしいものの、受傷直前にその影響があったとは考え難い。Bは、1月4日から5日にかけて、長時間にわたり全身に繰り返し外力を受け、その結果、ほぼ上半身は青黒く変色し、腹部及び頭部に疼痛を来たし、しだいに活力が低下し、呼吸が苦しくなって死亡した。これらの経過から判断すると、外傷に起因して死亡が惹起されたことは明らかであろう。本例の死亡を引き起こした要因を外傷以外に求めることは、資料から見る限りありそうにない。すなわちBは外傷に起因して死亡したと推定される。」としたうえ、Bの身体に、「広範な皮下および筋肉内出血による失血と筋肉の挫砕、脳浮腫と、おそらくは肺浮腫、肝や腸間膜血管の損傷による失血、胃腸管の損傷による出血と浮腫など、あるいはこれらの病変のうちいくつかが起こったと考えられ、仮にそのようであれば、Bの死因は外傷性ショックとして理解できよう。」と判断し、「前記の資料からは、Bの死因としては、外傷性ショックが最も疑われる。外傷性ショック以外に考え難い。」というのである
- そうして関係証拠によれば、被告人がBに加えた暴行の内容、態様及びBの受傷の状況、更にBが死亡するに至る経緯が、M鑑定人の判断するところに相応符合するものであることが認められ、これらと各証拠とによって認められ、名ところをも併せ考慮すれば、Bの死因は、外傷性ショック死と十分に認定判断することができるのである
と判示し、死体のない事案について、傷害致死罪の成立を認めました。
③医学的判断による因果関係の認定
上記判例のほかに、医学的な判断により暴行と致死との因果関係が認められた判例を紹介します。
宇都宮地裁判決(昭和61年3月20日)
暴行の被害者である精神病院入院患者の死因につき、「向精神薬の副作用等による可能性が払拭できない」との被告人の弁護人の主張が排斥され、長期間にわたり大量投与された向精神薬による副作用による突然死の可能性を疑う余地はないとして、暴行と被害者の死亡との間に因果関係を認め、被告人らの暴行による外傷性ショック死であるとして、傷害致死罪の成立を認めました(字都宮病院リンチ事件)。
裁判官は、
- 本件暴行の態様、程度をみるに、金属パイプによる多数回にわたり、パイプが変形するほどの殴打、手すりにつかまって跳躍しながらの踏みつけ、最後にベッドからとび降りる勢いを利しての膝打ち等、極めて執拗かつ強烈なものといわざるを得ない
- D医科大学法医学教室医師Yが、「死因は、(1)外傷性ショック死、(2)後腹膜下出血、(3)脾臓ないし肝臓ないし腎臓破裂に基づく失血死、(4)腸間膜動脈損傷に基づく失血死、(5)外傷に基因する吐物吸引による窒息死(以上はいずれも広義の外傷性ショック死に含まれる。)の5つの可能性が考えられるが、そのうちでは(1)の外傷性シヨツク死が最も疑われる。被害者の死亡は向精神薬の副作用に基づくものではなく、死亡前3時間ないし4時間前に加えられた本件暴行に基づいて惹起されたものと強く推定される。」と判断しているのは、充分首肯することができる
- 殊に前認定の、被害者の血液混じりの吐物や血便等は、内臓損傷の存在及びそれが寄与しての外傷性ショック死であることを強く疑わせるものというべきである
- 従って、本件は、被害者の死体解剖がなされていない事案であるが、被害者の死因は、医師Yの鑑定が述べているように、被告人O、被告人K、被告人Hの暴行に基づく外傷性ショック死(広義)によるものと認めるほかなく、このように認定することは、本件暴行の態様、被害者の死に至るまでの経緯等からみて、何ら矛盾はないものと認められ、被告人O、被告人K亨、被告人Hの本件暴行と被害者の死亡との間には、法律上の因果関係が存在するといわなければならない
旨判示し、医学的判断のもとに、傷害と致死の因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとしました。
東京高裁判決(昭和61年5月13日)
被害者が、被告人の絞頸行為に先行して、他の者によって頸部に紐様のものを巻きつけられるなどの暴行を加えられ、これによる遷延性窒息死の可能性があるとの主張を排斥した事例です。
まず、弁護人は、
- 被告人が腰紐で被害者の頸部を絞める際に加えた力の程度は、本来、それだけで被害者を死亡させるほど強いものではなかったが、右行為に先立ち、被害者が本件当日、何者かによって首を締められるなどのいじめを受けて頸部に傷害を負い、かなり体力的に弱っていたため、これが原因となって不運にも死亡するに至ったものであるにもかかわらず、右の事情の存在を否定し、被告人の絞頸行為は、それ自体人を死亡させるに足りる十分危険なものである旨認定した原判決には、事実の誤認がある
と主張しました。
この主張に対し、裁判官は、
- 被害者が、本件当日午後2時30分頃、通学先の小学校から帰宅した際、その様子はいつもと違って元気がなく、被告人の質問に対して、学童からいじめられた趣旨と受けとれる答えをしたこと、当時、被害者の前頸部の中央部分に長さ6~7cm、幅1~2mmの、あたかも手首にゴム紐を巻いた際に生ずるような痕跡が生じていたことは、原判決の挙示する諸証拠によって明らかなところである
- これによれば、本件当日、被害者が何者かによっていじめられ、その際、その態様等を明らかにできる資料はないものの、頸部に紐様のものを巻きつけられるなどの暴行を加えられた可能性のあることを否定できない
- しかしながら、これをもって直ちに所論(※弁護人の主張)がいうように、被害者が被告人の行為に先行する右絞頸行為によって、遷延性窒息死するに至ったことを疑うべき余地があるということはできない
- すなわち、およそ人が絞頸などの頸部圧迫により遷延性窒息死に至る場合には、絞頸行為によって意識を喪失し、その後、死亡に至るまでの間に、一時意識を回復するという事態を生じないものであることは、原審第4回公判調書中の証人Dの供述部分によって明らかなところ、このことは、当審において取り調べた鑑定人Nの公判廷における供述に照らしても肯認できるところであり、いやしくも窒息者が一時蘇生し自力で道路を歩行するなどの行動をとり得るものとは到底考えられず、もしこのようなことがあったとすれば、絞頸と死亡との間に窒息を唯一直接の原因とする因果関係を認めることはできない
- 本件においては、被害者が帰宅当時その前頸部に生じていた痕跡は、前記のように軽度のものであり、一時的にしろ意識不明を伴う窒息状態を招来したとは推認し難いばかりでなく、被害者は本件当日の午後2時30分頃、学校から自宅までかなりの距離をランドセルを所持して自力で歩行して帰宅し、いつもよりは元気がない状態であったとはいうものの、帰宅後も特段苦痛を訴えた事実もなく、被告人の質問や叱責に対応できていたことが認められるのである
- したがって、被告人が原判示絞頸行為に及ぶ以前の時点において、既に被害者が遷延性窒息死に至るべき状態にあったものとは認められない
- そして、原判決の挙示する諸証拠によれば、被告人は被害者の頸部に巻いた腰紐の両端を両手で持って、同女がうめき声を発するまで強く締めつけたことを認めることができるのであって、被告人が被害者に対して加えた右の絞頸行為は、それ自体のみによっても被害者の死亡の結果を招来するに十分なものといわなければならない
と判示し、医学的判断をもとに、傷害と致死の因果関係を認め、傷害致死罪が成立するとしました。
因果関係の認定に「結果の予見可能性」は必要ない
暴行と死亡との因果関係を認めるに当たり、「結果の予見可能性」が必要かが議論されます。
結論は、暴行と死亡との因果関係を認めるに当たり、
死亡の結果の予見可能性は必要ない
というのが答えになります。
判例は、予見可能性の存在を要件としないとすることで一貫しています。
なお、行為者において全く予見しえないような結果に対しても、判例は当然に因果関係の存在を認める訳ではないないことを申し添えます。
この判例で、裁判官は、
- 傷害致死罪の成立には傷害と死亡との間に因果関係の存在を必要とするにとどまり、致死の結果についての予見は必要としない
と判示しました。
この判例で、裁判官は、
- 暴行により、特異体質の被害者をショック死するに至らしめたときは、致死の結果を予見する可能性がなかったとしても傷害致死罪が成立する
と判示しました。