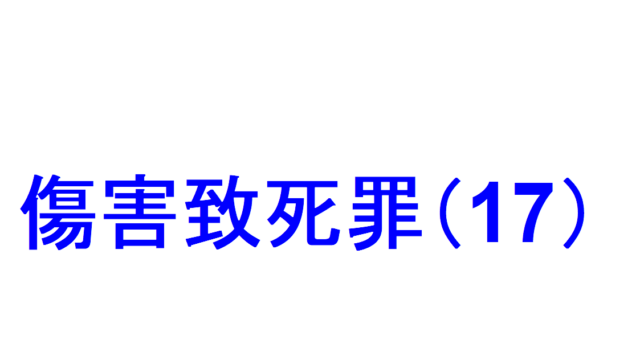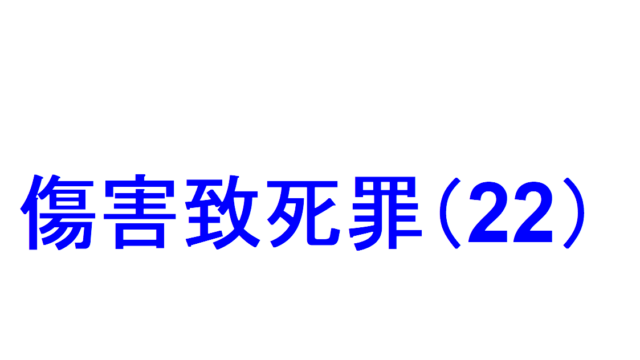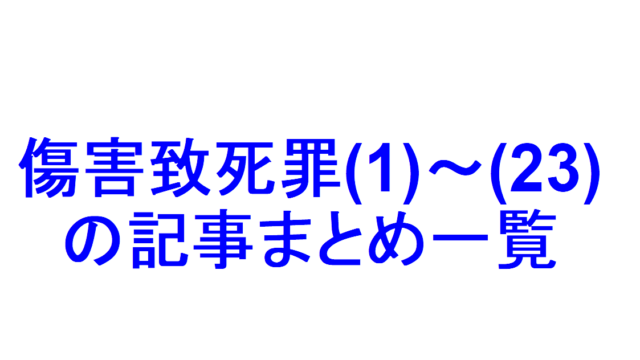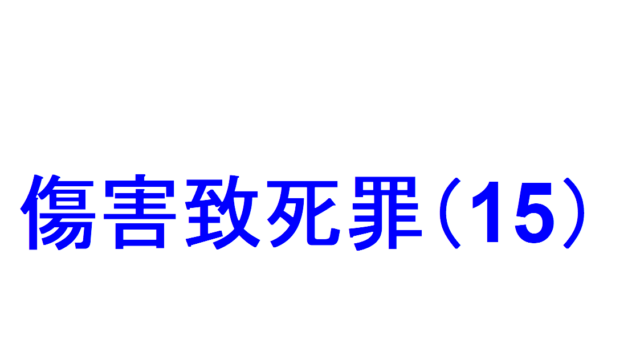傷害致死罪(21) ~「承継的共同正犯」「共犯関係からの離脱」「共犯者のどちらの暴行で致死にいたらせたか不明な場合における共同正犯の認定」を判例で解説~
前回の記事の続きです。
傷害致死罪における承継的共同正犯
承継的共同正犯とは
ある人(犯人A)が犯罪行為に着手し、その犯罪行為が終わっていない段階で、あとからやって来た人(犯人B)が、犯人Aと共謀し、残りの犯罪行為をAとBの両方で実行する場合
の犯罪形態をいいます(詳しくは前の記事参照)。
傷害罪致死罪において、承継的共同性が認められた事例として、以下の判例があります。
名古屋高裁判決(昭和47年7月27日)
被害者を暴力団事務所に連れ込み、いわゆるヤキ入れを行ったが、途中で、その後の処置につき指揮をとるため事務所に呼び出された組長の舎弟分である被告人が、これまでの暴行により傷害を負い衰弱していることを認識した上、自らも暴行を加え、更に、その後、事務所に帰った組長が激烈な暴行を加え、結局、被害者を死亡させた事案で、被告人に傷害致死全体の責任を認めました。
共犯関係からの離脱
傷害致死罪において、共犯関係からの離脱の有無が争点となった判例として、以下の判例があります。
この判例は、共犯関係からの離脱を認めず、共犯者に傷害致死罪の成立を認めた判例です。
Aは、Bと共謀のうえ、共同して被害者に対し暴行を加え、一段落した際、Bに対し帰る旨を告げて現場を立ち去ったが、その後にBが引き続いて暴行を加え、結局、被害者を死亡させるに至った事案です。
裁判官は
- 被告人が帰った時点では、Bにおいて、なお制裁を加えるおそれが消滅していなかったのに、被告人において格別これを防止する措置を講ずることなく、成り行きに任せて現場を去ったに過ぎないのであるから、Bとの間の当初の共犯関係が右の時点で解消したということはできず、その後のBの暴行も、右の共謀に基づくものと認めるのが相当である
と判示し、Aに対して共犯関係の離脱はなく、傷害致死罪が成立するとしました。
共犯者のどちらの暴行で致死にいたらせたか不明な場合における共同正犯の認定
東京高裁判決(昭和46年3月23日)
この判例は、暴行を共謀した者のうちで、被害者を日本刀で刺して死亡させたのが、被告人両名のいずれかではあるが、いずれの者か判断できないとして、暴行の共謀による傷害致死の限度で責任を認め、量刑した事例です。
裁判官は、
- 被告人A、Bは、被害者に刺傷を与えた実行者でもなく、また、その共謀者でもないものとしてその刑を考量すべきである
- 実行者がいずれともわからないからといって、その殺人の罪責を両者に分担させるような感じをもたせてはならないことは裁判の原則上当然の事理である
旨判示し、殺人罪で懲役7年に処した原判決は重すぎるとして、殺人罪よりも軽い傷害致死罪の量刑の基準で処断する判決を言い渡しました。
東京地判判決(昭和62年3月18日)
被告人両名の2歳の女児に対する傷害致死の事案で、裁判官は、
- その死因が長期間にわたり生じた多数の外傷が共同して引き起こしたニ次性の外傷性ショックであるか、一次的な外力の作用による一次性のショックであるかが特定できず、 また、被告人らの暴行の態様、程度等も具体的に特定できない場合であっても、被告人らに対して共謀による傷害致死の責任を間うことができる
としました。