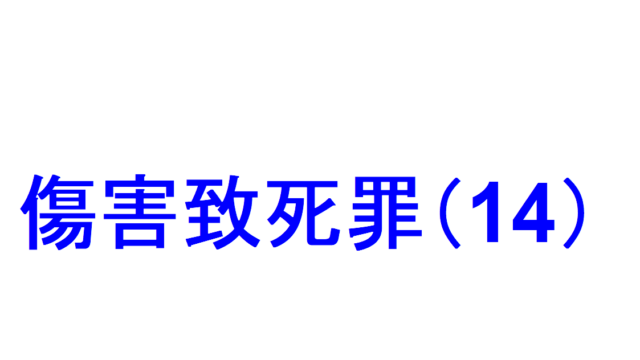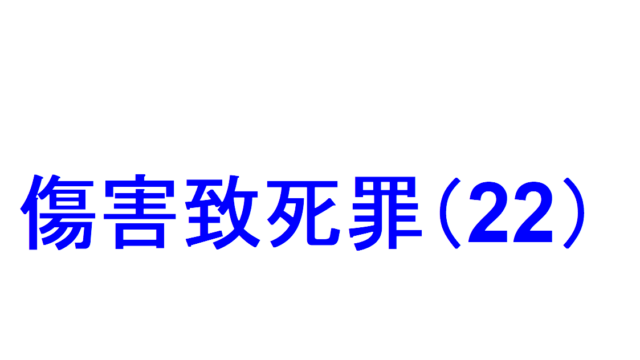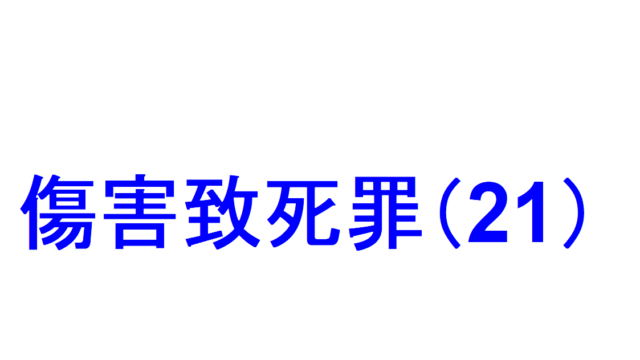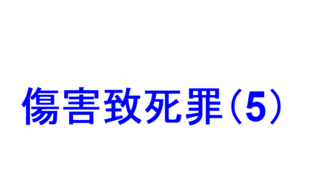傷害致死罪(4) ~「自動車を使った傷害罪・傷害致死罪②」を判例で解説~
前回の記事に続き、自動車を使った傷害罪・傷害致死罪についての続きを書きます。
「暴行・傷害の未必の故意」と「認識ある過失」の認定の判断
接触事故を繰り返しながら酩酊運転を行った行為については、「暴行・傷害の未必の故意」なのか、「認識ある過失」なのかの判断は微妙なところです。
「暴行・傷害の未必の故意」が認められれば、暴行罪・傷害罪・傷害致死罪が成立することになります。
「暴行・傷害の未必の故意」が認められず、「認識ある過失」に止まれば、暴行罪・傷害罪・傷害致死罪は成立せず、過失運転致死傷罪の成立することになります。
このあたりの判断は判例を検討しつつ、個別の事例ごとに判断することになります。
東京地裁判決(昭和48年11月2日)
嫌がらせ目的で、先行車Sを追抜く際に幅寄せし接触した上、S車両を対向車Kと衝突させた事案につき、運転者Sに対する関係では傷害罪が成立するとしましたが、対向車運転者Kに対する関係では、暴行ないし傷害の未必的故意を否定し、業務上過失傷害罪が成立するとしました。
裁判官は、
- 本件の訴因によれば、被告人の所為中、Kに対する点も傷害罪を構成するものとされており、検察官は、その理由として、被告人は、Sに対してばかりでなく、Kのような対向車の運転者に対してS車との衝突による傷害の未必的故意を有していたものであり、かりにこの未必的故意が認められないとしても、被告人のSに対する行為とKの傷害との間に相当因果関係が認められるから、そうである以上、Kに対しても傷害罪の成立があると述べている
- しかし、証拠によれば、被告人の本件所為は、もっぱらS車に対する急激な憤慨の情に発したもので、犯意としては、S車に接触するかも知れないとの未必的認識があったにとどまり、それ以上にS車と対向車との衝突までは考え到らなかったものと認めるのが相当である(実況見分調書等からうかがわれる本件現場における当時の交通量の程度も、いまだこの認定を妨げるものではない。)
- すなわち、Kに対する暴行ないし傷害の未必的故意を認めることは困難である
- 被告人のSに対する行為とKの傷害の間に相当因果関係の認められることは、検察官所論のとおりであるが、Kに対する暴行の未必的故意を認めえない以上、Kに対する傷害罪は成立しないものと解すべきである
と判示しました。
東京地裁判決(昭和49年11月7日)
この判例は、上記判例とは反対に、相手車両と対向車双方の搭乗者に対する暴行の故意を認めた事例です。
被告人がAにいやがらせをしようと自動車を幅寄せしたところ、ハンドル操作を誤って自車をA車に衝突させ、AとA車の同乗者B、Cに傷害を負わせたうえ、A車を反対車線に押し出し、D車に衝突させ、Dに傷害を負わせ、D車の同乗者のEを死亡させた事案につき、幅寄せが暴行に当たるとしてA、B、C、Dに対する傷害罪、Eに対する傷害致死罪の成立を認めました。
この判例は、
- 自動車で高速道路を走行中、併行して進行している右隣の自動車に対していやがらせ等のために、自車をその至近距離にまで接近させる行為が刑法208条の暴行に当たると認定した点
- ABC3名に対して暴行を加え、その結果、ABC3名のほか、予想しなかつたD、Eについても傷害を負わせるとともに、Eを死亡させた行為につき、暴行の際にA~Eの5名の傷害の結果発生に対する過失も認められる状況にあったとして、A、B、C、Dに対する傷害罪、Eに対する傷害致死罪の成立を認定した点
が注目されています。
裁判官は、
- 被告人の所為は、「A車の車内にいる者にいやがらせをしてやろう。」という意図の下に被告車の車体右側をA車の車体左側至近距離に接近させた点がAとBとCとの3名に対する暴行の故意に基づく暴行行為に該当し、右暴行行為とその最中における過失行為とにより、右3名にいずれも傷害を負わせた点はそれぞれ刑法204条の傷害罪に該当し、右3名に対する前記暴行の故意に基づく前記暴行行為とその最中における判示過失行為とによりDに傷害を負わせた点も刑法204条の傷害罪に該当し、AとBとCとに対する前記暴行の故意に基づく前記暴行行為とその最中における過失行為とにより、Eを死亡させた点は刑法205条の傷害致死罪に該当する
- この行為は、1個の行為で5個の罪名に触れる場合であるから刑法54条1項前段、10条により一罪として最も重いEに対する傷害致死罪の刑で処断することとした
判示しました。
大阪地裁判決(昭和58年4月4日)
被告人運転車両に衝突の危険を生じさせながら逃走した相手車両を追跡し並進するに至った際、相手車両を停止させようとして、相手車両の進路右前方に自車を進出させたため、両車両が衝突、接触し、相手車両が電柱に激突して、相手車両の同乗者が死亡し、運転者が負傷した事案につき、傷害の未必的故意を認定した事例です。
裁判官は、
- 高速で走行する自動車同士が衝突すれば、これに乗車している者の身体に何らかの傷害を負わせることになることは経験則上明らかなことで、被告人が両車両の衝突を未必的に認容していた以上、本件被害者両名に対する傷害の未必的な故意があったものといわざるをえない
と判示し、被告人には傷害の未必の故意があったとして、傷害罪の成立を認めました。
東京高裁判決(平成7年4 月25日)
自動車を運転していた被告人が、暴走族が暴走していると思って自動二輪車を追跡し、 自車を追突させて運転者Aを死亡させた事案につき、暴行の故意があったとして、傷害致死罪の成立を認めました。
裁判官は、
と判示し、傷害致死罪の成立を認めました。
警察官から逃走を図り、警察官を死傷させる場合は、暴行の故意が明確である
警察官から車両の停止を求められるなどしたが、逃走を図り、その際、警察官を死傷させた場合は、一般の歩行者や車両に対するよりも、加害の対象、目的が特定されており、暴行の故意が明確である場合が多いです。
警察官から逃走を図り、警察官を死傷させた行為について、傷害罪や傷害致死罪の成立を認めた事例として、以下の判例があります。
岐阜地裁判決(昭和48年7月19日)
飲酒運転中、追跡中の白バイの進路を妨害してこれに接触し、逸走させて運転中の警察官を転落死させた事案につき、傷害致死罪の成立を認めました。
裁判官は、
- 被告人は、白バイが追い上げて、自車に接近するのを認めるや、白バイに追抜きを許せば停車を余儀なくされて、酒気帯び運転等が発覚するのを恐れるあまり、白バイの進路を妨害して追抜きを阻止し逃走しようと決意し、ハンドルを必要以上に右に切って自車を白バイの進路上に進出させ。K巡査に接近させる暴行を加えた結果、自車の右後部を右白バイの前輪付近に接触させて、同車の操縦の自由を失わせたうえ、道路左側の堤防上に逸走させ、K巡査を約4.6メートル下方の農業用排水路に転落させて頭部打撲の傷害を負わせ、よつて、K巡査を右傷害に基づくクモ膜下出血により即死させた
と罪となるべき事実を認定し、傷害致死罪の成立を認めました。
福岡高裁判決(昭和52年2月3日)
他人が運転席の右側窓枠をつかんでいるのに、これを振り切ろうと自動車を走行させることが、暴行罪に当たるとした事例です。
停止を求めて、 自車をつかんだ警察官Aを振り切ろうと加速走行することが、暴行の故意に基づくと認定し、その走行行為で警察官Aにけがを負わせたことについて、傷害罪の成立を認めました。
裁判官は、
- 被告人の所為は、単なる自動車の走行行為ではなく、自車の窓枠を手でつかんで追従するAを振切ることを意図し、故意に約200メートルの区間にわたり急に加速したり減速したりしながら平均時速約23キロメートルの速度で自車を進行させたものであるから、右走行行為がAに向けられた有形力の行使であることは明らかである
- Aはその当初、自己の意思で被告車の窓枠をつかんだものであるが、それは被告車を引き止めるための行動であって、その後の段階における追従走行、とりわけ前示約200メートルの間にわたり強引に引張られる状態でのAの走行がAの意思に反したものであることは否定できないところである
と判示しました。
東京高裁判決(昭和56年6月24日)
白バイで追跡してきた交通取締警察官を自車を急転把させて転倒させ、轢過して死亡させた事案につき、傷害の故意を認め、傷害致死罪の成立を認めた事例です。
裁判官は、
- ダンプカーが白バイと衝突する直前に急激に右に進路を変えようとした際、換言すれば、被告人が右に急転把しようとした際、被告人が、K巡査が乗車する白バイがダンプカーの右側方に追随して来て、右前部の運転席近くを走行していること、及びその進路前方に向けダンプカーを急激に右転把すれば、K巡査が安定を欠き、その運転の自由を失うか、又はダンプカーが白バイに衝突するかして白バイを転倒させ、K巡査に傷害を負わせることがあることをそれぞれ認識していたこと、並びにそれにもかかわらず白バイの進行を妨害するために、敢えて急激な右転把をしたことを認めるに十分である
- 被告人は、すぐ本件衝突地点近くの歩道上へ戻って来たところ、近所の住民や本件衝突を目撃した自動車運転者ら十数人が、「ひどいことをするもんだね。誰がやつたんだろう。」などと話をしているのを聞き、「俺だよ。」、「あんな文句をつけるから、こういうことになるんだ。」、「ざまをみやがれ、いい気味だ。」などと口走り、何ら慌てたり、悪びれたりする様子がなかった
- 被告人には、傷害の故意があったと断ぜざるを得ないのである
と判示し、傷害の故意を認め、傷害致死罪の成立を認めました。
福岡高裁判決(昭和56年7月13日)
暴走族取締り中の警察官の直近を自動二輪車を加速して通り抜けようとし、その警察官に衝突死亡させた行為について、暴行の故意を認め、傷害致死罪が成立するとしました。
裁判官は、
- 警察官との距離が未だ約27メートルもある段階で、すでに東側歩道に3、4メートル位にまで近づいて来ている同人らを認めていながら、その直前をそれまでの時速約60キロメートルをさらに約70キロメートルに加速して通り抜けようとさえしていること、しかもその際、ことさら顔を伏せ、前方をよく見ないで運転し、東側歩道端から1.5メートルないし2メートルくらいの部分をほぼ一直線に進行して、T巡査にほとんど正面衝突し、同人を即死させていること等の事情は証拠上疑いがない
- 以上の状況に徴すれば、被告人としても、自車を時速70キロメートルもの高速度でT巡査らの至近距離に接近、通過させることが危険であり、これに対する同人らの対応の仕方如何によっては、自車を同人らに衝突させる事態を招来することぐらいは、認識していなかったとは考えられないからである
- これに被告人が頭をハンドルにつけ、前かがみの姿勢で前をよく見ないで運転したことについては、捜査段階の間を通じほぼ一貫して、警察官に衝突するかもしれないと思い身を守るためにしたとの旨述べており、この供述は前記の状況に照らし十分信用できると思われること、原審第一回公判では自車を警察官に衝突させるかも知れないと認識していたことを認めていることを合わせて考えると、すくなくとも被告人は、自車をT巡査の至近距離に接近させる際、これを同人に衝突させ、負傷させるかもしれないことを認識しながら、それもやむを得ないと認容していたものと認めるのが相当である
と判示し、暴行の故意を認め、傷害致死罪の成立を認めました。
特殊な事例
特殊な事例として、以下の判例があります。
東京高裁判決(昭和63年5月31日)
過失により被害者を自車底部に巻き込みんで重傷を負わせ、その後に傷害の故意を生じ、さらに運転を続行するという加害故意に及んだ結果、被害者を死に至らせたが、死因となった負傷が右いずれの行為によるものか不明の場合であったため、業務上過失致死罪の成立が否定され、業務上過失傷害罪と傷害罪の二罪が成立し、両者は併合罪になるとしました。
裁判官は、
- 被告人の最初の発進時からバス停留所到着時までの間の行為は、業務上過失傷害罪を、同所の発進時から振り落とし行為終了時までの間の行為は傷害罪をそれぞれ構成し、両罪は併合罪の関係にあるものというべきであるから、原判決が両者をひっくるめて一個の業務上過失致死罪としたのは、事実を誤認したものである
と判示しました。