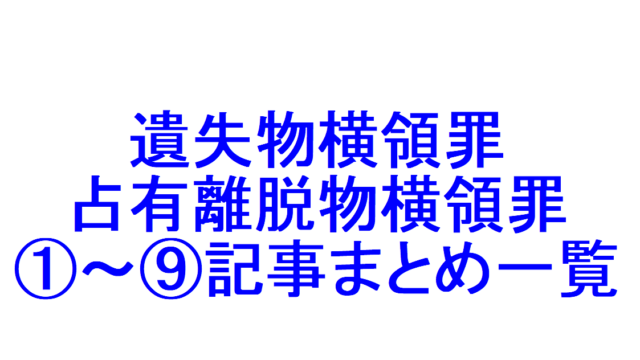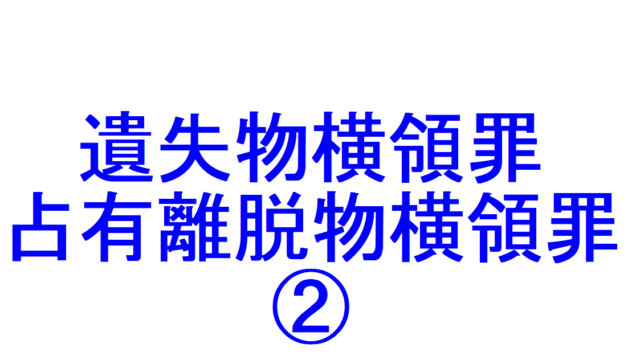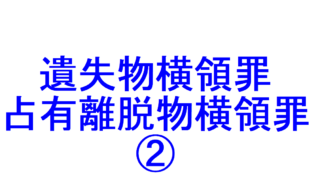前回の続きです。
前回は、『「占有を離れた」と認められ、窃盗罪は成立せず、遺失物等横領罪が成立した判例』を説明しました。
今回は、これとは反対に、『「占有を離れた」と認められず、遺失物等横領罪が成立せず、窃盗罪が成立するとした判例』を説明します。
「占有を離れた」と認められず、遺失物等横領罪は成立せず、窃盗罪が成立するとした判例
判例において、窃盗罪(刑法235条)で起訴された事案で、所有者等の占有を離れていたとして、遺失物等横領罪(遺失物横領罪・占有離脱物横領罪)(刑法254条)にとどまるとされた判例が数多くあります。
どのような判断基準で、窃盗罪になるのか、それとも遺失物等横領罪になるのかは、判例の傾向をつかんで理解していくことになります。
判例を読んでいくと、占有の有無の判断に当たり、重視されたと思われる事由について、以下の4つの類型に整理することができます。
- 施設等管理者当の支配領域内にあることを重視したと思われるもの
- 時間的・場所的接着性を重視したと思われる物
- 所在場所及び財物の性質等が重視されたと思われるもの
- 帰還する習性を備えた家畜等
それでは、この4つの類型ごとに、判例を紹介していきます。
① 施設等管理者等の支配領域内にあることを重視したと思われるもの
放置された財物であっても、
- ⑴ 未だ所有者等の包括的支配下にあると認められる場合
- ⑵ その場所等を管理する者のいわば第二次的な占有に包摂されると解される場合
には、「占有を離れた」とはいえず、その放置された財物を領得しても、遺失物等横領罪には当たらず、窃盗罪が成立します。
まず、『⑴ 未だ所有者等の包括的支配下にあると認められる場合』の判例として、以下のものがあります。
大審院判例(大正15年10月8日)
この判例は、
- 飲食店の女主人が、他人から預かっていた財布を店内の階段のかたらわに放置し、その所在を見失っていたとしても、それが屋内に存する限り、女主人の占有を離脱しておらず、第三者がこれを不法に領得すれば窃盗罪が成立する
としました。
東京高裁判例(昭和31年5月29日)
この判例は、
- 倉庫内に納められた物については、倉庫保管責任者において、その存在や数量を知らないとしても、倉庫内に納められた以上は、これに対する保管の意思を有していたものと解され、これを領得した被告人には、窃盗罪が成立する
としました。
次に、『 ⑵ その場所等を管理する者のいわば第二次的な占有に包摂されると解される場合』の判例として、以下のものがあります。
大審院判例(大正8年4月4日)
この判例は、旅館の便所内に宿泊客が忘れた財布について、
- 財布の所有者の占有からは離脱しているが、旅館主が、その財布を認知しているか否かにかかわらず、その財布は、旅館主の占有下にある
として、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪の成立を認めました。
札幌高裁判例(昭和28年5月7日)
この判例は、旅館の脱衣場に入浴の際に宿泊客が忘れた腕時計について、
- 腕時計の所有者の占有からは離脱しているが、旅館主が、その財布を認知しているか否かにかかわらず、その腕時計は、旅館主の占有下にある
として、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪の成立を認めました。
大審院判例(大正11年9月15日)
銀行の事務室内で、支払主任が机の下に落とし、それに気付かないまま放置されていた銀行所有の札束を、銀行員が帰宅した後に清掃中の用務員が見つけて領得したという事案で、
- 札束は、支払主任の占有を離れたとしても、銀行建物管理者の占有に属する
として、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪の成立を認めました。
高松高裁判例(昭和25年6月2日)
被害者が県の交通自動車停留所に置き忘れ、その停留所を兼ねた県交通自動車営業所内のごみ箱の上に置かれていた女性用革靴につき、被告人が、その営業所の用務員から「あなたのですかと尋ねられた際、とっさに「私の靴です」と虚偽の答えをして持ち去った事案で、
- 女性用革靴は、自動車営業所の管理人の占有下にあった
として、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪の成立を認めました。
この判例は、営業所のごみ箱の上という放置場所の性質のほか、営業所の関係者が所有者を尋ねるという管理者的行動を採っていたという特殊事情を考慮し、営業所の管理人の占有を認めたものと考えられています。
東京高裁判例(昭和33年3月10日)
公衆電話を利用した者が、電話機内に放置した硬貨を被告人が領得したという事案で、
- 硬貨は公衆電話を管理する電話局長等の管理に服する
として、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪の成立を認めました。
なお、この判例については、電話局長等による硬貨に対する客観的支配が弱いことを理由として、占有を認めたことに疑間を呈する見解もあります。
② 時間的・場所的接着性を重視したと思われるもの
被害者が置き忘れた物に関しては、
- 被害者が置き忘れるなどした後、犯人がそれを領得するまでの時間が短い(時間的接着性)
かつ、
- 犯人がそれを領得した時点における被害者と財物との距離関係(揚所的接着性)も短い
という場合に、被害者の占有がなおも及んでいるとして窃盗罪の成立が認められる傾向にあります。
道路・駅の構内・公園など、不特定多数者が出入りする開放的空間における置き忘れ事案の判例
被害者がバスを待つ間に、行列中に一時置き忘れたカメラについての占有の有無が争われた事案で、裁判官は、
- 刑法上の占有は、人が物を実力的に支配する関係であって、その支配の態様は、物の形状その他の具体的事情によって一様ではないが、必ずしも物の現実の所持又は監視を必要とするものではなく、物が占有者の支配力の及ぶ場所に存在するをもって足りると解すべきである
- しかして、その物が、なお占有者の支配内にあるというを得るか否かは、通常人ならば何人も首肯するであろうところの社会通念によって決するのほかはない
- 本件カメラは、被害者がバスを待つ間に、身辺の左約30cmのコンクリート台の上に置いたものであったこと、被害者は行列の移動に連れてそのまま改札口の方向へと進んだが、カメラを置いた場所から約19.58m進んだ地点で置き忘れに気付き、直ちに引き返したが、その時には既に被告人がこれを持ち去っていたこと、行列が動き始めてからその場に引き返すまでの時間は約5分であったことなどの事実関係を客観的に考察すれば、カメラはなおも被害者の実力的支配のうちにあったもので、占有を離脱した物とは認められない
と判示し、被害者の占有は未だ失われていないから、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪が成立するとしました。
東京高裁判例(昭和35年7月15日)
被害者が、混雑時の渋谷駅の山手線の出札口で切符を買った際に、出札口の台の上にカメラを放置し、友人と話しながら5分を超えない時間内に10mくらい歩いたところで置き忘れに気付き、すぐに引き返したが、その間に被告人が持ち去った事案で、裁判官は、
- 刑法上の占有は、人が物を実力的に支配する関係であって、その支配の態様は、物の形状その他具体的事情によって一様ではないが、必ずしも物の現実の所持又は監視を必要とするものでなく、物の占有者の支配力の及ぶ場所に存するをもって足りる
- また、その物がなお占有者の支配内にあるかどうかは、通常人ならば何人も肯首するであろうところの社会通念によって決すべきである
- 本件における事実関係においては、社会通念上、本件カメラの占有は、なお被害者にあるものと判断すべきであり、本件場所が東京都内でも最も乗降客の多い渋谷駅付近であり、時間も最も混雑する頃で、人が相当混雑していたと思われること及び5分間も経っていたことを理由として、被害者の占有が失われ、本件カメラは、占有離脱物であるとすることは、当たらないといわなければならない
と判示し、被害者のカメラに対する占有は失われていないと判断しました。
この判例は、結論として、客観的には窃盗罪が成立するが、犯人の内心は、窃盗の故意ではなく、占有離脱物横領の故意でカメラを領得していることから、占有離脱物横領罪が成立すると判決しています。
理由は、窃盗罪や占有離脱物横領罪のような故意犯については、故意がなければ犯罪は成立しないという刑法のルール(刑法38条)になっているからです(詳しくは前の記事参照)。
東京高裁判例(昭和54年4月12日)
被害者が、東京駅の新幹線の特急券窓口で特急券を購入した後、すぐその足で乗車券窓ロに行って乗車券を購入したが、その時になって財布を特急券窓ロに置き忘れたことに気付き、慌てて引き返したが、既に被告人がその財布を持ち去っていた事案で、
- 財布を忘れたことに気付くまでの時間は約1, 2分で、窓口間の距離も約15.6m あったことから、被害者の財布に対する占有は失われていない
として、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪が成立するとしました。
福岡高裁宮崎支部判例(昭和29年4月23日)
露天店近くで被告人と話しをしていた被害者が、その場を立ち去る際、酒に酔っていたため、手提げ鞄を被告人の前に置き忘れ、約300m歩いたところでこれに気付いて直ちに通りがかりの車で引き返したが、その間に被告人が手提げ鞄を持ち去ったという事案で、
- 手提げ鞄は、露天商の店主の管理内にあったとは認められないが、犯人以外の者の支配力が及ぶ場所内に一時的に置き忘れられたに過ぎない
- しかも、その置いた場所が判然としていることなどから、未だ遺失物とはいえない
として,遺失物横領罪ではなく、窃盗罪の成立を認めました。
被害者が公園のベンチの上にポシェットを置き忘れ、ベンチから約27m離れた地点まで歩いて行った時点で、被告人がそのポシェットを領得した事案で、裁判官は、
- 被害者がこれ(ポシェット)を置き忘れてベンチから約27mしか離れていない場所まで歩いて行った時点であったことなど本件の事実関係の下では、その時点において、被害者が本件ポシェットのことを一時的に失念したまま現場から立ち去りつつあったことを考慮しても、被害者の本件ポシェットに対する占有はなお失われておらず、被告人の本件領得行為は窃盗罪に当たる
と判示しました。
東京高裁判例(昭和35年7月26日)、最高裁判例(昭和37年5月18日)
列車の出口近くの席に座って仮睡中であった被害者が、終着駅に到着した際、網棚の上にショルダーバッグを置き忘れたまま慌てて下車したため、近くにいた被告人が他の乗客が未だ全部降りきらないうちに素早くこれを持ち去ったという事案で、
- 被害者が立ち去ってから犯人がこれを領得するまでの時間が極めて短い
- 被害者のショルダーバッグに対する占有は、依然として継続していた
として、諸事情を総合判断した上、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪の成立を認めました。
広島高裁判例(昭和35年12月15日)
被害者が道端で休息した後に、数メートル先の草刈り場に行くために立ち上がった際、腕時計を路上に落としたのを、その場で目撃していた被告人が、被害者が立ち去ると同時にそれを拾い上げて、密かに持ち帰った事案で、遺失物横領罪ではなく、窃盗罪の成立を認めました。
大阪高裁判例(昭和35年12月23日)
映画館内の観覧席後方で泥酔していた被害者が、誤ってポケットから落とした札束を、1m足らずの距離で並んで映画を立ち見していた被告人が、靴で踏んで隠し、間もなく被害者が映画館から連れ出されると、それを拾い上げて領得したという事案で、遺失物横領罪ではなく、窃盗罪の成立を認めました。
名古屋高裁金沢支部(昭和45年3月10日)
この判例は、時間的・場所的接着性に加えて、
閉鎖的空間に置かれていること
も考慮して占有の継続を認めた判例です。
被害者が、10名以内の特定の者のみが使用する飯場の敷地内にある風呂場で入浴する際、現金等在中の免許証入れを柱等の隙間に差し入れたまま置き忘れ、飯場に戻って数時間失念していたところ、その間に被告人が持ち去ったという事案で、裁判官は、
- たとえ所有者において物の存在を一時失念していたとしても、その物に対する支配力を推及するに相当な場所的時間的範囲内にあり、かつ所有者の支配意思が明確に認められるものは、占有を離脱したものとはいえない
などと判示し、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪の成立を認めました。
被害者が置き忘れたのではなく、あえてその場所に置き去りにしておいたものを領得した場合の判例
大阪高裁判例(昭和30年2月7日)
市場で買い物をしていた被害者が、購入した食品類を竹籠に入れて上から風呂敷を掛け、駅のガード下の道路端に置き、他の店に預けてあった品物を取りに行って引き返して来るまでの間に、被告人がこれを持ち去った事案で、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪を認めました。
東京高裁判例(昭和30年3月31日)
被害者が列車を待ち合せ中、乗客の列の中にボストンバッグと手提げかばん各1個を置いたまま約10分間その場を去って電報を打ちに行ったところ、犯人がその隙にこれらを領得した事案で、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪の成立を認めました。
大阪高裁判例(昭和25年5月10日)
進行中の列車から白米を投げてもらって受け取った被害者が、巡査の制服姿の被告人らの姿を見て、食糧の不法輸送のかどでの取調べを受けるのをおそれ、その場に白米を置き去って付近に隠れ、監視していたところ、被告人らがその事情を知りながら領得した事案につき、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪の成立を認めました。
名古屋高裁判例(昭和31年3月5日)
被害者が飲食店で飲酒した後、深夜、自転車を引きながら店から約80m離れた人家が軒を連ねた地点まで至ったところで、店に忘れ物をしたことに気付き、自転車(比較的新しく、自己の住所氏名をペンキで明記したもの)を路上に施錠をせずに立て置いたまま店まで引き返し、すぐに戻ってきたところ、被告人がその間に自転車を持ち去っていたという事案で、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪の成立を認めました。
被害者が歩道の端にあったゴミ箱の上にカメラ等在中のショルダーバッグとカメラの三脚を置いて、約7m離れた店舗の中に入り、表戸を開けたまま約5分間とどまっていたところ、その間に被告人がショルダーバッグを持ち去ったという事案で、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪の成立を認めました。
名古屋高裁判例(昭和52年5月10日)
被害者が名古屋駅構内にある高速バスの待合室で休息中、室内には利用客が数人しかおらず、比較的閑散としていたことから、食事をとるべく待合室のすみの床の上に旅行かばん(幅約50cm,高さ約2.30cm)を置いたまま、約203m離れた駅構内の食堂へと出かけ、約35分後に戻ったが、被害者が食堂に出かけた直後にその様子を見ていた被告人が旅行かばんを持ち去った事案で、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪の成立を認めました。
東京高裁判例(平成21年7月1日)
開店中のファーストフード店の店内で、アルバイト清掃員がトイレ前に設置された収納棚の上に、自己の携帯電話機を置いて清掃作業に従事していたため、被告人がこれを見つけて領得したという事案で、
- 被害品があった場所は、開店中の店舗内ではあったが、客全員を移動させて清掃作業に従事していたことから一種の密室構造の場所であったこと
- 被害者と被害品との距離が約10mであったこと
- 携帯電話機という社会的に高度に有用な有価物であり,その所有者がいることは被告人にも分かっていたと推認できること
などを理由として、被害者の占有を肯定し,占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪が成立するとしました。
暴行等の事件の被害者が被害を受けている最中に現場付近に落とした物を犯人が見つけて持ち去った事案の判例
大審院判例(昭和8年7月17日)
傷害の犯行の過程で暴行を受けていた被害者が、たまたま落とした財布の中から被告人が金銭を抜き取った事案で、被害者の占有が肯定され、遺失物横領罪ではなく、窃盗罪が成立するとしました。
東京高裁判例(昭和30年4月28日)
強姦未遂の被害者が、被告人につかまれた手を振り切って逃げようとした弾みに付近に落とした腕時計を被告人が持ち去った事案で、被害者の占有が肯定され、遺失物横領罪ではなく、窃盗罪が成立するとしました。
名古屋高裁判例(昭和32年3月4日)
強盗未遂の犯行を受けた被害者が、逃げる途中に道路上に落としていった物を被告人が持ち去った事案で、被害者の占有が肯定され、遺失物横領罪ではなく、窃盗罪が成立するとしました。
判例の傾向分析
以上の置き忘れられた物に対する占有に関する判例を見ると、被害者の占有の継続の有無を判断するに当たり、
- 被害者が当該財物を置き忘れてから犯人がそれを領得するまでの時間や、犯人がそれを領得した時の被害者と財物の距離(時間的・場所的接着性)
- 置き忘れた場所の状況や見通し状況
- 被害者の認識及び行動(被害者が置き忘れたことに気付いて引き返したかどうか、引き返した場合には引き返すまでの時間や、置き忘れた地点と引き返した地点との距離関係、置き忘れた場所を記憶していたかどうかなど)
- 犯人が被害者の置き忘れた状況を目撃していたかどうか
を考慮していることが分かります。
考え方として、刑法上の占有が物に対する実力的な支配である以上は、置き忘れ事案に関しては、まず何よりも、財物及び放置場所の性質とともに、犯人による領得行為がされた時点における被害者と物との時間的・場所的接着性に着目することになります。
被害者が置き忘れに気付いて引き返した地点や、引き返すまでの時間、被害者が置き忘れた状況を被告人が目撃していたかどうかという点も、被告人の窃盗の故意を認定する前提事情として認定されている場合が多いです。
③ 所在場所及び財物の性質等が重視されたと思われるもの
上記判例のように時間的・場所的接着性があるとはいい難いが、
財物の特性やその所在場所
などから占有を肯定したと思われる判例として、以下のものがあります。
財物の性質と財物が所在する場所の性質に照らし、社会通念上、他者の占有が及んでいると認めたといえる判例
大審院判例(大正3年10月21日)
看守者がいない寺の建物内に安置されていた仏像を領得した事案で、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪の成立を認めました。
最高裁判例(昭和31年2月14日)
北海道内の村有林内で、他人が盗伐・放置してあった木材を、被告人が運び出して領得した事案で、裁判官は、
- 村有林の管理者である村長において、その木材の存在を知ると否とを問わず、それが村有林内にある限り村長の占有下にあり、森林窃盗に当たる
判示し、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪が成立するとしました。
ゴルファーが誤ってゴルフ場内の人工池に打ち込み放置したロストボールに対して、裁判官は、
- ゴルフ場側においては、早晩その回収、再利用を予定していたというのである
- 右事実関係のもとにおいては、本件ゴルフボールは、ゴルフ場側の所有に帰していたのであって無主物ではなく、かつ、ゴルフ場の管理者においてこれを占有していたものというべきである
- ゴルフ場側がその回収、再利用を予定しているときは、ロストボールは、ゴルフ場側の所有及び占有にかかる
と判示し、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪が成立するとしました。
収納の困難性・煩雑さという意味での財物の性質と財物が所在する場所に着目して占有を認めたといえる判例
東京高裁判例(昭和30年5月13日)
縁日ごとに営業する露店業者が、夜間照明のため共同で使用し、閉店後は仮設電柱から取り外して輪巻きにし、責任者が片付けるまでの間、一時的に道端に分散して置くのを常としていた電燈用ソケットが付いた電線を、道端に置いてある間に被告人が持ち去ったという事案で、
- 未だ保管者である露店業者の代表者の支配を離脱したとはいえない
として、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪の成立を認めました。
東京高裁判例(昭和36年6月21日)
水田に取り囲まれた幅員約2mのあぜ道内で、持ち主の居宅からも見通しが利く場所に置いてあった農耕用一輪車を被告人が領得したという事案で、
- 農家の者が、使用の便宜上、放置している物かその場に一時置き忘れた物であるかのいずれかであることが窺い知れるから、未だ持ち主の占有下にある
として、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪の成立を認めました。
一時的に駐輪してある自転車についての判例
路上や駐輪場に一時的に駐輪してある自転車については、社会通念上、所有者の占有下にあると認められる場合が多いです。
自転車については、自転車が置かれていた場所などから、
一時的な駐輪と推知できるかどうか
が判断の分かれ目になるといえます。
写真材料店の雇人が、慌てて店の戸締りをしたために、屋内に取り入れるのを忘れ、夜間、店の角から1.55m離れた隣家の公道上の看板柱の傍らに立て掛けたまま放置されていた店主の自転車を、被告人が、翌早朝午前3時頃に持ち去ったという事案で、裁判官は、
- 客観的に見ても、写真材料店方に属する物件の置場所と認められる同店北側角より1.55mの地点にある同店隣家の公道上の看板柱のそばに立掛け置いたこと
- 人がその所有物を屋内に取り入れることを失念し、夜間これを公道に置いたとしても、所有者において、その所在を意識し、かつ、客観的に見て、該物件がその所有者を推知できる場所に存するとき、その物件は常に所有者の占有に属するものと認められる
と判示し、自転車は未だ店主の占有に属するとして、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪の成立を認めました。
高松高裁判例(昭和37年10月27日)
パチンコ店の店員が、午後10時頃に帰宅する際、雨が降っていたため、店の前の歩道上に駐輪していた通勤用の自転車を店舗内にしまうように他の店員に依頼して帰宅したところ、その店員が自転車をしまい忘れたため、翌午前0時頃に被告人が持ち去ったという事案で、
- 自転車は、未だ所有者の占有下にあった
として、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪の成立を認めました。
福岡高裁判例(昭和58年2月28日)
昼頃に自転車で市場にやってきた被害者が、市場内の居酒屋で飲酒をした後、自転車を近くの人道専用橋の上に無施錠で止めたまま、約600m離れた自宅に帰宅し、翌朝これを取りに行ったところ、先立つ午前3時頃(放置されて約14時間後)に被告人が自転車を乗り去っていたという事案で、
- 上記橋が隣接する市場に来る客の事実上の自転車置き場になっており、終夜、自転車を置いたままになっていることが度々あったこと
- 本件自転車が新品で、被害者の名前の記入があり、前かごには被害者の持ち物も入っていたこと
などを理由に、自転車は未だ被害者の占有下にあるとして、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪の成立を認めました。
震災などで、持ち主が物を握持していないことに特別な事情がある場合の判例
大審院判例(大正13年6月10日)
氏名不詳者が、関東大震災の際に、一時ほかの場所に避難するために公道に搬出していた布団等を、被告人が持ち去った事案で、
- 一時的にその場を離れた場合でも、所有者がその物の存在を認識し、かつ、これを放棄する意思でなかったときは、その物は所有者の支配内を離脱した物ではない
などと判示して、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪の成立を認めました。
この判例に対しては、占有意思を重視しすぎているとか、客観的な支配が全く認められないなどとして疑問を呈する見解もあります。
一方で、大震災という特殊な状況や、布団という運搬が容易でない物であるなどの事情から、占有を推知させる客観的状況があったといえるとする見方もあります。
判例の結論としては、大震災のような特別な状況下においては、放置物件や放置状況などから他人の占有下にあると推認できるのであれば、占有を認めてよいと判断したということになります。
水中という握持が困難な場所にある物の占有が問題となった事案の判例
水中や海中において、占有意思とそれを推知させる客観的事情を重視し、占有を肯定した判例として、以下のものがあります。
大阪高裁判例(昭和30年4月22日)
製鋼会社工場の岸壁に面した運河の中に、同社が陸揚げ作業中に落下させた鉄くずを、被告人が勝手に引き揚げて領得した事案で、裁判官は、
- その場に同社の荷揚げのためのクレーンがあること、現場付近に見張所があり、川底に沈下した金属類の無断拾得を禁ずる旨の立札も設置されていたこと、同社の監視人が常時付近を巡回していたこと、付近の水面使用については同社が県知事から特別の許可を得ていたこと等の事情を考慮すれば、鉄くずは、同社の管理下にあり、同社が占有している状態にあると認めるのが相当である
として、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪の成立を認めました。
ちり回収船の人夫と海女である被告人らが、海中に取り落とした外国製時計約900個入りの麻袋1袋の引き揚げを、落とし主から依頼され、潜水してこれを海底に発見したにもかかわらず、岸壁直下付近の泥の中に隠匿した上、不発見であった旨依頼主に告げて倉庫の陰に立ち去らせた後、再び潜水してこれを引き揚げて、密かに持ち去ったという事案で、裁判官は、
- 本件のように、海中に取り落した物件については、落主の意に基づきこれを引揚げようとする者が、その落下場所の大体の位置を指示し、その引揚方を人に依頼した結果、該物件がその付近で発見されたときは、依頼者は、その物件に対し管理支配意思と支配可能な状態とを有するものといえる
- 依頼者は、その物件の現実の握持なく、現物を見ておらず、かつ、その物件を監視していなくとも、所持すなわち事実上の支配管理を有するものと解すべき
と判示し、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪の成立を認めました。
④ 帰還する習性を備えた家畜等
家畜等の動物で、占有者たる飼い主の下に帰還する習性を備えているものについては、飼い主が管理する場所の外に一時的に出たとしても、未だ帰還し得る場所におり、特に逃走して野性に復するなどしていない限り、未だ飼い主の占有が及ぶと解されています。
このような判断をした判例として、以下のものがあります。
大審院判例(大正4年3月18日)
被害者が、被告人の牧場に2頭の牛を無断で放牧し、時々、見回りに来るなどしていたところ、被告人が見回りの隙をついて、被害者(放牧者)に無断でこの2頭の牛を売却したという事案で、
- これらの牛は放牧者の支配するものである
として、牛2頭に対する被害者の占有を認め、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪を認めました。
大審院判例(大正5年5月1日)
奈良県春日神社の所有する牡鹿1頭が、境内の外にある他人所有の藪の中に出遊していたところ、被告人が捕えて、食用のため肉を切り取ったという事案で、
- この鹿が野生に服して神社管理者の事実上の支配を離脱して逸走した事実は認められない
として、牡鹿に対する神社の占有の継続を認め、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪が成立するとしました。
大審院判例(昭和11年12月2日)
ウルップ島に放牧されていた狐を密漁した事案で、同島では農林省が島内一円を飼養地域とし、禁漁区を設置するとともに監視者を配備するなどして養狐事業を実施していたことなどを理由として、
- 同島の狐は全て国家の所有に属し、農林省所轄の養狐場管理者の占有に属する
として、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪の成立を認めました。
広島高裁岡山支部判例(昭和27年3月20日)
他人の家の前まで出遊していた飼い犬を領得した事案で、
- その一事(飼い犬が他人の家の前まで出遊していたこと)をもって、直ちに所有者の占有を離脱したとはいえない
として、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪の成立を認めました。
8年間飼育訓練され、毎日運動のために放してやると、タ方には家の庭に帰って来ていた猟犬が、他人の家に出遊していたところで、その猟犬を領得した事案で、裁判官は、
- 8年間も飼育訓練され、毎日運動のため放してやると、夕方には同家の庭に帰って来ていたことが認められ、このように、養い訓らされた犬が、時に所有者の事実上の支配を及ぼし得べき地域外に出遊することがあっても、その習性として飼育者のもとに帰来するのを常としているものは、特段の事情の生じないかぎり、直ちに飼育者の所持を離れたものであると認めることはできない
と判示し、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪の成立を認めました。