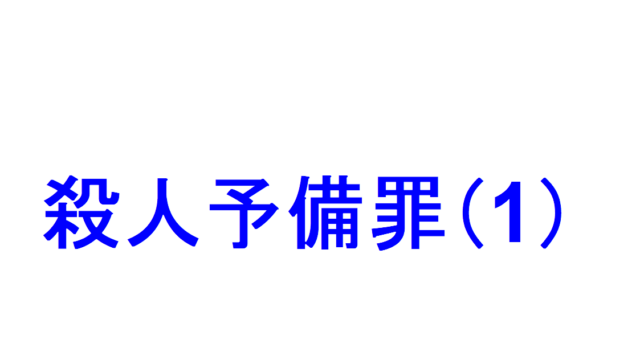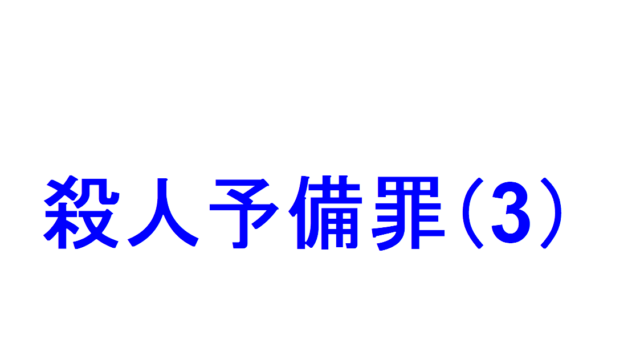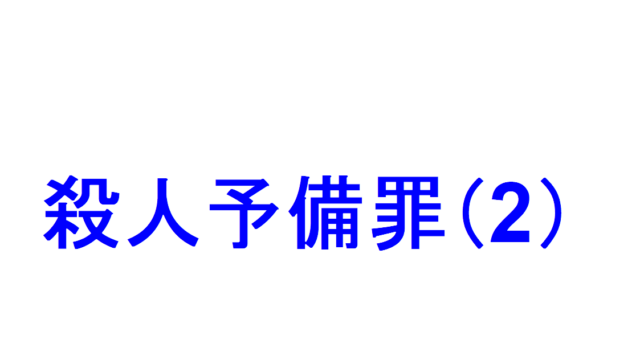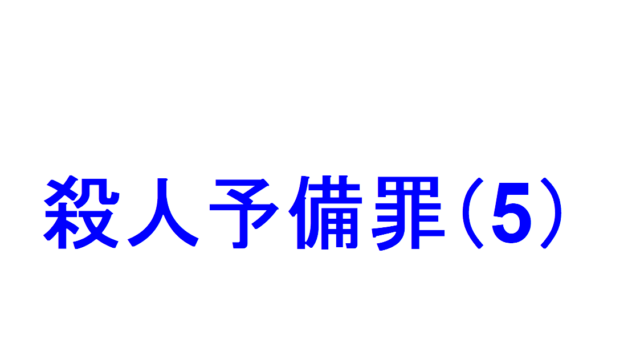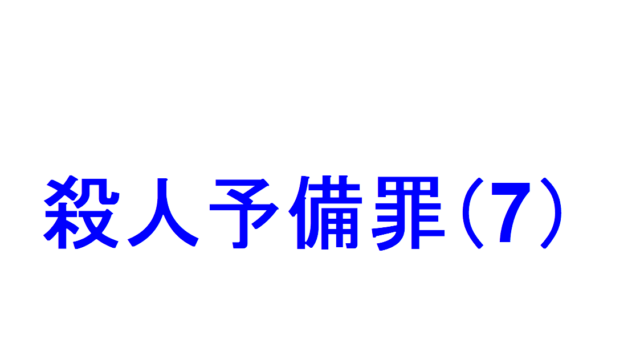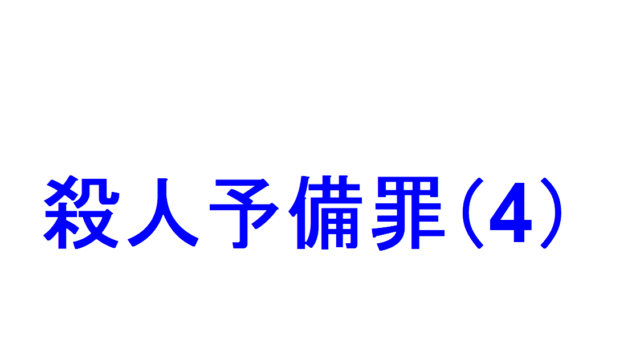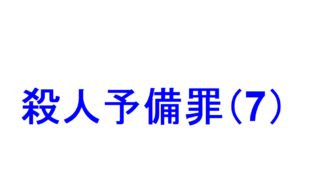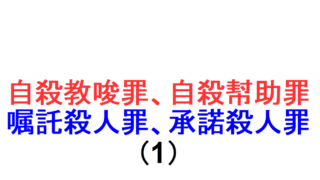殺人予備罪(8) ~「殺人予備罪と①住居侵入罪、②爆発物取締罰則2条違反の罪、③凶器準備集合罪、④銃砲刀剣類所持等取締法違反、⑤強盗殺人罪」を解説~
殺人予備罪(刑法201条)と
- 住居侵入罪
- 爆発物取締罰則2条違反の罪
- 凶器準備集合罪
- 銃砲刀剣類所持等取締法違反
- 強盗殺人罪
との関係について説明します。
①住居侵入罪との関係
住居侵入罪(刑法130条)と殺人予備罪との関係について説明します。
殺人予備罪とは、殺人の準備(刃物を持って待ち伏せる、殺人をするための毒物を購入するなど)をした場合に成立する犯罪です。
殺人の目的で凶器を携えて被害者宅に侵入したが、殺人の実行に着手しなかった場合、殺人予備罪と住居侵入罪は、観念的競合の関係に立ちます。
この点について以下の判例があります。
大審院判決(明治44年12月25日)
裁判官は、
- 他人を殺害する目的をもって、その住宅に侵入したる者の行為は、一面において殺人予備罪に当たり、他の一面において家宅侵入罪に当たるをもって、いわゆる一個の行為にして2個の罪名に触れるものとし、その重きにしたがって処分すべきものとす
と判示し、住居侵入罪と殺人予備罪が観念的競合の関係にあるとしました。
②爆発物取締罰則2条違反の罪との関係
他人を殺害する目的で爆発物を用意したが、操作を誤って事前に爆発させたときは、爆発物取締罰則2条違反の罪と殺人予備罪は、観念的競合の関係になります。
参考となる裁判例として、以下のものがあります。
東京地裁判決(昭和43年2月15日)
飛行機にダイナマイトを乗せ、飛行機を爆発・墜落させて、飛行機に乗っていたAを殺害しようとしたが、誤って空港のトイレ内で爆発させたため、殺人は未遂に終わった殺人予備罪と爆発物取締罰則2条の事案です。
裁判官は、
- 被告人の殺人予備の行為は刑法201条に、爆発物を使用せんとした行為は爆発物取締罰則2条に該当するが、右は1個の行為で2個の罪名に触れる場合であるから、同罰則第12条、刑法10条により重い後者の罪の刑に従い処断する
とし、殺人予備罪と爆発物取締罰則2条違反の罪とは、観念的競合の関係になるとしました。
③凶器準備集合罪との関係
凶器準備集合罪(刑法208条の2第1項)は、公共的な社会生活の平穏に対する犯罪であって、個人の生命の危険に対する殺人予備罪とは保護法益を異にするから、殺人の目的で凶器を準備して集合したときは、凶器準備集合罪と殺人予備罪の成立し、両罪は観念的競合の関係になります。
④銃砲刀剣類所持等取締法違反との関係
殺人で使用するための刃物の不法携帯(銃砲刀剣類所持等取締法違反)と、それを含む一連の行為による殺人予備罪とは併合罪の関係になる場合と観念的競合になる場合とがあります。
併合罪になるとした裁判例
札幌高裁判決(昭和50年6月10日)
裁判官は、
- 刑法54条1項前段にいう一個の行為とは、法律的評価をはなれた構成要件的観察を捨象した自然的観察のもとで、行為者の動態が社会的見解上1個のものと評価をうける場合をいうものと解すべきところである(最高裁判所昭和49年5月29日大法廷判決)
- これを本件についてみると、殺人予備の所為は、被告人が町長Aを殺害しようと企て、武器として本件ナタ1丁、登山用ナイフ1丁を買い入れ、ナタの柄の部分に紐をビニールテープでとりつけてナタが手から離れないように工作し、これで下宿先の部屋の柱を試し斬りするなどの練習をした上、町長Aの顔写真が掲載してある雑誌の写真部分を切り抜き、擬装爆弾などとともに前記ナタ及び登山ナイフ各1丁を携帯し、原判示の日時、場所に赴いて、町長Aの出勤を待ち伏せしたことを内容としていることは原判文上明白であって、その行為、動態は殺人の企図のもとに時間的継続と場所的移動を伴う一連の行為と目されるのに対し、原判示第三の右ナタ及び登山用ナイフ各1丁の不法携帯の行為は、右殺人予備における一連の行為中の一定の時点・場所におけるものであって、前記の自然的観察からするならば、社会的見解上、右殺人予備の一連の行為とは可分的な別個独立の行為と評価すべきものである
- したがって、これを刑法54条1項前段にいう一個の行為とみることはできず、両者は併合罪の関係にあるものと解するのが相当である
と判示し、殺人で使用するための刃物の不法携帯(銃砲刀剣類所持等取締法違反)と、それを含む一連の行為による殺人予備罪とは併合罪の関係になるとしました。
観念的競合になるとした裁判例
福岡高裁那覇支部判決(平成18年11月28日)
被害者を殺害する目的で、自宅から包丁を手にして、約5. 1キロメートル離れた被害者不在の被害者方に徒歩で向かった行為は、殺人予備と銃砲刀剣類所持等取締法違反の観念的競合となると認定した事例です。
裁判所は、
- 本件は、被害者に長年にわたり執拗につきまとうなどしていた被告人の、一連のストーカー行為等の規制等に関する法律違反、及び、被害者殺害の目的で包丁を手にして徒歩で自宅から被害者宅に向かったという殺人予備・銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案である
- 殺人予備について、被告人には被害者を殺害する具体的意思がなかった上、客観的にも、殺人の実行に至る客観的かつ実質的な危険性が認められないから、殺人予備について無罪であるという事実誤認の主張に対し、殺害目的の点につき、本件に至るまでの経緯に照らし、被告人が包丁を手にした時点で被害者に対する強固な加害意思を有していたことが客観的に明らかであり、銃刀法違反で現行犯逮捕された時点で警察官に包丁携帯の理由を殺害目的と答えていること、捜査段階においてその旨の供述を維持しており、事件の経緯等に整合するものであること、殺意を否認し脅迫目的にすぎない旨の公判供述の内容は客観的状況にそぐわないことから、殺害目的を有していたことは明らかである
- 予備行為の実行行為性(殺害の実行に至る危険性)については、被告人宅から被害者宅までは徒歩で1時間以上の時間を要すること、本件当時、被害者がドライブに出かけていて不在にしていたこと、これまで被害者に刃物を示すなど、殺人の実行に至る危険のある行為をしたことがないことの諸事情を考慮しても、高度の殺傷能力を有する洋包丁を、その旨認識しながら携行し、被告人宅から約1キロメートル離れた被害者方に向かって歩いていた本件行為が、被害者殺害の実行に至る客観的・実質的危険を有していたことは明らかであるとした原審判断は相当なものとして是認できる
- なお、原判決は、殺人予備と銃刀法違反を併合罪として処断しているが、本件において、被告人は、被害者を殺害する目的で、包丁を手にして徒歩で被害者宅に向かい、もって、殺人の予備をするとともに、正当な理由による場合でないのに包丁を携帯したのであり、両罪は、社会的にみて1個の行為によるものとして、観念的競合の関係にあると解するのが相当である
と判示しました。
⑤強盗殺人罪との関係
殺人で使用するための物を準備し、機会を窺っているうち、殺人のほか、強盗の犯意も生じ、強盗殺人の行為を遂行した場合は、強盗殺人罪(刑法240条)の一罪が成立し、別に殺人予備罪は成立しません(殺人予備罪は強盗殺人罪に吸収される)。
参考となる判例として、以下のものがあります。
大審院判決(昭和7年11月30日)
裁判官は、
- 犯人が、被害者に対し、殺意を起こし、その犯行の用に供すべき物を携え、夜中、被害者が戸外に出て来たるを待ちたるところ、被害者が出て来ざるため、実行の着手に至らざりしも、なお殺意を継続して現場の傍らに隠れ、実行の機会を待つ中、財物奪取の犯意を加え、被害者を殺害して財物奪取の目的を遂げたる場合には、強盗殺人の一罪をもって論ずべきものとす
と判示しました。
①殺人罪、②殺人予備罪、③自殺教唆罪・自殺幇助罪・嘱託殺人罪・承諾殺人罪の記事まとめ一覧