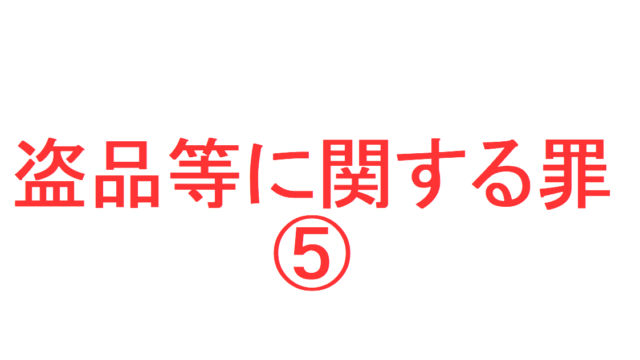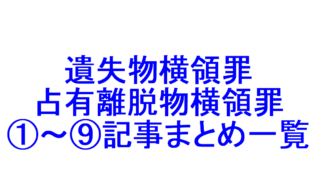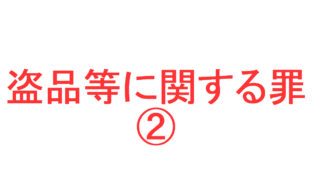これから複数回にわたり、盗品等に関する罪(刑法256条)について解説していきます。
盗品等に関する罪とは?
盗品等に関する罪(刑法256条)とは、
盗品等、すなわち窃盗、強盗など財産犯の被害にあった他人の財物(贓物)を、無償で譲り受けたり、運搬、保管、有償で譲り受け、有償の処分のあっせんをする罪
のことをいいます。
条文は以下のとおりです。
刑法 第256条(盗品譲受け等)
1 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
本条は、1項で盗品等を無償で譲り受けることを処罰し、2項で盗品等を運搬・保管・有償の譲受け・有償の処分のあっせんをすることを処罰します。
盗品等に関与する行為として、
- 無償譲受け
- 運搬
- 保管
- 有償譲受け
- 有償処分あっせん
の5種類の行為についてのみ処罰対象にしています。
法は、盗品等に関与する行為として、中核的なこの5種類の行為を選び出し、処罰対象としました。
1項と2項の違い
「1項の無償の譲受け」と、「2項の運搬・保管・有償譲受け・有償処分あっせん」の違いについて説明します。
1項は、単なる受動的、消極的、非営業的犯罪の位置づけにあります。
1項は、事後従犯的性格はあるとしても、本犯隠匿的性格は少なく、利欲犯的性格は少ないといえます。
これに対し、2項は、能動的、積極的、営業的犯罪の位置づけにあります。
しかも、2項の罪は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律2条2項1号に定める「犯罪収益」の対象となる犯罪です。
この意味は、たとえば、2項の盗品等有償譲受けの罪を犯し、犯罪収益(盗品自体が犯罪収益となる)を得た場合、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(11条、犯罪収益等収受)の罪も同時に成立(観念的競合)することになります。
この場合の犯罪事実としては、
被告人は、令和4年1月10日、東京都内において、A氏から、A氏が窃取してきたパソコン1台(10万円)を、それが盗品であることを知りながら代金5万円で買い受け、盗品等を有償で譲り受けるとともに、犯罪収益を収受した
となります。
2項の罪が、1項の罪に比べて特に重い理由
2項の罪(10年以下の懲役及び50万以下の罰金)が、1項の罪(3年以下の懲役)に比べて特に重い理由は、2項の罪は、
- 本犯(窃盗等を行った者)の犯行を容易にする事後従犯的性質がある
- 盗品等の処分を容易にするととで、本犯の犯行を助長する本犯助長的性質がある
- 本犯に乗じて利益を得ようとする利欲犯的性質がある
ことによります。
判例も、本罪の本犯助長的性質や利欲犯的性質を考慮して判決をしています。
最高裁判決(昭和26年1月30日)
この判例は、
と判示しました。
この判例では、
- 盗品等の有償の処分のあっせんをする行為は、窃盗等の被害者を処分の相手方とする場合であっても、被害者による盗品等の正常な回復を困難にするばかりでなく、窃盗等の犯罪を助長し誘発するおそれのある行為であるから、刑法256条2項にいう盗品等の『有償の処分のあっせん』に当たると解する
と判示しました。
保護法益(追求権説)
盗品等に関する罪の中心的な保護法益は、
財産犯の被害者が被害物を追求・回復する権利(「追求権」という)
です。
この考え方を、追求権説といいます。
判例も追求権説の考え方をとっています。
大審院判決(大正11年7月12日)
この判例は、盗品等に関する罪について、
- 他人の不法に領得したる物を運搬、寄蔵(保管)、牙保(有償処分のあっせん)、故買(有償譲受け)又は収受するにより成立するものにして、いずれの場合においても贓物(盗品等)の占有を不法に取得し、もって所有者の物に対する追求権の実行を困難ならしむるを本質とす
と判示しています。
大審院判決(大正8年11月25日)
この判例で、裁判官は、
- 贓物(盗品等)に関する行為を処罰する一面の理由は、その行為が贓物の移転を容易ならしめ、被害者をして、その回復を不能又は困難ならしむるの結果を生ずるがためにほかならず
と判示しています。
この判例で、裁判官は、
- 贓物(盗品等)に関する罪は、被害者の財産権の保護を目的とするものであり、被害者が民法の規定により、その物の回復を請求する権利を失わない以上、その物につき贓物罪(盗品等に関する罪)の成立することがある
と判示しています。
このように、判例は、本罪の罪質を、財産犯の被害物である財物に対する被害者の追求権を中心に捉えています。
追求権は、民法における返還請求権(物権的請求権)を指す
追求権は、判例が、
- 「返還の請求その他何等の権利」(大審院判決 大正11年7月12日)
- 「被害者が民法の規定によりその物の回復を請求する権利」(最高裁判決(昭和34年2月9日)
とするように、第一には、私法上の所有権に基づく返還請求権(物権的請求権)を指します。
さらに理解を進めて、学説では、追求権は、物権的請求権に限定されず、
- 被害者が法律上追求できる請求権
と定義すべきと考えられています。
被害者が法律上追求できる請求権の有無は、犯行時をもって決せられる
盗品等に関する罪の成否を決するに当たり、本罪の被害者は、法律上追求できる請求権を、本罪所定の各行為(盗品等無償譲受け、運搬、保管、有償譲受け、有償処分あっせん)の時に持っていればよいとされます。
後に、被害者の請求権が消えることになっても、本罪の成否に影響を与えません。
東京高裁判決(昭和25年5月26日)
この判例において、贓物の返還請求権の喪失と、既に成立した贓物罪への影響について、裁判官は、
- 贓物罪は、不法に領得せられた物件に対する被害者の返還請求権を侵害することによって成立するものであるから、同罪の成立するためには、その行為の時にむいて、かかる返還請求権を侵害することを要し、また、これをもって足るものと解しなければならない
- 従って、被害法益である返還請求権の有無は、専らその行為の時の時により、これを決めるべきである
- たとえ、後にこれが失われるようなことがあったとしても、既に成立した犯罪はなんらの消長を及ぼすものではない
と判示し、盗品等に関する罪の行為時に、盗品等としての性格を有していれば、その後、返還請求権が失われたとしても、本罪の成立に影響はないと判断しました。
特別法上の贓物罪
があります。
国外犯
盗品等関する罪の刑法256条2項の行為については、国民の国外犯規定(刑法3条16号)が適用されます。
この意味は、外国において、2項の罪(盗品等の運搬,保管,有償の譲受け,有償の処分のあっせん)を行った日本人に対し、日本の裁判所が刑事処罰を科すことができるという意味です。
犯罪の成立主体
1⃣ 本犯に盗品等に関する罪は成立しない
盗品等に関する罪が成立するためには、ある財物を盗むなどの盗品等にする行為(本犯の行為)が必要です。
盗品等に関する罪は、本犯が存在することを前提としているから、本犯については、本罪の主体にはなり得ません。
たとえば、宝石を盗んだ窃盗犯人(本犯)が、犯人自身が盗んだ宝石を犯人自身で買受けて、窃盗罪のほか、盗品等に関する罪(盗品等有償譲受け)も成立するという考え方は取り得ません。
自己の犯罪によって不法に領得した財物を運搬、保管などする行為は、不可罰的事後行為として、本犯の犯罪で評価し尽くされ、処罰の対象外になります。
よって、本犯が、盗品等に関する罪に該当する行為を犯しても、本犯の罪に重ねて盗品等に関する罪は成立しません。
この点について、以下の判例があります。
この判例は、
- 同一人が既に故買した物件を他に運搬するがごときは、犯罪によりて得たものの事後処分たるに過ぎないのであって、刑法はかかる行為をも同法第256条第2項によって処罰する法意でないことはあきらかである
と判示しています。
ただし、本犯であっても、
- 売却した盗品等を再度買い受けた場合
- 再転売に積極的に関与した場合
など、本犯の不可罰的事後行為として評価しうる範囲を超えたものについては、盗品に関する罪が成立する余地があると考えられます。
理由は、上記のような場合、後の行為は、本犯としての関与ではなく、盗品等に関する罪の実行犯に対する関与になるためです。
2⃣ 本犯の共同正犯に盗品等に関する罪は成立しない
実行共同正犯に限らず、共謀共同正犯についても、本犯であれば、盗品等に関する罪の所定の行為をしても、盗品等に関する罪は成立しません。
3⃣ 本犯と共同で盗品等に関する罪の行為を行った者に対しては、盗品等に関する罪が成立する
本犯と共同で、盗品等に関する罪の行為(保管・運搬など)を行った者(本犯の行為には関わっていない者)に対しては、その者は本犯に当たらないので、盗品等に関する罪が成立します。
この点について、以下の判例があります。
窃盗本犯である米兵らが横須賀市a所在の米軍倉庫から窃取した贓物を、貨物自動車に積載して売却するのに都合のよい東京都内に運搬するにあたり、被告人は贓物であることの情を知りながら、米兵らの依頼を受けて、米兵らに協力し、共同して横須賀市b町付近から東京都台東区e町まで運搬した事案で、裁判官は、
- 被告人の所為は贓物運搬の罪を構成する
- 窃盗本犯らにおいて、窃盗罪のほかに贓物運搬罪(盗品等に関する罪「盗品等運搬」)をもっては問擬(もんぎ)せられないからといって、これがため被告人の贓物運搬の罪の成立に消長をきたすものとはいえない
と判示し、本犯と共同で盗品等に関する罪を実行した者に対し、本犯には同罪が成立せずとも、共同で同罪を実行した者に対しては、同罪が成立するとしました。
4⃣ 本犯の教唆犯、幇助犯本犯の教唆犯や幇助犯については、共同正犯の場合と異なり、盗品等に関する罪が成立する
については、共同正犯の場合と異なり、盗品等に関する罪が成立します。
この点について、以下の判例があります。
この判例で、裁判官は、
- 窃盗教唆罪と贓物牙保罪(盗品等に関する罪「盗品等有償処分あっせん」)とは、別個独立の犯罪であるから、同一人が「窃取して来れば売却してやる」と言って、他人に対し、窃盗を教唆し、かつ、その贓物の売却を周旋して牙保(あっせん)をしたときでも、それは窃盗教唆と贓物牙保罪(盗品等に関する罪)の二罪が成立するのであって、後者が前者に吸収さるべきものではない
- そして、窃盗教唆が、正犯たる窃盗に準して処断されるということから、贓物牙保罪(盗品等に関する罪「盗品等有償処分あっせん」)は、窃盗教唆罪に当然に吸収されるという結論を導きだすことは到底できないのである
と判示しました。
この判例で、裁判官は、
- 窃盗の幇助をした者が、正犯の盗取した財物を、その贓物たるの情を知りながら買受けた場合においては、窃盗幇助罪のほか、贓物罪(盗品等に関する罪「盗品等有償譲受け」)が別個に成立し、両者は併合罪の関係にあるものと解すべきである
と判示しました。
窃盗等の本犯を教唆・幇助した犯人は、自ら本犯の行為をするものではないので、別に盗品等に関する罪が成立するのは当然といえます。
なお、窃盗等の本犯の教唆・幇助と、盗品等に関する罪との関係は、通常、手段又は結果の関係がないので、牽連犯ではなく併合罪になります。
この点について、以下の判例があります。
この判例で、裁判官は、
- 刑法54条後段の牽連犯が成立するためには、ある犯罪と他の犯罪との間に通常手段又は結果の関係があることが必要であって、被告人が主観的にある犯罪を他の犯罪の手段として行ったということだけでは足りないのである
- そうして窃盜教唆と贓物故買(盗品等に関する罪「盗品等有償処分あっせん」)との間には、通常手段又は結果の関係はないのであるから、被告人が贓物故買の手段として、窃盜教唆を行ったものであっても、牽連犯にあたるものでなく、両者は併合罪の関係に立つ
と判示しました。
5⃣ 被害者は盗品等に関する罪の主体にはならない
被害者は、盗品等に関する罪の主体にはなりません。
窃盗被害者が、被害品を無償で譲り受けたり、有償で買い受けたりしても、窃盗被害者に対して、盗品等に関する罪(盗品等無償譲受けや盗品等有償譲受け)は成立しません。
なお、被害品を窃盗被害者に譲り渡すために、被害品を運搬したり、被害品の買取りをあっせんした者に対しては、盗品等に関する罪(盗品等運搬、盗品等有償処分あっせん)が成立します。
この点については、以下の判例があります。
窃盗被害者から、盗品の回復を依頼されて、盗品を被害者宅に運搬し返還した事案で、裁判は、
- 結局窃盗犯人に協力して、その利益のために盗品の返還を条件に被害者をして多額の金員を交付せしめる等盗品の正常なる回復を困難ならしめた場合には、贓物運搬罪(盗品等に関する罪「盗品等運搬」)が成立する
と判示しました。
窃盗被害者は、盗品等に関する罪(盗品等有償譲受け)の罪に問われていません。
この判例で、裁判官は、
- 盗品等の有償の処分のあっせんをする行為は、窃盗等の被害者を処分の相手方とする場合であっても、被害者による盗品等の正常な回復を困難にするばかりでなく、窃盗等の犯罪を助長し誘発するおそれのある行為であるから、刑法256条2項にいう盗品等の「有償の処分のあっせん」に当たる
と判示しました。
窃盗被害者は、盗品等に関する罪(盗品等有償譲受け)の罪に問われていません。