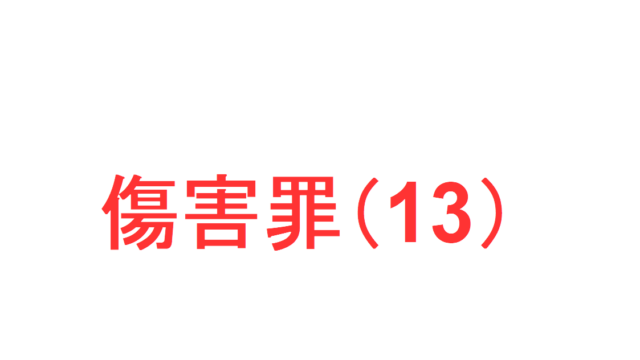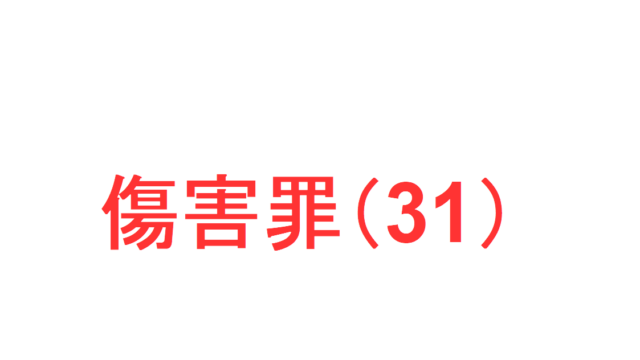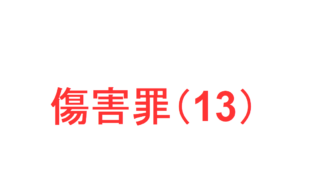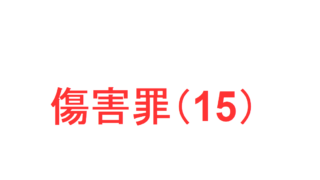前回記事では、傷害罪において違法性阻却事由となりうる「被害者の同意」について説明しました。
今回の記事では、傷害罪において違法性阻却事由となりうる「現行犯逮捕の際の傷害」「スポーツにおける傷害」について説明します。
傷害罪における違法性阻却事由(現行犯逮捕の際の傷害)
現行犯逮捕は、警察官のほか、一般人(私人)でもすることができます。
私人の現行犯人逮捕の際の傷害について、正当行為(刑法35条)として違法性阻却が認められることがあります。
この点について、以下の判例があります。
この判例で、裁判官は、
- 現行犯逮捕をしようとする場合において、現行犯人から抵抗を受けたときは、逮捕をしようとする者は、警察官であると私人(一般人)であるとをとわず、その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力を行使することが許される
- たとえその実力の行使が刑罰法令に触れることがあるとしても、刑法35条により罰せられないものと解すべきである
と判示しました。
たとえ逮捕行為で相手に傷害を負わせたとしても、それは刑法35条の正当行為として、傷害罪に問われずに済みます。
東京高裁判決(昭和51年11月8日)
この判例は、被告人の現行犯逮捕に伴う暴行を、私人による現行犯逮捕のための必要かつ相当な範囲内の行為と認められるとして、傷害罪は成立せず、無罪としました。
この判例で、裁判官は、
- 相手方の犯罪行為に対し憤慨し、または報復感情があったからといって、直ちに逮捕の意思を欠くものとはいえず、被告人に逮捕意思があったことが認められるところ、その行為は、社会通念上、同人の抵抗を排除し、逮捕を容易にするための実力行使として必要かつ相当と認められる限度をこえたものではない
- 被告人のKに対する行為は、その顔面を1回殴打した点を除けば、終始同人の襟首や手をつかまえて離さず、これをふりほどこうとしたKと取っ組み合い、警察官の制止によって手を放すまで押えつけていたというに過ぎないものであり、それは即ちに逮捕行為にほかならない
- Kの顔面を殴打した行為も、前記のような同人の本件当日における暴力的言動や被告人の抗議に対する反抗の姿勢など当時の状況のほか、殴打回数が1回であり、それ自体によってはKに傷害を負わせる程度のものでなかったことに照らせば、社会通念上同人の抵抗を排除し、逮捕を容易にするための実力行使として必要かつ相当と認められる限度をこえたものではないと解すべきである
- したがって、被告人のKに対する行為は全体として、現行犯人を逮捕するために必要かつ相当な範囲内のものであったと認めらる
- 以上のとおり、被告人のKに対する本件所為は、適法な現行犯逮捕の行為と認められるから、刑法35条により罪とならないものというべきである
と判示しました。
東京高裁判決(平成10年3月11日)
この判例は、私人による現行犯逮捕のために必要かつ相当な範囲の行為と認め、傷害事件について無罪とした事例です。
事案は、被告人が、被告人の自動車を損壊して逃走したAを追跡して取り押さえる際に、Aの顔面・頭部を拳及び木の棒で殴打する等の暴行を加え、加療2週間の傷害を負わせたというものです。
裁判官は、
- 現行犯逮捕をしようとする場合において、現行犯人から抵抗を受けたときは、逮捕しようとする者は、警察官であると私人であるとを問わず、その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力を行使することが許され、たとえその実力の行使が外形上は刑罰法令に触れていても、刑法35条により罰せられないものと解するのが相当である
- これを、本件についてみると、Aは、C方庭先に追い詰められるや、原付車を加速して被告人と石垣の間を突破しようとするなど、かなり危険な方法で逃走しようとした上、横から同人をつかまえにきた被告人に対して、顔面を殴打し、ヘルメットをぶつけ、石垣に押し付けて攻撃し、これに対して、被告人は、右抵抗を排除しようとして本件行為に及んだものであることが明らかである
- そして、右のようなAの抵抗の態様や被告人がその過程において自らも傷害を負わされていることなどに照らすと、被告人が、手探りでつかんだ木の棒でAを殴打したことや、Aに傷害を負わせたこともやむを得なかったというべきであり、右の行為は、社会通念上逮捕をするために必要かつ相当な限度内にとどまるものと認められる
- なお、被告人は、Aを殴り倒したのちも、何回かその頭部、腹部等を足蹴にする等の暴行を加えたが、右暴行はAが倒れた直後、まだ同人が反撃意思を喪失している否か分からない階段で、その意思を制圧するために加えられたものと認められるから、いまだ右の許容範囲を超えるものとまではいえない
- 原判決は、被告人が憤激してAの追跡を開始したことをもって、正当行為を否定する根拠の一つとしているが、被害者が犯人逮捕の意思と並んで、報復感情や懲罰感情を抱くことはむしろ自然なことであり、そのような感情を一部に抱いていても、そのことから直ちに逮捕行為全体が違法性を帯びるということはできない
- そうすると、被告人のAに対する本件行為は、現行犯逮捕にともなう適法な実力行使と認め得るから、刑法35条により罪とならないものというべきである
とし、傷害罪は成立しないとして無罪を言い渡しました。
現行犯逮捕に伴う傷害の違法性を阻却した上記各判例に対し、傷害の違法性を阻却したなかった判例として、以下の判例があります。
大審院判決(明治43年5月9日)
この判例で、裁判官は、
- 被告人は被害者の侮辱の言辞に立腹し、警察官のもとへ引っ張って行こうとして傷害を負わせたが、名誉毀損の現行犯人として逮捕し、これを司法警察員に引致しようとしたものであっても、これに暴行を加え傷害を負わせるのは、権利の行使とはいえない
と判示し、暴行は現行犯逮捕に伴う権利の行使とは認められず、違法性を阻却せず、傷害罪が成立するとしました。
相手方に犯罪行為があったというだけでは、これに対する暴行・傷害の違法性を欠くといえません。
暴行・傷害の違法性を欠くかどうかは、暴行・傷害が、犯罪の制止又は現行犯逮捕のためになされた必要かつ相当なものであるか否かについて、具体的状況に即して判断されることになります。
傷害罪における違法性阻却事由(スポーツにおける傷害)
公正に競技する目的でルールに従って通常の方法によるスポーツにおいて、相手又はチームメイトに傷害を負わせても、傷害罪を構成しません。
これは、
- 暴行・傷害の故意がないが故に構成要件に該当せず、暴行・傷害罪を構成しないとする考え方
もしくは、
に基づきます。
とはいうものの、限度を超えた「鍛錬」「練習」が違法性を有し、暴行・傷害罪又は傷害致死罪を構成する場合もあります。
限度を超えた「鍛錬」「練習」が違法性を阻却せず、傷害致死罪が成立するとした以下の判例があります。
東京地裁判決(昭和41年6月22日)
この判例は、大学ワンダーフォーゲル部のクラブ活動の慣行となっていたため、許されるものと考えて、いわゆるシゴキ行為をした者の責任について判示しました。
クラブ活動の錬成山行中に、被告人である上級生部員が、錬成のためのシゴキとして新人部員の頭部を木の棒でなぐるなどの暴行を加え、3名の新人部員にけがを負わせ、1名の新人部員を暴行により死亡させた傷害罪及び傷害致死罪の事案です。
まず、被告人の弁護人は、
- 本件錬成山行中、上級生部員が新人に有形力を加えるのは、団体山岳行動に耐えうる体力気力と山岳生活の能力を養成するためであるが、山岳行動は生命の危険度の高いスポーツであり、団体行動の場合には一人の力の低下は全体の力の低下を招くから、訓練は厳しくならざるを得ないが、農大においては体育部に属しているため、特に激しくなるのである
- 本件においてもそのような新人錬成という目的のために有形力を加えたものであり、新人の気力回復あるいは危険防止のためにも必要なことで、その手段、方法において許容し得る相当な範囲内の行為である
- 従って、たとえ外形上暴行罪の構成要件に該当する行為であっても、それは刑法第35条により違法性が阻却されるものである
と主張しました。
この主張に対し、裁判官は、
- 新人錬成山行は、あくまでも訓練行動であって、たえず、ぎりぎりの行動が要求される山岳行動とは、その趣を異にするのであるから、激励する等他にとるべき方法が考えられるのにかからず、何のためらいもなく、被告人らが時を接して殴打したことは、悲壮感すら感ぜられるところであって、決して正当化されるものではない
- 疲れてふらふらになつたMに、数人の上級生が殴る蹴るの暴行を加えて通り過ぎた後、被告人が通りかかって行ったもので、このような状況を考慮し、又、この殴打によつて鼻血が出た事実を合せ考えると、やはり著しく相当性を越えた行為であると言わざるを得ない
- 殴る蹴るということは、一個の人格を否定する行為である
- このような事が大学体育部の名において行われてよいはずはない
などと判示し、傷害罪及び傷害致死罪の成立を認めました。
東京高裁判決(昭和62年5月28日)
この判例は、大学空手部において1年生部員に集団暴行の制裁を加え、1名を死亡させ、他の1名に重傷を負わせた2年生部員の首謀者2名に懲役2年の実刑を科した原判決を維持した事例です。
裁判官は、
- 行為の態様が悪質であるうえに、発生した結果が極めて重大であり、関係者に深刻な影響を及ぼしたことなどを考慮すると、被告人らの刑事責任は重いといわなければならない
- 被告人らにおいて、大学生として本件のような行為が社会的に容認されないものであるとの認識が乏しかったこと自体、厳しい非難に値するうえに、この種事犯の再発を防止するという観点からみても、その背景事情を過大に評価し、被告人ら各個人の責任を軽視するのは相当でないと思われる
と判示し、傷害致死罪・傷害罪の成立を認めました。
次回記事に続く
次回記事では、「正当防衛の成立要件」などについて書きます。