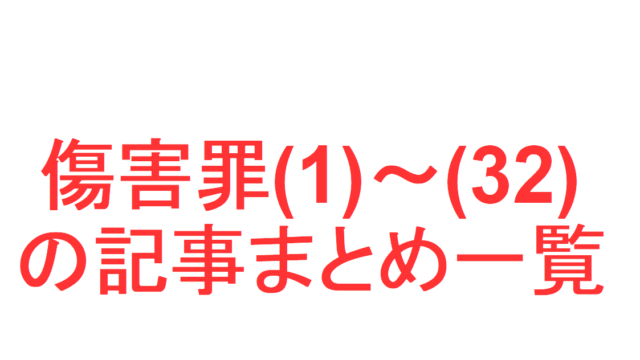強盗致傷罪と傷害罪における傷害の差異
傷害罪(刑法204条)の法定刑は、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
これに対し、強盗致傷罪(刑法240条)の法定刑は、「無期又は6年以上の懲役」であり、傷害罪と比べるとかなり重い刑が科せられることになります。
そこで、暴行か傷害かで、科される刑が著しく重くなる強盗致傷罪においては、暴行と傷害の限界が特に問題となります。
最高裁判例は、傷害罪と強盗致傷罪の傷害概念に差異はないとしている
最高裁判例の示すところでは、傷害罪と強盗致傷罪の傷害概念に差異のないというのが結論になります。
この点について、以下の判例があります。
最高裁決定(昭和37年8月21日)、最高裁決定(昭和41年9月14日)
この両方の判例で、裁判官は、
- 軽微な傷でも、人の健康状態に不良の変更を加えたものである以上、刑法にいわゆる傷害と認めるべきこと当裁判所の判例(昭和24年12月10日判決、昭和32年4月23日決定)の示すとおりであるから、原判決が原判示の傷を傷害と認め、被告人らの所為をもって刑法240条前段に問擬(もんぎ)したのは正当である
と判示しました。
ちなみに、強制性交等致傷罪(刑法181条、旧:強姦致傷罪)についても、最高裁決定(昭和38年6月25日)において、強盗致傷罪に関する上記の最高裁決定(昭和37年8月21日)を引用し、傷害罪と強制性交等致傷罪の傷害概念に差異のないことを明言しています。
上記の最高裁決定(昭和37年8月21日)と最高裁決定(昭和41年9月14日)に沿う判例として、以下のものがあります。
東京高裁判決(昭和38年12月12日)
強盗に際して、被害女性の首を押えつけ、肩を押し、その場に倒れた同女の上に乗りかかるなどの暴行を加え、同女の左頸部に長さ約1.5cm、幅1cmの全治までに約5日位を要する擦過傷を負わせた事案で、裁判官は、
- 強盗傷人罪における傷害は、傷害罪の傷害とは別異のものと解する余地はなく、更に強盗犯人が短刀で脅迫中、相手が短刀を握ったため傷害を生ぜしめた場合にも強盗傷人罪の成立を認めた判例(最高裁判所昭和24年3月24日判例)の存することを考えると、刑法240条(強盗傷人罪)の傷害の場合をも含むことがあるものとなさねばならぬ訳であって、特にこれを傷害罪よりも高度の傷害の結果を生じた場合に限定する根拠はいよいよ薄弱になるものといわなければならない
- 原審は、被告人の暴行により「赤疹」を生じたものとし、未だ傷害の程度に達しなかったものと認めたような表現を用いているが、被告人が被害者に与えたものは、「長さ1.5cm、幅1cmの擦過傷」であり、右傷害は「傷を消毒して汚さなければ化膿しない」が、化膿しないよう消毒薬を施用し、なお傷の部分を清潔に保つよう指示を与えたという意味で「5日間の加療を要する」ものであったことは明らかである
と判示し、傷害罪と強盗致傷罪の傷害概念に差異のないとして、強盗致傷罪の成立を認めました。
東京地裁判決(昭和43年6月6日)
この判例は、全治3日の打撲傷および擦過傷につき、強盗致傷罪の傷害に当たるとした事例です。
裁判官は、
- 被害者の受けた傷害は、全治3日間を要する打撲傷および擦過傷と診断されたものであり、また実際に格別の治療をせずに4、5日で痛みがとれ、約1週間で全治したことが明らかである
- しかし、被害者は殴られて頬が痛かったため、警察の勧めもあって、自ら医師の診察を受けに行ったというのであり、左頬骨の部位にはっきりとわかる程度の腫脹があって、擦過傷の範囲は3cmに及び、その部位には圧痛があり、また皮下出血があったばかりでなく、表皮が破れて表面にうっすらとにじむ程度の出血もあり、医師は治療の方法として冷湿布をするよう指示を与えたということである
- そして右の傷害は、被告人らの強盗の機会にたまたま生じたというものではなく、強盗の手段である暴行行為によって生じたものであることをも考えあわせると、本件の傷害は単に強盗罪に含まれるものではなく、強盗致傷罪の傷害と評価せざるを得ない
と判示しました。
福岡高裁判決(昭和47年11月16日)
窃盗の途中にA、Bに見つかり、逃げるためにAとBを殴るなどし、Aの腕部とBの指に傷害を負わせた事案で、裁判官は、
- これらの傷害は、Aは左前腕部と左下腿部にそれぞれ打撲を受け、左前腕部の傷は約1cm平方に表皮が破れて血がにじみ出ていたほか、その周辺約4cm平方が皮下出血を伴って腫れ上って痛み、2日間通院し、消炎酵素剤や鎮痛剤を用いて治療を受け、左下腿部は湿布しただけで痛みを消失したが、左前腕の出血部位は3日間位で痂皮ができたものの、4、5日間は痛みが持続し、9日位を経ても痛みが残ったことが認みられる
- Bにおいては、左手第三、四指及び左大腿部に打撲を受け、左第三、四指は擦過状の創傷を形成し、各第二関節付近からわずかながら出血し、左大腿部は直径約2cm位が紫色になっていて、2日間通院し、消炎酵素剤や鎮痛剤による治療による治療を受けたことが認められ、左手第三、四指の傷は4日間位包帯し、曲げると痛みを感じ、痂皮の剥離後化膿したが6日間位で殆ど治癒状態になったものの、現在でも長さ1cm前後の細い瘢痕二条が残っていることが認められる
- なお、当時はAにおいては物を持つとき左腕を自然にかばい、Bにおいても指を曲けると痛み、包帯もしていたので自動車の運転に支障があったものである
- A、Bは、いずれも痛みを覚え、通院加療している事実等を認定の上、A、Bに生理又は生活的機能に障害があったことは否定しがたく、日常一般に治療もしないで放置する程度の軽微なものではなく、治療を必要とするものであって、現実に医療を受けるに至ったものであり、到底日常生活で一般に看過されるほどの極めて軽微な傷害ということはできない
- 傷害は軽傷とはいえ、日常生活上一般に看過される程度の軽微なものとは言えず、強盗致傷罪を構成する傷害と認めるに足るものといわなければならない
- 暴行の強弱又は傷害の軽重のほかに、強盗に限り暴行又は傷害の定型(又は類型)そのものを特別に解すべき実定法上の根拠は見出しがたい
- もっとも、日常生活において一般に看過される程度のきわめて軽微なものであって、刑法上の傷害とはいえないものもないわけではないので、このようなきわめて軽微な傷害であれば、強盗致傷罪の傷害とするに足りないといえるのであるが、本件傷害はそのような傷害の類型性を欠くほど軽微なものではない
旨判示し、傷害事実を認め、強盗致傷罪を認定しました。
日常生活において一般に看過されるような極めて軽微な身体の損傷は、刑法上にいわゆる傷害にはあたらないと解するのが相当であるとした上、裁判官は、
- このことは、単に強盗致傷罪における傷害についてのみならず、傷害罪における傷害、強姦致傷罪における傷害その他刑法上の傷害一般についてすべて同一に解すべきものであって、傷害罪における傷害と強盗致傷罪その他刑法上の致傷罪における傷害との間に、その傷害の意義について何らの差異は存しないものというべきである
- 被害者の創傷の程度は、幸いにして軽微であったとはいえ、被害者において傷を受けたことの自覚は十分あり、客観的にも医師の治療を心要とする程度のもので、人の健康状態を不良に変更し、その生活機能をある程度損傷したものであることは明らかであって、吾人の日常生活において一般に看過されるほど甚だしく軽微なものであるとは到底いうことができない
- すなわち、被害者の受けた創傷は刑法上にいわゆる傷害にあたるものといわなければならない
- そうすると、本件被告人の所為は強盗致傷罪を構成する
と判示しました。
仙台高裁秋田支部判決(昭和36年2月22日)
この判例で、裁判官は、
- 刑法第240条前段の規定する強盗致傷罪は「強盗たる身分を有する者が強盗の実行中又はその機会において人に傷害の結果を発生せしめるにより成立する強盗罪と傷害罪との結合犯」であり(最高裁判所昭和24年3月24日判決)、強盗の機会に人に傷害を負わせた情状をもって特に刑の加重原因としているにすぎないのであるから、その手段である暴行が一般「暴行」概念(刑法第208条)と異なり、相手方の反抗を抑圧するに足る高度のものであることを要すること、あるいは同罪の法定刑が一般強盗罪の法定刑(5年以上の有期懲役刑)に比し重刑(無期又は7年以上の懲役刑)であることを理由に強盗致傷罪の構成要件である「傷害」が一般「傷害」概念(刑法第204条)と異なり幾分高度の傷害たるを要すると解する必要も理由もないというべきである
と判示し、強盗致傷罪にいう傷害は、傷害罪にいう傷害より若干高度のものであることを要しないとしました。
東京高裁判決(昭和34年4月15日)
この判例は、加療約5日を要する打撲傷について、強盗致傷罪の成立を認めました。
裁判官は、
- Kの受けた傷の程度は加療約5日を要する打撲傷であって、Kの供述によると、受傷後10日近くを経過した後においても、押せばいくらか痛んだことが認められる
- もっとも、右供述によるとその傷は別段治療をしないで自然に治っており、またKは被害を受けた翌日、畑仕事に従事した事実も認められるのであるが、これらの事情を考慮のうちに入れて判断しても、Kの受けた前記の傷は、日常生活において一般に看過される程度を超えて同人の生活機能を毀損したものであって、強盗傷人罪の構成要件である傷害に該当すると解するを相当とする
と判示し、強盗致傷罪の成立を認めました。
広島高裁判決(昭和53年1月24日)
この判例で、裁判官は、
- 被害者Aは、被告人から暴行を受けたため、顔面、胸部、右肘等に傷害を負ったものの、別に身体が痛かったわけではなかったが、警察官から医師の診察を受けた方がよいのではないかと言われて、当日早朝、外科医院に行って診察を受けたところ、顔面、胸部、右肘挫傷により全治までに約1週間を要する見込みと診断されたこと、医師は軽い傷害で別に治療せず放っておいても治癒するとは思ったが、同女が右肘に痛みを訴えていたため、同女に打身の薬と胸部の傷に対する塗り薬と右肘の傷に対する湿布薬を投与したこと、同女が同医院に通院したのはこの一回のみであり、またこれらの傷によって別に仕事に支障は感じなかったが、右肘の傷の痛みがとれないため一週間位患部に湿布したことが認められる
- してみると、その傷害の程度は幸いにして軽微であったとはいえ、被害者には傷を受けたことの自覚は十分あり、客観的にも医師の治療を必要とする程度のもので、人の健康状態を不良に変更し、その生活機能をある程度損傷したものであることは明らかであって、吾人の日常生活において一般に看過される程極めて軽微なものであるとは到底いうことができず、これが刑法上の傷害に該ることは明らかである
- そして、強盗致傷罪は強盗の機会に被害者に傷害を与えることによって成立するものであって、この場合の傷害を他の場合のそれと別異に解すべきものではない
- それゆえ本件が強盗致傷罪に該当することは明らかである
と判示しました。
下級審においては、傷害罪と強盗致傷罪の傷害概念に差異を設けている
上記の傷害罪と強盗致傷罪の傷害概念に差異はないとした最高裁判例に対し、東京地裁判決(昭和31年7月27日)において、裁判官は、
- 強盗傷人の罪が重刑である法意によれば、同罪の傷害たるには、医学上認められる病変あるいは創傷のうち、少なくともある程度の生活機能の毀損を伴うものであることを要すると考えるから、 日常生活において一般に看過される程度の毀損、例えば本人がほとんど痛痒を感じない微小な表皮剥落や、腫脹、あるいは、ごく短時間に自然快癒する疼痛の如きは、医学上はこれをもって創傷、あるいは病変と称し得ても、法律上、本罪(※強盗致傷罪)にいう傷害をもって論ずることはできない
と旨判示し、『日常生活において一般に看過され、ごく短時間で治る疼痛のような傷害は、強盗致傷罪における傷害にあたらない』とする見解を前提とし、強盗致傷罪は成立せず、強盗罪が成立するにとどまるとしました。
この東京地裁判決は、上記の最高裁判例があるにもかかわらず、主要判例となっています。
現在に至るまで、傷害罪と強盗致傷罪との傷害概念に差異を認める下級審判例は多く存在します。
大阪地裁判決(昭和34年4月23日)
この判例で、裁判官は、
- 刑法上いわゆる傷害とは、一般に他人の身体の生理的機能を毀損し、あるいは他人の身体の現状を不良に変更した場合を指すものと説かれているが、右は単なる医学上の概念ではなく法律上の評価であり、いかなる程度の生理機能の毀損あるいは不良の変更をもって刑法各本条の傷害と認め得べきかは、その各構成要件の様態、その立法趣旨に照らしそれぞれ自ら合理的差異あるものといわなければならない
- 殊に暴行罪と傷害罪とではその法定刑の下限を同じくするのに反し、強盗致傷罪の法定刑は強盗罪のそれに比し、有期懲役刑の短期に2年の差があり、無期又は7年以上(※平成16年以降は6年以上に法改正された)の懲役という重刑が科せられている点又強盗罪の構成要件要素たる暴行は被害者の反抗を抑圧又は困難ならしめるに足る程度の強度の暴行でなければならない点等から考えると、強盗致傷罪を構成すべき傷害は傷害罪のそれよりも幾分高度の生理機能の障害や身体の現状に対する不良変更をもたらすものであることを要し、本人がほとんど痛痒を自覚せず、あるいはごく短期間に自然快癒する程度の僅かな表皮剥脱、腫脹、その他極く微量の出血の如きは、右強盗致傷罪を構成すべき傷害にはあたらない
- これを本件についてみるに、被害者は本件被害にあった後約30分ないしそれ以上を経過し、所轄警察署へ出頭した時にはじめて右頬付近に1、2か所爪で掻かれた跡と思われる小さな創傷があり、わずかに血がにじんでいること、及び口唇もしくは口腔内からもごく小量の出血があることに気付いたもので、しかもそれまで何らの痛みをも自覚しておらず、殊に医師の診察や治療を必要とするなどとは毛頭考えてもいなかったのである
- 従って、右に認定したような極めて軽微な傷創は当然本件暴行行為中に含まれ、これをもっていまだ強盗致傷罪の構成要件である傷害にあたるものとはとうてい認め難い
と判示し、強盗罪は成立しても、強盗致傷罪は成立しないとしました。
名古屋地裁判決(昭和37年11月17日)
この判例で、裁判官は、
- 刑法上にいわゆる傷害とは、医学上のそれと直ちに同一とはいい難く、各法条の規定の趣旨、更には一般社会通念をも参酌して、目的論的にその内容が決定さるべきであり、しかして刑法240条前段の構成要件が、同法236条に比し、無期又は7年以上という重い法定刑に値する事実を類型化したものである以上、そこにいう傷害も又、当然かかる類型性をもったものでなければならないものと考えられる
- 従って、さしたる生理的機能障害を惹起せしめず、日常生活に支障を来たさず、日常生活上看過されうる程度のものであり、例えば、家庭でマーキュロクロームなどを塗布しておくだけで自然に治癒する程度のもので、通院加療といつた医療行為を特別に必要としない程度の軽微なものであれば、医学上の意味においては傷害といいうるものであっても、刑法240条前段にいう傷害をもって論ずることは出来ないと解するのが相当であろう
- 蓋し強盗罪(事後強盗罪の場合も含む)の構成要件としての暴行は、被害者の反抗を抑圧する程度のものであることを要するところ、右にのべた範囲内の傷害であれば、これが発生することがむしろ一般であり、このようなものは右暴行に伴う当然の結果として暴行行為のうちに含ましめて然るべきものと考えられるからである
- 従って、仮に右傷害が刑法240条にいわゆる傷害といい得るものであっても、別個に傷害罪として評価処断されるべきものではない
- 本件について考えてみると、被害者は交番で被害申告を終わってほっとした際、はじめて左手背、右手中指のところがすりむけて血がにじんでいるのに気がついたということであるが、その傷というのは左手の甲に長さ2cm位の引っかき傷のようなものが2本、右手中指の傷は直径1cm位の円型に表皮がはがれたようなものであり、左手の傷は1寸薬を塗って包帯をしたが、これも翌日にはとってしまい、間もなく自然治癒してしまったといつた程度で、右手中指の傷については現在は傷をうけたという記憶すらなくなっているという情況である
- 問題の傷害がかかる程度のものであるとすれば、前述の基準にてらし、これが強盗傷人罪の構成要件を充足するに足る傷害といいえないものであることは明白であるといわねばならない
と判示し、強盗致傷罪は成立せず、事後強盗罪(刑法238条)が成立するにとどまるとしました。
大阪地裁判決(昭和45年2月20日)
この判例は、軽微な創傷は強盗致傷罪おける傷害にあたらないとして強盗致傷罪の成立を否定した事例です。
裁判官は、
- 検察官は、強盗致傷罪にあたるとして、被害者Hに対しては加療2日間を要する左手背切創等の傷害を、被害者O対しては加療2日間を要する右耳翼等の切創による傷害を負わせた旨主張する
- そこで考えるに、強盗致傷罪における傷害には、社会生活上看過される程度の何ら治療を要せず、短期間で治癒し、生理的機能に何ら障害を及ぼさず、かつ通常人がみて身体の状態を不良に変更したと認められない程度のものを包含しないものと解すべきところ、関係証拠によれば、本件強盗に際し、被ったものと認められる被害者Hの左手背切創痕は、1cmにも満たぬ皮下にまで達しない軽い小さな傷痕であり、また同人の頸部捕縄痕は幅数mm、長さ、3~4cmの細長い1本の線状の極めて微量の皮下溢血斑が認められるに過ぎぬこと、同じく被害者Oの右耳翼および右肩切創はいずれも長さわずか1cmにも満たぬ極めて微量の溢血斑を認め得る程度のものであること、被害者らは受傷当時痛みもなく、したがって全然気づかず、警察官に指摘され勧められて医師の診察を受けるようになったこと、治療は赤チンキをつけ滅菌ガーゼをあてるという簡単なもので、その治療も一度受けただけで、その後格別の治療もせず自然に短時間で治癒したことが認められる
- 右の程度の傷害であれば通常人は何ら治療を施さず放置するものと考えられるのであって生活上支障を感ずることはないものといわなければならない
- そうすれば、本件は生理的機能に何ら障害を及ぼさず、通常人が見て身体の状態を不良に変更したものと認められないものというべく強盗致傷罪の傷害にあたらないものと考えるのが相当である
と判示し、強盗致傷罪の成立を否定しました。
福岡地裁小倉支部判決(昭和47年2月21日)
この判例は、打撲傷を強盗致傷罪の傷害にあたらないとした事例です。
裁判官は、
- 本件公訴事実の要旨は、「被告人両名が準強盗の罪を犯した際、加えた暴行により、Kに対し加療約7日間を要する左腕打撲兼左下腿部打撲症を、Sに対し加療7日間を要する左第三・四指打撲兼左大腿部打撲症の傷害を負わせた」というものである
- 医師T作成の診断書2通によれば、K、Sの両名は、本件被害を受けた後、同医師のもとで、右のような傷害の診断をうけていることが認められる
- しかしながら、医師Tに対する受命裁判官の尋問調書、K、Sの当公判廷における各供述によれば、Kの左前腕部は打撲により皮下出血し、腫脹もみられたが、その範囲は広いものではなく、レントゲン検査の結果異常は認められず、治療も消炎酵素剤と鎮痛剤を用いたにすぎなかったこと、Kの左下腿部、Sの左大腿部の打撲症、左第三四指擦過症とも本人の訴えがなければ外見上発見できない程度のものであったこと、医師Tは打撲症の所見がある場合は加療期間として通常5日ないし7日間を要する旨診断するのを通例としていること、また、両名とも警察官に勧められなければ病院にも行かず、そのまま放置するつもりであったと述べ、事実Kが次の日湿布を替えてもらいに1回行っただけであり、Sも初診日に診察等を受けただけでその後は1回も通院しなかつたこと、両名ともしばらく、すなわち2、3日は痛みを感じたが、日常生活に支障をきたすようなことはなく、受傷後1週間もたたぬうちに自然と何時の間にか痛みは消えてしまつていたこと等の事実が認められる
- 強盗罪の法定刑が5年以上の有期懲役であるのに対し、強盗致傷罪においては無期または7年以上(※現在は6年以上)の懲役という重い刑罰が科せられていること、強盗の手段たる暴行は相手方の反抗を抑圧するに足る程度の強度のものでなければならないことからみて、右程度の暴行が被害者の身体に加えられることにより通常生じることが予想されるような軽微な身体の病変はむしろ暴行行為に内包されるものとして同罪にいう傷害にあたらず、ここに傷害といいうるためには日常生活上一般に看過できない程度のもの、換言すれば少くともある程度の生活機能の毀損を伴うものであることを要すると解するのが相当である
- これを本件について考えて見るに、前記認定の如き身体損傷の外見、被害者自身の知覚、治療の方法・程度、治癒に要した日数、日常生活における支障の程度等を総合判断するとき、被害者K、Sの各傷害は医学的には傷害と称し得ても、前記の見地からはむしろ暴行の当然の結果として暴行のうちに含めて考えるのが相当であり、強盗致傷罪にいう傷害には該当しないものと解される
- 従って、被告人両名について強盗致傷罪の成立は認めることができない
と判示しました。
この判例で、裁判官は、
- 本件傷害は、極めて軽微な傷害であって、被害者はこれによって日常生活にもほとんど支障を来さなかったというのであるから、本件は強盗致傷罪にいう「人を負傷させた」場合に該当せず、強盗未遂罪と傷害罪が成立するに止まると解するのが相当である
と判示しました。
平成16年に強盗致傷罪の法定刑は7年から6年に引き下げられ、執行猶予を付することが可能になった
平成16年の刑法の一部改正により、強盗致傷罪の法定刑の下限は7年から6年に引き下げられました。
これによって軽微な強盗致傷事案については、酌量減軽によって3年懲役を言い渡すことができるようになり、執行猶予を付することが可能となりました。
(酌量減軽により、懲役6年を半分の懲役3年にまで減軽するとができる。そして、懲役3年の判決であれば執行猶予を付すことができるようになる)
この刑法の一部改正により、強盗致傷罪でも執行猶予を付することができるようになったことから、現在では、強盗致傷罪における傷害の意義を、傷害罪における傷害の意義と別意に解釈する実務上の必要性は小さくなっています。