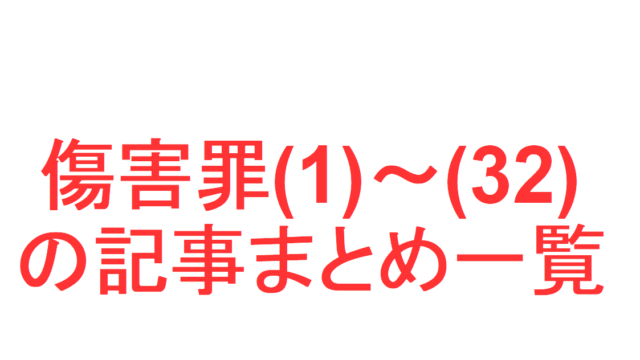前回の記事では、傷害罪の共同正犯に関し、「共謀者は 自ら傷害を負わせなくとも、犯罪行為全部の責任を負う」などついて説明しました。
今回の記事では、傷害罪の共同正犯に関し、「承継的共同正犯」「共犯関係の離脱」「間接正犯」について説明します。
傷害罪における承継的共同正犯
承継的共同正犯とは
ある人(犯人A)が犯罪行為に着手し、その犯罪行為が終わっていない段階で、あとからやって来た人(犯人B)が、犯人Aと共謀し、残りの犯罪行為をAとBの両方で実行する場合
の犯罪形態をいいます(詳しくは前の記事参照)。
傷害罪において、承継的共同性が認められた事例として、以下の判例があります。
名古屋高裁判決(昭和50年7月1日)
この判例で、裁判官は、
- 被告人は、犯行介入前の暴行についても共同正犯としての罪責を負うものと解するのが相当であるから、傷害が、被告人の介入の前後いずれの暴行によって生じたか明らかでないとしても、被告人は傷害の罪責を免れない
と判示しました
札幌地裁判決(昭和55年12月24日)
この判例は、傷害罪の共謀関係に中途から加功したが、実行行為を行わなかった者について、承継的共同正犯の成立が認められた事例です。
裁判官は、暴力団員である被告人が、輩下の暴力団組員が被害者に暴行を加えたことを認識した上、「やるなら2階でやれ」「余りひどくはやるなよ」などと指示したことなどを指摘し、被告人の共同正犯を認めました。
判決の具体的な内容は以下のとおりです。
裁判官は、
- 被告人は、被害者Mに暴行を加えた子分3名(K、S、G)に対し、「やるなら2階でやれ、1階はやばい」と指示したこと、これを受けた、K、S、Gの3名は、被害者Mを事務所2階に上げ、同所において、右3名は、更に被害者Mに対し、手拳でその頭部、腹部を数回殴打し、更に所携(しょけい)の棒状の物で、同人の頭部、背中等を多数回殴打するなどの暴行を加えている
- その際、事務所1階から上がって来た被告人は、被害者Mに右のような暴行を加えている右3名に対し、「どこのノレンをくぐっているかわからないから、あまりひどくはやるなよ」と指示していること、その後、右3名がしばらく暴行を続けたのち、被告人は右3名に対し、「もうこのへんでやめれ」と言って制止したこと、被害者Mは、K及びSから「とにかくお前が悪いんだから兄貴たちに謝って行け」などと命じられ、被告人に対し謝罪していること、その後、被告人は、被害者Mに対し、「ここであったことは誰にも言うな、警察や稼業の者にも言うな」と口止めをしたうえ、同人を帰宅させていること等の諸事実が認められる
- 被告人は、K、Sによる被害者Mに対する暴行の存在を認識のうえ、更にこれと包括される一連の同人への暴行に介入加担する意思で、K、S、Gと共謀し、その共謀に基づき、事務所1階及び2階において、被害者Mに対し、暴行が加えられたのであるから、このような場合、被告人は、共謀関係介入への加担の時点より前に他の共犯者らがすでに被害者に対してなした暴行についても、承継的に共謀共同正犯としての罪責を負うと解するのが相当である
大阪地裁判決(昭和63年7月28日)
この判例は、一連の暴行の途中で、既に加えられた暴行を認識した上、これに加わった者に対し、暴行に加担する前の受傷分を含め、全部の責任を負うとした承継的共同正犯の事例です。
裁判官は、
- 被告人乙及び被告人丙は、共謀のうえ、そのころ、同所において、Bに対し、こもごもその腕を引っ張り、被告人乙においてその腰部を殴打し、右下腿部を足蹴にするなどし、更にこもごもBの身に抱きつくなどの暴行を加えてBを自動車に乗せようとしていたところ、そのころ、所用を終えて駐車場に戻ってきた被告人甲は、同所において被告人乙と被告人丙がBと前記のとおり揉み合っているのを見るや、とっさに事態の成り行きを察知し、右被告人両名の右暴行の概況を認識のうえ、同被告人らに加担する意思を抱き、被告人乙及び被告人丙とその旨意思を通じ合い、引き続き、同所において、被告人3名は、こもごもBの頸部及び背部等を手拳で殴打し、その腰部を押すなどの暴行を加え、よって、右一連の暴行により、Bに対して、加療約1週間を要する右下腿・頸部・腰部打撲傷の傷害を負わせたものである
- 被告人甲は、自己が現認した被告人乙及び被告人丙と被害者Bとの状況から、それまでの同被告人らのBに対する暴行の概況を認識したうえで、あえてこれに加担しようと考え、同被告人らと共謀して暴行に及んだものと認めるのか相当である
- 被告人甲において、被告人らの被害者に対するそれまでの暴行につき、全く認識を欠き、これとは無関係にBに対して暴行に及んだものとは到底認められないのであるから、被告人甲は、その加功前に被告人乙及び被告人丙がなした暴行によるものも含め、被害者Bの受傷につき、傷害罪の共同正犯に問擬(もんぎ)されるものといわなければならない
と判示し、途中から暴行に加担した被告人甲に対し、暴行に加担する前の被害者の暴行も含め、共犯者として一連の暴行全部の責任を負うとしました。
東京地裁判決(平成8年4月16日)
共犯者の一部が先行して被害者に暴行を加えた後、他の共犯者が加わって恐喝の意思を相通じ更に暴行を加えて金員を喝取したとの事案につき、傷害罪と恐喝罪との混合的包括一罪が成立し、途中から加功した共犯者は、先行者が既に行った暴行によって生じた被害者の畏怖状態を認識・認容してこれを恐喝遂行の手段として積極的に利用する意思の下に犯行に加担したものと認められるから、犯行全体について共同正犯の罪責を負うとされた事例です。
事案の内容は、先行して2人が被害者に暴行を加えて傷害を負わせた後、後から来た2人が先行者の暴行によって被害者が畏怖しているのを認識、認容した上、これを恐喝遂行の手段として積極的に利用する意思の下に、先行者2人と意思を通じて、さらに被害者に暴行を加えて金員を喝取したというものです。
裁判官は、
- 本件恐喝と傷害は、被害者が同一であって、時間的、場所的に共通あるいは近接している上、恐喝の犯意形成前の暴行が実質的にみて恐喝の手段となっている関係が認められるから、両者の混合した包括一罪と認めるべきである
- そして、関係各証拠によれば、被告人C及び被告人Dは、先行者である被告人A及び被告人Bが既に行った暴行によって生じたEの畏怖状態を認識、認容した上、これを恐喝遂行の手段として積極的に利用する意思の下に、犯行に加担したものと認められる
- このような本件事実関係の下においては、被告人C及び被告人Dは、本件犯行全体について共同正犯としての罪責を負うというべきである
と判示し、犯行の先行行為者はもちろんのこと、犯行の後行行為者も共同正犯として犯行全部の責任を負うとして、傷害罪及び恐喝罪の刑責を負うとしました。
東京高裁判決(平成8年8月7日)
この判例は、共同正犯による傷害事件において、途中から共謀に加わった被告人に対して、共謀の成立前に他の共犯者の暴行によって生じた傷害の結果についても共同正犯の責任を認めた事例です。
裁判官は、
- 先行行為者の犯行に途中から後行行為者が共謀加担した場合、その後、行行為者に対して、加担前に先行行為者が行った行為及びこれによって生じた結果を含む当該犯罪についての共同正犯としての刑責をどの限度まで問うことができるかについては、考え方が分かれている
- 先行行為者の行為等を認識・認容して一罪の一部に途中から共謀加担した以上、常に全体につき共同正犯の刑責を免れないとする見解や、逆にこれをすべて否定する見解、さらには中間的な考え方として、後行行為者は、原則として共謀加担したとき以後の行為についてのみ刑責を負うが、後行行為者が先行行為者の行為等を自己の犯罪遂行の手段として利用したと評価すべき関係にある場合には、その限度で加担前の行為等について刑責を問われてもやむを得ないとする考え等がある
- 理念上どのように考えるべきかは大問題であるが、本件のような傷害事犯についてこれを考えるに当たっては、その前にまず、途中加担後の行為とされるものがどの範囲の行為とこれによる結果等を指しているかについてみておかなければならない
- 例えば、本件のごとく、先行行為者が傷害行為に及んでいるところへ、後行行為者が途中から共謀加担し、自らも暴行を加えて傷害を負わせたという場合、先行行為者の暴行行為等及びこれによって生じた傷害等の結果と後行行為者のそれとが証拠上明確に区別できるときは、刑責帰属について、前述した理念上の問題を別とすれば、実際上困難な問題はそれほどない
- しかし、途中加担後の行為といっても、その範囲が常に明白とは限らない
- 例えば、後行行為者によって加えられた暴行行為それ自体は特定・識別することができたとしても、それが、結果として単純暴行にとどまったのか、あるいはなんらかの傷害を生じさせたのかの特定・識別は、具体的事案においては案外容易ではない場合がある
- また、先行行為者が負傷させた箇所に後行行為者の暴行が重複して加えられ、それが先行行為による傷害の結果を思いのほか悪化させて、後行行為がその行為によって通常独自に生じさせそうな傷害よりもはるかに大きな診断結果となってあらわれる例が実務上みられるが、そうなると、診断書等によって被害者の身に現実に生じたと認められる傷害が、後行行為者の暴行のみによって生じたものなのか、あるいは先行行為者が生じさせていた傷害に後行行為者の暴行による傷害が付加して生じたものなのかの識別が必要となるのに、この識別はかなり困難となる
- さらには、共謀加担前及び加担後の双方の暴行が競合し合ってある治療期間を要する傷害を生じたと認められる場合、その中で後行行為者の暴行によって生じた傷害の程度や治療期間をどの範囲と認定すべきかとなるとなおさら困難である
- こうしてみると、一口に加担後の行為といっても、その範囲の確定は必ずしも容易ではないときがあるのであって、その点明確な識別・分離が不可能なものについては、後行行為者は、先行行為者の行為ないしそれに基く傷害の結果等について全体として共同正犯としての刑責を負うとすることもやむを得ないというべきであり、またそうする以外に適当な処理方法がないと考えられる一これに対して、加担前の行為ないしこれによる結果等を明確に区別できる場合には、傷害事犯のように、先行行為の結果等が後行行為に影響するという関係が比較的乏しく、いわば個別の傷害行為が寄り集まっているに過ぎない罪においては、途中から加担した後行行為者が、先行行為者の行為ないし結果等を自己の犯罪遂行の手段として利用したと評価すべき特別の事情でもない限り、途中加担者に対して、加担前の行為やこれによって生じた結果等についての刑責を帰属させるべき実質的根拠に乏しいと考えられる
- 本件被告人は、犯行現場において、HがSに対して制裁行為に出ていることや、Sがこれによって相当のダメージを負っていることを認識した上で共謀加担し、自らも敢えて暴行に及んだのであり、その際、被告人が加えた暴行は、先行行為者が負わせた傷害とかなり広い範囲で競合していて、どの傷害を被告人が加えたか識別・分離が不可能なこと前述のとおりであり、また、分離評価に適さない状態にあるから、被告人としては自己が加えた傷害を中心としつつ、これと分離不能の原判示傷害についてその刑責を問われてやむを得ない場合であると考えられる
- 以上の次第であって、被告人に対して、被告人が共謀加担する以前の、Hの暴行によって生じた傷害についても、共同正犯としての責任を認めた原判決に違法な点はなく、正当として肯認することができる
と判示しました。
承継的共同正犯を認めず、同時傷害の規定を適用した事例
承継的共同正犯を認めず、同時傷害(刑法207条)の規定を適用した事例として、以下の判例があります。
大阪地裁判決(平成9年8月20日)
この判例は、被告人両名が第三者の暴行に中途から共謀加担して被害者に傷害を負わせたが、右傷害の結果が共謀成立の前後いずれの暴行により生じたのか不明な事案において、被告人両名には傷害罪の承継的共同正犯は成立しないが、同時傷害の特例が適用されるとされた事例です。
裁判官は、
- 当裁判所は、承継的共同正犯が成立するのは、後行者において、先行者の行為及びこれによって生じた結果を認識・認容するに止まらず、これを自己の犯罪遂行の手段として積極的に利用する意思のもとに、実体法上一罪を構成する先行者の犯罪に途中から共謀加担し、右行為等を現にそのような手段として利用した場合に限られると解する立場(大阪高裁昭和62年7月10日判決)に賛同するものである
- そこで、このような見地から本件につき検討すると、確かに、後行者たる被告人両名は、先行者たるBが頭突き等の暴行を加えるのを認識・認容していたことが認められるが、それ以上に被告人両名がこれを自己の犯罪遂行の手段として積極的に利用する意思を有していたとか、現にそのような手段として利用したとかの事実は本件全証拠によっても認めることはできないから、結局、被告人両名には傷害の承継的共同正犯は成立しないというべきである
- しかし、以上から直ちに、被告人両名は、謀成立後の傷害の結果についてのみ傷害罪の共同正犯に問われると結論することはできない
- 本件傷害の結果は、共謀成立の前後にわたるB及び被告人両名の一連の暴行によって生じたことは明らかであるが、それ以上に、これがBの頭突き等の暴行にのみ起因するものであるのか、それともその後の被告人両名及びBの暴行にのみ起因するものであるのか、はたまた両者合わさって初めて生じたものであるのかは、本件全証拠によってもこれを確定することはできないからである
- そして、一般に、傷害の結果が、全く意思の連絡がない2名以上の者の同一機会における各暴行によって生じたことは明らかであるが、いずれの暴行によって生じたものであるのかは確定することができないという場合には、同時犯の特例として刑法207条により傷害罪の共同正犯として処断されるが、このような事例との対比の上で考えると、本件のように共謀成立の前後にわたる一連の暴行により傷害の結果が発生したことは明らかであるが、共謀成立の前後いずれの暴行により生じたものであるか確定することができないという場合にも、右一連の暴行が同一機会において行われたものである限り、刑法207条が適用され、全体が傷害罪の共同正犯として処断されると解するのが相当である
- 右のような場合においても、単独犯の暴行によって傷害が生じたのか、共同正犯の暴行によって傷害が生じたのか不明であるという点で、やはりその傷害を生じさせた者を知ることができないときに当たることにかわりはないと解されるからである
- よって以上により、当裁判所は、被告人両名には、本件傷害の結果につき同時傷害罪が成立し、全体につき傷害罪の共同正犯として処断すべきものと判断した次第である
と判示しました。
傷害罪の共犯事案における共犯関係の離脱
共犯関係の離脱を認めた事例
傷害罪の共犯事案において、共犯関係の離脱を認めた事例として、以下の判例があります。
名古屋高裁判決(平成14年8月29日)
この判例は、共犯の被告人に対する暴行とその結果失神した被告人をその場に放置したという行動によって共犯関係が一方的に解消されたと認定された事例です。
ます、被告人の弁護人は、
- 被告人は、公園駐車場において主犯格のBらとの共謀に基づき、Bと一緒に被害者に対して暴行(第一の暴行)を加えた後、Bの暴行を制止して被害者と話をし始めたところBから殴打されて気を失い、Bらと行動をともにすることができない状態になってしまったから、共犯関係からの離脱(あるいは共犯関係の解消)を認めるべき場合であるのに、これを認めず、その後Bが行った衣浦港岸壁における暴行(第二の暴行)の結果生じた傷害についてまで刑事責任を負わせた原判決は事実を誤認したものであって、これが判決に影響することは明らかである
と主張しました。
この主張に対し、裁判官は、
- Bを中心とし被告人を含めて形成された共犯関係は、被告人に対する暴行とその結果失神した被告人の放置というB自身の行動によって一方的に解消され、その後の第二の暴行は被告人の意思・関与を排除してB、Cらのみによってなされたものと解するのが相当である
- したがって、原判決が、被告人の失神という事態が生じた後も、被告人とBらとの間には心理的、物理的な相互利用補充関係が継続、残存しているなどとし、当初の共犯関係が解消されたり、共犯関係からの離脱があったと解することはできないとした上、第二の暴行の結果生じた傷害についても被告人の共同正犯者としての刑責を肯定したのは、事実を誤認したものというほかない
と判示し、原判決が第ニの犯行につき共犯関係の離脱を認めなかったのを否定し、弁護人の主張のとおり、共犯関係からの離脱を認めました。
共犯関係の離脱を認めなかった事例
傷害罪の共犯事案において、共犯関係の離脱を認めなかった事例として、以下の判例があります。
東京高裁判決(昭和40年4月27日)
この判例は、暴行の中途で犯意を失い、共犯者を制止した者に対し、共犯関係の離脱を認めなかった事例です。
まず、被告人の弁護人は、
- 被告人らの暴行に堪えかねた被害者が助けを求めて被告人にしがみついてきたので、被告人はかわいそうに思い、以後暴行の意思を失い、Tらの暴行の制止につとめ、これを停止せしめたもので、殴り倒されていた被害者が事終われりと考え立ち上ったところ、Tが突如所携(しょけい)のかみそりをもって、被害者の顔面に切りつけ、被害者に原判示の傷害のうち左側顔面切創の傷害を負わせたものである
- そうであれば、被告人が前記暴行制止の行動に出る前までの間に、ほかの共犯者が被害者に加えたであろう暴行によって生じたと推定できる原判示打撲傷及び裂傷の傷害につき、共犯としての責任を負うことを否むものではないが、暴行の制止に努めるようになった以後のTらの被害者に対する傷害についてまで被告人の責任が及ぶいわれはない
- 特に、Tがかみそりを携帯していたことは被告人の全く知らなかったことであるから、Tがかみそりをもって被害者に与えた前示傷害について、被告人に責任のないことは明らかである
と主張しました。
この主張に対し、裁判官は、
- 原判決挙示の関係証拠によれば、被告人は、小学校庭でTらが、被害者に対し暴行を加えることを了知の上、Tらと意思を通じて、共に被害者に暴行を加えたものである
- 最終段階において、Tによりかみそりをもって加えられた前示暴行も、その以前の暴行に引き続いてなされた一連の行為と認められるのであり、この一連の行為により被害者が原判示第一の傷害を負うに至ったことは明らかである
- 仮りに、被告人がTらの暴行の制止につとめたとしても、証拠上これによりTらの暴行を停止せしめたことは認め得ないのであるから、被告人が左様な行動に出るようになった以後のTらの暴行による傷害について責に任することはもちろんにして、また、被告人とTらとの間に前記の如く被害者に対する暴行の共謀がある以上、被告人においてTがかみそりを携帯していたことを全く知らなかったとしても、Tのかみそりによる前記傷害について責任のあることはいうまでもないから、原判決には所論(※弁護人の主張のこと)の如き事実誤認の違法は存しない
と判示し、被告人は暴行の制止につとめたとしても、実際に共犯者の暴行を停止させていないのであるから、共犯関係の離脱は認めらえないとして、傷害罪の共同正犯の責任を負うとしました。
なお、共犯関係の離脱については、前の記事で一般論を説明しています。
傷害罪における間接正犯
間接正犯とは、
他人を道具として利用し、他人に犯罪行為をやらせ、犯罪を実現する者
いいます(詳しくは前の記事参照)。
傷害罪における間接正犯の事例として、以下の判例があります。
大阪高裁判決(昭和49年4月18日)
この判例は、行為当時、心神喪失の状態にあった者を責任能力者と錯誤し、その者と共犯意思の下に、傷害、殺人未遂の犯行に及んだ被告人は、心神喪失者の行為について間接正犯として傷害罪、殺人未遂罪の刑責を負うべきであるとしました。