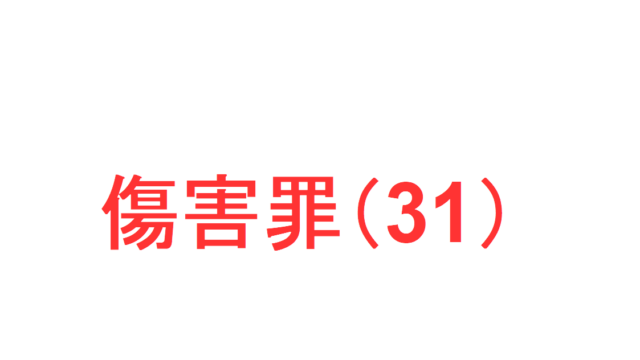前回の記事に引き続き、傷害罪と
- 強盗罪・強盗致傷罪
との関係について説明します。
傷害罪と強盗罪・強盗致傷罪の関係の説明テーマは、以下の①~⑦があり、長くなるので、【その1】と【その2】の2回にわけて説明しています。
今回の記事である【その2】では、⑤~⑦のテーマについて説明します。
- 強盗致傷罪は、「傷害罪」と「窃盗罪や恐喝罪」などとの併合罪として処理される場合が多い
- 暴行の程度が被害者の犯行を抑圧するに足る程度のものと認められない場合は、強盗致傷罪ではなく、恐喝罪と傷害罪との観念的競合になる
- 傷害が、財物奪取の犯意を生ずる前の暴行による場合、強盗致傷罪ではなく、傷害罪と窃盗罪との併合罪になる
- 傷害が、財物奪取の犯意を生ずる前の暴行による場合、強盗致傷罪ではなく、傷害罪と恐喝罪との併合罪になる
- 窃盗行為の着手がないとして、被害者に対する傷害罪・暴行罪を認定した事例
- 強盗の犯意発生の前後いずれの暴行による傷害であるか認定できないとして、強盗罪と傷害罪の包括ー罪を認めた事例
- 窃盗行為後に逮捕を免れるため、私人の逮捕者に暴行を加えた事案で、有効な逮捕行為を認定せず、強盗致傷罪ではなく、窃盗罪と傷害罪の併合罪とした事例
強盗罪・強盗致傷罪との関係【その2】
傷害罪と強盗罪(刑法236条)、強盗致傷罪(刑法240条)との関係について説明します。
⑤ 窃盗行為の着手がないとして、被害者に対する傷害罪・暴行罪を認定した事例
窃盗行為の着手がないとして、強盗致傷罪ではなく、被害者に対する傷害罪・暴行罪を認定した以下の判例があります。
札幌地裁小樽支部判決(昭和33年12月15日)
窃盗目的で住居に侵入し、物色前に家人に発見され、暴行に及んだ事案で、強盗致傷罪の起訴に対し、窃盗行為の着手がないとして、強盗致傷罪ではなく、暴行罪と傷害罪のニ罪の成立を認めた事例です。
裁判官は、
- 強盗致傷罪の訴因の要旨は、被告人は、窃盗の目的で本件家屋に侵入し、金品を物色中、被害者らに発見され、その逮捕を免れるため、同人らに暴行を加え、本件傷害を与えたというにある
- 証拠を案ずるに、被告人は本件家屋に侵人した目的が窃盗にあったと終始一貫して供述しているが、他にこれを裏づける確実な証拠もないのみならず、被害者の一人であるY子の証言によると、被告人の目的はむしろ婦女を姦淫するか又はわいせつ行為をすることではなかったかという疑惑も濃厚であり、被告人の目的を本件訴因の如く断定することは些か困難であるといわねばならない
- しかし、仮に検察官の主張のように、被告人の右目的が窃盗にあったとしても、被告人及び証人Yの供述によれぱ、被告人の窃取の目的であったという菓子類は、同家表店舖に陳列されており、被告人は、裏の縁側から戸を開げて屋内に入ったのであるが、そこから店舖へ到るには、その中間に八畳の間があり、店舖との境界はカーテンで仕切られていること、被告人は、まず表店舗内に入る前に家人がいるかどうかを確めるため、八畳間の隣の六畳の間に入ったところ、Y子に発見され、本件犯行に及んだものであること、被告人は表店舖内には全然人っておらず、右八畳においても、せいぜい表の店舖内の菓子類が眼に入った程度以上の行為には出ていないことが認められる
- 窃盗行為について、実行の着手が有りとするには、少くとも物に対する他人の事実上の支配を侵すについて密接な行為をなすことを要するものと解すべきところ、被告人の右行為がそのような意味における実行の着手に該当するとは到底考えられない
- 従って、窃盗の実行の着手があったことを前提とする強盗傷人の本件訴因はこれを認めることはできない
と判示しました。
東京高裁判決(昭和38年3月6日)
この判例は、強盗の目的で家内に侵入し、家人に発見され、所携(しょけい)の薪棒を持って殴打逃走し、傷害を加えた事案において、暴行前に物色など窃盗行為に着手した事実がなく、また右暴行は逃げるためで、金品強取の目的でないとして強盗致傷罪の成立を否定し、強盗予備罪、住居侵入罪及び傷害罪を構成するとした事例です。
裁判官は、
- 強盗傷人罪が成立しない要点は、被告人において窃盗罪に着手した後逮捕を免れるために暴行をなしたこと又は強盗罪の構成要件たる金品を強取する手段として暴行をなしたことはいずれも認められない点にある
- 薪棒で被害者を殴打したことが、強盗罪の構成要件である反抗を抑圧するための暴行であると認むべきか否かについては、検察官所論の如く、被告人の検察官に対する供述調書中には、被告人は金品強奪の犯意の下に右薪棒による殴打をしたのではないかと疑うべき供述が存しないではないが、しかしながら、被告人の捜査段階よりの供述及び被害者らの同様捜査段階よりの供述によって認め得べき被告人の当時の行動は、逮捕を免れ、逃走をまっとうしようとするに急であったという印象を与えこそすれ、あくまでも強盗を働くという意思に基いたものとは解し難いというべきである
- 本件は強盗傷人罪を構成するとみるには、証拠上欠けるところがあるというべきであり、原審のいうが如く、ただ強盗予備罪、住居侵入罪及び傷害罪の成立があるに止まるとみるべきである
と判示しました。
⑥ 強盗の犯意発生の前後いずれの暴行による傷害であるか認定できないとして、強盗罪と傷害罪の包括ー罪を認めた事例
強盗の犯意発生の前後いずれの暴行による傷害であるか認定できないとして、強盗罪と傷害罪の包括一罪を認めた事例として、以下の判例があります。
この判例で、裁判官は、
- 強盗傷人罪を構成するためには、傷害が強盗の機会において加えられたものであることを要し、それは強盗行為と傷害との間に場所的、時間的関係があるのみでなく、傷害が強盗たる身分を有する者によって加えられたこと、すなわち、犯人が強盗の犯意を生じた後の傷害であることを要する
- 従って、強盗の犯意を生ずる前の傷害は単純な傷害であり、その犯意を生じた後の傷害は強盗と傷害の結合犯たる強盗傷人罪の構成部分たる傷害であり、その意味におい て、強盗の犯罪を生じた時期を境としてその前後二群の傷害は切離された二個の行為であり、前の傷害と後の強盗傷人とは別罪である
- しかし、それは法律評価の問題であって、これを社会的現象として観るときは、その評価の対象たる二群の傷害は、一個の身体侵害の意思に基き、時を接して引続き行われるのであるから、これを一連不可分的のものとみるべきで、しかも後の傷害は強盗行為に伴うもので、これと結合一体の関係にあるのであるから、これらすべてを全体的に包括的に観察して、一連一個の行為と解するのが相当である
- すなわち、罪数的には、それは一種の接続犯的な傷害と強盗傷人との混合した包括一罪であって、重い強盗傷人罪の刑をもって処断すべき一罪と解するのである
- このことは、もとより前の単純傷害の部分が強盗傷人の傷害に性質を変化してしまうという意味ではなく、例えば、傷害か、強盗の犯意を生じた時期を境として、その前後二群の暴行のいずれによって生じたか不明の場合を考えれば、傷害が強盗の犯意を生じた後の暴行に基因することの証明がない限り、犯人を強盗傷人罪に問擬(もんぎ)することは許されないから、前後の暴行は強盗傷人にはならないけれども、前後の暴行は一体として観察されるから、結局単純傷害の責を犯人が負わねばならないのであって、傷害と強盗との混合した包括一罪であることを意味するのである
- 前の傷害と後の強盗傷人とを併合罪とする原判決の見解をとれば、この場合、傷害の結果を前後いずれの暴行にも帰せしめられない以上、暴行と強盗との併合罪となり、犯人に傷害の責を負わしめることができなくなるのであって、一連の暴行によつて生じた傷害の結果を、刑法上評価できないのは、明らかに不当である
- また右併合罪の見解は、途中、強盗の犯意を生じなかった場合、傷害となるに比しても権衡を失する
- 以上の次第で、前記の如く傷害と強盗傷人を併合罪とした原判決は法律の適用を誤ったもので、その誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、この点に おいて原判決は破棄を免れない
と判示し、傷害罪と強盗致傷罪の併合罪ではなく、強盗罪と傷害罪の包括一罪を認定しました。
福岡地裁判決(昭和47年3月29日)
この判例は、強盗致傷罪の起訴について強盗罪と傷害罪の包括一罪と認定した事例です。
裁判官は、
- Mが被告人らに金員および腕時計を強取された場所で、被告人らの一連の暴行行為により傷害を受けたことは、各証拠により明らかであるが、被告人らの強盗の犯意発生前後の各暴行の方法、程度および態様を検討すると、そのいずれによっても判示のような傷害をMに与えるのは不可能でないこと、木件が比較的短時間の接続した一連の暴行によるものであること等を考え合わせると、傷害が被告人らの強盗の犯意発生の前後いずれの暴行によって生じたものであるかについては証拠上明らかではないが、右傷害が判示場所において、被告人らの強盗の犯意発生前後のいずれかの暴行によって生じたものであることは証拠上明らかであるので、被告人らは少なくとも傷害の結果についても責任を負わなければならないところ、判示暴行の時間的、場所的一連性ないしは接着性に着目して、強盗罪と傷害罪の混合した包括一罪として重い強盗罪の刑で処断すべきものと解する
と判示しました。
浦和地裁判決(昭和33年9月10日)
この判例は、暴行の途中、強盗の犯意を生じた場合において暴行による傷害が強盗の犯意を生ずる前後いずれの暴行によるものか確定できない場合について、強盗致傷罪ではなく、傷害罪と強盗罪の観念的競合を認定しました。
裁判官は、罪となるべき事実について、
『被告人は、Sと共に、路上に差しかかつた際、折から同所を通りかかったOに出会うや、被告人らは共謀して、同人の頭部顔面を足蹴りしているうち、Sが「金を持ってんだべ、取っちゃえ」と言うや、被告人もこれに和して、ここに金品を強奪することを共謀して、更に続けて同様足蹴りして暴行を加え、その反抗を抑圧した上、同人所有の現金615円、身分証明書1枚を強奪し、その際前記一連の暴行により同人に対し全治10日間を要する眼囲打撲性皮下出血前額部擦過症、同部打撲裂創等の傷害を負わせたが、その傷害が金品強奪の犯意の生ずる前後いずれの暴行によるのか明らかでないものである』
と認定しました。
罪となるべき事実の認定理由について、裁判官は、
- 強盗傷人罪を構成するためには、傷害が強盗の機会におけるものでなければならないといわれているが、その意味は強盗行為と傷害との間に場所的、時間的関係があるというだけでは足りないので、傷害が強盗犯人によって惹起されたものであることを絶対の要件とする
- そして、右強盗犯人によって惹起されたといいうるためには、犯人が強盗の犯意を生じた後の傷害であることをいうのである
- 然るに、本件においては、前示認定の通り、Oが判示の傷害を受けた事は証拠上争いのないところであって、その傷害は、強盗の犯意を生ずる前後にわたる暴行に起因することも証拠上明らかであるが、その傷害が果して強盗の犯意を生じた後の暴行によって生じたもの、すなわち、強盗犯人によって惹起されたものである点については、遂に証拠上これを明確にすることができない
- 果して然らば、被告人の本件所為を強盗傷人罪として問擬(もんぎ)することは、とうてい許されないところである
- 次に、然らば右証拠上明認できる傷害の点を本件においていかに評価し、擬律するかがここで問われなければならない
- この点について、まず、この傷害が強盗の犯意を生ずる前後の暴行のいずれに起因するものであるか不明であるから、暴行=傷害としての罪責を被告人に帰せしめ得ないのではないかとの議論もあろう
- この見解は、強盗の犯意を生ずる前後の暴行をその犯意を生ずる時期を画して2個の暴行と考えることによるものである
- なるほど、強盗の犯意を生じた後の暴行は強盗罪の手段としての意味を有する
- そして、また、その前の暴行は単純な暴行としての意味しかないことは否定できない
- がしかし、それは暴行に対する法的評価の問題である
- その評価の対象としての行為は、本件においては既に認定したとおり、僅々5分か10分の間に1個の身体侵害の意思の発動に基くまさに一瞬の行為である
- この一瞬の暴行が強盗の犯意を生ずる時期を境として、2個の異なる法的評価を受けるからといって、そしてまた、本件傷害が2個に評価される暴行のいずれに起因するものか不明であるからという理由をもって、現にこの一瞬の暴行によって生じた傷害の結果を不問に付し、あるいは刑法上、これを評価できないとすることは決して正しい解釈態度ではない
- 証拠の観点からいえることは、最底限、本件においては、被告人に対し、強盗傷人罪としての罪責、あるいは強盗の犯意を生ずる前の暴行に基く傷害罪としての罪責を帰せしめえないということだけである
- 本件Oの受けた傷害が、被告人の行為によるものであることが否定できない以上、この傷害について、被告人が罪責を免れないことは蓋し当然である
- 更にまた、この場合、右一瞬の暴行に起因する傷害を、別個に単純傷害罪として評価し、被告人に強盗罪の他に傷害罪の罪責を負わすことになれば、強盗の犯意を生じた後の暴行については、これを強盗罪として、すなわち、その手段としての暴行の点において既に評価しているのであるから、傷害罪として罪責を問うとすれば、1個の暴行を重ねて評価し罪責を負わす結果を来たすのではないかという疑問がある
- しかし、それは当らない
- 本件において、現に生じた傷害の点を、単純暴行及び強盗罪として評価しただけでは、評価しつくしていないことは異論あるまい
- やはり傷害の点はそれなりに別個の評価を受け、この点については暴行及び強盗とは別に被告人の罪責を問わなければならない筋合である
- もし、その際、暴行の点について二重の評価を受けることがあっても、それは被告人の行為にして2個以上の罪名に該る限り当然の事である
- 刑法は、想像的競合罪(※観点的競合のこと)の処分については、当然にかかる事態の発生を予定しているものというべきである
- そして、被告人の本件行為を以上のように刑法上理解し、罪責を負わすことは健全な社会の通念にも合致するであろうし、機能的解釈としても正当な所以であると信ずる
- 従って、当裁判所としては、本件被告人の所為は、一面において強盗罪としての罪名にふれることは当然として、その手段たる暴行と、強盗の犯意を生ずる以前の暴行とが一瞬の暴行と解せられる限り、この暴行に基く傷害と右強盗罪とは1個の行為にして2個の罪名に触れる場合として処断せられるべきものと解した次第である
と判示し、強盗致傷罪ではなく、傷害罪と窃盗罪の観点的競合が成立するとしました。
仙台地裁判決(昭和39年7月17日)
恐喝の犯意で暴行を加え、途中で強盗の犯意を生じた場合において、傷害が強盗の犯意を生ずる前後いずれの暴行に起因するものであるかが不明の場合につき、強盗罪(恐喝行為を吸収)と傷害罪とのいわば混合した包括一罪として、結局最も重い強盗罪の刑で処断されるべきであるとした事例です。
裁判官は、
- 本件は、強盗致傷罪として起訴されたものであるが、同罪が成立するためには、傷害が強盗の機会において生じたものであることを必要とし、この「強盗の機会において」というには、傷害が少くとも犯人が強盗の犯意を生じた後の暴行によって生じたものでなければならない
- 従って、傷害が強盗の犯意発生の前後いずれの暴行に起因したものであるかが不明である場合には、これを強盗致傷罪として問擬(もんぎ)することは、疑わしきを被告人の不利益に帰せしめる結果ともなり、とうてい許されないところである
- これを本件について見るに、前示認定のとおり、Fが被告人Kに腕時計を奪取された場所で、被告人らの一連の暴行行為により傷害を受けたことは明らかであるが、この傷害が、被告人Kの強盗の犯意を生ずる前後いずれの暴行に起因するものであるかは、証拠上ついにこれを確定することができない
- しかしながら、右傷害は、前記場所において、被告人Kの強盗の決意発生前後のいずれかの暴行又は恐喝の共犯者たる被告人W、Gの暴行によって生じたものであることは、証拠上疑いのないところであるから、被告人Kは、少くとも傷害の結果について責任を負わなければならないわけである
- 従って、この点につき、被告人Kの利益に、右傷害は同人の強盗の犯意発生前の暴行によるものと解するを相当とするところ、強盗の犯意発生前の恐喝の手段としての暴行と強盗の犯意発生後の暴行とは、一連のもので、相接続する機会に前者より後者へと発展したものと認められるから、被告人Kの判示所為は強盗罪(恐喝行為を吸収)と傷害罪とのいわば混合した包括一罪として、結局、最も重い強盗罪の刑で処断されるべきものと解する
と判示しました。
新潟地裁判決(昭和45年12月11日)
強盗致傷の起訴につき、傷害の結果が、強盗の犯意発生前の恐喝の意思による暴行によって生じたものとして、強盗罪と傷害罪の包括一罪と認め、重い強盗罪の刑によって処断すべきであるとした事例です。
裁判官は、
- 公訴事実は、要するに、被告人3名が共謀して、Yから現金在中の財布および腕時計を強取し、その際、Yに傷害を負わせたというのであって、被告人3名につき、いずれも強盗致傷罪が成立するというのである
- ところで、そのうち被告人Kの罪責については後に述べることとし、はじめに被告人MとOの罪責について検討する
- まず両被告人の犯意の点を考える
- 判示のように、本件においては、通称西新道の道路上での、第一現場における暴行、脅迫行為と、栗の木川橋下での第二現場における暴行、脅迫および金品の奪取行為とに分れる
- 第一現場における両被告人の犯意については、両被告人の捜査官に対する各供述調書および当公判廷における供述によっても、せいぜい判示のような恐喝の犯意が認められるに止まり、強盗の犯意があつたか否かについては必らずしも明らかでないばかりでなく、その現場が新潟市内の飲食店などが密集する繁華街であつて、犯行時の午後12時ころにも酔客などの通行が多いと認められること、付近には看板灯や外灯の設備などがあって比較的明るい場所であり、被告人らの行為は容易に第三者の目撃できる状況にあること、Yがタクシーに乗り込まされる間際まで、Yと同行していたTが近くにいたこと、第一現場での両被告人の暴行、脅迫行為もこれを全体として見るときは、未だYの反抗を抑圧するに足りる程度に至っていたものとは認められないことなどの客観的状況に照らしても、両被告人が第一現場で強盗の犯意を有していた点については証明が十分でなく、恐喝の犯意に止まるものと認めるのが相当である
- そして、両被告人の強盗の犯意は、栗の木川橋下の第二現場に至ってはじめて生じ、判示のように、人目につかない暗い場所で強い暴行、脅迫を加えてYの反抗を抑圧して金品を強取したものと認められる
- このように、まず第一現場において恐喝の意思による暴行、脅迫がなされ、それが第二現場に至って強盗の犯意による暴行、脅迫に発展し、その結果、金品を強取したものであるが、両者は金品の奪取という単一の目的に向けられた一連の行為であり、行為の客観的側面においても、また両被告人の主観的な意思の側面においても連続性が認められるから、これを包括して重い強盗の一罪(なお傷害との関係については次に述べる)が成立するものと解する
- 次に右の強盗と本件の傷害との関係を考える
- 本件の被害者Yが、本件により判示のような下顎挫傷の傷害を負ったことは、証拠上明らかである
- そして、証人Dの証言(第一回)によれば、右の傷害は直接には第一現場での被告人Mの暴行により生じたことが認められ、この認定をくつがえすに足りる証拠はない
- ところで、強盗致傷罪を構成するためには、傷害が強盗の機会において受けたものであることを要し、換言すれば、傷害が強盗という身分を有する者による犯行の際に生ずること、すなわち犯人が強盗の犯意を生じた後のものであることを要するものと解する
- 本件のYの傷害は、右のように第一現場において受けたものであり、また第一現場においてはさきに述べたように両被告人は恐喝の犯意を有したに止まり、未だ強盗の犯意がなかったものであるから、右の傷害の事実は認められるとしても、本件については、そのことから直ちに強盗致傷罪を構成するものではなく、前記のような強盗罪とこれとを切り離された傷害罪とに分けて評価すべきものと解される
- そして、この強盗と傷害とは、本件の事実関係に徴すると、両者の混合した包括一罪が成立し、結局重い強盗罪の刑によって処断すべきものと解するのが相当である
と判示し、傷害の結果が、強盗の犯意発生前の恐喝の意思による暴行によって生じたものであるから、強盗致死罪は成立せず、強盗罪と傷害罪の包括一罪が成立し、重い強盗罪の刑によって処断すべきであるとしました。
この判例は、強盗との時間的・場所的な隔たりから、逮捕を免れるための警察官に対する暴行を強盗致傷と認めなかった事例です。
前夜、岡山県下で強盗を行って得た盗品を船で運搬し、翌晩、神戸で陸揚げしようとする際巡査に発見され、逮捕を免れるため暴行を加え、巡査を傷害した事案で、裁判官は、
- 本件犯行と、本件犯行の前日岡山県において行われた強盗の行為とは、その時期、場所、態様からいって、別個のもので、本件犯行は、上記強盗による贓物(盗品)を船で運搬し来り、神戸で陸揚しようとする際に、すなわち右強盗とは別個の機会になされたものである
とし、強盗と公務執行妨害、傷害の罪が成立するとました。
この裁判は、本件強盗について、既に確定判決を受けた一連の強盗事件と連続犯の関係にあるとして、免訴の言い渡しがなされたため、弁護人からより重い強盗致傷罪の成立を主張したという特異な事案でしたが、強盗と傷害は、時間的にも場所的にも同一機会と見られないという理由で、強盗致傷罪一罪が成立する弁護人の主張が排斥されたものです。
⑦窃盗行為後に逮捕を免れるため、私人の逮捕者に暴行を加えた事案で、有効な逮捕行為を認定せず、強盗致傷罪ではなく、窃盗罪と傷害罪の併合罪とした事例
窃盗行為後に逮捕を免れるため、私人の逮捕者に暴行を加えた事案で(※現行犯逮捕は一般人でもできる)、有効な逮捕行為を認定せず、強盗致傷ではなく、窃盗罪と傷害罪の併合罪とした以下の判例があります。
東京高裁判決(昭和52年12月21日)
この判例は、窃盗犯人が、窃盗の直後に暴行に及んだ案件につき、強盗致傷を認定した原判決を破棄し、窃盗と傷害の併合罪を認定した事例です。
判決の概要は、窃盗犯人である被告人が、被告人の不審な態度を見咎めたKと口論の上、Kに暴行を加えたが、被告人に逮捕を免れるための暴行であるとの意思はなく、被害者にも被告人を窃盗犯人として逮捕する意思はなかったとして、強盗致傷罪は成立しないとしたものです。
裁判官は、
- 被告人の暴行が果して窃盗犯人として、「逮捕を免れる」ためになされたものかどうか、Kにおいて被告人を窃盗犯人として逮捕する意思であったかどうかについて、検討を加える
- Kは、被告人を一時警察に突き出してやろうという気持があった旨供述する一方、畑の中の被告人を見咎めて「何してんだ、この野郎」と怒鳴りつけたのは、必ずしも被告人を窃盗犯人と確認しての言葉ではなく、まず声を掛けて、意見すべく考えて発した言葉であり、「酒を飲んで車を運転し、人の大根を盗むとは何事だ。お前のようなやつは警察につき出してやる。逃げるんだつたら逃げてみろ、ナンバーだって覚えてる。」「明るいところに行こう。」などと怒鳴りつけたのも、被告人の謝罪が単なる言葉のうえだけのもので、しかも被告人が謝罪するそばから前記のように反抗的言葉をもって怒鳴り返す態度に出たため憤慨し、被告人を脅し、かつ意見するためであって、真実、被告人を逮捕するつもりはなかった旨供述しており、Kは、当審における証人尋問調書中においても、被告人を逮捕する意思、ことに、窃盗犯人として逮捕する考えのなかったことを明言している
- また、被告人の襟首をつかんで連れて行こうとしたことについても、暗い所では何をされるか不安があったからで、逮捕の意図に基くものでなかった旨供述しているのである
- 更に、被告人の暴行が開始されてからのKの行動も、腕力に自信のあるKが被告人の暴行に対応し、これに反撃するといつた形態をとっていることを知ることができるのである
- しかも、Kは、被告人が暴行をやめた後、Kの妻から警察に連絡した旨聞かされると、被告人に対し、警察官がくる前に早く逃げろなどと申し向けているのである
- そしてまた、Kは妻の急報で現場に来た警察官に対しても被告人を窃盗犯人として逮捕しようとしたとの事情については何ら説明することなく、現場でつかみ合いの口論となった旨申し述べているだけであり、一方、被告人としても窃盗犯人として逮捕されそうになったので、逮捕を免れるためKに対して原判示の暴行に及んだことについてはこれを争い、被告人としてはKが高圧的に被告人を泥棒ときめつけたので憤慨し、さらに、酒飲み運転として警察に突き出すというので癪に触わって原判示暴行に及んだと終始供述しているのであって、以上の各事実によれば、Kが被告人を窃盗犯人として逮捕しようとし、被告人において右逮捕を免れるため原判示の暴行に及んだものと断定するについては、やはり合理的疑いを容れる余地がある
- 以上の次第であって、原判決が本件を窃盗犯人が逮捕を免れるため、原判示Kに対し、原判示暴行傷害を加えたものとして、強盗致傷と認定した措置には、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認があるものというべく、原判決は破棄を免れない
と判示し、判決が強盗致傷罪が成立するとしたのは誤りであるとし、窃盗罪の傷害罪が成立するものであるとしました。
京都地裁判決(昭和51年10月15日)
この判例は、暴行が窃盗の機会に行なわれたものではないとして事後強盗致傷罪の成立を否定し、窃盗罪と傷害罪の成立を認めた事例です。
窃盗未遂で現行犯逮捕され、逮捕者Mから約1時間警察に行くように説得され、一応これに応じてMと警察に赴く途中、約200m離れた地点で逃走を企てて、Mに暴行を加えて傷害を負わせた事案で、裁判官は、
- Mの当初の逮捕行為が本件暴行時まで継続していたとみるのは困難であって、被告人がMの説得に応諾した段階で逮捕状態は消滅したものとみられ、Mの警察への被告人の同行は有形力を用いないいわば任意の同行というべきものであり、しかも本件暴行が行われるまでに相当の時間的、場所的に隔たりがあるから、かかる状況のもとでは、たとえ窃盗行為後、警察への同行中に逃走のため暴行が加えられたとしても、その暴行はもはや窃盗の現場若しくは窃盗の機会継続中になされたものと解することはできず、従って窃盗犯人が逮捕を免れるため暴行を加えた場合に当らないから、本件につき事後強盗致傷罪は成立しないものといわなければならない
と判示し、事後強盗致傷罪ではなく、窃盗未遂と傷害罪によって処断しました。
次回に続く
次回の記事では、傷害罪と
- 強制性交等罪・強制性交等致傷罪(旧称:強姦罪・強姦致傷罪)
- 器物損壊罪
- 道路交通法違反(救護義務違反)
との関係について説明します。