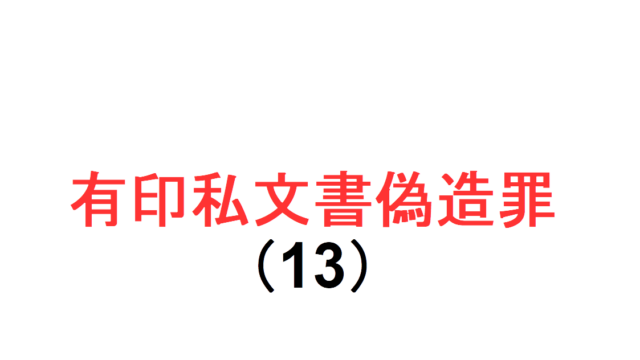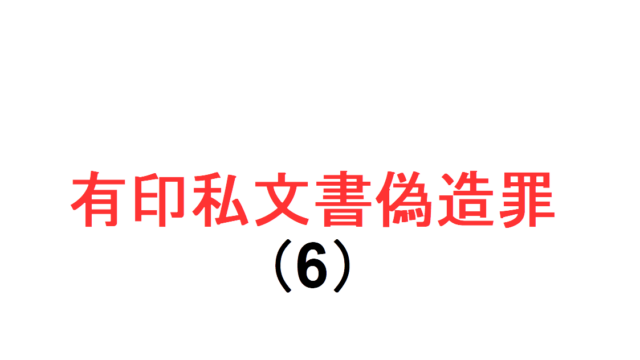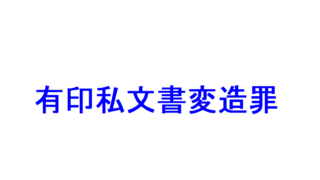有印私文書偽造罪(15)~「本罪と①公文書偽造罪、②窃盗罪・横領罪、③詐欺罪との関係」を説明
前回の記事の続きです。
この記事では、有印私文書偽造罪(刑法159条)を適宜「本罪」といって説明します。
他罪との関係
本罪と
との関係を説明します。
① 公文書偽造罪との関係
私文書である印鑑証明願書と公文書である印鑑証明書とが同一紙面に記載されるように、公文書と私文書とが1通の用紙に併存する場合に、両者を偽造したときは公文書偽造と私文書偽造の二罪が成立し、場合により観念的競合となり(大審院判決 明治43年6月23日)、あるいは牽連犯となります(大審院判決 昭和2年11月1日)。
学説では、一個の行為により、又は手段、結果の関係において、公文書の偽造と私文書の偽造とが行われた場合については、単一の文書偽造罪の成立を認め、最も重い刑を規定した罰条を適用すべきであるとの見解が少なくありません。
しかし、刑法が、公文書の偽造と私文書の偽造とを区別して規定している趣旨からみれば、両罪の観念的競合、牽連犯と解するのが妥当だとする見解が有力です。
② 窃盗罪、横領罪との関係
1⃣ 実印を盗捺して私文書を偽造したときは、実印の盗捺(印鑑を盗んで押印すること)は私文書偽造の構成要素に含まれ、両者は手段結果の関係にはなく牽連犯の関係にはなりません。
また、窃取、横領した用紙で文書を偽造したときは、窃盗罪又は横領罪と文書偽造罪とは併合罪の関係になります。
この点を判示した以下の判例があります。
大審院判決(大正2年2月3日)
裁判所は、
- 他人に属する借用証書の用紙を窃取し、これに窃取に係る本人の印鑑を盗捺し、本人名義の借用証書を偽造したる場合において、借用証書用紙の窃取は、文書偽造の普通手段に非ず
- また、文書偽造は窃取の当然の結果に非ざるをもって、右窃取の行為は、文書偽造に対し、独立の一罪を構成するものといわざるべからず
と判示しました。
大審院判決(大正4年11月29日)
裁判所は、
- 自己の占有する他人の白紙買渡証書を横領し、これを材料として文書を偽造したる場合においては、横領と偽造とは手段又は結果の関係を有せず、各独立罪を構成するものとす
と判示しました。
東京高裁判決(平成20年4月24日)
窃盗(未遂)の手段として偽造有印公文書行使が行われた場合であっても、両罪は、牽連犯の関係にはないとした判決です。
事案は、被告人が、コインロッカー内の金員の窃取を企て、検察事務官の身分証明書である検察事務官証票1通を偽造し、これをコインロッカーの管理会社従業員に提示して行使し、同人にコインロッカー計156台を解錠させるなどしてそのコインロッカー内に保管されていた荷物を物色したが、金員の発見に至らなかったため、窃盗の目的を遂げなかったという有印公文書偽造罪、偽造有印公文書行使罪、窃盗未遂罪の事案です。
裁判官は、
- 偽造有印公文書行使と窃盗未遂については、窃盗未遂の手段として偽造有印公文書行使が行われた場合であっても、両罪は、犯罪の通常の形態として手段又は結果の関係にあるものとは認められず、刑法54条1項後段所定の牽連犯の関係にはないと解するのが相当であるから、有印公文書偽造とその行使とは牽連犯の関係にあるが、これらと窃盗未遂とは併合罪の関係にあると解すべきである
と判示しました。
大審院判決(大正7年4月24日)
為替証書を窃取し(窃盗罪)、これに受取人の署名を偽署し、名下に偽造印を押捺してこれを行使した場合には、「窃盗罪」と「文書偽造罪・偽造文書行使罪」との間には牽連関係はなく、「窃盗罪」と「文書偽造罪・偽造文書行使罪」は併合罪になるとしました。
裁判官は、
- 被告が通信事務員として郵便物の区分に従事中、為替証書在中の郵便物を窃取し、なお為替証書に受取人の氏名を偽署し、名下に偽造印を押捺し、これを郵便局に提出行使したるときは、該文書偽造とその行使との間には手段結果の関係あるをもって刑法第54条後段、第10条を適用すべきものなりといえども、これらの罪と如上窃盗罪との間には牽連関係を存せず、全然独立する犯罪なるをもって併合罪として処断すべきものとす
と判示しました。
2⃣ なお、横領の手段として文書を偽造したときは、横領罪と文書偽造罪とは牽連犯の関係になります(大審院判決 大正11年3月31日)。
③ 詐欺罪との関係
他人名義の文書を偽造して財物を詐取した場合は、文書偽造罪、文書偽造行使罪、詐欺罪を一連の行為として行ったものであり、各罪の間には、順次、手段結果の関係があるため、併合罪ではなく、牽連犯になります。
この点について、以下の判例があります。
大審院判決(明治42年1月22日)
この判例で、裁判官は、
- 詐欺罪をなすにより、公正証書を偽造行使したる場合においては、該証書作成の委任状は、公正証書の成立と分離すべからざる密接の関係を有し、二者相まって、詐欺取得罪の実行手段たるべき行為にほかならず、故に裁判所が右委任状偽造の行使に対し、刑法第54条第1項を適用したるは相当なり
と判示し、文書偽造罪、文書偽造行使罪、詐欺罪は牽連犯の関係になり、一罪になるとしました。
大審院判決(明治43年12月16日)
この判例で、裁判官は、
と判示し、文書偽造行使罪と詐欺未遂罪は、牽連犯の関係になるとしました。
大審院判決(明治44年11月10日)
この判例で、裁判官は、
- 刑法第54条1項にいわゆる犯罪の手段たる行為とは、ある犯罪の性質上、普通その実行の方法として用いらるべき行為にして、かつ、その犯罪の構成要件とならざるものをいう
- 故に、偽造又は虚偽の事項を記載したる文書等を行使して、物を騙取したる場合においては、その行為は、詐欺罪構成の要件たる欺罔の手段たるに過ぎずして、欺罔そのものにあらざる
- 従って、その行為は、ただちに詐欺罪の構成要件となるものにあらず、しかも右行為は詐欺罪実行の方法として、普通、用いられるものに属するをもって、すなわち詐欺罪の手段たる行為なりというべきなり
- されば、本件虚偽の記載をなしたる文書の行使と詐欺取財との間に手段結果の関係あるものとし、刑法第54条第1項後段を適用したり
と判示し、文書偽造行使罪と詐欺未遂罪は、牽連犯の関係になるとしました。
仙台高裁判決(昭和26年9月17日)
借用証書の偽造と行使と詐欺の関係について、裁判官は、
- 本件借用証書の偽造と行使と詐欺とは、順次、手段結果の関係にあるから、刑法54条1項後段を適用し、一罪として処罰しなければならないのに、原判決は、右偽造と行為とのみをいわゆる牽連犯とし、詐欺はこれと独立して両者の間に併合罪の関係ありとして、法定の加重をしたのは誤りであり、かつ判決に影響を及ぼすことが明らかである
と判示し、一審の裁判所が、文書偽造・行使罪と詐欺罪を併合罪として判示したのは誤りであり、文書偽造・行使罪と詐欺罪を牽連犯の関係になるとしました。