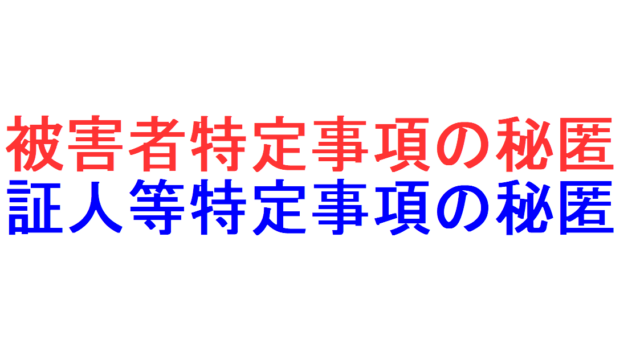被告人とは?① ~「被告人となるためには、当事者能力と訴訟能力が必要である」などを説明
被告人とは?
被告人(ひこくにん)を説明するに当たり、まずは被疑者(ひぎしゃ)を説明します。
被疑者とは、
犯罪を犯した疑いのある人で、まだ裁判にかけられていない人
をいいます。
被疑者は、検察官に事件を起訴されて裁判にかけられると、呼び名が「被疑者」から「被告人」に変わります。
つまり、被告人とは、
検察官に事件を起訴されて裁判にかけられた人
をいいます。
被告人は検察官と対等の地位が与えられる
被疑者は、捜査機関(警察官や検察官)から取調べを受けるなどの犯罪捜査を受ける立場にあり、被疑者の地位は、捜査機関と対等ではなく、捜査機関よりも低いといえます。
これに対し、被告人は、捜査段階における被疑者とは異なり、裁判の当事者として、検察官と対等の立場で裁判で戦う者となります。
なので、被告人は、検察官と対等の地位を与えられた者という位置づけになります。
被告人は「防御権の主体」といわれる
裁判において、検察官は、犯罪事実(公訴事実)を立証するため、攻撃的・能動的な訴訟行為を行います。
検察官の攻撃的・能動的な訴訟行為に対し、被告人は、防御的・受動的な姿勢となります。
このことから、被告人は「防御権の主体」といわれます。
被告人は、証拠方法でもある
被告人は、証拠方法(裁判官が事実認定の資料とするために取り調べることができる人や物)でもあります。
例えば、
- 被告人の法廷における供述は証拠となる(刑訴法322条2項、311条)
- 被告人の身体は検証の対象となる(刑訴法129条)
- 被告人が身体の検証を拒否すれば制裁を受ける(刑訴法137条、138条)
- 被告人が身体の検証を拒否すれば直接強制を受ける(刑訴法139条)
- 被告人の身体・物・住居などは捜索の対象となる(刑訴法102条1項)
などの規定があり、被告人は犯罪事実を証明する証拠になります。
なお、被告人の法廷での供述は証拠となることから、刑訴法規則197条1項において、
「裁判長は、起訴状の朗読が終った後、被告人に対し、終始沈黙し又個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨のほか、陳述をすることもできる旨及び陳述をすれば自己に不利益な証拠ともなり又利益な証拠ともなるべき旨を告げなければならない」
と規定し、裁判長は、被告人に対し、被告人の法廷での供述が、被告人の不利益な証拠ともなり、また利益な証拠ともなることを告知することを義務づけています。
被告人となるためには、当事者能力と訴訟能力が必要である
被告人となるためには、当事者能力と訴訟能力が必要です。
もし、事件を起訴されて、被告人となった者に、当事者能力又は訴訟能力がないということになれば、公訴が棄却され、裁判が打ち切られます。
当事者能力とは?
当事者能力とは、
訴訟法上、被告人となり得る能力
をいい、当事者能力は、
被告人が生存している限りある
という考え方になります。
被告人が自然人が死亡した場合、被告人は当事者能力を失うので、裁判官の決定で公訴が棄却されます(刑訴法339条1項4号)。
なお、法人にも訴訟能力があり、法人も起訴されて裁判にかけられて被告法人となる場合があります。
被告人たる法人の場合は、法人が存続しなくなったとき(法人が消滅したとき)に当事者能力を失い、この時に裁判官の決定で公訴が棄却されます。
法人が消滅する時期は、合併で解散した場合は合併の時です(最高裁決定 昭和40年5月25日)。
合併以外の事由で解散した場合は、清算法人として清算目的の範囲内で存続し(会社法476条)、刑事事件の訴追を受けることも精算事務の中に含まれるので、清算人において違反事件の結末を終了するまではその法人は消滅しません(最高裁決定 昭和29年11月18日)。
訴訟能力とは?
訴訟能力とは、
被告人が訴訟行為を有効になし得る能力(被告人が訴訟行為をなすに当たり、行為の意義を理解し、自己の権利を守る能力)
をいいます。
被告人が訴訟行為をなすためには、訴訟能力がなければなりません。
訴訟能力のない被告人の訴訟能力は無効となります。
訴訟能力がないと見なされる場合として、
被告人が心神喪失になった場合
が挙げられます。
例えば、統合失調症などの精神病が悪化し、心神喪失になる場合が該当します。
被告人が心神喪失の状態になったときは、訴訟能力を欠くことになるので、その状態が続いている間は公判手続が停止されます(刑訴法314条1項)。
被告人に訴訟能力がないために公判手続が停止された後、訴訟能力の回復の見込みがなく公判手続の再開の可能性がないと判断される場合、裁判所は、刑訴法338条4号に準じて、判決で公訴を棄却することができます(最高裁判決 平成28年12月19日)。
次回の記事に続く