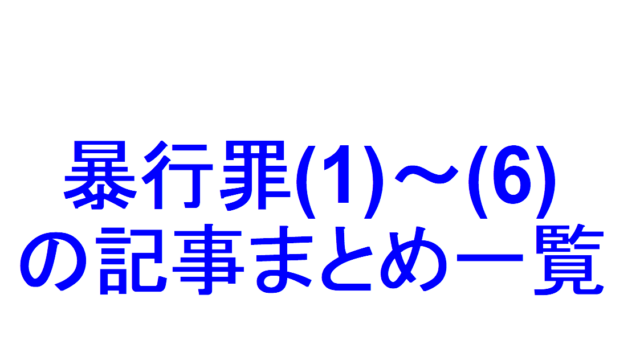暴行罪(4) ~「軽微な暴行による暴行罪の成否」「軽微な暴行が暴行罪が当たるかどうかは、構成要件の問題としてとらえるだけでなく、社会的相当性や違法性の問題も考慮する必要がある」を判例で解説~
軽微な暴行による暴行罪の成否
暴行罪における暴行は、「不法な」有形力の行使とされています。
「不法な」とされるのは、社会生活上許容される適法な行為と認められる有形力の行使と暴行罪における暴行を区別するためです。
たとえば、落とし物をした歩行者に追いつき、その肩に手をかけて呼び止めたり、喜びの余り友人に抱きつくなどは、「不法な」有形力の行使と評価されず、暴行罪は成立しません。
対して、見ず知らずの人に喧嘩を売るつもりで肩をたたいて呼び止める、わいせつ目的で通行中の女性に抱きつくといった行為は、「不法な」有形力の行使と評価でき、暴行罪が成立し得ます。
この「不法性」は、被害者に与えられた苦痛の有無、程度、行為の目的、行為当時の状況などを総合して、社会生活上認められるものかどうかによって決せられることになります。
軽微な有形力の行使の不法性を認め、暴行罪が成立するとした判例
軽微な有形力の行使の不法性を認めた事例として、以下の判例があります。
東京高裁判決(昭和56年4月1日)
見ず知らずの相手に対して、前額部付近を平手で1回押すようにたたき、右手の拳を軽く握り、手の甲を上にして頭部をこつこつと数回たたいた行為について、有形力の不法な行使であり暴行に当たるとしました。
軽微な有形力の行使の不法性を認めず、暴行罪は成立しないとした判例
暴行に当たらないとされた事例として、以下の判例があります。
広島高裁判決(昭和32年3月25日)
この判例は、単に相手を追跡しただけでは暴行といえないとしました。
事案は、
- 共産党員である被告人は、被害者から公安調査官であるとその身分を打ち明けられた上、被告人の所属する日本共産党に関する資料及び情報等の提供方つまりスパイ的行為を要望された
- すると被告人は、大声で仲間を呼んだ
- 被害者は、身の不安を感じ、あわてて被告人の手を振り切って逃走した
- 被告人は、被害者の停止を求め、その氏名身分などを確認しようとして、下駄履きのまま全速力で被害者を追走したところ、被害者は崖下に転落した
- 被告人は間もなく被害者を発見し、好意的に被害者を病院に連行し、治療を受けさせた
というものです。
裁判官は、
- 問題は、被告人が逮捕に相当するような強力な有形力を行使する意図で追跡したか否かにあるというべきところ、被告人が刑法にいわゆる逮捕に相当するような強力違法な有形力を行使する意図であったと認めることはできない
- してみれば、被告人が自己のもとを立ち去ろうとして逃走する被害者を追跡した行為は、もとより行過ぎで不当ではあるが、暴行の意思を認め難いのみでなく、その行為の態様もいまだ処罰の対象たる暴行の程度には達していないものと解すべきである
と判示し、単に相手を追跡しただけでは暴行罪は成立しないとしました。
東京地裁判決(昭和35年6月16日)
この判例は、追跡行為を「暴行」と見るべきか否かについて具体的に考慮すべき条件を判示した事例です。
この裁判は、被告人が、路上を通行中、Tから「馬鹿野郎」と罵られたのに憤慨し、Tと口論の末、逃げ出したTを追ってTを捕え、手拳を振ってTに殴りかかり、Tをショーウインドーのガラスに激突転倒させ、そのガラス破片により頸部胸腔内切創を負わせ、Tを失血により死亡させたという事実で起訴された事案です。
裁判官は、
- Tは、当時、相当酩酊しており、足もふらついていたこと、当裁判所の検証調書によれば、ウィンドー直前の路上の一帯に凹凸(当裁判所の検証調書によれば長さ約1.4m、幅約0.9mである。)が見られることなどから、あるいはT自ら逃げようとして、慌ててこの凹凸につまずいてガラス窓に激突したことも想像できる
- しかし以上は単に想像にしか過ぎず、被告人がTに殴りかかったという点に関してはもちろんのこと、Tを押したという事実についても他にこれを認定するに足る証拠はない
- しかも、被告人のこの点に関する供述がいずれも信用し難いものとすれば、被告人がTに殴りかかったという事実は認められないと見るべきである
- ところで、被告人において殴ろうとした事実がなくても、被告人の追跡行為を暴行と見ることができるのではないかという疑があるので、次にこの点について検討する
- 一件記録によると、被告人には、追跡の際、Tを捕えようとする気持のあったことはうかがえるが、更にTを捕えた上、Tに暴行を加えるまでの意図を推定するに足る資料は認められない
- また追跡中、被告人がTに向って声をかけたような事実も認められない
- 検察官は、追跡行為を暴行と認める判例(昭和25年11月9日最高裁判所第一小法廷判決、最高裁判所刑事判例集第4巻第11号2239頁)を挙げて、本件に類推すべきことを主張しているが、右判例を含めて追跡行為を暴行と認める諸判例(大正8年7月31日大審院判決、大審院刑事判決録25輯899頁、昭和32年5月9日東京高等裁判所第六刑事部判決、高等裁判所判例集第10巻第3号310頁)等の趣旨は、暴行と認める追跡行為自体に逃走者をして危害を予想させるような言動とか、凶器を携持するなど、客観的に相手の身体に危害を加える意思を推定させるに足る事実を伴うか、あるいは、既に暴行を加えられ、引き続き暴行を加えられることを避けるべく逃走した者を追って、これをして逃げ場を失わしめるような場合に、これらの追跡を暴行と解しているのである
- 本件の場合、被告人において単にTを捕えようとする意図しかなく、追跡に際し、Tに向って危害を加えるような言動を示していない
- また、追跡前の口論の際に、Tに対し、暴行を加えたという事実についても、第一回公判調書中証人Sの供述記載だけでは認定し難く、他にこれを認めるに足る証拠がない
- さらに、被告人がTに追いついたと思われる地点における道路、建物の位置、状況などからTをして逃げ場を失わしめたものとは考えられない
- かような場合、この追跡行為をもって、直ちに暴行と目することはできないと見るべきである
- 結局、本件については、以上の理由で被告人の暴行の証明がないことになる
- 従って、傷害致死の結果について、被告人にその責を帰することはできないものというべく、刑事訴訟法第336条後段により無罪の言い渡しをなすべきである
と判示し、本件の追跡行為は暴行とは認められないことから、傷害致死罪は成立せず、無罪となるとしました。
この判例のポイントは、
暴行と認める追跡行為とは、危害を予想させるような言動、凶器の携持など、相手の身体に危害を加える意思を推定させるに足る事実を伴うか、既に暴行を加えられ、引き続き暴行を加えられることを避けるべく逃走した者を追ったような場合である
と、追跡行為を暴行と認める条件を説明した点にあります。
岡山地裁判決(昭和43年12月11日)
この判例は、人を押して転倒された行為が刑法上の暴行とは認められないとされた事例です。
裁判官は、
- 検察官主張の訴因は「被告人は、判示日時・場所において、Fから不意に突き倒されたことに憤慨し、いきなり両手でFの肩付近を強く押して仰向けに突き倒し、Fの後頭部を路面に強打させ、よって判示日時・場所において、頭蓋骨骨折を伴う脳挫傷によりFを死亡させたものである。」というにあるけれども、以下述べる理由により傷害致死罪の成立を認めることはできない
- Fの飲酒酩酊の程度、被告人が福島を押した動機ないし意図及びその方法、程度、Fの転倒状況、Fが転倒したのは、被告人がFの肩付近を手で強く押したものか、あるいは軽く押したものかの蓋然性の程度、その他諸般の事情を比較総合すれば、被告人は、Fから理由もなく再三にわたって暴力を振われたことに立腹し、Fの肩付近を手で強く押したものと認めるよりも、むしろ、Fの暴力に多少立腹したものの、主としてFの暴力をたしなめ制止するため、不意に同人の肩付近を手で軽く押したところ、たまたま同人が相当程度飲酒酩酊していたので、足をすくわれ宙に浮いたような姿勢で頭からアスファルト舗装の路面に仰向けに転倒し、前示原因により死亡するに至ったものであると認めるのが相当である
- ところで、本件被告人の行為は、その動機、意図、方法、程度等諸般の事情に徴すれば、通常の社会生活関係において正当な行為として認容される域にとどまる程度のものと認められ、いまだ刑法208条にいう不法な有形力の行使としての暴行には該当しない
- したがって、被告人には暴行の故意をも認められないので、傷害致死罪は成立しないものといわねばならない
と判示し、被告人がFを押して転倒された行為を暴行と認定できないから傷害致死罪は成立しないとしました。
なお、この裁判で、裁判官は、傷害致死罪は成立しないとしましたが、過失致死罪は成立するとして、無罪の言い渡しはしていません。
東京地裁判決(昭和37年2月26日)
この判例は、留置場において、酔って騒いでいる同房者を寝かしつけようとして浴衣の袖を引っ張った行為について、その動機、態様、方法、程度等諸般の観点より考察して、社会生活上相当なる行為に属し、いまだ刑法にいわゆる暴行に該当するような有形力の行使とは認められないとしました。
東京地裁判決(昭和42年8月15日)
被害者が被告人のわきを通りかかった際、被告人がいきなりテーブルのかげから横に足をつき出した行為は、酔客にありがちな悪戯とみる余地も大きく、これが刑法上の暴行に当たると確定することは困難であるとしました。
裁判官は、
- 被告人がHの足部を蹴とばしたとの点については、証人の供述によると、Hが被告人のわきを通りかかつた際、被告人がいきなリテーブルのかげから横に足をつき出し、その足がHの右足にあたったことが認められるが、その行為は、それ自体、Hに肉体的苦痛を与えるような性質のものではなかったことがうかがわれる
- また、その行為がどのような状況のもとに行なわれたか等について、Hの供述はきわめてあいまいで、混乱もあり、十分な心証を得ることができない
- したがって、右の行動は、酔客にありがちな悪戯とみる余地も大きく、これが刑法上の暴行にあたると確定することは困難である
として、暴行罪の成立を否定しました。
東京高裁判決(昭和45年1月27日)
仲間とふざけ合っていて、仲間に当てるつもりで、その足を殴ろうとしたところ、たまたま電燈の消えたときであったため、間違って近くに来ていた被害者のひざに当たって軽い怪我を負わせたのは、暴行としての違法性を欠くとしました。
そして、ふざけ合って仲間の足を殴る意思で、誤って他人のひざを打ち、傷害を負わせた場合は、過失傷害罪にはなっても、傷害罪にはならないとしました。
裁判官は、
- 本件は、被告人が仲間とふざけ合っていて、仲間に当てるつもりで、その足を殴ろうとしたところ、たまたま運悪く電燈の消えたときであったため、間違って近くに来ていた被害者のひざに当たって、軽いけがを負わせるに至ったという事案であることが明らかである
- そうしてみると、被告人の所為は、暴行としての違法性を欠くものであるから、本件は、過失傷害罪の成立する余地はあるとしても、傷害罪は成立しない場合であるというべきである
と判示しました。
過失による暴行は、暴行の故意を欠くため、暴行罪や傷害罪を成立させない点がポイントになります。
東京高裁判決(昭和56年4月1日)
教員の生徒に対する軽微な暴行が体罰にはあたらず、正当な懲戒権の行使の許容限度内の行為であるとされた事例です。
事案は、被告人(教員)が、A(生徒)から「何だ、Bと一緒か。」と言われたことに対し、平手及び手拳で同人の頭部を数回殴打したというものです。
裁判官は、
- 被告人は、Aが中学一年生の時、国語を担任しており、同人の性格が陽気で人なつこい反面、落ち着きがなく軽率なところがあることを知っていたが、被告人に対して話しかけたり、ふざけたりするようなことも比較的多い生徒であったので、被告人としても同人に対してはある種の気安さと親近感を持つていたことも事実であり、さらにこれに加えて、被告人の年令、教師としての経験、教育熱心な日頃のまじめな勤務態度等をも併せ考慮すれば、原判決が認定するように、被告人がAの右言動によって憤慨・立腹し、私憤に駆られて単なる個人的感情から暴行に及んだとすることは、行為の動機・目的を単純化しすぎるものといわざるをえない
- むしろ、被告人としては、Aの前記のような言動を現認して、同人が自ら望んでまで中央委員に選出されていながら、従前の軽率さがまだ直っていないと思い、二言三言その軽はずみな言動をたしなめながら前示のような行為に出たのが、事の真相であったと思われる
- とすれば、被告人の本件行為の動機・目的の主要な本質的な部分は、中学二年ともなった生徒に社会生活環境のなかでよく適応していけるような落ち着いた態度を身につけさせるため、教育上生活指導の一環としてその場で注意を与えようとするにあったものと認めて差支えないものと考える
- 刑法208条の暴行罪にいう「暴行」とは、人の身体に対する有形力の不法な行使をいうものと一般に解されている
- そこで、被告人の本件行為が暴行罪にあたるか否かを検討してみると、その行為の程度は、比較的小柄なAに身長、体重ともに勝った被告人の体格を考慮に入れても、はなはだ軽微なものといわなければならないが、この程度の行為であっても、人の身体に対する有形力の行使であることに変わりはなく、仮にそれが見ず知らずの他人に対しなされたとした場合には、その行為は、他に特段の事情が存在しない限り、有形力の不法な行使として暴行罪が成立するものといわなければならない
- Aに対して被告人がした本件行為は、刑法35条にいわゆる法令によりなされた正当な行為として違法性が阻却され、刑法208条の暴行罪は成立しない
と判示し、教師である被告人の正当に対する暴行は、軽微である上、正当な行為であるとして、暴行罪の成立を否定し、無罪を言い渡しました。
【考察】
これらの判例から、軽微な暴行が暴行罪が当たるかどうかは、構成要件の問題としてとらえるだけでなく、社会的相当性や違法性の問題も考慮する必要があることが分かります。