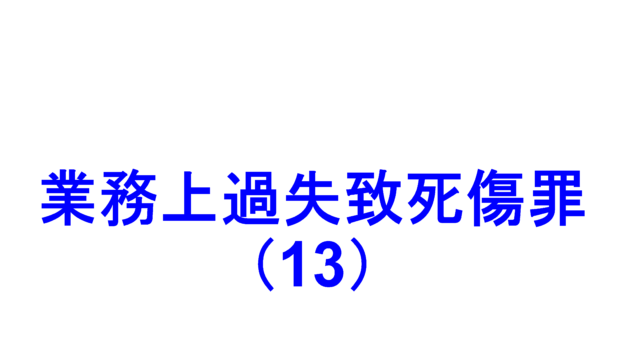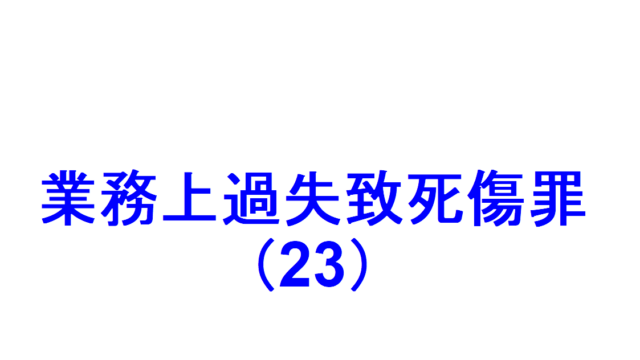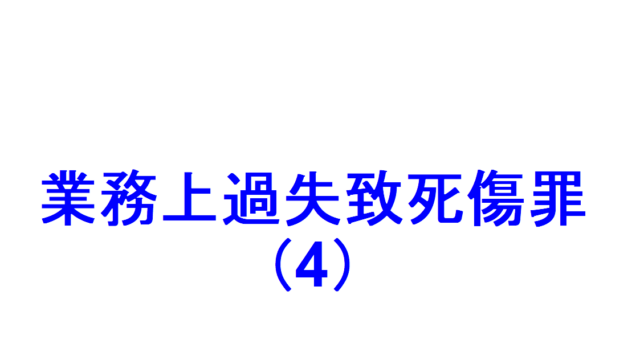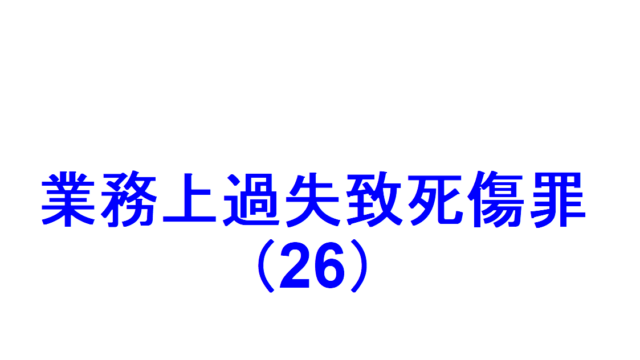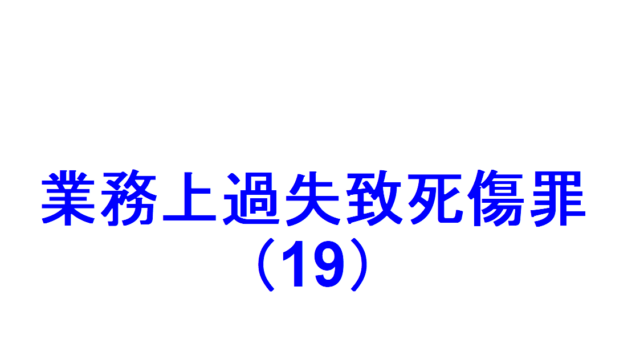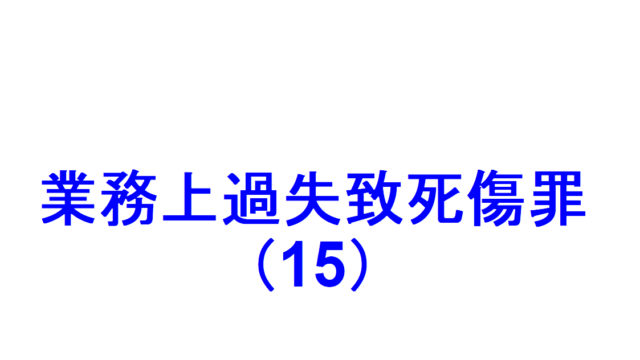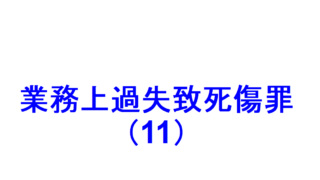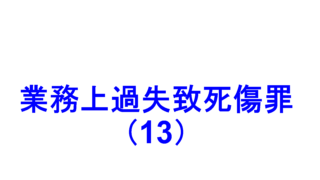前回の記事の続きです。
今回の記事では、因果関係が争われた裁判例のうち、
- 交通事故による受傷と死亡との間に、医師の治療行為の際の過誤があった場合、死亡の原因が被害者側の既往症の再燃・進展による場合、 あるいは被害者の特異体質・稀有な症状の発生による場合などであっても、当初の被告人の過失と被害者死亡との間に因果関係があるとされた事例
- 交通事犯以外の危険を伴う行為について、被害者等の行動や自然現象が結果発生に寄与したとしても因果関係が肯定されるとした事例
を紹介します。
交通事故による受傷と死亡との間に、医師の治療行為の際の過誤があった場合、死亡の原因が被害者側の既往症の再燃・進展による場合、 あるいは被害者の特異体質・稀有な症状の発生による場合などであっても、当初の被告人の過失と被害者死亡との間に因果関係があるとされた事例
東京高裁判決(昭和56年7月27日)
交通事故により外傷を受けて入院中死亡した被害者に対する治療の過程において、医師が被害者の血液型を誤認した輸血ミスがあり、被害者の死亡に輸血ミスが寄与した疑いがないとはいえない場合において、交通事故による受傷が少なくとも一原因として死亡したことが認められる以上、輸血ミスが死亡原因として競合していると否とにかかわらず、被告人の過失と被害者の死亡との間に因果関係を認めることができるとした事例です。
裁判官は、
- 刑法上過失の行為と他人の死亡との間に因果関係があるというためには、過失と結果との間に経験則上、通常予想し得る範囲内でのいわゆる条件関係(原因結果の関係)があることをもって足り、当該過失が、結果発生の唯一または直接の原因であることを要するものではなく、他の要因と相まって結果を生じさせた場合をも包含すると解するのが相当である
- そうであれば、本件において、被害者が、本件の交通事故により左腎破裂及びその他筋組織の挫滅等の外傷を受け、これを少なくとも一原因として死亡するにいたったことが認められる以上、その治療の過程においてなされた医師の不適合輸血が死亡原因として競合しているか否かにかかわらず、被告人の過失と被害者の死亡との間に刑法上の因果関係を認めることができる
と判示し、被告人の過失行為と死亡との結果との因果関係を肯定し、業務上過失致死罪(現行法:過失運転致死罪)が成立するとしました。
東京高裁判決(昭和54年2月8日)
被告人が起こした交通事故により、脳挫傷等の傷害を受けた被害者が、受傷後8か月に及ぶ期間の入院加療中に全身衰弱をきたし、その結果、沈静化していた肺結核を再燃させて死亡した場合において、被告人の過失行為と死亡との間に因果関係を認めた事例です。
裁判官は、
- 本件は、被告人が、業務上の過失により走行中の自車を被害者に衝突させ、その結果、被害者が脳挫傷等の重傷を負い、この傷害に起因する因果の過程をたどって死亡するに至った事案である
- 被害者が受傷してから死亡するに至るまでの間に、被害者自身または医師を含む第三者の故意ないし過失による行為等によって右因果の系列が断たれたとすべき要因の介入は全く認められないのであるから、被告人の過失行為がなかったならば、被害者の死の結果も発生しなかったという関係が認められる
- そればかりでなく、本件のような自動車の衝突事故による傷害によって、被害者が直接または余病を併発して死亡するであろうことは、社会経験上稀有のことではなく、一般人においてこれを予見することも十分可能であるといわなければならないところである
- 原判決のいう相当因果関係説によっても、行為と死の結果との間に因果関係があるというためには、個々の具体的経過事実についてまで予見しうることは必要ではなく、社会経験上、通常予想しうる程度の関係があれば足るとすべきものである
- よって、被害者が被告人の過失行為による右傷害の結果長期にわたる臥床を余儀なくされて全身衰弱をきたし、その結果、肺結核症が再燃、進展して死亡するに至ったことの明らかな本件の場合には、確かに被告人は被害者が肺結核症の病巣を有していたことを予見しえなかったとしても、被告人の過失行為と被害者の死亡との間の刑法上の因果関係を認めるに十分である
と判示し、被告人の過失行為と死亡との結果との因果関係を肯定し、業務上過失致死罪(現行法:過失運転致死罪)が成立するとしました。
東京高裁判決(昭和60年6月17日)
事故により左下腿開放骨折の傷害を受けて治療中、投薬による薬剤過敏症と事故によって生じた肝臓後部を中心とする抵抗滅弱部とが相まって大量出血を来し、そのショックに基づく急性腎不全に陥って死亡した事例です。
裁判官は、
- 本件のような運転の態様からすれば、対向車両との衝突の危険は当然予測し得るところであるうえ、本件のような状況下で車両相互間の衝突事故が発生すれば、その衝撃により相手方の身体の枢要部分に重大な傷害を負わせることは充分あり得る
- その場合、直ちに適切な加療措置が講ぜられたとしても、当該傷害に基づき、あるいは当該傷害に伴って派生したニ次的症状に基づき、被害者が死亡することのあり得べきことは、経験則上容易に予見し得るところであり、因果関係の存在を肯認するための要件としては、右程度の予見で足りるものと解すべきである
- そして、具体的に発生した被害者の傷害及び受傷後死亡するに至るまでの経過が、右予見の範囲を逸脱するものでない限り、因果関係の存在は肯認されて然るべきである
- 本件のような軟部組織の高度の挫滅を伴う左下腿開放骨折の傷害が発生した場合、破壊された骨髄から出た脂肪や挫滅した皮下脂肪が血管に入って脂肪栓塞症を起こし、あるいは血液中のヘモグロビンや筋肉中のミオグロビンが腎臓毒として働らき、ネフローゼを起こすことにより、死亡の結果を生じ得るものとされるが、そのような通常の経過をたどらず、前示のように加療のために投与した薬剤による過敏症と事故の衝撃による抵抗減弱部の存在とが相まって大量出血を招き、そのショックに基づく急性腎不全が死因となったとしても、現在の医学の水準に照らし担当医の加療行為に落度がなく、適切なものであったと認められる以上、右のような経過による死亡の結果発生は、前述の予見の範囲を逸脱するものとはいい得ない
と判示し、被告人の過失行為と死亡との結果との因果関係を肯定し、業務上過失致死傷罪(現行法:過失運転致死傷罪)が成立するとしました。
交通事犯以外の危険を伴う行為について、被害者等の行動や自然現象が結果発生に寄与したとしても因果関係が肯定されるとした事例
夜間潜水の講習指導中、受講生らの動向に注意することなく、不用意に移動して受講生らのそばから離れ、受講生らを見失ったインストラクターである被告人について、その後の指導補助者や被害者らの行動に適切を欠くところがあったことも否定できないとしつつ、被告人の行為は、指導者からの適切な指示、誘導がなければ事態に適応した措置を講じることができないおそれがあった被害者を溺死させる結果を引き起こしかねない危険性を持つものであるとして、被告人の行為と被害者の死亡との間の因果関係を肯定した事例です。
裁判官は、
- 被告人が、夜間潜水の講習指導中、受講生らの動向に注意することなく不用意に移動して受講生らのそばから離れ、同人らを見失うに至った行為は、それ自体が、指導者からの適切な指示、誘導がなければ事態に適応した措置を講ずることができないおそれがあった被害者をして、海中で空気を使い果たし、ひいては適切な措置を講ずることもできないままに、でき死させる結果を引き起こしかねない危険性を持つものであった
- 被告人を見失った後の指導補助者及び被害者に適切を欠く行動があったことは否定できないが、それは被告人の右行為から誘発されたものであって、被告人の行為と被害者の死亡との間の因果関係を肯定するに妨げないというべきである
と判示し、被告人の行為と死亡との因果関係を認め、業務上過失致死罪が成立するとしました。
福岡高裁判決(平成10年4月9日)
水深が深く、自然光の届かない閉鎖的で複雑な構造を有する場所でのダイビングサービスを提供したダイビングサービス業者について、被害者がリバースブロック(水深の深いところから浅い場所に浮上する際に、水圧の変化に伴って中耳の気圧を下げる必要があるところ、気圧が下がらずに、中耳から外耳に圧力が加わって痛み、めまい等を引き起こす現象)を起こしてパニックとなり溺死したため、結果回避可能性がなかったと主張された事案です。
裁判官は、
- 業者は参加したダイバーがパニックに陥らないようにし、また、あるいは仮にパニックに陥ったとしてもそれに適時に適切な対応をとれるようにしておく必要がある
とした上で、
- 危険性を事前に告知したり、十分な監視体制を敷くなどの措置をとって事故を未然に防止する注意義務を認め、このような注意義務を果たしていれば被害者らが死ぬことはなかった
と認定し、事故発生を未然に防止するための措置をとるべき業務上の注意義務違反と被害者の死亡との間に因果関係を肯定し、業務上過失致死罪が成立するとしました。
札幌地裁小樽支部判決(平成12年3月21日)
雪上散策のツアー中に発生した雪崩によって、休憩中のツアー客2名を死傷させた事案で、ツアーガイドの被告人に対して、雪崩による遭難事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務を怠ったとして、業務上過失致死罪の成立が認められた事例です。
裁判官は、
- 具体的な状況に照らして、雪崩の発生の予見可能性があったとした上で、雪崩自体は自然現象であるが、遭難事故発生を避けるための安全な行程を選定するなどして事故発生を防止できたのであるから、被告人が目的地を選定し、雪崩の通過地域となるおそれがあることが明らかな地点で休憩させたことにより遭難事故が発生したことは明らかであり、過失と結果の間に因果関係があることは明白である
とし、業務上過失致死罪の成立を認めました。
業務上過失致死傷罪、重過失致死傷罪、過失運転致死傷罪の記事まとめ一覧