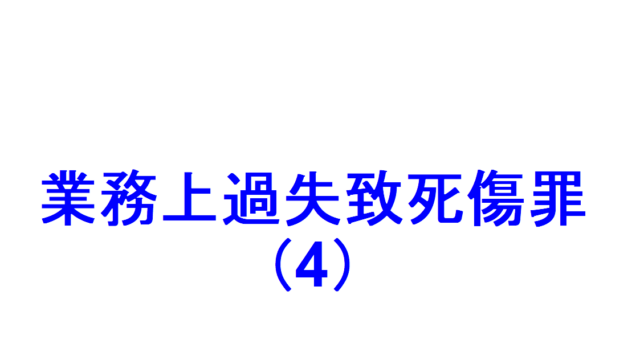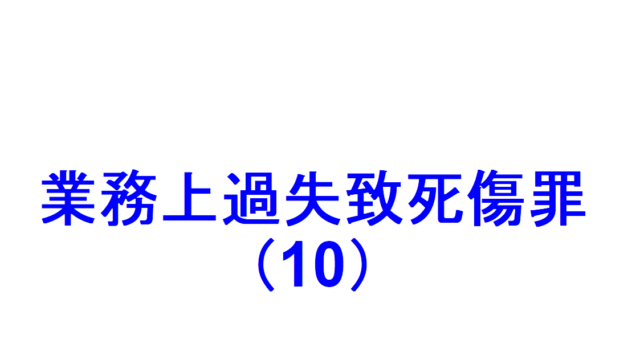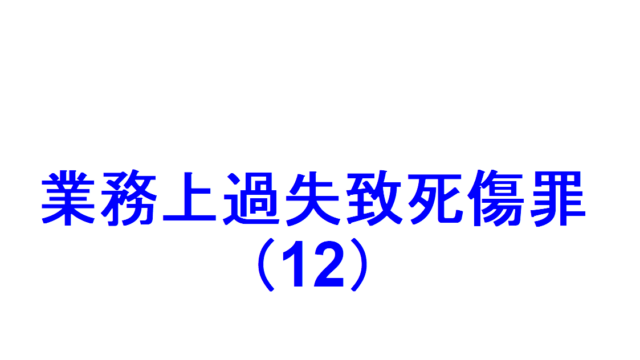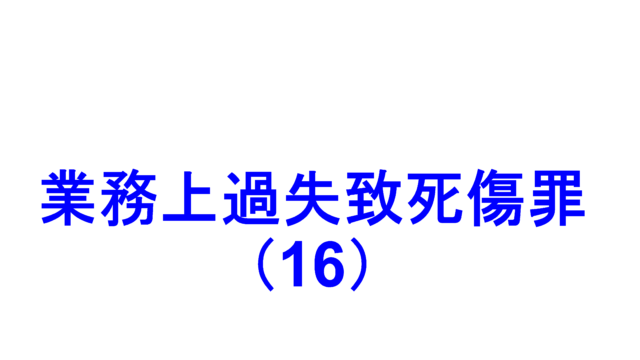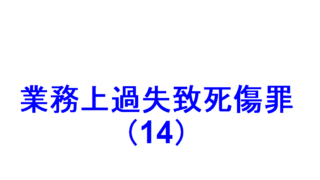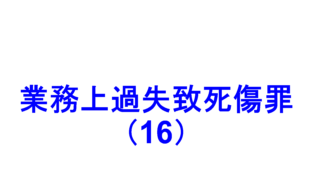頸椎捻挫などの自覚症状に基づく傷害を肯定した事例
業務上過失致死傷罪(刑法211条前段)が成立するには、人に死傷の結果を発生させなければなりません。
(なお、「傷害」の意義については、傷害罪の記事その1、その2参照)
業務上過失致死傷罪は、「傷害」の結果が発生したかが争われることが多々あります。
特に、低速度での衝突事故の際の頸椎捻挫などでは、傷害の発生を外形的に証明する手段がなく、被害者の自覚症状に基づいて診断が行われるため、争いとなることが多いです。
このような頸椎捻挫に関して、傷害の発生を肯定した裁判例として以下のものがあります。
東京高裁判決(平成元年10月25日)
上り坂発進時に、自車を後退させて後続車に衝突させた交通事故について、衝突の物理的衝撃が鞭打ち症発症の限界値に及ばないとの鑑定結果が有益な証拠であることを認めながら、他の関係証拠の内容を詳細に検討し、衝突による負傷の事実を認めた事例です。
まず、被告人の弁護人は、
- 原判決は、被告人が上り坂で発進するにあたり、ブレーキを確実に操作しなかったため、自車を後退させ、後方で停車中のA運転の自動車に衝突させて、同車助手席に同乗中のBに全治約10日間を要する頸腕症候群の傷害を負わせた旨認定しているが、本件衝突によりBが負傷したと認定できる証拠はないから、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある
と主張しました。
この主張に対し、裁判官は、
- 証拠関係に基づき考察するに、衝突による頸部捻挫、頸部挫傷の頸部損傷には、頭頸部の鞭打ち運動を直接の契機とする本来の鞭打ち症のほかに、必ずしも頭頸部の鞭打ち運動を伴わずに生じるものとがあり得、時にこの両者は厳密に区別されることなく鞭打ち症と言われることがある
- Bの供述自体からは、本件においてBの頭頸部の鞭打ち運動が起き、これを直接の契機として頸部捻挫、頸部挫傷等の傷害が生じたというような受傷の経緯の細部は確定し難いのであるが、かなり急な上り坂において前方に停止していた車両が前進すると思っていたのに、突然後退して来たのを見て、抱いていたえい児をかばうために、慌てて後ろの方に退避しようとして力が入り、不安定な姿勢になったとき、衝突されたはずみで転倒し、後頭部をへッドレストに打ち当てたような場合、あるいはBが右のような状況のもとで瞬間的に急激かつ不自然な動きをしたため、頸部に無理な力が加わったような場合には、その結果として、頸部の鞭打ち運動を伴うにせよ伴わないにせよ、頸部捻挫、頸部挫傷等の傷害を負うことは十分あり得ることであると考えられる
- ところで、C医師、D医師の各証言は、それぞれC医師作成の外科外来日誌、診療報酬明細書及びD医師作成の診療録により裏付けられており、また、鑑定に照らして検討しても、各医師の診断、治療に疑問な点はなく、更に、それぞれ独立になされたものであるのに、診断の結果が重要な点で合致ないし符合しており、いずれも措信できると認められる
- そうして、Bの証言は、内容が具体的かつ詳細であり、Bにはことさら大げさに痛み等の症状を申し立てたり、過大な賠償を求めるような態度はうかがわれず、転院のいきさつを見ても不自然な点はなく、C、D両医師の診断により裏付けられていることなどに徴し、措信できるものと認められる
- その他、証拠を精査しても、Bの受傷が詐病であることを具体的に疑わせるに足りる状況は認められない
- そうしてみると、右に掲げた各原審証言及びこれを裏付ける関係証拠によれば、原判示Bの受傷の事実は優に肯認することができるというべきである
と判示し、被害者Bが助手席で生後6か月の子どもを抱いていたため、その位置、姿勢から頸椎捻挫等の傷害を負うことがあり得るとし、Bの頸部捻挫、頸部挫傷の傷害を認め、業務上過失傷害罪(現行法:過失運転致傷罪)の成立を認めました。
福岡高裁判決(昭和59年9月17日)
自動車による軽微な追突事故によっても、むち打ち症が発生することがあると判示し、これを否定した一審の無罪判決を破棄自判した事例です。
事案は、被告人運転車両が、被害車両の後部に時速約5kmで追突し、被害車両の運転者Aに加療約79日間の急性頸部捻挫を、同乗者Bに入院加療133日間を要する頸椎捻挫の傷害をそれぞれ負わせたというものです。
裁判官は、
- 本件事故は、被告人運転車両のボディ左側中央付近が、A運転車両の後部右側角に衝突したというものである
- その際、被告人運転車両ボディ左側中央部付近のアルミ製パイプがA運転車両の後部右側角にひっかかった状態となって、被告人運転車両の加速度がA運転車両に加えられたと認めるのが相当である
- 証人Kの供述及びK作成の鑑定書によれは、形状及び重量が本件両車両に近似した車両を用い、普通貨物自動車のサイドブレーキを軽くかけて停車させ、その後部右側角に鋼索の一端を結び、右車両の右斜め前方に大型貨物自動車を停車させ、たるませた状態の右鋼索の他の一端をその後部中央に結んだうえ、右大型貨物自動車を本件事故の際、被告人運転車両が進行したと推測される方向に向かって、時速5ないし8キロメートルの速度で進行させ、右鋼索が緊張した直後に大型貨物自動車を急停止させるという実験を行ったところ、普通貨物自動車は前方に22メートル、 左方に1メートル移動し、右車両助手席に加えられた加速度は3.2gであったことが認められる
- 右事実に照らすと、本件事故の際、A運転車両の補助枠や被告人運転車両のボディ左側のアルミ製パイプの損壊などによって衝撃力(加速度)がある程度吸収されていること、本件事故と右実験における車両の重量や進行方向の相違を考慮に入れても、本件事故によってA運転車両が前方に移動したとの原審証人A及びBの各供述は信用することができる
- 以上の各証拠を総合すれば、A、Bの両名は、本件事故によって頸部(椎)捻挫の傷害を生ずる程度の衝撃を受けたと認めるのが相当である
- してみると、本件事故後、頭から肩にかけて痛みを生じ、手がしびれ、あるいは腫れた感じになったとの証人A及びBの各供述は信用することができる
- 頸椎捻挫の中には他覚的に異常が認められない場合も多く、A、Bの訴える自覚症状は頸椎捻挫の症状と合致しているとの証人Kの供述、右両名の訴える自覚症状、首を他動にこ動かした場合の反応、治療を受ける態度などから仮病とは考えられないとの医師の供述を総合すると、A、Bの両名は、本件事故によって頸部(椎)捻挫の傷害を受け、その治療のために通院あるいは入院したと認めるのが相当である
- 以上の次第で、本件公訴事実は関係証拠によって優にこれを認定することができ、A及びBの各傷害の点について証明が不十分であるとして無罪を言い渡した原判決は事実を誤認したものであり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから破棄を免れない
と判示し、鑑定などから本件事故により頸椎捻挫等の傷害を生ずる程度の衝撃を受けたことを認定し、業務上過失傷害罪(現行法:過失運転致傷罪)の成立を認めました。
次回の記事に続く
次回の記事では、上記のような傷害を認定した事例とは逆に、
- 傷害の発生を否定した事例
を紹介します。
業務上過失致死傷罪、重過失致死傷罪、過失運転致死傷罪の記事まとめ一覧