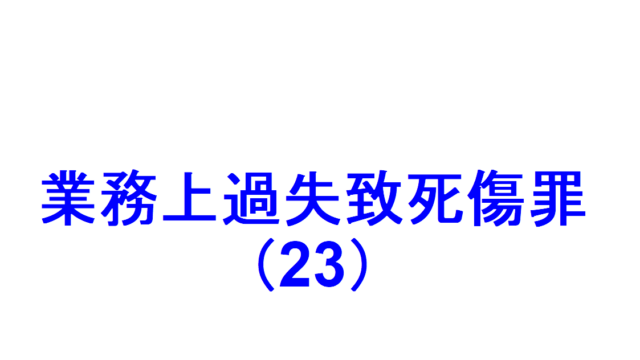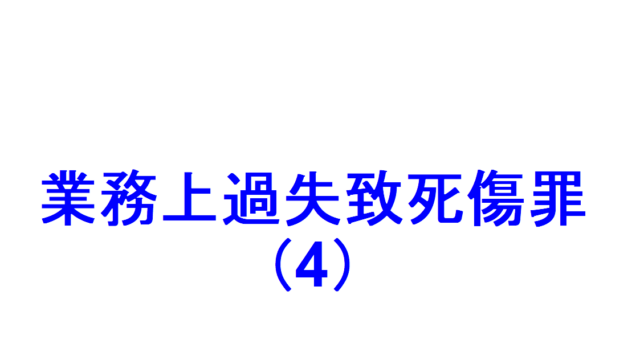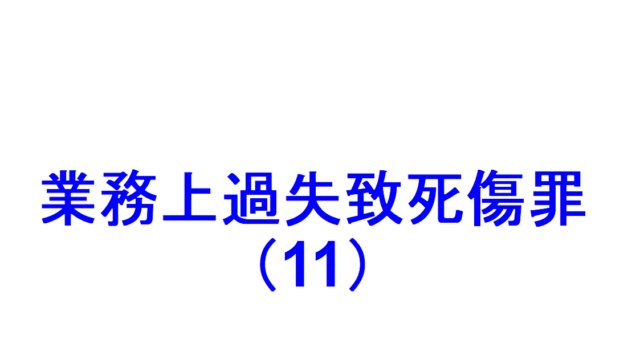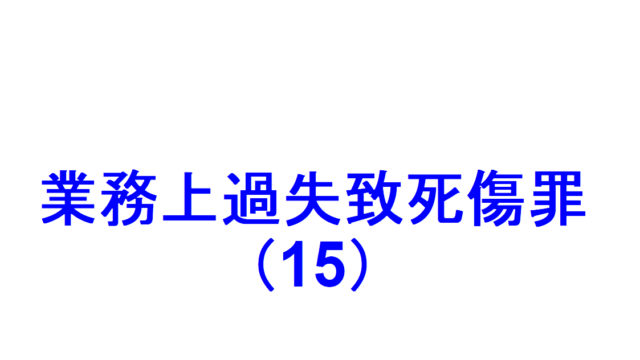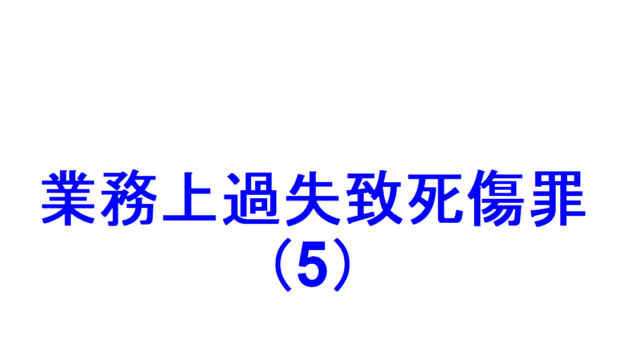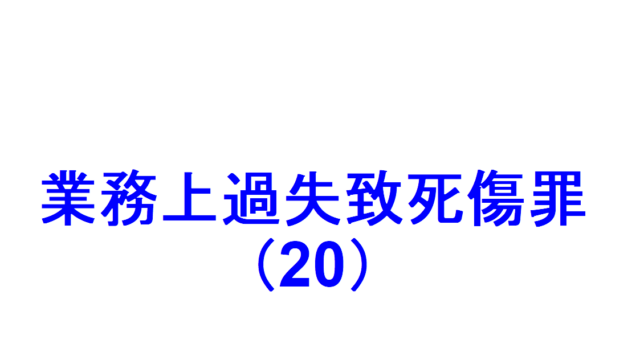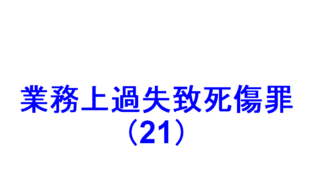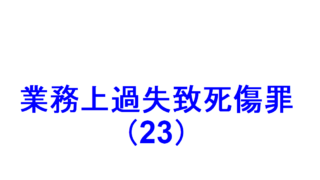船舶航行業務従事者の注意義務
船舶事故は、船が沈没すれば死亡事故になり得るなど、業務上過失致死傷罪(刑法211条前段)が成立する事案です。
船舶航行の業務に従事する者は、危険な業務に従事する者として、事故を防止する注意義務が課せられています。
その注意義務の内容として、
- 船舶を航行するに当たっては、進路前方、左右を注視し、相手船を認めた場合は、その動向に注意を払い、必要に応じて、注意喚起信号、疑問信号を発して相手船に避譲を求め、その動向を明らかにするように努めること(神戸地裁判決 昭和43年12月18日)
- 衝突の危険が予想される場合には、減速、機関停止、後進全速、激右転等の措置をとること(広島地裁判決 昭和53年9月11日)
が挙げられます。
船舶事故の裁判例
船舶事故の裁判例を紹介します。
被害船の存在を見落としが原因となった事故
長崎地裁判決(昭和63年1月26日)
夜間、漁船(6.1トン)の船長が操船航行中、進路付近のいか釣り漁船(0 .88トン)に気付かず、自船を衝突させ、いか釣り漁船の船長を海中に転落させて溺死させた事案です。
裁判官は、
- 付近には小型いか釣り漁船が操業していることが予想されたので、速力を減ずるとともに見張員を置くなどして航行すべきであったのに、いずれも怠り進路の安全不確認のまま進行したのは注意義務違反である
とし、業務上過失致死罪の成立を認めました。
広島高裁判決(平成2年3月22日)
高性能船の操船者である被告人が前方注視を怠って被害船に気付かずに直進したため、小型船舶に衝突し、小型船の船員を死傷させた事案で、被告人の前方注視義務違反が認められるとし、業務上過失致死罪が成立するとしました。
相手船が自船を避けてくれる誤信したことが原因となった事故
広島地裁判決(昭和53年9月11日)
狭い水路において、旅客フェリー(1,933トン)と大型貨物船(7,520トン)とが衝突し、旅客フェリーの乗客が死傷した事案で、旅客フェリーの船長の過失が認められ、業務上過失致死傷罪の成立が認められた事例です。
裁判官は、
- 旅客フェリーの船長としては、衝突が予見できたから、時速16ノットを12ノットに減速するはもちろん、状況に応じ機関停止、後進全速、激右転等の措置によって安全に停止あるいは右転できる程度に十分減速して進行すべきで、本件水道の地形、水深、可航幅、相手貨物船と本船のトン数、船の長さ等から、相手船が右転して、航路筋の右側についてくれると信頼することはできない
と判示し、相手船が避けてくれることを信頼するのが相当な場合ではなく、船長に減速しなかった過失が認められるとし、業務上過失致死傷罪が成立するとしました。
横浜地裁判決(昭和43年6月26日)
深夜、貨物船(9,282トン)の船長が、自船の左前方にある護衛艦(排水トン2,350トン)を追い越そうとして、そのまま航進すれば衝突するおそれがあったのに、護衛艦が避けて自船に進路を譲るものと思い込み、針路を保持したまま増速し、護衛艦を追い越そうとして衝突し、護衛艦の乗務員を死傷させた業務上過失致傷罪の事例です。
裁判官は、
- 貨物船の船長としては、早期に右転を令して自船を右方に迂回させ、さらには必要に応じて機関の停止や後進を令して自船を減速させるべきであった
とし、貨物船の船長の過失を認め、業務上過失致傷罪が成立するとしました。
濃霧などの悪天候の場合の事故
濃霧などの悪天候の場合については、一層の安全確保が必要となります。
この点に関する裁判例として、以下のものがあります。
津地裁判決(平成17年11月28日)
A汽船とB汽船が衝突し、B汽船の乗組員6名が死亡、1名が負傷した事案です。
裁判官は、
- A汽船の一等航海士として事故当時、A汽船の操船業務に従事していた者に対し、 自船前方約3海里を航行中のB汽船をレーダー映像で発見し、B汽船の左船側を通過して航行するため進路を変更したが、当時は濃霧で視界が制限されていたので、レーダーなどによる動静注視を厳にし、B汽船との位置関係を的確に把握した上で適宜減速したり、必要に応じてその進路を変更するなどの措置を講じて事故を未然に防止すべき注意義務違反がある
とし、A汽船の操船業務に従事していた者の過失を認め、業務上過失致死傷罪が成立するとしました。
千葉地裁判決(平成5年3月31日)
波が高く靄のため視界が悪い状況のもとで、徒に港と思われる方向に航行を継続した場合、針路を誤り、陸岸に接近しすぎて磯波を受けて船を転覆させる危険が予想されたのに、漫然と航行を継続し、磯波を受けて船を転覆させ、乗船していた8名の者に致死傷の結果を生じさせた事案において、操船していた者Aのみならず、同人に操船を引き継いだ者B及び操船指導を引き受けていた者Cについても、業務上過失致死傷罪が成立するとされた事例です。
裁判官は、
- A、B、Cの3名について、それぞれ事故発生を予見し回避すべき義務があり、さらに沖合で船位、方位を失ったことに気付いた時点でボートの進行を停止し、その海域にとどまるのが転覆の回避に最も適切な措置であり、3人の者による迷走行為は、この結果回避義務に違反したものである
とし、A、B、Cの3名に業務上過失致死傷罪が成立するとしました。
狭い海域や交通が集中する場所における事故
狭い海域や交通が集中する場所などにおける航行事故の裁判例として、以下のものがあります。
横浜地裁判決(昭和54年9月28日)
海上交通のふくそうする湾内において、大型タンカー(43,724トン)が右から航行して来た貨物船(10,874トン)と衝突し、33人が死亡、6人が重軽傷を負った事案で、大型タンカー船長に対し、緊急停船の措置をとり、衝突事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があったとし、業務上過失致死傷罪が成立するとした事例です。
裁判官は、
- 船長としては、当時、海上交通安全法施行後間もなく、行政指導も徹底してなく、本海域において衝突を回避すべき航法も明確ではなく、航路左右両側は浅瀬が多く、転舵は危険を伴うので、直ちに機関を停止し、全速後進を指令し、緊急停船の措置をとるべきであった
とし、大型タンカー船長の過失を認定し、業務上過失致死傷罪が成立するとしました。
鹿児島地裁判決(平成9年1月10日)
遊漁船(2.1トン)の船長が、岩礁や浅瀬に囲まれた狭い海域を航行中、船尾方向から高さ約5メートルの高波を受けて遊漁船を転覆させて、釣り客3名を溺死させた業務上過失致死罪の事例です。
裁判官は、
- 本件事故現場では、周期的に高さ約4メートルから5メートルの磯波が打ち寄せている状況にあり、船長もこれを認識していたから、船尾から高波を受けて転覆する危険性を予見することは可能であり、危険な本件海域の航行を避けて迂回するなどして本件事故を回避する措置をとるべき注意義務がある
と判示し、船長の過失を認め、業務上過失致死罪が成立するとしました。
夜間の航行における事故
夜間の航行における事故に関する裁判例として、以下のものがあります。
名古屋地裁判決(昭和44年11月13日)
夜間、漁業船(7,159トン)が自動操舵により航行中、左側の独航船群のうちの1隻(84.7トン)に衝突し、独航船を沈没させて乗員を死亡させた業務上過失致死罪の事例です。
裁判官は、
- 漁業船航海士としては、航海中、絶えず自船の周囲への注意を怠らず、常に前方、左右に対しては厳重な見張警戒をし、殊に自動操舵に切り替えるような場合には、船長の許可を求めて万全を期すか、周囲の状況を十分に観察して安全を確認した上、切替後は前にも増して厳重な見張警戒をし、他船又は障害物の接近をなるべく早期に発見し、他船が近距離に接近した場合には速やかにその動向を確認し、汽笛を吹鳴して警告を発し、自船の針路を変更する等適宣な措置を講ずべきであった
とし、漁業船航海士の過失を認め、業務上過失致死罪が成立するとしました。
神戸地裁判決(昭和43年12月18日)
夜間、貨物船(9,547 トン)の船長が、自船の左前方に、衝突のおそれのある横切り関係で来航して来る貨客船(239トン)を認めながら、この動向に注意を払わず航行し衝突させ、貨客船の乗員を死傷させた業務上過失致死傷罪の事例です。
裁判官は、
- 貨物船船長としては、貨客船の動向を自ら注視するか、又は見張員をして注視させ、適切、適確な操船の指揮をし、特に夜間であって相当接近しており、自船は針路、速力を保持する義務を有するから、余裕をもって確実に信号を発し、相手船の意向が不明の場合は、さらに続けて注意喚起信号や疑問信号を繰り返して相手船に避航を促すか、少なくともその動向(右転か左転か)を明らかにするよう促し、それに対応する措置をとるべきであった
と判示し、貨物船船長の過失を認め、業務上過失致死罪が成立するとしました。
船舶の装備不良に伴う事故
船舶の装備不良に伴う事故に関する裁判例として、以下のものがあります。
大阪地裁判決(昭和48年4月14日)
主発電機の気中遮断器が、前日を含め、時折外れたことのあるタグボート(149.52トン)が、狭隘な水路で、観光遊覧船(22.2トン)を時速約6ノットでその左舷側から追い越そうとしたところ、その主発電機の気中遮断器が外れ、操船不能になって遊覧船に衝突し、観光遊覧船を覆没させて乗員を死傷させた業務上過失致死傷罪の事例です。
裁判官は、
- タグボート船長としては、遮断器が外れた場合には、全く操船不能に陥るから、自船の速力を減じて遊覧船の追越しを断念するか、あえて追い越す場には操舵手に対し、的確な指示を与えつつ、遊覧船の側方に十分な間隔を保って追越進航し、追越中、右遮断器が外れ、操船不能に陥った場合には、直ちに汽笛を吹鳴して遊覧船の注意を喚起し、速やかな避譲を促すべきであった
と判示し、タグボート船長の過失を認め、業務上過失致死傷罪が成立するとしました。
被害船側に過失があるとし、業務上過失致死罪の成立を否定した事例
被害船側に過失があるとし、業務上過失致死罪の成立を否定した事例として、以下の裁判例があります。
大阪高裁判決(平成4年6月30日)
漁船K丸が夜間無灯火で航法に違反して向かって航行してきた伝馬船と衝突し、伝馬船の乗員に傷害を負わせたとして、漁船K丸の船長が業務上過失傷害罪で起訴された事例です。
裁判官は、
- 伝馬船は、全くの無灯火で狭い水路における右側端航行義務に違反しており、本件で衝突を回避するためには、K丸は速力を4ノット程度以下にしなければならなかったのであり、上記のような伝馬船のあることまで予想して極端に減速徐行するまでの義務はない
と判示し、漁船K丸の船長に過失はないとし、業務上過失傷害罪の成立を否定し、無罪を言い渡しました。
【参考事例】
上記裁判例とは逆に、被害船が無灯火だったが、被告人の過失を認め、業務上過失致死罪の成立を認めた以下の裁判例があります。
福岡高裁判決(平成9年3月13日)
海上タクシーとして運航される汽船船長が、付近海域の航海経験が豊富であることからレーダーを使用せず、目測のみで約24ノットの速力で進行中、無灯火で航行中の漁船に衝突させ、漁船を転覆させて乗員を死亡させた業務上過失致傷罪の事例です。
裁判官は、
- 汽船船長は、事故現場の海域の実情等に照らし、小型漁船が無灯火で航行することは十分予見でき、レーダーを使用していれば、被害漁船の船影を捉え、前方海上に他船が存在することを十分認識でき、その後は目視で注意すれば、被害漁船を発見し、衝突を回避できた
と判示し、汽船船長の過失を認め、業務上過失致傷罪が成立するとしました。
業務上過失致死傷罪、重過失致死傷罪、過失運転致死傷罪の記事まとめ一覧