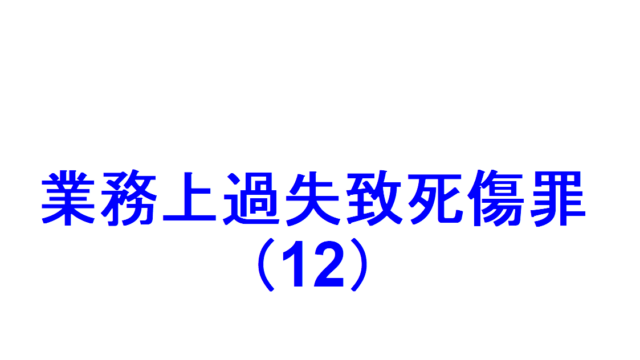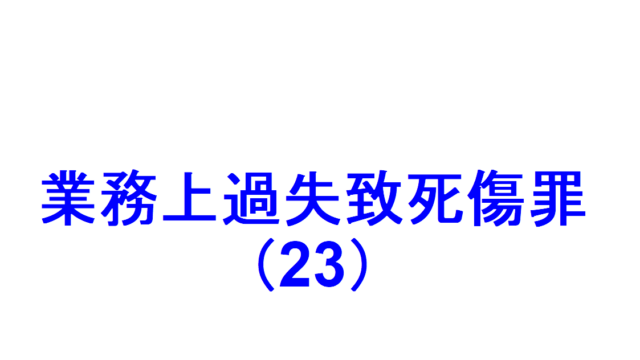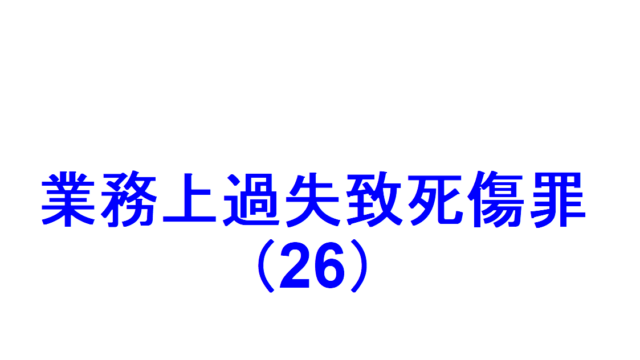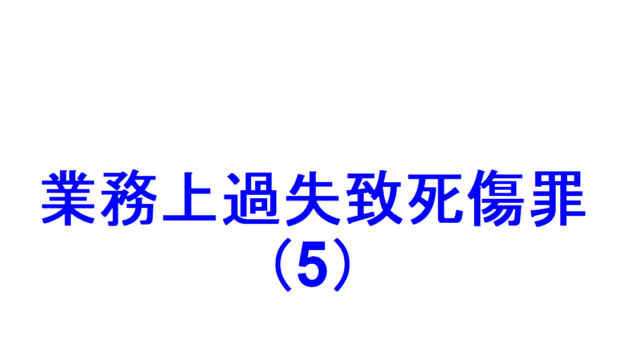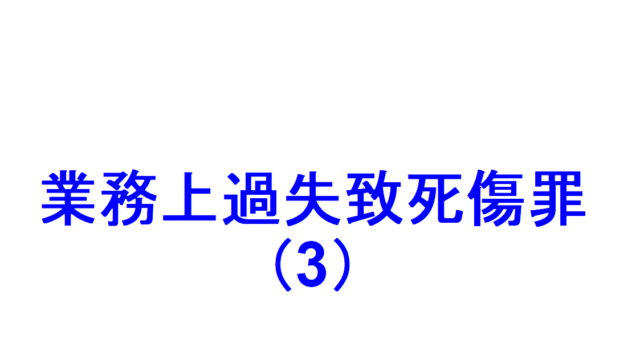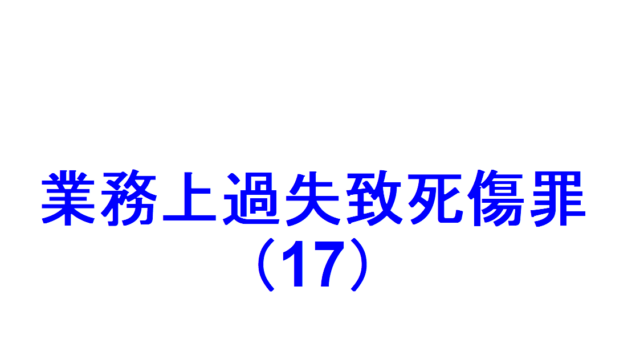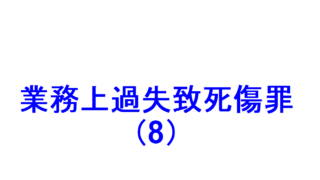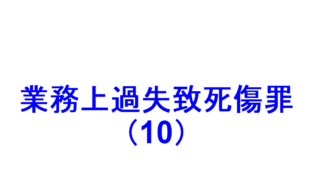業務上過失致死傷罪(9) ~「段階的過失論(直近過失論)」「過失併存論」を説明~
前回の記事の続きです。
段階的過失論(直近過失論)
業務上過失致死傷罪(刑法211条前段)は、過失行為すなわち注意義務に違反した行為を処罰するものです(過失についての説明は前の記事参照)。
つまり、業務上過失致死傷罪の成立を認めるに当たり、行為者(被告人)に過失があったことが必要になります。
この過失を認定する考え方に、段階的過失論(直近過失論)があります。
段階的過失論(直近過失論)とは、
結果に対し、直近の不注意のみを過失犯の過失とすべきである
とする考え方です。
実際に、段階的過失論(直近過失論)の見解をとる裁判例も多く見られます。
裁判官は、
- 実定法上、現実に結果が発生した場合にのみ過失犯の成立を認め得るとされている以上、発生した結果と無関係にある時点における被告人の不注意な行動を非難することは無意味である
- よって、被告人の過失責任の存否を判断するには、まず、現実に生じた法益侵害の結果を起点として因果の連鎖を遡り、被告人の作為または不作為によって因果の流れを変え得たと目される最初の分岐点において被告人による結果の予見およびその回避の可能性を検討し、 これが否定された後、はじめて順次それ以前の段階に遡って同様の検討を繰り返すことが必要であり、かつ、 これをもって足りる
と判示し、過失を認定するに当たり、段階的過失論(直近過失論)の考え方を用いました。
東京高裁判決(昭和46年10月25日)
裁判官は、
- 同一人が時間的に連続し、かつ順次原因・結果の関係をなす2個以上の行為によって結果を発生させた場合において、過失犯の成否を考えるに当たっては、たとえその行為がいずれも過失によるものであっても、あとの行為が行なわれなければ要するに結果は発生しなかったわけである
- よって、まずその結果に最も近接した最終の行為が過失行為としての要件をそなえているかどうかを考え、もしこれをそなえている場合には、この行為のみを刑法上の過失行為とみるべきである
- もし結果に接着した行為に対し、不可抗力その他の事由により過失行為としての責を問うことができないような場合には、その前の行為に遡って順次過失の有無を論ずべきである
と判示し、過失を認定するに当たり、段階的過失論(直近過失論)の考え方を用いました。
東京高裁判決(昭和47年1月17日)
裁判官は、
- 刑法上の過失犯を考える場合には、一定の結果に最も近接した最終の行為が過失行為としての要件をそなえているかぎりは、その行為のみを刑法上の過失と認めるべきで、それ以前の行為は、たとえ責むべきものがあるにしても情状として考慮するのが相当である
と判示し、過失を認定するに当たり、段階的過失論(直近過失論)の考え方を用いました。
段階的過失論(直近過失論)に対する批判意見
学説において、段階的過失論(直近過失論)に対しては、以下のような批判意見があります。
- 刑法上の過失が直近の落ち度に限られ、先行する落ち度が評価されない理由が不明である
- 先行行為に落ち度があっても、直近の過失行為が認定できない場合に無罪となるのは不合理である
- 直近過失以外の過失が、単なる情状事実となり、訴因に反映されないのは不自然である
なお、このような批判意見があるものの、上記裁判例のように、段階的過失論(直近過失論)の考え方を用いている事例は多々あり、段階的過失論(直近過失論)の考え方は、実務において支持されているといえます。
過失併存論
段階的過失論(直近過失論)に対する考え方として、過失併存論というものがあります。
過失併存論とは、
結果に向けられた数個の不注意は、すべてを過失行為として理解すべきである
とする見解をいいます。
過失併存論を用いた裁判例として、以下のものがあります。
自動車を高速度で運転した上、前方注視を欠いたことで、歩行者との衝突し、歩行者を死亡させた業務上過失致死罪(現行法:過失運転致死罪)の事案で、裁判官は、
- 運転者が前方注視義務を尽くしていても、衝突事故自体はこれを回避することができなかったと認められる場合であっても、運転者が前方注視義務を尽くし、歩行者をその発見可能地点で直ちに発見して急制動の措置をとっていたとすれば、衝突の衝撃が大幅に緩和され被害の結果が現実のそれよりも軽いものとなる蓋然性があったと考えられるときは、高速運転と前方注視義務違反の点は、いずれも、生じた結果に対し因果関係を有する運転者の落度ある態度として、刑法上の過失を構成する
と判示し、過失を認定するに当たり、過失併存論の考え方を用いました。
東京高裁判決(昭和44年8月4日)
道路を横断していた2歳児に自動車を衝突させて死亡させた業務上過失致死罪(現行法:過失運転致死罪)の事案で、被告人の過失の内容は、最高速度違反ばかりではなく、さらに、前方注視義務違反も併存するものとして原判決を破棄した事例です。
裁判官は、
- 原判決が本件事故を不可避的なものではなく、被告人の過失によるものとした点は正当であるが、その過失をただ高速度という点に求め、その速度を時速60キロメートルくらいと認定した点において失当である
- 本件事故は、当時被告人が法令により制限された最高速度たる40キロメートル毎時を超え時速50キロメートルくらいの速度で進行していたことと、前方左右を注視していなかったこととを内容とする過失によってひき起されたものと認定するのを相当とするから、これらの点において、原判決には、結局、事実の誤認がある
と判示し、被告人の過失の内容は速度違反だけではなく、速度違反と前方不注視が併存するものであるとし、過失の認定に過失併存論の考え方を用いました。
東京高裁判決(昭和47年7月25日)
交通事故防止のための注意義務の懈怠が数個存在する場合に、刑法上の責任条件たる過失は事故の発生に最も接着したもののみに限らないとされた事例です。
被告人の弁護人が、
- 被告人の過失として、(イ)漫然時速約70キロメートルで進行したこと、(ロ)急停車しようとして強くブレーキを踏んだことの2点を認めているが、交通事故においては、その結果発生までの経過には、数個の不注意ないしは規則等の不遵守が認められる場合でも、結果に結びつく法律上の過失は(従ってその前提となる注意義務も)1個であり、しかも事故にもっとも接着したものが過失であって、他は経過としての事情と理解すべきであるから、本件においても、仮に被告人の過失が認められるとすれば、それは1個でなければならないのに、原判決が、右のように2個の過失(2個の注意義務)を認定したのは、被告人に対し、いかなる過失を認定したのか不明であり、判決の理由に不備がある
と主張したのに対し、裁判官は、
- 交通事故において、犯人が2個以上の注意義務を怠り、死傷の結果を発生せしめた場合、その結果発生に対し、相当性のある不注意が1個でなければならないと解すべき理由はない
と判示しました。
秋田地裁判決(昭和48年10月5日)
夜間、降雨中の道路を、前照灯下向きのまま時速約60~65キロメートルの高速で進行中、進路前方を対向歩行中の歩行者を約6.3メートルに接近してはじめて発見し、自車を歩行者に衝突させて死亡させた業務上過失致死罪(現行法:過失運転致死罪)の事案で、高速運転の点だけでなく、前方不注視の点も過失の内容をなすと解するのが相当であるとした事例です。
裁判官は、
- いわゆる段階的過失論によれば、本件の場合は減速せすに高速で走行したことのみが過失であって、前方不注視は過失とならないものとされるが、本件の場合のように、減速義務のみではなく、前方注視義務をも履行しなければ事故を回避することができないときは、高速走行とともに前方不注視もまた過失の内容をなすものと解するのが相当である
と判示しました。
業務上過失致死傷罪、重過失致死傷罪、過失運転致死傷罪の記事まとめ一覧