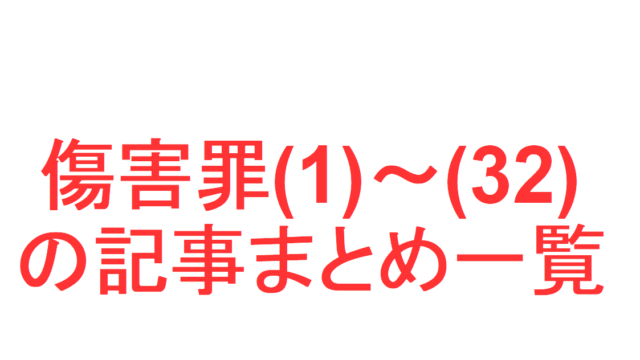傷害罪(18) ~傷害罪における違法性阻却⑨「自救行為による違法性阻却」を判例で解説~
前回の記事では、傷害罪において違法性阻却事由となりうる「警察官の違法な職務執行に対する傷害罪の成否」などについて説明しました。
今回の記事では、傷害罪において違法性阻却事由となりうる「自救行為による違法性阻却」について説明します。
自救行為とは?
まずは自救行為について説明します。
自救行為とは、
国家に頼らず、自らの力で自分の権利を守ること(自力救済すること)
をいいます。
極端な例ですが、たとえば、自分の家族を殺された場合、犯人は国家により裁かれます。
しかし、「国家による裁きを待っていられない!」「自の力で犯人に復讐して自分の権利を守る!」と考え、復讐をして犯人を殺すことは、自救行為と位置づけることができます。
ですが、本来、自救行為は禁止されています。
どんな場合でも国家が、国民の権利を守り、救済することになっているためです。
日本では、国民が、自らの力で、自らの権利を守り、自らを救済する「自力救済」を前提としていないのです。
しかし、自力救済を全く禁止してしまったら、国家による救済を待っていられない緊急事態が起こったときに、国家は、国民に対し、「自力救済はせずに、そのままやられろ」と宣告する状態になってしまいます。
なので、自力救済を完全に禁止することは妥当ではありません。
そのため、自力救済は、一定の限度で認められているのです。
自力救済をして、それが犯罪行為になっても、違法性が阻却され、犯罪を成立させないのです。
自力救済は、違法性阻却事由となるのです(より詳しくは前の記事参照)。
傷害罪における自救行為に関する判例
傷害罪において、自救行為(自救行為を敢行する中で行われた正当防衛)に関する判例として、以下の判例があります。
この判例は、一般論として、承諾を得ないで建物を使用している者が、建物所有者側の者において無断でその屋根を引きはがすのを見て憤慨し、かつ自己の占有権を防衛する意思をもって、相手を殴打する行為は、正当防衛に当たるとしました。
もっとも、この裁判の事件では、被告人は、何ら屋根の取り壊しを制止すべき交渉をすることなく、いきなり丸太をもって背後から被害者を殴打したもので、やむを得なかったものとは認められず、傷害罪が成立すると判示されています。
被害者において自救行為の許される状況があったとは認められない事案でした。
具体的な判決内容は以下のとおりです。
裁判官は、
- 被告人は、小屋の屋根のトタン板の取りはずし作業をしていたAの頭と肩とを背後から丸太棒を持って怒鳴りながら2回殴打したこと、被告人は、検察官に対し、Aを殴打したのは正当防衛による旨を供述しているが、司法警察員に対しては「私は急いで自宅へ帰り、物置小屋を見ると、4、5人の人夫が壊しているので、立腹して壊している現場へ行きました。見ると道具を外へほうり出しているので、かっとなり、どこで握ったのかはつきり記憶しませんが、現場で丸太棒を持って、おれの家の小屋を誰に断って壊しているのかと言うと、人夫 は、私達は連合会の命令で来たのや、文句があれば上の人に言ってくれと申したので、私は丸太棒を握り、Aに傷を負わしたが、興奮していたので、どこをたたいたか記憶はない」と供述していることが認められる
- 以上を総合すると、小屋に対する被告人らの占拠が不法なものであったとしても、これを排除するには法的手段によるべく、実力をもって右小屋の取り壊しをするがごときことは、ま さに急迫不正の侵害に該当するというほかはなく、被告人が判示暴行をあえてしたのは、防衛の意思によるとともに、相手方に対する憤激によるものと考えられる
- そして、行為が正当防衛となるためには、専ら防衛の意思によることを要するとの考え方もあるが、しかし他人から侵害をうけて憤激の情を持つことなく、専ら防衛の意思によって反撃する場合に限り正当防衛を認めるのは、人間本来の感情性を無視した立論というのほかはなく、憤激の情を発しながら、かつ防衛の意思による場合でも、正当防衛となる場合があるとすべきであり、それが正当防衛となるか否かは、刑法第36条にいわゆるやむことを得ざるに出でたか否かによって決すべきものと解するのを相当とする
- そして、やむことを得ないか否かは、具体的状況に照し、通常何人も執るべき程度の行為であるか否か、換言すれば相当性があるか否かによって決すべきである
- 被告人の本件行為は、屋根に上っているAに対し、屋根の取り壊しを制止すべき交渉をすることなく、いきなり丸太棒を持って、しかも背後から同人の頭と肩とを殴打したもので、かくのごときは、やむことを得なかったものとすることは到底できない
- 従って、被告人は傷害の罪責は免れないことはもちろんである
と判示しました。
登米簡裁判決(昭和45年12月23日)
この判例は、割賦販売代金の支払いを遅滞していた被告人から販売物件である扇風機を引き揚げようとして被告人方座敷に侵入した割賦販売会社の社員に対する傷害について、侵入行為を違法なものと認め、正当防衛として傷害罪は成立せず、無罪を言い渡した事例です。
公訴事実は
- 被告人は、自宅において、扇風機代金の請求に訪れたMと口論し、Mに左眼付近を1回殴打されたことに立腹し、Mと取組み合いの喧嘩となり、Mを屋外に転落させる暴行を加え、よってMに対し、約1週間の加療を要する右手打撲症等の傷害を与えた
という傷害罪の事案です。
裁判官は、
- Mが被告人方座敷へ立ち入った点について考えてみるに、被告人が扇風機の代金の支払を遅滞していたのであるから、会社としては、あくまでもその代金の支払を求めるつもりならばその代金の請求を、現物の返還を欲するならば契約を解除して現物、もしくは、現物なきときはこれに代る損害賠償の請求を、いずれも民事手続によってその実現をはかるべきであり、代金の支払を遅滞しているからといって買主が拒否しているのにこれを実力で排除して無理やり持ち去ろうとすることは許されないものといわなければならない
- 支払猶予をこう被告人の態度、被告人の年齢、職業、割賦弁済の経過期間、代金額等を考慮すれば、会社において、ただちに現物を持ちかえらなければならないという緊急な事態であったとは到底認めることはできない
- 会社の発行する月賦販売契約書記載の契約条項4項には「貴会社が必要と認めた場合は、いつでも貴会社又はその代理人が購入機械の検査をすることに同意し、かつその作業を妨げません。」とあり、同5項には「私が上記割賦金支払の約定に違返した場合は・・・・・・本契約を解除されて機械及び附属品を引揚げられても異議を申しません。」とあり、同6項には「前項により貴会社が機械及び付属品を引き揚げるため、貴会社又はその代理人が機械の存在するいずれの場所にも自由に立入り、その機械及び付属品を任意に他へ搬出することを認め、これを理由として住居侵入の告訴もしくは損害賠償の請求等は決していたしません。」とある
- 何人も憲法および法律によって、住居の不可侵、自己の占有物について、みだりにその占有を奪われない権利を持っていることは明らかであり、しかもそれは極めて重大な権利である
- 右のように販売者側に有利で、かつ、買主側の権利侵害を多分にともなうおそれのある条項の効力については非常に問題のあるところであるが、これも買主側のその具体的な状況の場において異議なく同意し立ち入り、引き揚げに応ずる場合はともかくとして、買主が明確に拒否する態度を示しているのにこれを強行することは絶対に許されないものといわなければならない
- したがって、Mが被告人方より扇風機を持ち帰ろうとして、M方座敷に侵入した所為(現物確認のためでも同じ)は、まさに目前にさし迫った違法の侵害行為というべく、被告人がそれを阻止すべくMの胸のあたりを押した行為およびMに殴打されて止むなく同人の胸倉にしがみつきもみ合った行為は、その全体においてMの侵害行為に対し、自己の権利を防衛する意思のもとになされた反撃行為と認めるのが相当である
- そうすると、被告人の前記行為は正当防衛としてその行為の違法性を阻却し、罪とならないものといわなければならない
- よって、刑事訴訟法336条を適用し、被告人に対し、無罪の言い渡しをする
と判示しました。