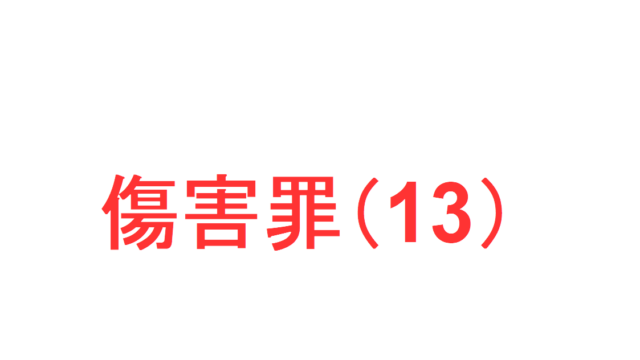傷害罪(9) ~「傷害罪における『事実の錯誤』」を判例で解説~
傷害罪における「事実の錯誤」
傷害罪(刑法204条)を犯すに当たり、暴行を加える相手を間違ったり、犯人がけがを負わすつもりでなかった者にまでけがを負わせることがあります。
この状況を「事実の錯誤」といいます。
「事実の錯誤」とは、犯人が認識していた犯罪事実と、実際に発生した犯罪事実が食い違う場合をいいます。
たとえば、
夫を殺すつもりで食事に毒をもったのに、友人が毒をもった食事を食べてしまい、友人を殺してしまった…
というケースの場合、犯人が認識していた犯罪事実と、実際に発生した犯罪事実とが食い違うので、「事実の錯誤」となります(詳しくは前の記事参照)。
「事実の錯誤」の結論として、事実の錯誤があったからといって犯罪は不成立とはならず、きちんと犯罪は成立します。
傷害罪における事実の錯誤について、判例を紹介して説明します。
傷害罪における事実の錯誤の判例
大審院判決(明治35年4月7日)
この判例で、裁判官は、
- 強盗を殴打創傷したる場合といえども、なお殴打創傷罪を構成す
- 従って、強盗なりと誤信して他人を殴打創傷せしめたる所為をもって、罪となるべき事実を知らざりしものというを得ず
と判示し、強盗犯と勘違いして相手を殴り、けがをさせた場合であっても、傷害罪は成立するとしました。
大審院判決(明治42年3月12日)
この判例で、裁判官は、
- 刑法第204条の犯罪を構成するには、殴打する意思の存在を要すること論なし
- 従って、同条の犯罪は、人を殴打するの意思をもって暴行を加え、傷害の結果を生ぜしむるにより成立するものなれば、その意思をもって暴行を為したる以上は、その結果が犯人の観察せざりし客体の上、すなわち目的以外の人に発生するも、意思と結果との間に因果の関係なきものというを得ざれば、その場合においても加害者は殴打創傷罪の制裁を免がれることを得ず
と判示し、殴る相手を間違え、別の人を殴ってけがをさせた場合であっても、傷害罪は成立するとしました。
大審院判決(大正3年11月18日)
この判例で、裁判官は、
- 小児を背負いたる者が転倒すれば、小児はこれを共に転倒すべきは必然の事に属するをもって、小児を背負いたる者を突き飛ばし、これをして転倒せしむる者は、小児の転倒すべき事はこれを予測せざるべからず
- すなわち、小児を背負いたる者を突き飛ばすは、小児に対してもまた暴行なること論を竢たず
- 従って、これがため小児に負傷せしめたるときは、傷害罪の責を免れるを得ず
と判示し、子どもを背負った人を殴って転倒させ、その子供にけがをさせた場合、その子供に対しても傷害罪が成立するとしました。
大審院判決(大正6年12月14日)
この判例で、裁判官は、
- 刑法第204条の罪は、単に他人に対し、故意の暴行により傷害の結果を生ぜしむるによりて成立すべきものにして、他人に対し、故意に暴行を加え、よって傷害の結果を生ぜしめたる以上は、その傷害の結果が犯人の目的としたる者と異なる客体の上に生じたる場合といえども、暴行の意思とその暴行に基づく傷害の結果との間に、因果関係の存在を認める
- 従って、傷害罪の成立に必要なる条件に欠ける所なきをもって、犯人は右法条の罪責を負うべきものにして、暴行の認識なき過失傷害罪をもって論ずべきものにあらず
と判示し、犯人の目的とした人でない人に暴行を加えてけがをさせた場合でも、暴行の意思があり、暴行と傷害の結果に因果関係があるので、傷害罪が成立するとしました。
大審院判決(大正11年5月9日)
この判例で、裁判官は、
- 人に対し、故意に暴行を加えたるにより、傷害又は傷害致死の結果を生じたるときは、たとえその結果が犯人の目的とせず、かつ毫も意識せざりし客体の上に生じたる場合といえども、傷害罪又は傷害致死罪の成立を妨げず
と判示し、暴行罪にとどめるつもりで暴行を加え、結果的に傷害・傷害致死の結果を生じさせた場合でも、傷害罪・傷害致死罪が成立するとしました。
大審院判決(昭和6年4月8日)
この判例で、裁判官は、
- 方法又は目的物の錯誤ある場合において、故意を阻却するものに非ざることについては、本院判例の存する所なるをもって、本件において、被告人がMを殴打しようとして『ステッキ』を振り回したる意外にも、その行為によりDに創傷を負わせるに至りたるとするも、傷害罪としての故意責任を免れるべからざるや論を俟たず
と判示し、傷害の方法や、傷害を加える目的物を錯誤があっても、傷害の故意を阻却せず、傷害罪が成立するとしました。
福岡高裁判決(昭和27年9月5日)
この判例で、裁判官は、
- 被告人はAなる人に斬つける意思をもって攻撃し、同じく人たるBに傷害の結果を生ぜしめたものであるから、Bに対する傷害につき、傷害罪の成立ある事もちろんである
と判示しました。
被告人が、Bを殴打しようとして、これを制止しようとしたCを殴打した場合、Cに対する傷害罪の成立を認めた事例です。
裁判官は、
- 人を殴打する意思をもって人を殴打した以上、暴行罪はただちに成立し、その殴打された者が殴打しようとした者と異っても、暴行罪の成立に必要な故意に影響を来すものではない
- されば、被告人がBを殴打しようとして、これを制止しようとした同人の内妻「C」を殴打した以上、同女に対する暴行の故意がないものとはいえない
- それ故、原判決が被告人のCに対する犯行をもって、刑法第204条に問擬(もんぎ)したのは正当である
と判示しました。
高松高裁判決(昭和31年2月21日)
この判例で、裁判官は、
- 仮に被告人に、Aに暴行を加える事により、その打撃がBにも及ぶという認識がなかったような場合であっても、かかる状況下において、人に暴行を加える意思の下に暴行を加え、人を負傷せしめた以上は、その傷害の結果発生がたとえ犯人の目的とした人と異なり、しかも予期しない人の上に生じたときでも、その間に相当因果関係の認め得られる限り、その結果につき、当然故意犯としても責任を負担しなければならないのである
- そして、この場合、その傷害が発生するに至った過程が、犯人の下した手が犯人の目的とする客体以外のものに当たったとか、目的とするものと予期しないものとの双方に共に当たったという場合に限らず、Aを突こうとして手を下し、Aを突いたため、Aが犯人の予期しないBに当ってBが転倒し、Bに傷害の結果が発生したという場合においても結論を異にすべき理由がない
と判示しました。