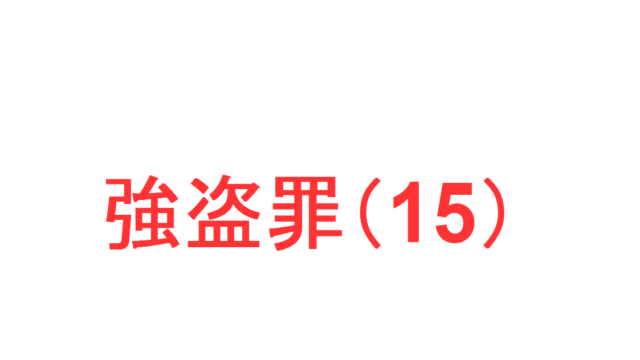強盗罪と暴行罪、傷害罪、脅迫罪との関係
強盗罪(刑法236条)と暴行罪(刑法208条)、傷害罪(刑法204条)、脅迫罪(刑法222条)との関係について説明します。
暴行・脅迫が強盗の手段として行われた場合には、暴行罪、脅迫罪は別罪として成立しない
暴行・脅迫が強盗の手段として行われた場合には、暴行・脅迫は、強盗罪の構成要件要素なので、強盗罪のほかに、暴行罪・脅迫罪が別罪として独立して成立することはありません。
暴行・脅迫後に、強盗の犯意が生じた場合の強盗罪の成否
他の目的で暴行・脅迫を加えた後に、財物奪取の意思が生じた場合は、
- 被害者の反抗を抑圧する程度の新たな暴行・脅迫がなされない限り、強盗罪は成立しないとする判例
- 新たな暴行・脅迫がなくても強盗罪は成立するとした判例
の2つがあり、判断が分かれています(詳しくは前の記事参照)。
強盗罪が成立する場合、強盗の手段としての暴行・脅迫は、強盗罪に吸収される
強盗罪が成立する場合、前の暴行・脅迫と強盗罪とは別罪を構成し、両者は併合罪となるものではなく、前者の暴行・脅迫は、強盗罪に吸収されて、強盗罪の一罪が成立するにすぎません。
財物を奪取してから、暴行・脅迫を加えて、その奪取を確保する場合についても、強盗罪の一罪が成立し、暴行・脅迫は別罪として成立しません(詳しくは前の記事参照)。
強盗罪が成立しなかった場合には、強盗行為に伴う暴行・脅迫は、暴行罪・脅迫罪として独立して成立し、その後の窃盗罪または恐喝罪との併合罪ということになります。
強盗の犯意を途中で生じた場合の傷害罪、強盗罪、強盗致傷罪の成立関係
強盗の犯意を途中で生じた場合に、傷害罪、強盗罪、強盗致傷罪のどの罪が成立するかについては、以下の①~③のパターンで整理できます。
① 強盗以外の目的で傷害が生じた後、強盗の犯意を生じて、強盗致傷罪を犯した場合
→強盗致傷罪の一罪が成立する
② 強盗以外の目的で傷害が生じた後、強盗の犯意を生じて、強盗罪を犯した場合
→傷害罪と強盗罪が混合した包括一罪が成立する
又は
→傷害罪と強盗罪が成立し、両罪は併合罪となる
③ 強盗以外の目的で傷害が生じた後、強盗の犯意を生じて、強盗罪を犯した場合で(上記②の類型)、傷害の結果が強盗の犯意形成前後のいずれの暴行によって生じたか判定できない場合
→傷害罪と強盗罪が混合した包括一罪が成立し、最も重い強盗罪の刑で処断する
①の類型の判例
①の類型(強盗以外の目的で傷害が生じた後、強盗の犯意を生じて、強盗致傷罪を犯した場合→強盗致傷罪の一罪が成立する)の判例として、以下の判例があります。
この判例で、裁判官は、
- 強盗の犯意を生ずる前の傷害は、単純な傷害であり、その犯意を生じた後の傷害は、強盗と傷害の結合犯たる強盗傷人罪の構成部分たる傷害である
- その意味において、強盗の犯意を生じた時期を境として、その前後二群の傷害は、切離された二個の行為であり、前の傷害と後の強盗傷人とは別罪である
- しかし、それは法律評価の問題であって、これを社会的現象として観るときは、その評価の対象たる二群の傷害は、一個の身体侵害の意思に基づき、時を接して引き続き行われるのであるから、 これを一連不可分的のものとみるべきで、しかも、後の傷害は強盗行為に伴うもので、これと結合一体の関係にあるのであるから、これらすべてを全体的に包括的に観察して、一連一個の行為と解するのが相当である
- すなわち、罪数的には、それは一種の接続犯的な傷害と強盗傷人との混合した包括一罪であって、重い強盗傷人罪の刑をもって処断すべき一罪と解する
と判示し、強盗傷人罪の一罪が成立する
また、この判決では、傍論として、
- 例えば、傷害が、強盗の犯意を生じた時期を境として、その前後二群の暴行のいずれによって生じたか不明の場合を考えれば、傷害が強盗の犯意を生じた後の暴行に基因することの証明がない限り、犯人を強盗傷人罪に問擬(もんぎ)することは許されないから、前後の暴行は強盗傷人にはならないけれども、前後の暴行は一体として観察されるから、結局、単純傷害の責を犯人が負わねばならないのであって、傷害と強盗との混合した包括一罪であることを意味するのである
- 前の傷害と後の強盗傷人とを併合罪とする原判決の見解をとれば、この場合、傷害の結果を前後いずれの暴行にも帰せしめられない以上、暴行と強盗との併合罪となり、犯人に傷害の責を負わしめることができなくなるのであって、一連の暴行によって生じた傷害の結果を、刑法上評価できないのは、明らかに不当である
- また、右併合罪の見解は、途中、強盗の犯意を生じなかった場合、傷害となるに比しても権衡を失する
と判示しました。
②の類型の判例
②の類型(強盗以外の目的で傷害が生じた後、強盗の犯意を生じて、強盗罪を犯した場合→⑴ 傷害罪と強盗罪が混合した包括一罪が成立する、又は、⑵ 傷害罪と強盗罪が成立し、両罪は併合罪となる)の判例として、以下の判例があります。
【⑴ 傷害罪と強盗罪が混合した包括一罪が成立するとした判例】
新潟地裁判決(昭和45年12月11日)
強盗致傷の起訴につき、傷害の結果が、強盗の犯意発生前の恐喝の意思による暴行によって生じたものとして、強盗罪と傷害罪の包括一罪と認め、重い強盗罪の刑によって処断すべきであるとした事例です。
裁判官は、
- 公訴事実は、要するに、被告人3名が共謀して、Yから現金在中の財布および腕時計を強取し、その際、Yに傷害を負わせたというのであって、被告人3名につき、いずれも強盗致傷罪が成立するというのである
- ところで、そのうち被告人Kの罪責については後に述べることとし、はじめに被告人MとOの罪責について検討する
- まず両被告人の犯意の点を考える
- 判示のように、本件においては、通称西新道の道路上での、第一現場における暴行、脅迫行為と、栗の木川橋下での第二現場における暴行、脅迫および金品の奪取行為とに分れる
- 第一現場における両被告人の犯意については、両被告人の捜査官に対する各供述調書および当公判廷における供述によっても、せいぜい判示のような恐喝の犯意が認められるに止まり、強盗の犯意があつたか否かについては必らずしも明らかでないばかりでなく、その現場が新潟市内の飲食店などが密集する繁華街であつて、犯行時の午後12時ころにも酔客などの通行が多いと認められること、付近には看板灯や外灯の設備などがあって比較的明るい場所であり、被告人らの行為は容易に第三者の目撃できる状況にあること、Yがタクシーに乗り込まされる間際まで、Yと同行していたTが近くにいたこと、第一現場での両被告人の暴行、脅迫行為もこれを全体として見るときは、未だYの反抗を抑圧するに足りる程度に至っていたものとは認められないことなどの客観的状況に照らしても、両被告人が第一現場で強盗の犯意を有していた点については証明が十分でなく、恐喝の犯意に止まるものと認めるのが相当である
- そして、両被告人の強盗の犯意は、栗の木川橋下の第二現場に至ってはじめて生じ、判示のように、人目につかない暗い場所で強い暴行、脅迫を加えてYの反抗を抑圧して金品を強取したものと認められる
- このように、まず第一現場において恐喝の意思による暴行、脅迫がなされ、それが第二現場に至って強盗の犯意による暴行、脅迫に発展し、その結果、金品を強取したものであるが、両者は金品の奪取という単一の目的に向けられた一連の行為であり、行為の客観的側面においても、また両被告人の主観的な意思の側面においても連続性が認められるから、これを包括して重い強盗の一罪(なお傷害との関係については次に述べる)が成立するものと解する
- 次に右の強盗と本件の傷害との関係を考える
- 本件の被害者Yが、本件により判示のような下顎挫傷の傷害を負ったことは、証拠上明らかである
- そして、証人Dの証言(第一回)によれば、右の傷害は直接には第一現場での被告人Mの暴行により生じたことが認められ、この認定をくつがえすに足りる証拠はない
- ところで、強盗致傷罪を構成するためには、傷害が強盗の機会において受けたものであることを要し、換言すれば、傷害が強盗という身分を有する者による犯行の際に生ずること、すなわち犯人が強盗の犯意を生じた後のものであることを要するものと解する
- 本件のYの傷害は、右のように第一現場において受けたものであり、また第一現場においてはさきに述べたように両被告人は恐喝の犯意を有したに止まり、未だ強盗の犯意がなかったものであるから、右の傷害の事実は認められるとしても、本件については、そのことから直ちに強盗致傷罪を構成するものではなく、前記のような強盗罪とこれとを切り離された傷害罪とに分けて評価すべきものと解される
- そして、この強盗と傷害とは、本件の事実関係に徴すると、両者の混合した包括一罪が成立し、結局重い強盗罪の刑によって処断すべきものと解するのが相当である
と判示し、傷害の結果が、強盗の犯意発生前の恐喝の意思による暴行によって生じたものであるから、強盗致死罪は成立せず、強盗罪と傷害罪の包括一罪が成立し、重い強盗罪の刑によって処断すべきであるとしました。
【⑵ 傷害罪と強盗罪が成立し、両罪は併合罪となるとした判例】
高松高裁判決(平成16年9月21日)
被告人が、共犯者と共謀の上、被害者の頭部を木刀で殴るなどの暴行を加えて、加療約3週間を要する傷害を負わせた後、被害者に対し、その反抗を抑圧するに足りる脅迫を加えて現金8000円を強取した上記②の類型の事案です。
原審が、傷害と強盗が混合した包括一罪と認定したのに対し、裁判官は、
- 傷害の結果が、強盗の犯意発生前に加えられた暴行により生じていることが明らかな場合と、そうでない場合とを区別せず、一様に傷害と強盗の混合包括一罪とする趣旨をいうものとすれば、犯人が、被害者に対する暴行の直後、その現場において、新たに強盗の犯意を生じることが決して稀な事例でなく、また、広範な併合罪処理の規定を設ける現行法の下では、明らかに合理性を欠くというべきである
と判示して、原審を破棄し、被告人の所為につき、傷害罪と強盗罪が成立し、両者は併合罪の関係にあるとしました。
③の類型の判例
③の類型(強盗以外の目的で傷害が生じた後、強盗の犯意を生じて、強盗罪を犯した場合で(上記②の類型)、傷害の結果が強盗の犯意形成前後のいずれの暴行によって生じたか判定できない場合→傷害罪と強盗罪が混合した包括一罪が成立し、最も重い強盗罪の刑で処断する)の判例として、以下の判例があります。
なお、財物強奪後に傷害を与えたことが分かる場合には、強盗致傷罪の一罪が成立します。
仙台地裁判決(昭和39年7月17日)
恐喝の犯意で暴行を加え、途中で強盗の犯意を生じた場合において、傷害が強盗の犯意を生ずる前後いずれの暴行に起因するものであるかが不明の場合につき、強盗罪(恐喝行為を吸収)と傷害罪とのいわば混合した包括一罪として、結局最も重い強盗罪の刑で処断されるべきであるとした事例です。
裁判官は、
- 本件は、強盗致傷罪として起訴されたものであるが、同罪が成立するためには、傷害が強盗の機会において生じたものであることを必要とし、この「強盗の機会において」というには、傷害が少くとも犯人が強盗の犯意を生じた後の暴行によって生じたものでなければならない
- 従って、傷害が強盗の犯意発生の前後いずれの暴行に起因したものであるかが不明である場合には、これを強盗致傷罪として問擬(もんぎ)することは、疑わしきを被告人の不利益に帰せしめる結果ともなり、とうてい許されないところである
- これを本件について見るに、前示認定のとおり、Fが被告人Kに腕時計を奪取された場所で、被告人らの一連の暴行行為により傷害を受けたことは明らかであるが、この傷害が、被告人Kの強盗の犯意を生ずる前後いずれの暴行に起因するものであるかは、証拠上ついにこれを確定することができない
- しかしながら、右傷害は、前記場所において、被告人Kの強盗の決意発生前後のいずれかの暴行又は恐喝の共犯者たる被告人W、Gの暴行によって生じたものであることは、証拠上疑いのないところであるから、被告人Kは、少くとも傷害の結果について責任を負わなければならないわけである
- 従って、この点につき、被告人Kの利益に、右傷害は同人の強盗の犯意発生前の暴行によるものと解するを相当とするところ、強盗の犯意発生前の恐喝の手段としての暴行と強盗の犯意発生後の暴行とは、一連のもので、相接続する機会に前者より後者へと発展したものと認められるから、被告人Kの判示所為は強盗罪(恐喝行為を吸収)と傷害罪とのいわば混合した包括一罪として、結局、最も重い強盗罪の刑で処断されるべきものと解する
と判示しました。
福岡地裁判決(昭和47年3月29日)
この判例は、強盗致傷罪の起訴について強盗罪と傷害罪の包括一罪と認定した事例です。
裁判官は、
- Mが被告人らに金員および腕時計を強取された場所で、被告人らの一連の暴行行為により傷害を受けたことは、各証拠により明らかであるが、被告人らの強盗の犯意発生前後の各暴行の方法、程度および態様を検討すると、そのいずれによっても判示のような傷害をMに与えるのは不可能でないこと、木件が比較的短時間の接続した一連の暴行によるものであること等を考え合わせると、傷害が被告人らの強盗の犯意発生の前後いずれの暴行によって生じたものであるかについては証拠上明らかではないが、右傷害が判示場所において、被告人らの強盗の犯意発生前後のいずれかの暴行によって生じたものであることは証拠上明らかであるので、被告人らは少なくとも傷害の結果についても責任を負わなければならないところ、判示暴行の時間的、場所的一連性ないしは接着性に着目して、強盗罪と傷害罪の混合した包括一罪として重い強盗罪の刑で処断すべきものと解する
と判示しました。