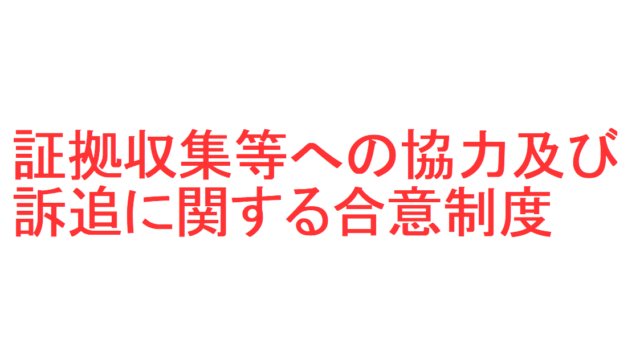訴因変更⑦~「訴因変更の手続の流れ(方法・時期)」「裁判所の訴因変更命令」「控訴審における訴因変更」などを説明
前回の記事の続きです。
訴因変更の手続
- 検察官が、裁判官に対し、訴因変更を請求する
- 裁判所が、検察官が請求した訴因変更を許可する
という流れで行われます。
裁判所が、検察官の訴因変更の請求なしに、職権で訴因変更をすることができない点がポイントです。
訴因変更の手続の流れを以下で詳しく説明します。
訴因変更は、検察官が請求し、裁判所が許可する手続による
訴因の追加・変更・撤回は、第一次的には、検察官の請求によってなされます(刑訴法312条1項)。
訴因変更を行うのは検察官の権限であり、訴因変更を行う主体も検察官です。
そして、検察官の訴因変更の請求に対し、裁判所の許可・不許可がなされます。
検察官の訴因変更の請求は、裁判所の許可があって、初めて効力を生じます。
裁判所は、検察官の訴因変更の請求が「公訴事実の同一性」を害しないものであるときは、訴因変更を許可しなければならない
1⃣ 裁判所は、検察官の訴因変更の請求が「公訴事実の同一性」を害しないものであるときは、訴因変更を許可しなければなりません(刑訴法312条1項)。
訴因は、公訴提起の時点で収集された証拠に基づいて検察官が構成したものなので、公判審理が進むにつれて、起訴状に記載された訴因と公判廷に顕出された証拠とが合致せず、有罪判決を得るために訴因を変更する必要が生じる場合があります。
そのような場合でも、裁判所が訴因変更を認めないとしたら無罪判決を余儀なくされるため、刑罰法令の適正な運用という刑事訴訟の目的(刑訴法1条)が阻害され、被告人が不当な利益を得ることになります。
そこで、裁判所は、検察官の訴因変更の請求が「公訴事実の同一性」を害しないものであるときは、訴因変更を許可しなければならないとされるものです。
2⃣ 検察官が訴因変更を請求した場合に、裁判所が、訴因変更後の訴因について無罪の心証を抱き、訴因変更前の訴因について有罪の心証を抱いていた場合に問題となります。
この問題については、最高裁は、当事者主義を強調して、上記のような場合にも検察官の訴因変更の請求を許可すべきであるとしています。
裁判官は、
- 刑訴法312条1項は、「裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。」と規定しており、また、わが刑訴法が起訴便宜主義を採用し(刑訴法248条)、検察官に公訴の取消を認めている(刑訴法257条)ことにかんがみれば、仮に起訴状記載の訴因について有罪の判決が得られる場合であっても、第一審において検察官から、訴因、罰条の追加、撤回または変更の請求があれば、公訴事実の同一性を害しない限り、これを許可しなければならないものと解すべきである
と判示しました。
公訴事実の同一性の判断基準
公訴事実の同一性の判断基準について、判例は、
- 変更前の訴因と変更後の訴因の両訴因の事実が基本的な事実関係を同じくしていれば両者は公訴事実の同一性の範囲内にある
とする「基本的事実同一説」という立場をとっています。
そして、その判断に当たっては、
- 日時
- 場所
- 犯行方法
- 被害者、被害物件等の近接性・同一性の有無・程度
を考慮し、両訴因を対比して、これらが両立する場合には公訴事実の同一性はなく、反対にこれらが両立しない関係にある場合には公訴事実の同一性があるとします。
判例
1⃣ 公訴事実の同一性が認められた判例として以下のものがあります。
同一被害者にかかる馬の売却代金の着服横領と馬そのものの窃取について、業務上横領罪から窃盗罪へ訴因変更したことについて、公訴事実の同一性を有するとした事例です。
裁判所は、
- 被告人は家畜商を営むものであるが、昭和25年7月25日頃、家畜商Aより同人所有の馬4頭の売却方を依頼され、同月29日うち2頭をBに代金6万円で売却しこれを保管中、同月30日新潟県西蒲原郡a町C旅館において、内金3万円を着服して横領をしたとの業務上横領の訴因と、被告人は昭和25年7月30日、新潟県西蒲原郡b村大字cD方から同人が一時Aより預っていたAの父E所有の牝馬鹿毛および青色各1頭を窃盗したとの窃取の訴因とは、事実の同一性を失わない
- 前者が馬の売却代金の着服横領であるのに対し、後者は馬そのものの窃盗である点並びに犯行の場所や行為の態様において多少の差異はあるけれども、いずれも同一被害者に対する一定の物とその換価代金を中心とする不法領得行為であって、一方が有罪となれば他方がその不可罰行為として不処罰となる関係にあり、その間基本的事実関係の同一を肯認することができるから、両者は公訴事実の同一性を有するものと解する
と判示しました。
恐喝罪として起訴された事実を収賄罪として認定したことについて公訴事実の同一性が認められるとした事例です。
裁判所は、
- 原判示の収賄の事実は、検事はこれを恐喝として起訴していることは所論のとおりである
- しかし、検事が恐喝として起訴した事実と原判示の事実との間には金員の提供者、収受者、収受の日時、場所、金員の額のいずれもが同一であって、ただ金員の収受者が提供者を恐喝して金員を交付せしめたのか、単に職務に関し提供された金員を収受したのかの点において、おのおのその認定を異にするだけである
- されば起訴事実と原判示事実との間には基本たる事実関係を同じくするものと認められるから、原判示事実は起訴事実と同一性を失わないものといわなければならぬ
- 従って起訴事実の罪名と罪質とが原判示事實の罪名と罪質とに一致しないからといって、原判決には審判の請求を受けない事件について判決をしたものということはできない
と判示しました。
業務上横領と詐欺について公訴事実の同一性を認めた事例です。
裁判所は、
- 被告人はA事務局の外務員として同連盟賛助会員の募金並びに賛助金集金等の業務に従事中、昭和26年3月24日頃から同年8月16日頃までの間、25回にわたってB株式会社ほか24名から集金した合計175000円をその都度ほしいままに着服横領したとの業務上横領の訴因と、被告人は昭和25年10月末まで右事務局員として右事務に従事し同日解職されたものであるが、なお右事務局員であるが如くよそおい前記期間中右25名から賛助金名義で前記金額を騙取したとの詐欺の訴因とは、事実の同一性を失わない
と判示しました。
覚せい剤使用罪につき使用時間、場所、方法に差異のある訴因間において公訴事実の同一性が認められた事例です。
裁判所は、
- 覚せい剤使用罪の当初の訴因と変更後の訴因との間において、使用時間、場所、方法に多少の差異があるとしても、いずれも被告人の提出した尿中から検出された覚せい剤の使用行為に関するものであって、事実上の共通性があり、両立しない関係にあると認められる場合には、右両訴因は、公訴事実の同一性を失わない
と判示しました。
なお、覚醒剤などの薬物の使用事件は、被告人が犯行を黙秘していたり、うその供述をしていると認められる場合においては、検察官は薬物の使用日時・場所・方法を特定することができない場合があります。
その場合は、実際の裁判においては、犯行(薬物の使用)の日時・場所を幅広くとり、概括的訴因で起訴することが認められています。
この点に関する以下の判例があります。
覚せい剤使用罪における訴因の特定について、裁判所は、
- 覚せい剤使用の日時を「昭和54年9月26日ころから同年10月3日までの間」、その場所を「広島県a郡b町内及びその周辺」、その使用量、使用方法を「若干量を自己の身体に注射又は服用して施用し」との程度に表示してある公訴事実の記載は、検察官において起訴当時の証拠に基づきできる限り特定したものである以上、覚せい剤使用罪の訴因の特定に欠けるところはない
と判示しました。
2⃣ 上記判例とは逆に、公訴事実の同一性が認めらなかった判例として以下のものがあります。
「銅板を窃盗した犯人にリヤカーを貸与した窃盗幇助」と「犯人が窃取した銅板を買い受けた贓物故買(現行法:盗品等有償譲受け)とは併合罪の関係にあるとして公訴事実の同一性を否定した事例です。
裁判所は、
- 被告人は昭和27年12月30日頃の午後11時半頃、肩書自宅において、Aが川崎市aB化学工業株式会社工場内より同工場長某の管理にかかる銅製艶付板32枚(価格9万6千円相当)を窃取するに際し、同人から例の銅板を会社から持出すからリヤカーを貸してくれと頼まれてこれを貸与し、よって同人の右窃盗の犯行を容易ならしめて幇助した」との窃盗幇助の公訴事実と、「被告人は昭和27年12月31日頃肩書自宅において、Aから、同人が他より窃取して来たものであることの情を知りながら、銅製艶付板32枚(価格9万6千円相当)を金3万円で買受け賍物の故買をした」との賍物故買の事実との間には、公訴事実の同一性がない
と判示しました。
略式裁判について訴因変更の必要がある場合
略式裁判とは、検察官の請求により、簡易裁判所の管轄に属する(事案が明白で簡易な事件)100万円以下の罰金又は科料に相当する事件について、被疑者に異議のない場合、正式裁判によらないで、検察官の提出した書面により審査する裁判手続です。
分かりやすく言うと、略式裁判とは、公開の法廷に裁判官、検察官、被告人が出頭して裁判を行うことなく、裁判所の書面審査により被告人に刑罰を科す手続です。
略式裁判は裁判所による書面審査のみなので、略式裁判について訴因変更の必要があるとされた場合には、略式手続内で訴因変更を行うことができません。
なので、裁判所は、略式不相当として事件を通常手続(公開の法廷に裁判官、検察官、被告人が出頭して裁判を行う正式裁判)に移した上で、検察官の請求・裁判所の許可により訴因変更を行うことになります(刑訴法463条)。
裁判所の訴因変更命令
訴因変更は、一時的には検察官の請求によってこれをなすのが原則です。
しかし、法は、二次的なものとして、裁判所も審理の経過に鑑み、適当と認めるときは、検察官に対して訴因の追加・変更を命じることができるとしています(刑訴法312条2項)。
これは、訴因変更の要否について、裁判所と検察官の見解が相違した場合、検察官が訴因変更の請求をしないと、裁判所は訴因の拘束力によって無罪判決をせざるを得なくなるため、それを防ぐために裁判所にも訴因変更の命令権を与えたものです。
なお、裁判所の訴因変更命令は、裁判所の権限ではありますが、義務ではありません。
訴因は検察官が審判の対象を限定するものなので、裁判所としては、検察官が掲げた訴因の範囲内で審判すれば足り、その範囲を超えて審判する義務はないためです。
また、裁判所が、検察官に対し、訴因変更命令を発しても、検察官がこの命令に従って訴因変更の手続を採らない限り、訴因変更の効力は生じません。
これは、訴因変更は検察官の権限であるためです(最高裁判決 昭和40年4月28日)。
訴因変更の方法
訴因変更は、原則、書面で行うが、口頭でもできる
検察官が訴因変更(訴因の追加、撤回、変更)を請求する場合は、その旨を記載した書面を裁判所に提出します(刑訴法規則209条1項)。
そして、検察官は、訴因変更の書面を公判期日(公判が開かれる日)に公判廷において朗読します(刑訴法規則209条4項)。
ただし、被告人が在廷する公判廷においては、裁判所の許可を受け、 口頭で訴因変更を請求することができます(刑訴法規則209条7項)。
訴因変更による公判手続の停止
訴因変更によって、被告人の防御に実質的な不利益を生じるおそれがあると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、裁判所の決定で、被告人の防御の準備に必要な期間、公判手続が停止されます(刑訴法312条4項)。
訴因変更の時期
訴因変更の時期については制限がありません。
第一審であれば、公訴提起から結審に至るまでの間(判決言渡しの前まで)、いつでもできます。
結審後に訴因変更を行う必要が生じた場合は、弁論(審理)を再開した上で行うことになります。
控訴審・上告審における訴因変更
控訴審で訴因変更は可能である
控訴審(高等裁判所による審理)における訴因変更は、控訴審が「事後審」(一審判決の当否を一審判決の時点を基準として事後的に審査するもの)の構造であるため、訴因変更を否定する説もあります。
しかし、判例は、控訴審裁判所が事実の取調べ(刑訴法393条)をして一審判決を破棄自判(刑訴法400条)する場合には、「続審」の性格を持つことになるため、控訴審での訴因変更を肯定しています。
裁判官は、
- 控訴審が一審判決の当否を判断するため事実の取調を進めるにつれ、検察官から訴因変更の申出がある場合に、控訴裁判所は審理の経過に鑑み、訴訟記録並びに原裁判所(※一審の裁判所)及び控訴裁判所において取り調べた証拠によって原判決(※一審の判決)を破棄し自判しても被告人の実質的利益を害しないと認められるような場合においては、訴因変更を許すべきものと解するのが相当である
と判示しました。
上告審は訴因はできない
上告審(最高裁判所による審理)は、法律審であるため、上告審での訴因変更はできません。
次回の記事に続く
次回の記事では、
- 起訴状の訂正(補正)
- 起訴状の訂正(補正)と訴因変更の違い
を説明します。