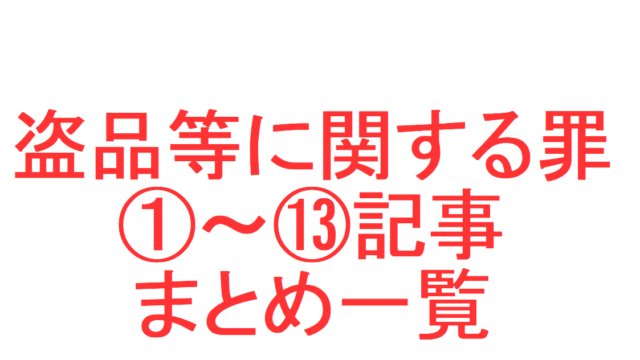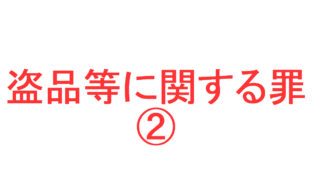盗品等に関する罪③ ~「犯罪の成否(本犯の有責性・処罰・起訴の有無・公訴時効・裁判権)」「親族相盗例の適用」「横領罪との成立時期」を判例などで解説~
犯罪の成否 ~本犯に有責性の有無は問わない~
盗品等に関する罪(刑法256条)において、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為をした者(例えば、窃盗犯人)」を「本犯」と定義しています。
本犯の行為が、この定義に該当すれば、盗品等に関する罪の成立にもつながります。
ここで、本犯の行為が、犯罪として、どの程度の厳格さで成立していればよいかが疑問になります。
まず、この疑問の結論を言う前に、前提知識として、犯罪は、
- 構成要件該当性
- 違法性
- 有責性
の3つの要件がそろったときに成立することをお伝えします(詳しくは前の記事参照)。
では、この疑問の結論をいいます。
盗品等に関する罪における本犯の犯罪行為は、
- 構成要件該当性
- 違法性
の2つの要件があればよいとされます。
- 有責性
までは必須とされず、本犯の行為に有責性がなくても、盗品等に関する罪における本犯の行為の認定に支障は生じません。
ちなみに、有責性とは、責任能力の有無を問うものです。
具体的には、
- 幼児
- 高度の精神病者
については、責任能力がないとして、犯罪を犯しても、有責性がないため、無罪になります。
判例は、本犯が14歳未満の子どもだった事案で、子どもが持ち出した他人の財産について、盗品等該当性を認め、盗品等に関する罪の成立を認めています(大審院判決 明治44年1 月12日、大審院判決 大正3年5月12日、大審院判例 大正3年12月7日)。
判例は、本犯の行為について、構成要件に該当し、違法な行為であれば足り、有責性までは必要ないという考え方をとっています。
親族相盗例の適用
1⃣ 盗品等に関する罪は、親族相盗例が適用される犯罪です(刑法257条)。
親族間において盗品等に関する罪を犯しても、刑が免除されます。
刑が免除されるとは、例えば、有罪になって懲役1年の実刑に処せられても、刑が免除されることにより、刑務所で受刑をせずに済みます。
2⃣ では、「本犯」の窃盗罪に親族相盗例の適用があった場合(刑法244条)はどうでしょうか(例えば、被告人が被告人の母親の財布を盗んだ場合)。
窃盗罪は、犯人と財物の所有者・占有者との間に一定の親族関係がある場合は、刑が免除されます(詳しくは前の記事参照)。
盗品等に関する罪における本犯(窃盗犯)の行為が親族間の犯罪であり、盗品等に関する罪の物品が親族相盗例の適用がある窃盗犯人の取得した物品であった場合に、盗品等に関する罪は成立するかという問題があります。
この問題の答えは、盗品等が親族相盗例の適用がある犯人の取得した物品であったとしても、盗品等であることに変わりはなく、盗品等に関する罪を成立させます。
理由は、親族相盗例は、単に刑の免除に該当するにすぎず、犯罪が成立して有罪であることは明らかであるため、このような結論が導かれるものです。
本犯に日本の刑法または裁判権が及ばない場合
たとえば、
- 外国人による外国での窃盗のように、本犯の行為に対し、日本の刑法の適用がない場合
- 免責特権を有する外国人の日本国内での窃盗のように、日本の裁判権が及ばない場合
に、その盗品を、盗品等に関する罪における盗品等を認めることができ、本罪が成立するかどうかについて説明します。
1⃣ 外国人による外国での窃盗のように本犯の行為に刑法の適用がない場合
この場合についての判例はありません。
学説の考え方として、以下のようなものがあります。
盗品等に関する罪が成立するとする考え方
刑法の適用がないとしても、これを適法なものとするものではない。
盗品等に関する罪の国際的取締りの必要性から、盗品等該当性が認められる。
よって、盗品等に関する罪の成立が認められる。
盗品等に関する罪は成立しないとする考え方
本犯の行為には、少なくとも構成要件に該当し、違法な行為であることを要するのだから、この場合には、盗品等該当性を否定すべき。
本犯の行為に刑法の適用がないのに、その行為により得た財物を日本の刑法で盗品等と直ちに認定するには、違法な物の流通が容易に国境を越えて行われる現在、新たな立法が必要である。
よって、盗品等に関する罪は成立しない。
2⃣ 免責特権を有する外国人の日本国内での窃盗のように、日本の裁判権が及ばない場合
この場合については、単に日本が裁判権を有しないにすぎないだけであり、刑法自体の適用はできるのであるから、盗品等該当性が認められ、盗品等に関する罪が成立します。
この点について、以下の判例があります。
福岡高裁判決(昭和27年1月23日)
この判例で、裁判官は、
- 刑法256条に所謂贓物は、他人の犯罪行為により不法に領得された物件で、被害者において法律上追求することができるものを指称し、かかる物件について、その贓物たることの情を知って同条所定の行為をなす限り、すべて贓物罪を構成するものであって、不法領得の本犯が何人であるかは問うところではない
- 従って、我が裁判権に服しない占領軍々人が、我領土内において、占領軍物資を窃取した場合、その窃盗行為を我が刑法上、不法領得行為に該当しないとか、その窃取した占領軍物資が贓物(盗品等)でないということはできない
と判示しました。
本犯の処罰の有無(起訴の有無、公訴時効)
本犯が、
- 起訴され、刑事処罰されているどうか
- 公訴時効が成立しているかどうか
は、盗品等に関する罪の成否に影響を与えません。
この点について、以下のとおり説明します。
1⃣ 本犯の起訴と処罰
本犯の行為が、構成要件に該当し、違法である限り、本犯が現実に起訴され、処罰される必要はありません。
本犯が起訴され、処罰を受けていなくても、盗品等に関する罪は成立します。
この点について、以下の判例があります。
大審院判決(明治44年3月9日)
この判例で、裁判官は、
- 贓物に関する罪は、贓物たる事実を認識して、その収受、運搬、寄蔵、故買、または牙保をなすにより成立し、該贓物が、何人の被害に係るものなるやは問うところにあらず
- 贓物罪における贓物は、犯罪行為により収得せし物件なることを要するに過ぎずして、その物件を収得したる行為が、既に処罰せられ、もしくは、贓物罪と共に起訴せられたることを要せず
と判示しました。
大審院判決(大正2年10月30日)
この判例で、裁判官は、
- 苟も贓物たる情を知りて、これを故買したる以上は、刑法第256条第2項の罪を構成すべく、その贓物を売却したる者が、起訴もしくは処罰せられたると否とは該犯罪の成立になんらの影響なし
と判示しました。
2⃣ 本犯の公訴時効
本犯に対する公訴時効が成立していても、盗品等の判断に影響はなく、盗品等に関する罪は成立します。
この点について、以下の判例があります。
大審院判例(明治42年4月15日)
この判例で、裁判官は、
と判示しました。
本犯が既遂に達していることを要する
盗品等に関する罪が成立するためには、本犯の財産罪が、犯罪として完成に達している(既遂に達している)必要があります。
これは、本犯の犯行が既遂に達しない限り、領得された財物が盗品等であると認められないためです。
また、財物が取得される以前に、譲受け、運搬、保管、処分のあっせんの約束や、そのための行為は、本犯の幇助行為になることはあっても、盗品等自体が存在しないため、 盗品等に関する罪は成立しません。
この点ついて、以下の判例があります。
最高裁判決(昭和35年12月13日)
この判例で、裁判官は、
- 窃盗罪の実行を決意した者の依頼に応じて、同人が将来窃取すべき物の売却を周旋しても、窃盗幇助罪の成立することあるは格別、贓物牙保罪(盗品等有償処分あっせん罪)は成立しない
- しかし、その後、同人が窃取してきた贓物(盗品等)について、情を知りながら現実に売却の周旋をした場合には、賊物牙保罪が成立する
と判示しています。
この判例で、裁判官は、
- 本犯たるAの杉材窃取行為の前に行われたる被告人の杉材売却の周旋行為につき、賍物牙保罪の成立を認められない
- 本犯であるAの窃取行為後であるc駅における被告人の行った「物品の検収、引渡の立会」のみでは、賍物牙保罪を構成すべき「周旋仲介行為」には当らない
- 苟くも、被告人において、Aが杉材を窃取するものであるとの情を知りながら、その杉材の売却周旋をなす行為のある以上、それはAの窃取行為を容易ならしめるもの、すなわら窃盗の幇助にほかならないことはたやすく認められる
と判示しました。
横領罪と盗品等に関する罪の成立時期
本犯が横領罪の場合には、横領の時点において、財物は盗品等となるため、本犯の横領罪と、盗品等に関する罪が、同時期に成立することがあります。
この点について、以下の判例があります。
大審院判決(明治43年1月17日)
この判例で、裁判官は、
- 自己の占有する他人の財物を横領したる場合に在りては、その物件は占有者が権限外において、これを処置したるものなれば、その処分行為と同時に贓物を組成するものとす
と判示しました。
大審院判決(明治44年3月24日)
この判例で、裁判官は、
- 被告が既に占有したる物といえども、犯罪によりて横領したるものは、刑法第256条にいわゆる贓物なりとす
と判示しました。
大審院判決(大正2年6月12日)
この判例で、裁判官は、
- 苟も自己の占有する他人の物を不法に譲り渡さんとする行為あるにおいては、相手方がこれを買い受ける意思をなすを待たずして横領罪は完成し、その領得物は、贓物たるの性質を具有するものとす
- 従って、情を知りて、これを買い受けたる相手方の行為は、横領罪の共犯にあらずして、贓物故買罪(盗品等有償譲受け)に該当するものとす
と判示しました。
大審院判決(大正4年2月19日)
この判例で、裁判官は、
- 横領罪は、犯人において、自己の占有せる他人の物を自己に領得する意思を表現する行為ありたる瞬間において完成し、特にその物に対する処分行為の完了を要せさるものとす
- 他人の物の占有者が、第三者に対して、不法にその物を売り渡し、もしくは、担保に供せんとする意思表示をなしたる場合においては、この時において、横領罪は直ちに完成し、同時にその物は、贓物を組成すべきをもって、その情を知りてこれを買い受け、もしくは、担保として交付を受けたる者に対しては、当然、贓物に関する罪の成立あるものとす
と判示しました。
大審院判決(昭和22年2月12日)
この判例で、裁判官は、
- 他人の財物の占有者が、不法にこれを売却するの意思を表示し、その情を知りながら、これを承諾して買い受けたるときは、贓物故買罪(盗品等有償譲受け)成立するものとす
と判示しました。
東京高裁判決(昭和29年10月19日)
業務上横領罪の共犯が成立するか、贓物牙保罪(盗品等有償処分あっせん罪)が成立するかが争点となった事案で、裁判官は、
- 被告人Aは、被告人Bから、被告人Bの業務上占有に係る漁網用綿糸を不法に売却し横領しようとする決意を告げられ、その売り込み斡旋方を依頼されたにとどまること明らかであり、被告人Bの業務上横領の所為について、共謀したものとは認められない
- そして、被告人Bが、被告人Aに、その業務上占有に係る漁網用綿糸を不法に売却し、横領しようとする決意を告げ、かつ、その売却の斡旋を依頼した行為は、すなわち、漁網用綿糸を不法に領得しようとする意思を外部に表現した行為と認むべきであるから、これによって横領行為は完成し、漁網用綿糸は、同時に贓物たる性質を具備するに至ったものと解す
- したがって、被告人Aが、被告人Bの依頼を承諾し、その事情を知りながら、これをCに対し売却の周旋をした所為を贓物牙保罪(盗品等有償処分あっせん罪)に問擬(もんぎ)していることは相当である
と判示しました。
なお、委託物を他人に不法に売り渡す約束をした時点で横領罪は完成するから、約束後に物の引渡しをした場合は、横領罪の成立時期と盗品等に関する罪の成立時期はずれます。
偽造通貨行使によって得た財物は盗品といえるか?
本犯である財産犯が、犯罪として独立していない場合に、その取得にかかる財物が盗品等といえるかが問題になります。
偽造通貨を行使して財物を得た場合、偽造通貨行使罪(刑法148条2項)のほか詐欺罪(刑法246条)が成立するか議論がありますが、詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収されます。
この点について、以下の判例があります。
大審院判決(明治43年6月30日)
この判例で、裁判官は、
と判示しました。
大審院判決(昭和7年6月6日)
この判例で、裁判官は、
- 偽造通貨を行使して、詐欺罪をなしたるときは、その詐欺罪の行為は、偽造通貨行使罪に、当然、包含せられ、別罪を構成せず
- 偽造通貨を行使して、詐欺をなしたる事実につき、裁判所が審理の上、偽造通貨行使の罪を認定したる以上、詐欺の点につき、更に別個の判断をなす必要なし
と判示しました。
上記判例のとおり、詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収されるとはいえ、偽造通貨を真正通貨であるとして、人を欺いて財物を得た行為は、詐欺罪に当たります。
そのため、詐欺罪の処罰が偽造通貨行使罪に吸収されるとしても、偽造通貨行使によって得た財物は、明らかに「詐欺罪に当たる行為によって領得された物」にほかなりません。
さらに、偽造通貨行使罪が盗品等に関する罪の保護法益に関する部分までを評価し尽くしているとはいえません。
なので、偽造通貨行使罪によって得た財物は、それを譲り渡したりすれば、盗品等として、盗品等に関する罪を成立させると考えられています。