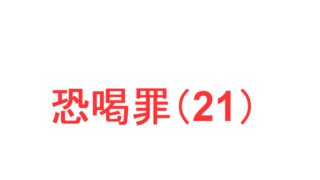恐喝罪(刑法249条)と「脅迫罪」「暴行罪」「傷害罪」「強盗罪」「強要罪」との関係について、判例を示して説明します。
脅迫罪との関係(恐喝罪が成立する場合には、手段である脅迫は恐喝罪に吸収される)
恐喝罪が成立する場合には、手段である脅迫は恐喝罪に吸収されます。
この点について、以下の判例があります。
大審院判決(明治43年2月18日)
この判例で、裁判官は、
- 刑法第54条にいわゆる犯罪の手段たる行為とは、あるいは犯罪の性質上、これが手段として普通に用いられるべき行為にして、しかも、その罪の構成要件にあらざるものをいう恐喝罪における脅迫は、常に恐喝の手段として用いられるところの行為なるも、その行為たるや、恐喝罪の実行行為に属し、その罪の構成要件をなすものなるをもって、恐喝罪以外に別に脅迫罪ざるものを構成せざると同時に刑法第54条にいわゆる犯罪の手段たる行為にして他の罪名に触れるものにあらざるなり
と判示しました。
暴行罪との関係(恐喝罪が成立する場合には、手段である暴行は恐喝罪に吸収される)
恐喝罪が成立する場合には、手段である暴行は恐喝罪に吸収されます。
この点について、以下の判例があります。
大阪高裁判決(昭和24年11月7日)
この判例は、最初の暴行の際には財物要求の意図はなかったが、その暴行によって被害者が畏怖しているのに乗じ、その機会継続中、更に脅迫して財物を喝取した場合は、全体として1個の恐喝罪が成立するのであって、最初の暴行を別個に観察すべきではないとしました。
裁判官は、
- 被告人は、最初の暴行の際に財物要求の意図をもっていたというのではなく、暴行によって被害者が畏怖しているのに乗じ、その機会継続中、更に脅迫して帽子1個を喝取したというにあって、このことは挙示の証拠によって十分認め得られるところである
- そして、このように暴行によって被害者が畏怖しているのに乗じ、その機会継続中、更に脅迫して財物を喝取した場合にあっては、全体として1個の恐喝罪が成立するのであって、最初の暴行を別個に観察すべきでないと解するのが相当であるから、原判決が刑法第208条を適用しないで同法第249条第1項を適用処断したのは正に当を得たものである
と判示し、手段である暴行は恐喝罪に吸収され、恐喝罪のみが成立するとしました。
大阪高裁判決(昭和42年10月21日)
被告人が、金員要求の意思を持たずに、数名と意志を通じ、数名で被害者に暴行を加え、その暴行により被害者が畏怖しているのに乗じて金員喝取しようとしたが未遂に終わった恐喝未遂の事案です。
裁判官は、
- 暴行は恐喝罪の構成要素であるから、暴行により相手方を畏怖せしめた状態を利用して財物を喝取したときは全体を評価して一個の恐喝行為となすべきである
- 被告人が当初暴行に際しては金員要求の意思をもっていなかったが、被害者がその暴行により畏怖しているのに乗じ、金員を要求し、もしこれに応じないときは更に危害を加えかねない気勢を示して金員を喝取しようとしたのであるから、右暴行はこれが暴力行為等処罰に関する法律違反に該当する場合であっても、恐喝罪の構成要件を組成するものとして当然吸収せられ、別罪を構成するものでないと解するのが相当である
と判示し、手段である暴行は恐喝未遂罪に吸収され、恐喝未遂罪のみが成立するとしました。
仙台高裁判決(昭和27年11月14日)
この判例は、最初の暴行の際には財物要求の意図はなかったが、その暴行によって被害者が畏怖しているのに乗じ金員を喝取しようとしたが、その目的を遂げなかった場合は、全体として1個の恐喝未遂罪が成立するのであって、最初の暴行を別個に観察すべきではないとしました。
傷害罪と恐喝罪の関係(傷害罪と恐喝罪とは観念的競合の関係になる)
恐喝罪が成立する場合には、手段である暴行は恐喝罪に吸収されますが、傷害の結果を生じた場合は、傷害罪と恐喝罪とは観念的競合の関係になります。
この点について、以下の判例があります。
被告人が相手方に対し、短刀を抜いて突きつけ、危害を加える勢いを示して脅迫して金員を交付させた際、その短刀で相手方の鼠蹊部を突刺して全治3週間の切刺傷を加えた事案です。
裁判官は、
- 被告人は恐喝罪と傷害罪とにつき、刑法第54条第1項前段の規定を適用して処断されなければならない
- 傷害行為は恐喝行為とは別個に、これの事前若しくは事後においてなされたのではなく、傷害行為がただちに恐喝行為の手段としてなされたと言うからである
と判示し、傷害行為は恐喝の手段としてなされたものだから、傷害罪と恐喝罪は観念的競合の関係に立ち、両罪は一罪になるとしました。
この判例で、被告人の弁護人は、
- 被告人のAに対する恐喝罪の成立ありと仮定しても、同罪と被告人の暴行(その結果は傷害に至った所為)の罪とは 併合罪の関係に立つものであり、刑法第54条第1項前段の想像的競合犯(※観念的競合)の関係にはない
と主張しました。
この主張に対し、裁判官は、
- 恐喝は、威嚇的方法によって害悪を告知して人を畏怖せしめることにより一定の財産的利益を取得することを本質とする
- 而して、その威嚇的方法は、相手方の反抗を抑圧する程度のものでない限り、特に制限はな いから、不利益なる事項を告知する内容を有する言語等のほか狂暴なる身体の態度による威嚇等をも包含し、かつ、その方法にして同時に他の罪名に触れる場合には、恐喝罪の成立と同時に右の他の犯罪の成立をも来すことになる
- 本件においては、被告人は、運転者Aからタクシーの乗車賃の支払請求を受けるや、その支払を免れるため「このやろう」等と叫び、かつ同人を殴打負傷するに至らしめ、その後、賃金の一部を支払ったが、右言動によりAをして、これの上、右請求を続けていては如何なる害悪を受けるやも測り得ないとの畏怖の念を抱かしめ、そのため右賃料残金60円の支払請求を断念せしめて財産の利得をしたというのである
- 故に、右によれば、右殴打傷害による畏怖と、言語による畏怖とが同時に発生し、その双方相俟って請求断念に至らしめたものである
- 而して、これの場合、右言語による威嚇は恐喝罪の本来的構成要件をなすにとどまるが、殴打傷害は、それ自体犯罪を構成すると同時に、一面恐喝罪との交渉を生じ、その畏怖の念発生の起因となっているものである
- 故に、原判決において、結局右傷害罪と恐喝罪とを刑法第54条第1項前段の想像的競合犯(※観念的競合)の関係にあるものと認めたのは正当であり、所論の如く(※弁護人が主張するように)両者は併合罪の関係にありとなすは首肯し難い
と判示しました。
東京高裁判決(昭和46年8月19日)
この判例で、裁判官は、
- 被告人が、被害者に対して脅迫暴行を加えた当初は、被害者に馬鹿にされたと考えて憤激の余に出たものであって、金員喝取の手段としたものではないと認め得るが、その結果、被害者の畏怖している状態に乗じて金員喝取の意図を生じ、来合せた他の両被告人と意を通じ、更に激しく暴行を加えて畏怖の念を深め、結局3000円の現金を交付させているのである
- 職権により調査するに、原判決は被告人ら共謀による恐喝罪と傷害罪を認定し、両罪を併合罪として処分していることが明らかである
- しかし、本件における被告人らの被害者に加えた一連の暴行は、一面において恐喝の意図を達する手段として、他面同人に対する敵意の表現として行われたものであり、その結果、被害者を畏怖させて金員を交付させると共に、同人に傷害を負わせたのであって、一個の行為で数個の罪名に触れる場合に当る
- 両罪を併合罪として処断した原判決は法令の適用を誤ったものであり、その誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、破棄を免れない
と判示し、一審の判決が傷害罪と恐喝罪の両罪は併合罪になると判示したのを否定し、両罪は、観念的競合の関係になり、一罪となるとしました。
福岡高裁判決(昭和39年10月21日)
この判例は、恐喝の手段である傷害に対する略式命令が確定した後に、更に恐喝で起訴された事案に対して、恐喝の事実は傷害の事実と基本的事実関係が同一であり、同一の公訴事実に対して更に起訴されたものとして免訴を言い渡しました。
傷害罪と恐喝罪は、観念的競合の関係に立つため、このような結論が導かれるものです。
裁判官は、
- 略式命令の傷害の事実が本件公訴事実の恐喝の一手段であるSに対する傷害と同一のものであることはあきらかである
- そして、Sに対する傷害は、本件公訴事実の恐喝の重要な一手段をなしており、金員の出所もほとんどがSではないが、これを交付しているのはSである
- したがって、略式命令の傷害の事実と恐喝の本件公訴事実とは、基本的な事実関係が同一であるから、本件公訴事実は、確定の略式命令があるのにこれと同一の公訴事実について起訴したものであり、免訴すべきものである
と判示しました。
強盗罪との関係
同―人に対して、接続する機会に、恐喝次いで強盗致傷を犯した場合は、包括して重い強盗致傷の一罪が成立します。
この点について、以下の判例があります。
この判例で、裁判官は、
- 当初の暴行による恐喝がやがて次の段階にその程度を越えて強盗に発展したもので、相手方に暴行を加えて畏怖させて金品を取るという点において両者共通の要素を含むものであるから、原判決が法律の適用において、これを包括して重い強盗傷人の一罪として取り扱ったとしても、必ずしも失当とは言えない
と判示しました。
仙台高裁判決(昭和39年7年17日)
この判例は、同一人に対してけん銃を示しての強盗行為が先行したが、警察に通報されたと思っていったん逃走して未遂に終わり、その後電話をかけて脅迫し、翌日、指定口座に現金を振り込ませた事案について、強盗既遂一罪ではなく、強盗未遂と恐喝既遂の包括一罪が成立するとするとしました。
大阪地裁判決(平成4年9月22日)
この判例は、強盗の目的で、被害者Aに包丁を突き付けて強盗行為に着手し、相手の反抗を抑圧するに足りる程度の脅迫が加えられたにもかかわらず、被害者Aに反抗抑圧に至らない程度の恐怖心を生じさせたにとどまり、その結果、被害者Aが売上金の持ち去りを黙認した事案につき、強盗未遂と恐喝既遂の成立を認め、両罪は観念的競合の関係にあるとしました。
裁判官は、
- 被害者Aが最終的に、被告人が売上金を持ち去ることに抵抗しなかったのは、被告人の先の脅迫行為により、その意思を制圧され、反抗を抑圧されていたためとまでは認めがたく、従って、強盗罪について既遂を認めることはできないが、当時、Aが、その意思を制圧され、反抗を抑圧される程度には至らないにしても、これ以上被告人の要求を拒否して抵抗すれば何らかの危害を加えられかねないと畏怖していたことは明らかであり、そのため、不本意ながらも被告人の持ち去りを黙認して交付したものと認められる
- Aが、被告人の持ち去りを積極的に拒否する態度にでなかったからといって、同人の立場等から考えても、同人が被告人の右脅迫と無関係に、全くの任意の意思で被告人に売上金を交付したとは、とうてい考えられない
- そして、被告人は、右ビニール袋を持ち去るに際して、新たな脅迫行為にはでていないが、その時点での被害者の畏怖は、それに先立ち、同じ財物に向けられた強盗行為としての脅迫によるものであるから、これに乗じて売上金を持ち去った被告人の行為は恐喝罪を構成するものというべきであり、先の強盗未遂罪とこの恐喝罪とは一個の行為により二個の罪名に触れる観念的競合の関係にあると評価すべきものと考えられる
と判示しました。
強要罪と恐喝罪の関係
強要罪ではなく、恐喝罪の成立を認めた判例として、以下の判例があります。
パチンコの景品買いをしていた被告人が、パチンコ店から景品のたばこを持って出て来た被害者Aにつきまとい、被害者に対し、「売れよ、売れよ、こっちへ来い」などと言って横路地に連行して脅迫し、畏怖した被害者からその所持するたばこ20個(金800円相当)を交付させ、その代価300円を手渡した事案です。
裁判官は、
- 原判決は、右被告人の所為をもって被害者Aをして強いて右煙草を売渡させ義務なき行為を行わしめたものとして刑法第223条第1項(※強要罪)に問擬(もんぎ)しているのであるが、被告人の右所為は、被害者Aを脅迫し同人より煙草ピース20個を交付させたもので強要罪には該当せず、恐喝罪を構成するものと解すべきである
と判示して、強要罪ではなく、恐喝罪の成立を認めました。
患者が医師を脅迫して、麻酔薬の注射施用を強いる場合は、恐喝罪は成立せず、強要罪が成立するとした以下の判例があります。
高松高裁判決(昭和46年11月30日)
この判例は、患者が医師を脅迫して、医師がその治療のために必要、適当と認めない麻酔薬の注射施用を強いるのは、その対象が非財産的な医療行為であって、財産的処分行為ではないから、恐喝罪は成立せず、強要罪が成立するとしました。
裁判官は、
- 強要罪と恐喝罪とは、人を畏怖させて意思決定の自由を侵害する点において共通するものであるが、強要罪が非財産的利益の供与ないし行為を対象とするのに対し、恐喝罪は財産的処分行為を対象とする点において明らかに相違があり、その相違こそ自由に対する罪としての強要罪と財産犯である恐喝罪との差異に由来するものにほかならない
- ところで、およそ、医師が患者を診察した結果その治療を必要とする限り、その症状に応じて投薬ないし処方箋の交付のほか各種の注射を施用することは治療手段として当然のことであり、右医師の診察とこれに伴って行なう注射施用等の治療手段とは一体となって医師の技能および技術の発現ないしは行使としての医療行為であると解すべきであって、その治療に用いる注射液等の薬剤そのものが財産的価値のあるものであることを理由に、注射液の注射施用もしくは投薬をとらえて恐喝罪のいわゆる財産的処分行為であるとするのは、医療行為の性質を正解しないものといわなければならない
と判示し、医師の注射施用は、財産的処分行為ではないため、恐喝罪は成立せず、非財産的な医療行為であることから強要罪が成立するとしました。