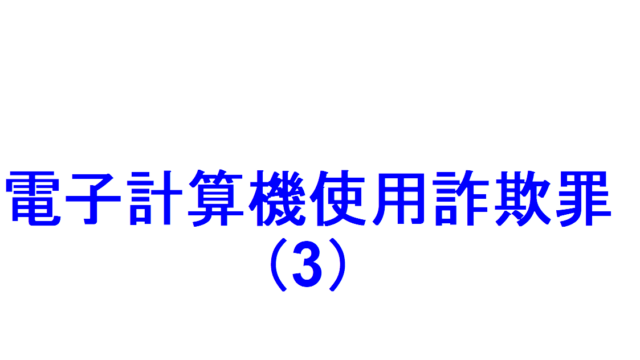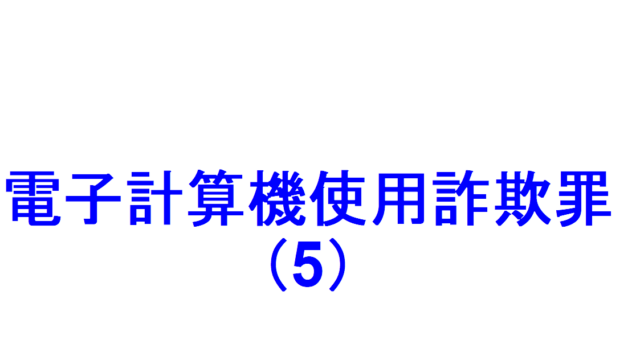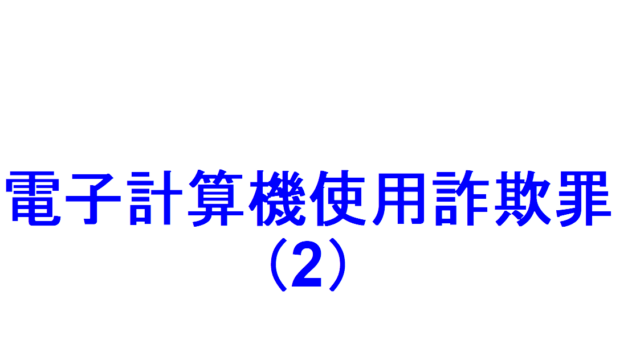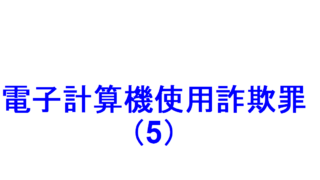電子計算機使用詐欺罪(6) ~「多数回の電子計算機使用詐欺行為間の罪数関係(包括一罪か否か)」「他罪(電磁的記録不正作出・供用罪、詐欺罪、窃盗罪、横領罪、背任罪)との関係」を判例で解説~
多数回の電子計算機使用詐欺行為間の罪数関係(包括一罪か否か)
金融機関の職員が、オンラインシステムを悪用して多数回にわたり、架空入金データの入力という同じ態様の電子計算機使用詐欺(刑法246条の2)の犯行を繰り返した場合、その各犯行間の関係については、その全体が単一の犯意に基づいて同じ場所、同一の事情の下で、時間的に連続して行われた場合は、包括一罪になると解されます。
しかし、各犯行が、その犯行日ごとにその都度共犯者間で謀議がなされた上、同一日に数回に分けて振込入金の操作がなされたような事案では、同一犯行日ごとになされた数回の振込処理が包括的一罪を構成すると解されます。
この点について、以下の判例があります。
東京地裁八王子支部判決(平成2年4月23日)
オンラインによる電信為替送金のシステムを悪用して、勤務先の電算機の端末から不正の振込発信をし、これと接続している被仕向(振込先)銀行の電算機に接続された磁気ディスクに記憶された預金口座の預金残高を書き換えた行為が電子計算機使用詐欺罪に当たるとされた判例です。
判決の中で、裁判官は、
- 本件各犯行の罪数について検討するに、関係各証拠によれば、確かに、被告人両名は、当初の段階で本件犯行方法につき謀議をなし、各犯行はいずれも基本的にはほぼその当初の謀議どおりの方法により行っていることが認められる
- しかしながら、右証拠によれば、被告人両名は、当初は多くとも数千万円程度の不正振込を企図していたもので、最終的に不正振込が9憶7000万円もの莫大な額になることまでは被告人両名共予想していなかったものであり、また、本件では各犯行日の直前ころにいつも被告人両名の間で電話等の方法により具体的な振込額等についての謀議がなされていることも認められるのであって、右各事実からは、本件全体が単一の意思の発現として行われたとは到底認められず、したがって、本件全体が包括的一罪を構成するものではないと解するのが相当である
- そして、右のとおり、各犯行日毎にその都度、謀議がなされており、更に、右証拠によれば、同一犯行日に振込が数回に分けてなされたのは、同一口座に一度に多額の振込がなされることになるのを防ぐためなど便宜的な理由に過ぎないものと認められることなどから、本件各犯行は、同一犯行日になされた数回の振込をもってそれぞれ包括的一罪を構成し、犯行日が異なれば別罪を構成するというべきである
と判示しました。
電磁的記録不正作出・供用罪との関係
電磁的記録不正作出・供用罪(刑法161条の2)と電子計算機使用詐欺罪とは、原則として牽連犯になるものと解されます。
電磁的記録不正作出・供用罪が財産上不法の利益を得るための手段、電子計算機使用詐欺罪が財産上不法の利益を得た結果の関係に立つためです。
考え方は、文書偽造罪・同行使罪と詐欺罪が牽連犯の関係に立つのと同じです(前回記事参照)。
詐欺罪、窃盗罪との関係
電子計算機使用詐欺(刑法246条の2)は、詐欺罪(刑法246条)の処罰規定できない詐欺行為である
を処罰するために設けられた規定です。
人に対する欺罔行為がない詐欺行為、財物の占有移転を伴わない詐欺行為は、詐欺罪の構成要件を満たさないため、詐欺罪で処罰することができません。
そこで、電子計算機使用詐欺罪を新設し、上記詐欺行為を処罰できるようにしました。
電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)の条文には、「前条(刑法246条)に規定するもののほか」と規定されており、詐欺罪を補充する規定であることが明示されています。
なので、ある犯罪に対して、詐欺罪が成立する場合は、電子計算機使用詐欺罪は適用されず、詐欺罪で犯人を処罰することになります。
詐欺罪の構成要件を満たさず(人に対する欺罔行為がない、財物の占有移転がない)、詐欺罪を適用できない場合に、電子計算機使用詐欺罪を適用して犯人を処罰することなります。
たとえば、電子計算機使用詐欺に外観上は該当する行為であっても、事務処理の過程に人に対する欺罔行為が存在し、詐欺罪が成立すると認められる場合には、詐欺罪が適用されることになります。
例えば、取引データのプリントアウトを行って、一定の権限者が個々の取引についての決裁をした後に、財産権の得喪・変更に係る電磁的記録が作出されることとなっている場合に、取引データそのものを改変したときは、その後に作出される財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録に基づき財産上不法の利益を得たとしても、これが当該権限者の錯誤に基づく処分行為によるといえるものである限り(人を介した欺罔行為と言える限り)、電子計算機使用詐欺罪ではなく、詐欺利得罪(2項詐欺)が成立することとなります。
これに反し、例えば、磁気テープの搬入・装填等単なる機械的な作業に従事するにすぎないオペレーターを欺いて誤った磁気テープを事務処理に用いさせたとしても、これが処分行為をなし得ないものである限り(このオペレーターが財産の処分行為を行い得ないものである場合)、詐欺利得罪の成立を認めるととはできず、電子計算機使用詐欺罪の間接正犯の成否を検討することになります。
電子計算機使用詐欺罪を犯して、財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作り、もって財産上不法の利益を得た者が、その後これを利用して現金を引き出したような場合には、その態様にもよりますが、別途当該現金についての詐欺罪又は窃盗罪を構成することがあります。
その場合における両罪(「電子計算機使用詐欺罪」と「詐欺罪又は窃盗罪」)の罪数関係については、もともとこのような財物の取得は財産上不法の利益の全部又は一部が現金化したものにほかならないと考えると、行為者の意図、目的、不法利得と現金引出しの時間的相互関係、財産上不法の利益を提供した銀行と現金の占有を喪失した銀行が同一か否か等諸般の事情を勘案し、不法利益が専らその後の現金引出しの手段にほかならないと認められれば、両罪は包括一罪の関係にあると解されます。
そうでなければ、両罪は併合罪の関係にあると解されます。
横領罪との関係
電子計算機使用詐欺罪と横領罪(業務上横領罪)の関係について説明します。
つまり、電子計算機使用詐欺罪により財産上不法の利益を得た後、不実記録に基づき自己が占有する財物を着服したときは、電子計算機使用詐欺罪と横領罪(業務上横領罪)とは、手段と結果の関係になるため、牽連犯になると考えれられます。
例えば、銀行の現金を保管している銀行員が自己の預金口座の残高を水増しした上、これに基づき払戻金を受けて現金化し、この現金を着服したような場合です。
この考え方は、先ほど説明した電子計算機使用詐欺罪と詐欺罪又は窃盗罪とが牽連犯の関係に立つのと同じ考え方です。
背任罪との関係
電子計算機使用詐欺罪に当たる行為が、同時に同じ被害者に対する背任罪にも当たるときは、詐欺罪と背任罪との関係(前回記事参照)と同様に、電子計算機使用詐欺罪のみが成立します。
ただし、背任罪に当たる行為が、民事法上は有効とされる結果、電子計算機に与えられる情報が虚偽のものとはいえず、作出される電磁的記録も不実のものといえない場合、例えば、金融機関の役職員が金融機関名義で不良貸付を行ったようなときは、貸付先の預金口座に貸付金を入金する行為は電子計算機に虚偽の情報を与えたものとはいえないので、電子計算機使用詐欺罪は成立せず、背任罪のみが成立することになります(東京高裁判決 平成5年6月29日参照)。