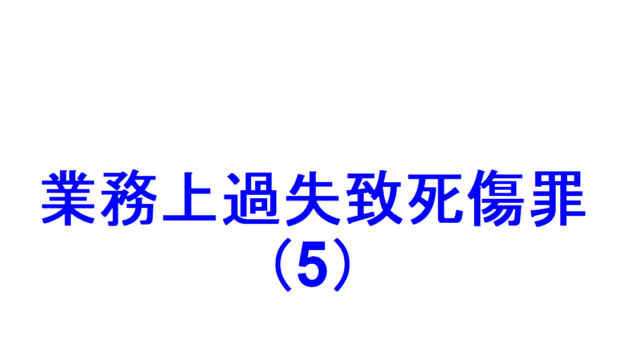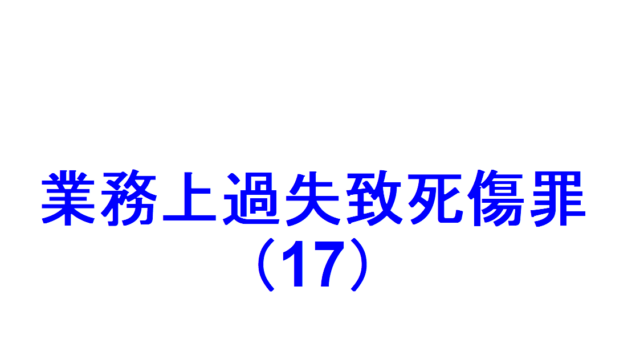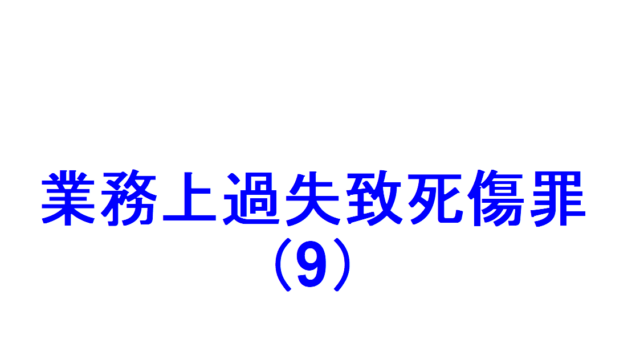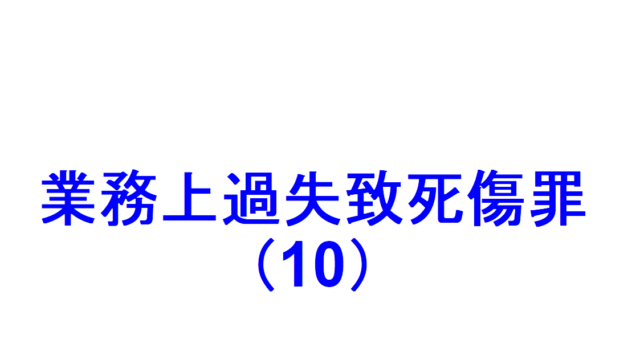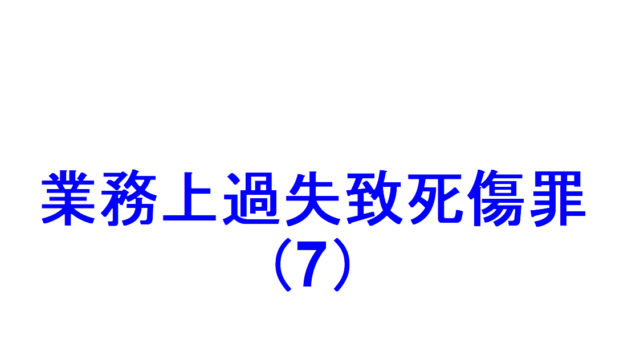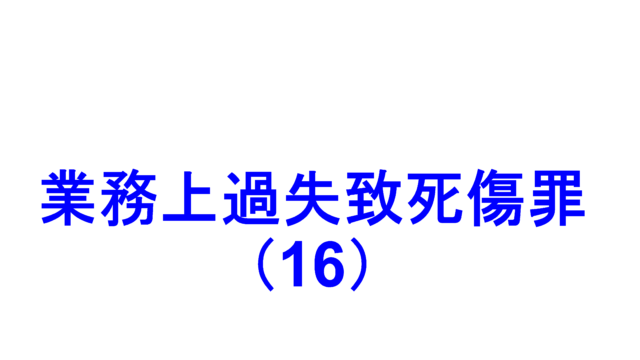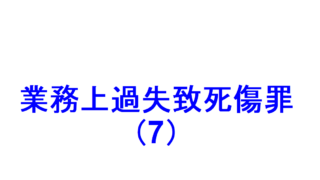業務上過失致死傷罪(6) ~信頼の原則④「信頼の原則が適用される範囲(相手方が泥酔者、幼児、老人などで通常の判断能力を期待し得ない場合)」を説明~
前回の記事の続きです。
信頼の原則の適用範囲について類型を作って整理すると、
- 加害者(被告人)が交通法規に違反している場合
- 信頼の原則を基礎付ける条件が整っていない場合
- 相手方の不適切な行動について、予測が可能な場合
- 相手方が泥酔者、幼児、老人などで通常の判断能力を期待し得ない場合
となります。
まずは、今回の記事では、
④ 相手方が泥酔者、幼児、老人などで通常の判断能力を期待し得ない場合
について説明します。
④ 相手方が泥酔者、幼児、老人などで通常の判断能力を期待し得ない場合
相手が泥酔者、幼児・児童、老人などで通常の判断能力を期待し得ない場合は、被告人に信頼の原則が適用されず、被告人の過失(注意義務違反)が認定され、業務上過失致死傷害や過失運転致死傷罪の成立することがあります。
泥酔者、幼児・児童、老人などは、結果回避のための適切な行動をとることが期待できないとして、信頼の原則が適用される前提を欠くとされることが多いです。
泥酔者
被害者が泥酔者であった場合の参考となる判決として、以下のものがあります。
東京高裁判決(昭和34年4月8日)
被告人がトラックを運転し、道路に停車中の貨物自動車と酩酊して道路に背を向けてしゃがんでいる人との間を通り抜けようとしたところ、トラックの後部が酩酊者に接触し、酩酊者にけがを負わせた業務上過失傷害罪(現行法:過失運転致傷罪)の事案です。
裁判官は、
- 飲酒酩酊した者は、不用意の間に予測し難い異常な行動をなす虞のあるものであるから、被告人が、その者が酩酊していることを認めた以上、そのしゃがんでいる者に対し、特に警笛を鳴らして注意を喚起し、避譲せしめるか、あるいは場合により、被告人自ら又は同乗のMをして下車の上、道路傍らなど安全な場所に退避せしめる等の手段を講じ、何らの危険なきことを十分確認した後進行することこそ、大型貨物自動車を運転する被告人の本件の如き場合において特にとるべき注意義務であるというべきである
- しかるに、被告人は、被害者が動くかもしれないという認識を有しながら、これを退避せしめる等危険防止に適切な処置をとることなく、漫然その傍らを通過し得るものと軽信し、かっ速力は極度に減じたとはいえ、前輪のみに注意し、前輪が通れば後輪も通ると思い、その後は何ら特別の注意をなさず進行したことの証拠上明らかな本件においては、被告人は大型貨物自動車の運転者としてとるべき業務上の十分な注意義務を尽くさなかったものといわざるを得ない
- もっとも、被害者にも少なからざる過失のあったことは、そのとおりであるが、被害者に重大なる過失があったからとて直ちに被告人の責任を阻却するということはできない
と判示し、信頼の原則を適用せず、被告人の過失を認定し、業務上過失傷害罪(現行法:過失運転致傷罪)が成立するとしました。
道路中央に酒に酔って立っていた被害者が、被告人が運転する自動車に進み出て衝突した事案で、被告人の過失(注意義務違反)を認め、業務上過失傷害罪(現行法:過失運転致傷罪)の成立を認めた事例です。
裁判官は、
- 被告人は、時速約40kmで国道を進行中、道路中央に佇立していた被害者Aを発見したのにかかわらず、何ら除行措置を執らず、同一速度をもって同人の直前を通り抜けようとしたところ、同人が急に自動車の進路に進み出たので、自動車の右側車体を同人に突き当て、よって傷害を与えたものであることを明認できる
- このように自動車の往来する道路を横断しようとして、その中央まで進み出た歩行者が自動車の接近し来るのに気付き、立ち止まった場合においても、常に必らずしも、そのままの姿勢で佇立し、自動車の通過を待つものとは限らず、何らかの衝動に基づき、突然、前進する場合のあることは日常経験するところである
- 本件の場合、被害者は本件事故の発生直前、酒に酔つた風で道路中央に立ち、手を振りながら交通整理のような格好をしていたことが認められるので、被告人にして前方注視の義務を怠らなければ、右の如き挙動により酒に酔った被害者が突如自動車の進路に進み出ることのあるのは、当然予見し得たところであるから、その動静に細心の注意を払い、右の如き場合、直ちに臨機の措置を講じ、もって、危険の発生を未然に防止し得る如く、速力を減じ、佇立者と相当の間隔を保ちつつ通過する等の業務上の注意義務の存することは言うを俟たないところである
- 然るに、被告人は右注意義務を怠り、漫然40kmの速度のまま、その前方を通り抜けようとした過失に基づき、本件事故を惹起したものであるから、到底過失の責を免かれない
- よって、原判決が被告人に対し、業務上過失の責任を認めたのは正当である
と判示し、信頼の原則を適用せず、被告人の過失を認定し、業務上過失傷害罪(現行法:過失運転致傷罪)が成立するとしました。
幼児・児童
幼児についても、予測し難い行動に出ることは時おりあるので、幼児がいることに気付き、又はいることが予想される場合には、万全の措置をとらなければなりません。
先ほど説明した泥酔者と同じく、幼児・児童を被害者とする場合も、被告人に信頼の原則が適用されず、被告人の過失(注意義務違反)が認定され、業務上過失傷害や過失運転致傷罪の成立することがあります。
なお、どこまでが児童に当たるかにつき、10歳を児童として扱っている判例があるので、一つの指標となります。
児童が予想外の行動に出ることも予測して注意義務を尽くすべできであるとして過失が認められた事案として、以下の判決があります。
10歳の児童と遊んでいた7歳の被害幼児が、被告人運転の自動車に背を向けていて、全く被告人運転の自動車が進行してくるのに気付いていなかったところ、その被害幼児が、いきなり被告人運転の自動車の前にかけ出したため、その児童に衝突してけがをさせた業務上過失傷害罪(現行法:過失運転致傷罪)の事案です。
裁判官は、
- いわゆる「信頼の原則」なるものは、近時、高速度交通機関や医療行為その他の社会的効用の高い危険業務が拡大するにつれて意識にのぼり、その注意義務の負担に合理的限度を設けることを要請されるにいたった結果、これらの危険業務に携わる者に課せられるべき刑罰法令上の注意義務の具体的内容を定める基本原則として、次第に容認されつつあるものである
- 右のような沿革上、その多くは、鉄道職員または医療関係者などのように、共同して危険防止にあたり、協力関係にある者相互間の、事故防止のために負担すべき注意義務について論ぜられているのである
- されば、本件のように自動車交通事故のなかでも、特に車両相互の関係でもない、ただ無心に路上ないしその付近で遊ぶ頑是ない幼児に対する関係の事案においては、もともとこれを適用し難い要素が存するのである
- すなわち、この原則が適用されるためには、何よりもまず、その前提として、行為者たる被告人にとって、信頼されるべき他の交通関係者たる本件被害者の危険回避措置を期待し得る状況がなければならなかったにかかわらず、本件においては、何らそのような状況は見当らない
- 本件被害者が、かねて学校ないし家庭で、道路交通の安全に関する特別の教育をほどこされ、あるいは道路における通行や遊戯につき再三の注意を受けていたとしても、また、これまでに本件事故現場付近路上で、交通の妨害にわたる挙動に出で、運転手などから叱責されるようなことがあったとしても、本件当時、これらの事実を未だ確知する由もなかった被告人としては、世上よく「子どもを見たら赤信号と思え。」といわれているのに、本件被害者が、それゆえに道路の交通秩序を守り、自動車の交通による危険の有無をよく理解して行動する能力があるものと考え、本件事故回避の措置 に出るべきものと期待し得るはずもなかったわけである
- とにかく本件は、既に約60mの手前から被害者らの遊んでいるのを望見した被告人が、特にそのうちの被害者は背を向けて被告人車両の進行に全く気付かぬままの状態であったのであるから、容易に不測の行動に出ることを予想されたにもかかわらず、ほんの一挙手一投足の労を惜しみ、警音器を吹鳴する等の注意義務を怠つたことが主因となって発生した事故と認められるのであって、いわゆる「信頼の原則」を適用すべき余地は全く存しないこと明らかである
と判示し、被告人に、信頼の原則を適用する余地はないとして、業務上過失傷害罪(現行法:過失運転致傷罪)の成立を認めました。
大阪高裁判決(昭和54年11月22日)
被告人が自動車を運転して、時速約10kmで横断歩道の手前にさしかかったところ、同歩道上の右側部分に2台の車両が前後に停止し、その車両の間の同歩道右側への見通しが困難であったが、被告人は右車両間に左方へ横断しようとして立ち止った少女(被害男子の姉)があるのに気を許し、その後方からの横断者はないものと軽信して、横断歩道直前での一時停止せず、前記停止車両の間から左方へ横断しようとしてかけ出してきた被害男子(8歳)に自車右側面を衝突させてけがをさせた業務上過失傷害罪(現行法:過失運転致傷罪)の事案です。
裁判官は、
- このように横断歩道上を横断しようとして、その中央付近手前まで歩んで来た歩行者が、進行してくる被告人車を見て危険を感じ、同歩道の中央付近手前で一旦立ち止まったとしても、横断歩道における歩行者の優先を保護しようとする道路交通法38条の規定の趣旨にかんがみると、右は同条1項後段にいう「横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者」にあたるというべきである
- そして、被害男子の姉が横断歩道上の前記地点で一旦立ち止まったとしても、当時の状況に徴すると、同姉の後方からさらに横断者のあり得ることが予想される状況にあったのであるから、自動車運転者である被告人としては、同姉の姿を認めるや直ちに、右横断歩道の手前の停止線の直前で(仮に被告人が同姉の姿を最初に発見した時点が、所論のように被告人車の運転席が停止線付近まで来たときであったとしても、事理は全く同様であって、その時点で直ちに)一時停止し、横断者の通行を妨げないようにしなければならなかったのである
- 所論(被告人の弁護人の主張)は、しきりに、横断歩道上、右側への見透しがきかない状況にあった点を強調し、一時停止しても、結果は同じであった旨主張するが、そこが、歩行者優先の横断捗道である以上、前記のとおり見通しが困難であれば、一層、安全確認のため一時停止すべきであり、更に進行するに際しても、最徐行するなどして横断歩道上の右方の安全を慎重に見極めつつ進行すべき業務上の注意義務があったのである
- しかるに、被告人はこれを怠り、時速約10キロメートルのままで進行した過失により、本件衝突事故を惹起するに至ったことが前掲証拠により明らかに認められる
- そして、他に右認定を覆すに足りる証拠はない
- してみると、被告人が横断歩道の直前での右のような一時停止及び右方の安全確認義務を十分に履践しておれば、本件衝突事故は避け得られたことは明らかであるから、本件事故が被害者の不注意によって発生したとする所論(被告人の弁護人の主張)の主張は失当といわなければならない
と判示し、信頼の原則を適用せず、被告人の過失を認定し、業務上過失傷害罪(現行法:過失運転致傷罪)が成立するとしました。
被告人に過失なしとして、業務上過失傷害(現行法:過失運転致傷罪)の成立を否定した判決
自動車を運転する被告人が、徐行、吹鳴、声がけなどの一定の注意義務を尽くしている場合には、被害者が突飛な行為に出ることまで予測することは酷であるとし、被告人に過失はないとし、業務上過失傷害罪(現行法:過失運転致傷罪)の成立を否定した判決があります。
東京高裁判決(昭和36年9月29日)
被告人に過失はないとし、業務上過失傷害罪(現行法:過失運転致傷罪)の成立を否定し、無罪を言い渡した事例です。
事案は、被告人は自動車の運転者であって、普通乗用自動車を運転して進行していたところ、道路西側(被告人の進行方向左側)付近にバスの停留所があり、被告人はバス停留所の前方約20mくらいにさしかかったとき、停留所付近の路上に20~30人の婦人、子供らがバスを待ち合わせているのを認めたが、このとき被告人としては時速約15kmで進行していたこと、被告人は停留所の10mくらい手前に接近したとき、被害男子(8歳の小学生)ほか2名の児童がバスに乗るために道路東側のバス停留所に向けて道路を斜に横断しはじめたのを発見したので、直ちに停車の措置をとったが、そのとき被害男子以外の2名の児童は、被告人の車が進行して来るのをいち早く発見して、元来た道路傍らに引き返えしたので何事もなかったが、被害男子は、被告人の自両車の進行して来るのに気がつかず、一旦道路中央部まで進出した後、ようやく気がついて、道路横断を中止して右旋回し、元に戻ろうとしたとき、停車を完了した被告人の自動車の左前照灯に左手を接触させ、左手に加療1か月の傷害を負ったというものです。
裁判官は、
- 本件事故は、被害者が道路からは見通しのきかない建物の内部から不意に被告人の自動車の前面近くに飛び出したことに第一の原因があると認むべきである
- しかし、かくの如き行動は、いかに年端のゆかない児童に対しても是認すべきでないことはもちろんであるのみならす、更に被害者がひるがえして元来た方向へ戻る動作をしたについても、通常ならは左側に身をひるがえして難を避けるのがむしろ自然であると認められたのに、かえって自動車の進行して来る方向にせん回したということは、当人としてはとっさの場合の判断であるから、強ちこれを避難すべきではないとしても、客観的にみれば不自然たるを免れ得なれのであり、かつ、そのために左手を大きく振る姿勢となったので、自動車の前照灯に触れる事態は起らなかったと認められるから、この意味からいえば、被害者はその不自然な動作をしたため、本来免れ得たはずの負傷を免れ得なかったものと認めざるを得ないのである
- 而して、以上の如き被害者の行動は、通常これを予想することは困難であると認められるが、かかる事態においても、自動車運転者に対しては、これに対処して事故発生を回避すべき万全の転方法を要求するというが如きは、いささか苛酷な運転上の注意義務を課する結果となるものというべきである
- 果して然らば、本件において、被告人のとった速度なり運転方法について、注意義務の欠缺を責めるのは困難であるというべきであり、換言すれば、本件においては、被告人に本件事故の原因たる業務上の過失があったことを認定するに足る証拠は十分であるとはいいが難いのである
と判示し、被告人の過失は認められないとし、業務上過失傷害罪(現行法:過失運転致傷罪)の成立を否定し、無罪を言い渡しました。
東京地裁判決(昭和46年2月18日)
被告人が自動車を運転し、横断歩道の直前で一旦停止後発進するに際し、横断歩道の側端付近でネズミの死がいをみていた小学生(9歳)を認めたが、その小学生が横断歩道を横断しないと軽信して発進し、小学生に衝突して傷害を負わせた事案について、「本件の自動車運転者としては、被害者の突飛な行動に出ることまでを事前に予想すべきではない」として被告人の過失を否定し、業務上過失傷害罪(現行法:過失運転致傷罪)の成立を否定し、無罪を言い渡した事例です。
裁判官は、
- 被告人は、被害者の動静注視は十分につくしていたと認められるし、また、本件当時の次のような状況、すなわち、本件現場が自動信号機によって交通整理の行われている大きな交差点の出口付近であり、都電の軌道敷を含めて車道幅員は計20メートルを越える大通りであって、学童等がしばしば不規則な行動をして遊びまわるようなことが予想されるようなところ(たとえば露地等の裏通りとか、広場付近、あるいは団地内の道路等)とはまったく異る場所であること、被害者らが当時9才の小学生で、しかも下校途中であったこと(幼児ではなく、また、交通規則等の遵守を期待できる通常の通行人と目し得る者であって、一見して交通秩序や危険にまったく無関心な路上遊戯者といえるような状態にある者とは認められない)を考えると、前記弁解事実のような状況下における通常の自動車運転者に、しゃがんでいる被害者が本件においてとったような突飛な行動に出るかも知れないことまでも事前に予想すべきであるとすることは難きを強いることになるというほかなく、これを予見すべきであるとして構成されている検察官主張の注意義務はこれを認めることはできない、といわなくてはならない
- なお、検察官の主張する警音器の吹鳴は、本来、本件のような状況下においてはそれ自体を業務上の注意義務としては認めることができない(なぜならば、ただ警笛を鳴らしてみても、相手がその警告を理解しないときには、他の注意、たとえば発進自体をさし控えるか、相手の近くで再び停止する等のことをつくさないかぎり、結果回避は結局不可能であるからである)のみならず、かりに、そうでないにしても、被告人の弁解するように、もし、被害者が被告人車両の存在に気づいていたとすれば、そのような歩行者になお義務として警告を与えるべきであるとすることはいささか酷といわなければならない
- そして、被告人は、被害者のしゃがんでいる姿をしばらく見届けたうえ、これを注視しながら、5キロ程度のきわめてゆるい速度で前進し、被害者の突然の動きを認めるとただちに急制動措置をとっているのであるから、この経過にも通常の自動車運転者としてとるべき態度に欠けるところはないと認められる
と判示し、被告人の過失は認められないとし、業務上過失傷害罪(現行法:過失運転致傷罪)の成立を否定し、無罪を言い渡しました。
老人
老人について、「老人は多少の例外はあるとしても、車両の進行状況に対する判断及び行動能力が通常の成人に比し相当劣っており、不測の行動に出ることのあることは経験上明らかである」と判示する判決(大阪高裁判決 昭和48年10月30日)があり、被害者が老人であることは、その行動を予測し得るを判断する上での要素となっています。
ただし、老人といっても、判断能力、行動能力に個人差が認められるため、その行動を予測し得たかどうかの判断は、事件ごとの具体的事情の下で個別に判断することになります。
参考となる判決として、以下の者があります。
大阪高裁判決(昭和48年10月30日)
老人の横断歩行者が、中央分離帯の切れ目に立ち止まり、被告人運転の自動車の方を見ているのを発見していた上で急な横断を開始していたとしても、その老人に自動車で衝突した被告人に過失あるとし、業務上過失傷害罪(現行法:過失運転致傷罪)の成立を認めた事例です。
裁判官は、
- 被害者は、バス停留所に行く途中、被告人車の後方から進行して来たバスを認め、それに乗るつもりで横断を急ぎバスに気を奪われて被告人車の進行してくるのに気付かず、あるいは失念して横断を開始したものか、あるいは被告人車が進行してくるのに気付いていながらその進行状況の判断を誤り、先に横断できるものと考えて急いで横断を開始したものかのいずれかであるものと思われるのであるが、いずれにせよ被害者が一たん分離帯の切れ目に立ち止まって被告人車の方を見ていたことから、被害者が被告人車に気付き、被告人車をそのまま通過させるものと信じたことも一概に非難することはできない
- しかしながら、被害者は当時69歳の老人であり、その年齢の正確な認識はともかく、被告人も老人であることに気付いていたのである
- そして、老人は多少の例外はあるとしても、車両の進行状況に対する判断力及び行動能力が通常の成人に比し相当劣っており、不測の行動に出ることのあることは経験上明らかである
- 被害者が、中央分離帯の切れ目に立ち止まって被告人車の方を見ていたのも、横断歩行中一時停止したのにすぎず、依然として横断を続行する態勢にあったものであるから、右のように被告人車両の進行状況に気付かず、あるいはこれを失念ないし判断を誤って進路に出てくることもあり得ることは通常予測しうるところである
- しかも、被告人車は、中央分離帯からわずかに約1.2メートルしか隔たっていない地点(被害者との間隔もこれと大差はない)を走行しており、被害者が不測の行動に出た場合、これを避けるだけの余裕が十分あったわけではないから、被告人としては、かような不測の事態に対処するため、被害者に対し、警笛を吹鳴して警告を与えるとともに、直ちに減速し、被害者の動向に注意を払って進行すべき注意義務があるものと認めるのが相当である
- 本件は、被告人が右注意義務を怠った過失により発生したものと考えられる
- 被告人が前記注意義務を尽して進行しておれば、被害者の横断開始をより早期に発見し、的確なハンドル操作と制動操作とにより被害者との衝突を回避できたことは明白である
と判示し、老人が不足に行動にでることがあることを前提とし、被告人の過失を認め、業務上過失傷害罪(現行法:過失運転致傷罪)が成立するとしました。
奈良地裁葛城支部判決(昭和46年8月10日)
この判決は、「老人の未然に危険を避け得る能力は一般成人に劣るものとは考えられない」と述べた上で、それでもなお被告人に過失は認められないとして、業務上過失致死罪(現行法:過失運転致死罪)の成立を否定し、無罪を言い渡した事例です。
自動車を時速約50kmで運転する被告人が、前方を走る老人(63歳)の運転する自転車を追い越そうとした際、老人が進路を右に移したのを約20mに近接して初めて認め、急制動のうえ左に転把したが及ばず、自車を老人運転の自転車に接触転倒させ、老人を頭部挫傷等の傷害により死亡させた業務上過失致死罪(現行法:過失運転致死罪)の事案です。
裁判官は、
- 一般に老人と幼児、児童は、突然異常な行動にでる可能性が大であるといわれているところである
- しかし、幼児、児童の場合には、身体の動作が激しく、また事前に危険を察知し得る能力に劣る点があるから、突然異常行動にでる可能性は大きいといえるが、老人の場合は、身体的動作の敏捷性に欠けるとはいえ、社会的経験は豊かであるから、高齢者 (五感の作用若しくは知的判断能力に欠陥を有することが予想される)でない限り、事前に危険を察知し、未然に危険を避け得る能力においては一般成人に劣るものとは考えられない
- 従って、自動車運転者が、本件のように、老人であることを認めた場合において、当該老人に安全な自転車操縦を期待できない状況が、その挙動などから判断し得る場合でない限り、当該老人が突然異常な行動にでる危険性はないものと判断したとしても、それを責めることはできないものと解される
- そこで本件の場合、被告人が被害老人を認めた時点において、被害老人は右折するなどの進路変更の気配をみせることなく、安定した走行状態で国道左端を直進しており、被害老人の進路には障害物はなく、従って、被害老人に安全な自転車操縦を期待し得ない状況になかったこと、被告人が被害老人を発見した地点においては、被害老人の進路変更を予見できる道路状況ではなかったことなどの事情を考慮すると、自動車運転者が警音器を吹鳴すべき具体的な危険があったものと認められない
と判示し、業務上過失致死罪(現行法:過失運転致死罪)の成立を否定し、無罪を言い渡しました。
業務上過失致死傷罪、重過失致死傷罪、過失運転致死傷罪の記事まとめ一覧