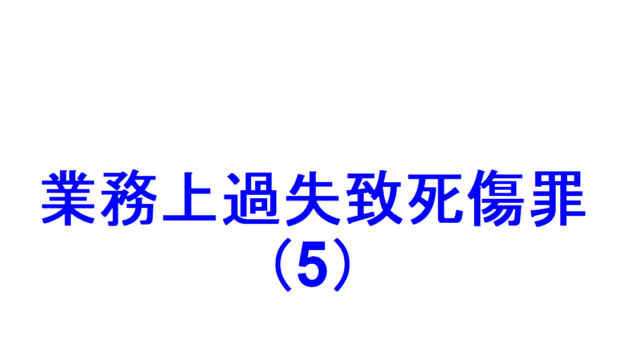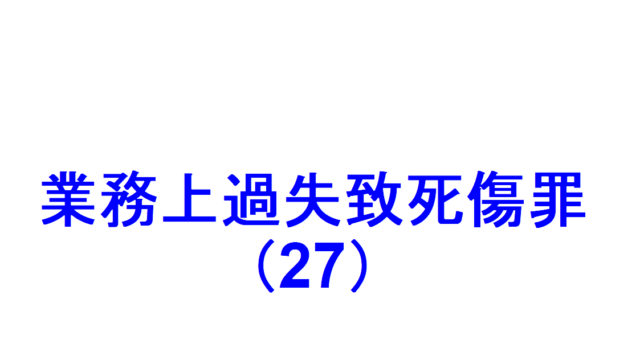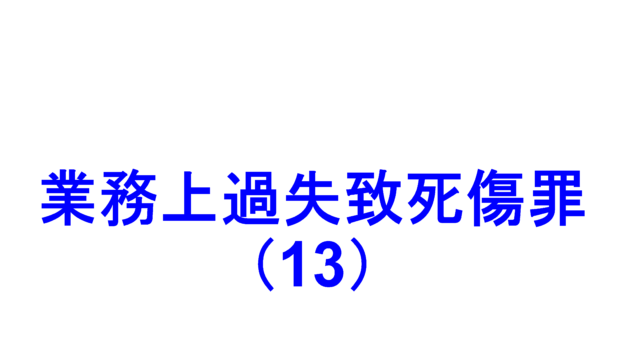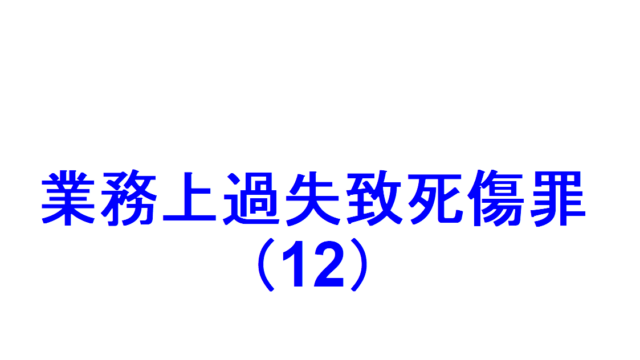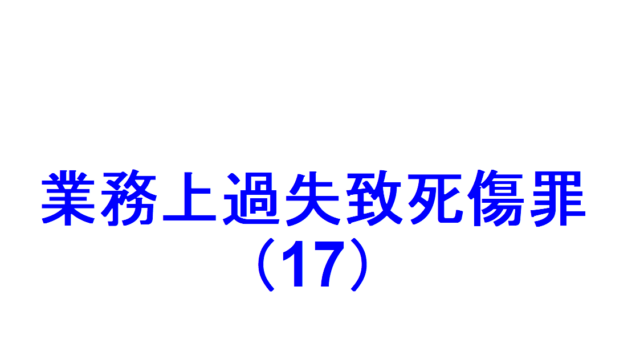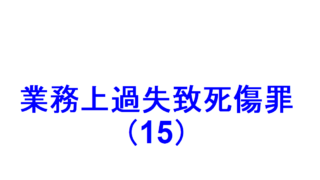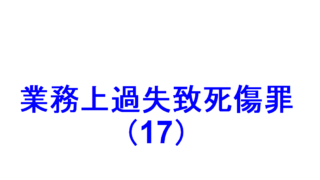前回の記事の続きです。
前回は、頸椎捻挫などの自覚症状に基づく傷害を肯定した事例を紹介しました。
今回は、業務上過失致死傷罪(刑法211条前段)において、傷害の発生を否定した裁判例を紹介します。
傷害の発生を否定した事例
東京高裁判決(平成2年1月18日)
交通事故による負傷事実の立証が不十分であるとして、業務上過失傷害罪(現行法:過失運転致傷罪)が成立するとして有罪とした原判決を破棄し、無罪を言渡した事例です。
事案は、被告人が運転する普通貨物自動車が、時速約20~25kmで前方に停止していた被害者A運転の自動車に衝突し、Aに加療約4週間を要する外傷性頭頸部症候群などの傷害を負わせたとして起訴された事案です。
裁判官は、
- 証拠をあれこれ勘案すると、医学的見地からしても、Aの痛み等各症状の訴えと各種の診断結果からして、外傷性頭頸部症候群という断定を下せるか、はなはだ疑問であるのみならず、カ学的見地からしても、被告人車がA車に追突したその状況からして、果たしてAに外傷性頭頸部症候群、いわゆる鞭打ち症が発生する可能性があったか疑問があるといわねばならない
- そして更に、当審で取調べた鑑定人作成の鑑定書によれば、「被告人車とA車の両車の損傷状況等からして被告人車がA車に追突した際の速度は、時速3キロメートルから高くても同4キロメートルであり、追突されたことによりA車が押し出されたときの速度は時速1ない1.5キロメートルで、追突によりA車に加わった最大加速度は0.3ないし0.4Gであり、アメリカで行われた椅子に人を乗せてその椅子を急に動かす実験結果によると、被実験者が頸部に痛みを訴えはじめたときの椅子の最大加速度は、首が後方に曲がる場合は約3G、前方に曲がる場合は約4Gであるといわれていることからすると、A車に加わった程度の加速度では鞭打ち症になるとは考えられなく、さらに、Aに外傷性頭頸部症候群が発生した可能性があることの理由として原判決が挙げる衝突時の同人の姿勢に関連しては、Aが証言するようなやや前かがみの姿勢では、後方から押す力が働いても頸部は前後に屈伸し難くなり、かえって鞭打ち症は発生し難くなると考えられる。」というのである
- してみると、原判決がAに外傷性頭頸部症候群が発生したと認定したのは、もはや誤りであるといわねばならない
と判示し、傷害の発生を否定し、無罪を言い渡しました。
東京高裁判決(昭和59年7月26日)
軽四輪貨物自動車を運転して一時停止中、同車を自然発進させて時速1~2kmで進行し、普通乗用自動車に追突させて約4か月の頸部挫傷(いわゆる鞭打ち症) などを負わせたとする公訴事実について、因果関係が認められないとして原判決を破棄し、無罪を言い渡した事例です。
裁判官は、
- 被害者A、Bの両名は、被害車両が被告人車に追突されたことを奇貨として、被告人から損害賠償名下に多額の金員を取得しようと考え、医師に対し、本件事故により頸部挫傷ないしはむち打ち症となったように装って、愁訴をしたものであって、Bについては、本件当時、妊娠4か月であって、長時間にわたりドライブをし、追突事故にあったこと等のために、下腹部痛及びむち打ち症の症状に類似する頭痛など若干の症状は生じたとも窺われるが、Bの大部分の愁訴及びAの愁訴、並びに右各愁訴の全部が事実であるかの如きAの供述は、いずれも虚偽である疑いが極めて濃いものといわざるをえないものと考える
- したがって、右各愁訴が真実であることを前提とするA、B両名に対する医師の各診断、並びに右事実のほか、追突の際における衝撃についての右両名の各供述は措信できないものであるのに、右各供述をも真実であることを前提とする鑑定人Kの鑑定はその前提を欠くものというべく、右各診断及びK鑑定をもって右両名が本件事故により右傷害を負った旨の事実を認める証拠とすることはできないものといわなければならない
- 以上に判示したとおり、当審における事実の取調べの結果を参酌すると、
本件各証拠によっては、本件事故により孝、ゆう子の両名が原判示の傷害を負った事実があるものと認めることはできず、結局その証明がないものといわなけれはならないから、右事実を認定してA、B両名に対する業務上過失傷害罪の成立を認めた原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認があるものというべく、原判決は破棄を免れない
と判示し、A、Bの傷害の成立を否定し、無罪を言い渡しました。
福岡簡裁判決(昭和63年4月26日)
自動車の追突事故に関する業務上過失傷害罪(現行法:過失運転致傷罪)被告事件につき、被害者Aに、鞭打ち症が生じたことが認定できないとして、無罪を言い渡した事例です。
裁判官は、
- 追突時の被告人車の速度は先に認定したとおり極めて低速であったこと、及び両車両の損傷程度等を総合すると、A車はほとんど前方に押し出されていないと認めるのが相当である
- この点においても「むちうち機転」は起り得なかったのではないかとの疑が残る
- 医師が頸部捻挫・腰部捻挫により5日間の加療を要する旨の診断書を作成したことは先に認定したとおりである
- Aの愁訴自体は否定しうべくもなく、医師が患者の信頼に応え、その愁訴を重視することも何ら批判しうべきことではないけれども、客観的な、あるいは医学的な根拠を欠く判断は、「むちうち症」の発生について、そのメカニズム上疑問がある本件においては、(医師の診断書は)採用の限りではないと言うべきである
- 以上のとおりであるから、傷害の発生につき、合理的な疑いを超えた確信をいだかせるに足る証拠はなく、本件公訴事実は結局犯罪の証明がないことに帰する
などと判示し、Aの傷害の成立を否定し、無罪を言い渡しました。
神戸簡裁判決(昭和62年1月22日)
被告人が運転する自動車が、時速約3kmで道路の右側車線に進出した際、被害車両に接触し、被害車両に乗っていたAとBに、加療約15日間の頸椎捻挫等の傷害を負わせたとして起訴されたが、傷害の証明が十分でないとして、業務上過失傷害罪(現行法:過失運転致傷罪)の成立が否定された事案です。
裁判官は、接触の揺れが極めて軽微であると認められること、被害者の供述に虚偽や誇張が存在することから、
- 被害者両名にむち打ち運動による頸椎捻挫が発生したと認めるには強い疑念を抱かざるを得ない
と判示し、被害者の傷害の発生を認めることはできないとして、業務上過失傷害罪(現行法:過失運転致傷罪)の成立が否定しました。
(なお、判決では、安全運転注意義務違反を認定し、無罪の言い渡しをしていない)
宇治簡裁判決(昭和60年7月9日)
自動車の追突事故により、外傷性頸部症候群、右膝挫傷および腰椎圧迫骨折等の傷害を負わせた旨の訴因について、事故により傷害を負ったことの証明がないとし、業務上過失傷害罪(現行法:過失運転致傷罪)の成立を否定し、無罪を言い渡した事例です。
裁判官は、
- 本件追突による衝撃が極めて軽微なものであり、右衝撃による身体の揺れがあったとしても、わずかなものであったと推認される
- 本件追突の衝撃により、被害者の右膝部分が前部座席の背もたれで打ったとしても、それが打撲傷を生ずるほどのものであったかどうか、多分に疑念を抱かざるをえない
- そして、これに、本件追突の際の身体の揺れについて、被害者の供述部分が必ずしも真実を述べたものとは思われず、右供述が信用性に欠けるものであることをも考え合せると、被害者が医師に訴えた自覚症状も果して真実であったかどうかは疑わしい
- 結局、被害者に対する右のような疑念が払しょくできない以上、主として被害者の自覚症状に基づいてした医師の診断結果に関する証拠をもっては、被害者が本件事故により右傷害を負った旨の事実を認める証拠とすることはできない
と判示し、無罪を言い渡しました。
業務上過失致死傷罪、重過失致死傷罪、過失運転致死傷罪の記事まとめ一覧