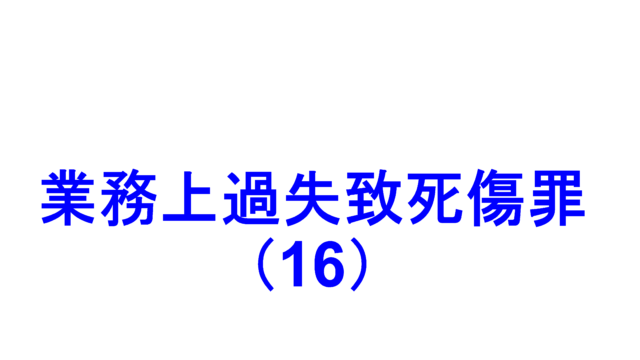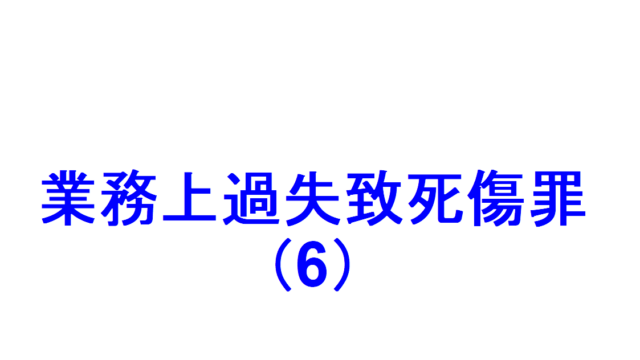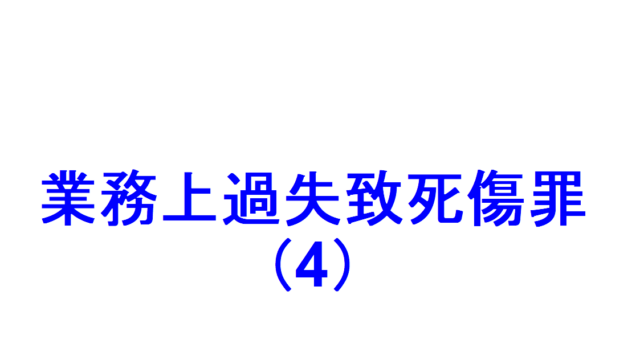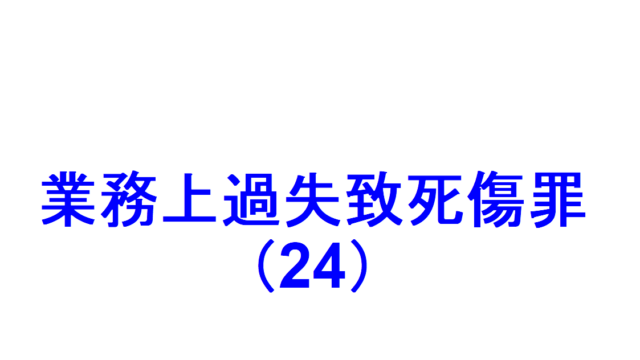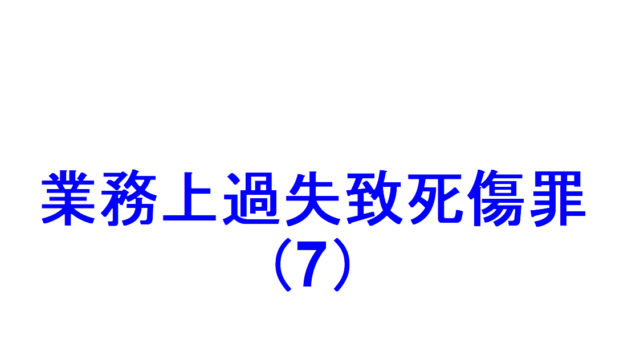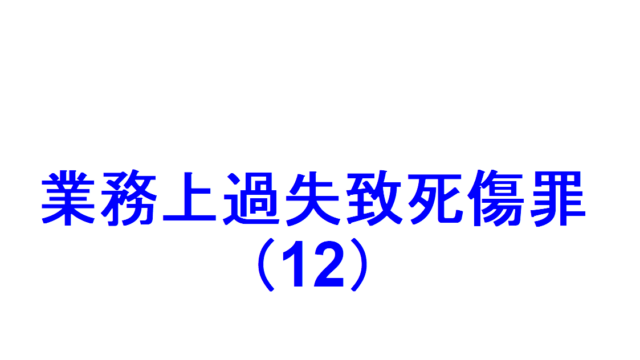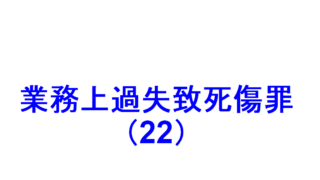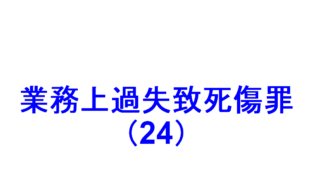業務上過失致死傷罪(23) ~「航空機操縦者の注意義務」を説明~
前回の記事の続きです。
航空機操縦者の注意義務
航空機事故は、ひとたび事故が発生すれば死亡事故になるなど、業務上過失致死傷罪(刑法211条前段)が成立する事案です。
航空機の操縦に当たっては、関係法規や運航規程に従い、飛行中は、前方左右を注視し、相手機を認めた場合には、接触、衝突の防止に努め、また障害物との接触、衝突を避げ安全航行に努めるべき義務が課せられます。
航空機事故の裁判例
航空機事故の裁判例を紹介します。
法令を遵守しないことが過失認定に影響した事例
航空機操縦の危険性に照らすと、法令を遵守しないことが、過失認定に影響する度合いは大きいと考えられます。
この点、参考となる裁判例として、以下のものがあります。
飛行機操縦者である被告人が、雲による視界不良な場所を飛行中に山腹に衝突して飛行機を炎上・破壊し、乗客9名を死傷させた業務上過失致死傷罪の事案です。
被告人が操縦していた飛行機は、安全な雲中飛行をするのに十分な計器類の塔載装置もなく、計器飛行方式による飛行が許されていない水陸両用単発飛行機であり、この点が、被告人が法令を遵守せずに飛行を行ったとして被告人の過失認定に影響を与えました。
裁判官は、
- 視界方式により飛行機を操縦する場合にあっては、視界上良好な気象状態において飛行すべきであり、また航空法施行規則等に従い、合理的な理由なしに雲中を飛行し、又は所定の最低安全高度以下の低空を飛行することは許されず、たとえ、帰投すべき空港の気象状態が前線の通過により悪化しつつあった場合でも、なお一般的特別有視界気象状態の最低基準1マイル程度の視程があり、レーダーによる進入誘導を受けて着陸することが可能である以上、注意義務に違反する
- 事故は飛行機が層雲中を飛行中、標高約300メートルの山腹に衝突したものであり、裁判所は、機長としては、進行方向に層雲が広がり雲の切れ間が認められない場合、出発空港へ帰投すべきである
とし、被告人の過失を肯定して、業務上過失致死傷罪が成立するとしました。
なお、この高裁判決は最高裁でも支持されています(最高裁決定 昭和46年10月7日)。
航空交通管制官の誤った管制指示による事故の事例
航空管制官の誤った管制指示に基づき、航空機が発進して事故となった場合、航空管制官に過失が認められ、航空管制官が業務上過失致死傷罪の罪に問われる場合があります。
参考となる裁判例として、以下のものがあります。
名古屋地裁判決(昭和37年10月10日)
航空管制官である被告人が、飛行機操縦士に対し、誤った示指を出し、空港滑走路上で飛行機同士が衝突する事故を起こし、飛行機の乗員が死傷した業務上過失致死傷罪の事案です。
裁判官は、
- 被告人は、滑走路上に旅客機がいたのに、戦闘機に離陸支障なしの管制指示を出した過失により、旅客機と戦闘機を衝突させ、乗員を死傷させた
とし、事故の原因を航空管制官である被告人の過失ある管制指示であると認定し、被告人に対し、業務上過失致死傷罪が成立するとしました。
航空管制官の誤った指示により、航行中の飛行機甲機と乙機が著しく接近し、両機の衝突を避けるために急降下した甲機の乗客らが負傷した業務上過失傷害罪の事案です。
裁判官は、実地訓練中の航空管制官Aにおいて、両機が異常接近しつつあることを知らせる警報を認知して巡航中の乙機を降下させることを意図しながら、便名を言い間違えて上昇中の甲機に降下を指示し、Aの指導監督者である航空管制官Bにおいて、これに気付かず、直ちに是正しなかったことは、ほぼ同じ高度から甲機が上記指示に従って降下するのと同時に、乙機も航空機衝突防止装置によって発せられる降下指示に従って降下し、両機の接触、衝突等を引き起こす高度の危険性を有する行為であって、これと上記事故との因果関係も認められ、かつ、A、B両名において、両機がともに降下を続けて異常接近し、両機の機長が接触、衝突を回避するために急降下を含む何らかの措置を余儀なくされるととが予見できた事実関係の下で、A、B両名について過失を認めました。
航空管制官とは異なりますが、航空機の操縦について指示すべき立場にある者の過失が問われた事例です。
編隊飛行訓練中の自衛隊機と民間機とが空中衝突し、乗員が死亡した業務上過失致死罪の事案です。
裁判官は、訓練教官である被告人には、見張り義務があり、これを履行していれば民間機は注視野の中にあり視認可能であって事故は回避可能であったとして、被告人の過失を認定しました。
航空機の離発着時に生じた事故事例
航空機の事故は離発着の際に生じることが多いです。
参考となる裁判例として、以下のものがあります。
東京地裁判決(昭和51年3月23日)
旅客機が離陸滑走の際、機首の方向が離陸方向から偏向を生じ、前車輪による方向修正機能が失われていたため滑走路から逸脱して機体を損壊し、乗客が負傷した業務上過失傷害罪の事例です。
裁判官は、
- 機長としては、速やかに主車輪とエンジンによる全制動を図るなどして、滑走路外への逸脱を防止し、また万一逸脱することになっても、低速で路外に進入し、滑走路付近で停止することができるようにすべきである
- 航空機のように、事故が発生すれば極めて重大な結果になることが多い交通機関の操縦者には、安全確保のための高度な注意義務が課せられており、航空機の離陸滑走に際し、滑走路が湿潤状態にあって離陸滑走直後から機首が除々に偏向を加え、一定の前車輪操作によって方向修正をはかっても効果がない等判示の具体的状況のもとでは、機長は、すみやかに制動措置を講じ、もって事故の発生を未然に防止すべき注意義務がある
と判示し、機長の過失を認定しました。
福岡高裁宮崎支部判決(昭和57年2月23日)
降雨追風の中を着陸した航空機がオーバーランして堤防に激突大破し、乗客らが負傷した業務上過失傷害罪の事案です。
裁判官は、
- 機長としては、運航規程等に従い、滑走路上に定められた接地帯上に着陸接地するか、困難な場合は、代替空港へ着陸するなど、採り得る危険回避の措置は残されていた
- すなわち、結果回避措置は時間的にも行動的にも可能であったものと認められる
- しかるに、被告人は、注意義務を懈怠し、危険発生の予見を怠り、これらの臨機の結果回避措置を採らず、ために事故を招き、乗客に対し傷害を負わせたものである
- そうだとすれば、被告人の所為が航空法に違反し、かつ業務上過失傷害罪を構成することは明らかである
と判示しました。
機長の操縦には過失が認められないとして業務上過失致死傷罪の成立が否定された事例
航空機の操縦において、具体的状況に照らして機長の操縦には過失が認められないとされる事案も少なくありません。
参考となる裁判例として、以下のものがあります。
大分地裁判決(昭和49年3月20日)
旅客機が着陸の際、滑走路内で停止せず、その末端を越え、数百十メートル東方の堤防に激突、炎上し、乗客ら40名を死傷させた航空機事故につき、操縦士の過失責任が否定され、業務上過失致死傷罪は成立しないとして無罪が言い渡された事例です。
裁判官は、
- 旅客機が着陸の際、3つの制動機器の連続故障により、滑走路で停止せず、末端を越えて百数十メートル離れた堤防に激突した場合について、事故は不可抗力的に生じたものと認められる
とし、操縦士の過失責任はないとしました。
仙台地裁判決(昭和41年3月31日)
旅客機が着陸滑走後、着陸のやり直しをするため、離陸しようとして浮揚した際、右主翼端が吹流し取付用ポールに激突するなどし、旅客機が地面に激突し、乗員乗客が死傷した事案です。
裁判官は、
- 被告人は、機長として操縦者に一般に要求される技術を有しており、かつ具体的操作に当たって技量の発揮を怠り、操作上の誤りを犯したといえない
- 被告人の過失を問うことはできない
とし、機長の過失を否定し、業務上過失傷害罪は成立しないとして無罪を言い渡しました。
羽曳野簡裁判決(昭和61年2月14日)
ヘリコプターにより雪中飛行訓練中、雪原に緊急着陸しようとして横転大破した事案です。
操縦者の被告人は、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律違反(同法6条2項:過失による航空機を墜落・破壊)で起訴されました。
裁判官は、
- 被告人は着陸目標が目標物としての適格性に欠け、錯覚が混入した可能性があるなどのため進入が不安定となった可能性があること、当時、被告人は、白一色の雪の中にあって、これにげん惑され、高度感覚と水平感覚を失い、操縦の自由を失っていたのであるから、復行操作を誤ったとする証拠はない
- 人を過失犯として処罰をするためには、その者の置かれた状況下にあって、その者と同じ地位、身分にある平均的人間として何をなすことができたか、何をなすべきであったかを考え、これについて、刑事上の過失として処罰するに価する行為があったかどうかを問うことが必要である
- 被告人は、回転翼航空機の事業用操縦士の資格を有するが、本件事故は被告人が同資格を取得してニ月余り後の時期に、会社から命ぜられ、訓練生としての始めての雪中訓練飛行に参加した際に発生したものであり、しかも右訓練の初日の雪中体験飛行の課程においての突然の雪原着陸においてであった
- 被告人は、教官から着陸進入を命ぜられ、被告人自身も緊急事態の認識を有し、雪原着陸以外の他の方法を選択する余地のない行為であった
- あるいは、被告人の技能がより優秀であれば、本件事故の発生にいたらなかったかも知れないが、被告人にはその行った具体的操作において、当時被告人が現に有し、かつ被告人と同じ程度の訓練生が有している技能をもって、そのなすべき操作を怠り、またそのなすべからざる操作を行ったということはできない以上、被告人に対し本件事故の発生についての過失を問うことはできない
と判示し、無罪を言い渡しました。
名古屋高裁判決(平成19年1月9日)
旅客機が航行中、激しく揺れて乱高下し、乗員、乗客が天先や床にたたきつけられるなどし、1人が死亡、13人が重軽傷を負った事案で、検察官に業務上過失致死傷罪で起訴された事例です。
検察官は、
- 降下中の旅客機の対気速度が著しい増加傾向を示し、同機の最大運用限界速度を超過するなどしたため、機長は減速措置を講じようとしたが、その際、操縦輪を強く引いて過大な力を加えるオーバーライドという不適切な操縦方法をとり、これによって、自動操縦装置を自動的に解除させた
- その結果、機体姿勢の修正操作に伴う数回の機首の上下動を発生させ、その衝撃により本件事故を引き起こした
とし、業務上過失致死傷罪が成立すると主張しました。
この主張に対し、裁判官は、
- 操縦輪がオーバーライドされて自動操縦装置が解除されたことは認められるが、機長が故意に行ったことについて疑問が残る
- 自動操縦装置が解除された段階で既に何らかの原因で機首上げが起こっていた可能性が否定できず、自動操縦装置の解除が被害者の死傷につながったことも認められない
と判示し、犯罪の証明がないとして、無罪を言い渡しました。
業務上過失致死傷罪、重過失致死傷罪、過失運転致死傷罪の記事まとめ一覧