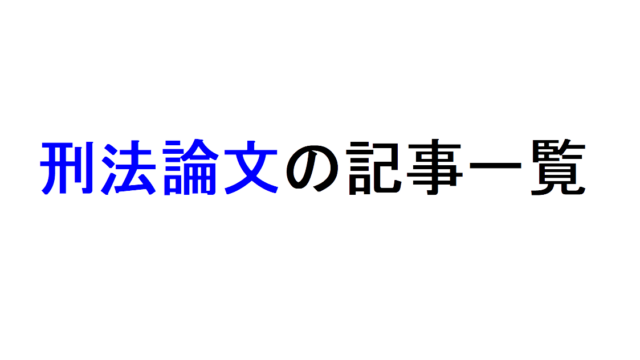刑法論文(17)~令和3年司法予備試験の刑法論文問題から学ぶ~
令和3年司法予備試験の刑法論文問題から学ぶ
令和3年司法予備試験の刑法論文問題の答案を作成してみました。
この論文からは以下のテーマが学べます。
1⃣ 窃盗罪(刑法235条)
- 他人に預けた窃盗犯人の所有物に対する窃盗罪の成否
- 他人に預けた財物を窃取した場合の自救行為の成否
2⃣ 建造物等以外放火罪(刑法110条2項)
3⃣ 不作為による殺人罪の幇助犯、自殺幇助罪(刑法202条)、殺人罪(刑法199条)
- 不真正不作為犯の成立要件
- 幇助犯の成立要件
- 認識した犯罪事実と現実に実行した犯罪事実が異なる場合の故意の成否
問題
以下の事例に基づき、甲及び乙の罪責について論じなさい(住居等侵入罪及び特別法違反の点を除く。)。
1 甲(50歳)は、実父X(80歳)と共同して事業を営んでいたが、数年前にXが寝たきり状態になった後は単独で事業を行うようになり、その頃から売上高の過少申告等による脱税を続けていた。甲は、某月1日、税務署から、同月15日に税務調査を行うとの通知を受け、甲が真実の売上高をひそかに記録していた甲所有の帳簿(以下「本件帳簿」という。)を発見されないようにするため、同月2日、事情を知らない知人のYに対して、「事務所が手狭になったので、今月16日まで書類を預かってほしい。」と言い、本件帳簿を入れた段ボール箱(以下「本件段ボール箱」という。)を預けた。
Yは、本件段ボール箱を自宅に保管していたが、同月14日、甲の事業の従業員から、本件帳簿が甲の脱税の証拠であると聞かされた。甲は、税務調査が終了した後の同月16日、Yに電話をかけ、本件段ボール箱を回収したい旨を告げたが、Yから、「あの帳簿を税務署に持っていったら困るんじゃないのか。返してほしければ100万円を持ってこい。」と言われた。
甲は、得意先との取引に本件帳簿が必要であったこともあり、これを取り返そうと考え、同日夜、Y宅に忍び込み、Yが保管していた本件段ボール箱をY宅から持ち出し、自宅に帰った。
2 甲は、帰宅直後、Yから電話で、「帳簿を持っていったな。すぐに警察に通報するからな。」と言われた。甲は、すぐに警察が来るのではないかと不安になり、やむなく、本件帳簿を廃棄しようと考えた。甲は、自宅近くの漁港に、沖合に突き出した立入禁止の防波堤が設けられており、そこに空の小型ドラム缶が置かれていることを思い出し、そのドラム缶に火をつけた本件帳簿を投入すれば、確実に本件帳簿を焼却できると考えた。そこで、甲は、同日深夜、本件段ボール箱を持って上記防波堤に行き、本件帳簿にライターで火をつけて上記ドラム缶の中に投入し、その場を立ち去った。
その直後、火のついた多数の紙片が炎と風にあおられて上記ドラム缶の中から舞い上がり、周囲に飛散した。上記防波堤には、油が付着した無主物の漁網が山積みにされていたところ、上記紙片が接触したことにより同漁網が燃え上がり、たまたま近くで夜釣りをしていた5名の釣り人が発生した煙に包まれ、その1人が同防波堤に駐車していた原動機付自転車に延焼するおそれも生じた。なお、上記防波堤は、釣り人に人気の場所であり、普段から釣り人が立ち入ることがあったが、甲は、そのことを知らず、本件帳簿に火をつけたときも、周囲が暗かったため、上記漁網、上記原動機付自転車及び上記釣り人5名の存在をいずれも認識していなかった。
3 甲は、妻乙(45歳)と2人で生活していたところ、乙と相談の上、入院していたXを退院させ、自宅で数か月間、その介護を行っていたが、自力で移動できず回復の見込みもないXは、同月25日から、甲及び乙に対して、しばしば「死にたい。もう殺してくれ。」と言うようになった。甲は、Xが本心から死を望んでいると思い、その都度Xをなだめていた。しかし、Xは本心では死を望んでおらず、乙もXの普段の態度から、Xの真意を認識していた。
乙は、同月30日、甲の外出中、Xの介護に疲れ果てたことから、Xを殺害しようと決意し、Xの居室に行き、「もう限界です。」と言ってXの首に両手を掛けた。これに対し、Xは、乙に「あれはうそだ。やめてくれ。」と言ったが、乙は、それに構わず、殺意をもって、両手でXの首を強く絞め付け、Xは失神した。乙は、その後も、Xの首を絞め続け、その結果、Xは窒息死した。
甲は、Xが失神した直後に帰宅し、乙がXの首を絞めているのを目撃したが、それまでのXの言動から、Xが乙に自己の殺害を頼み、乙がこれに応じてXを殺害することにしたのだと思った。甲は、Xが望んでいるのであれば、そのまま死なせてやろうと考え、乙を制止せずにその場から立ち去った。乙は、その間、甲が帰宅したことに気付いていなかった。
仮に、甲が目撃した時点で、直ちに乙の犯行を止めてXの救命治療を要請していれば、Xを救命できたことは確実であった。また、甲が乙に声を掛けたり、乙の両手をXの首から引き離そうとしたりするなど、甲にとって容易に採り得る措置を講じた場合には、乙の犯行を直ちに止めることができた可能性は高かったが、確実とまではいえなかった。
答案
第1 甲の罪責
1 甲がY宅から段ボール箱を持ち出した行為につき、窃盗罪(刑法235条)が成立しないか。
⑴ 本件段ボールは、乙が甲から預かっているものであり、甲の所有物であることから、甲にとって本件段ボール箱は「他人の財物」に当たらず、それを窃取しても窃盗罪は成立しないのではいか。
これは窃盗罪の保護法益が問題となる。
窃盗罪の保護法益は、財産法秩序の維持の観点から、他人の財物に対する事実上の支配(占有)そのものであると解する。
刑法242条が「自己の財物であっても、他人が占有…するものであるときは、…他人の財物とみなす」と規定するのは上記の窃盗罪の保護法益の理解に基づくものであると解する。
よって、本件段ボール箱は、甲がYに預けたものであり、他人であるYが事実上支配(占有)するものであるから、甲にとって「他人の財物」に当たる。
したがって、甲が、他人の財物である本件段ボール箱を窃取すれば窃盗罪が成立する。
⑵ 「窃取」とは、目的物の占有者の意思に反し、その占有を侵害し、その物の占有を自己又は第三者の占有に移すことをいう。
「占有」とは、人が財物を事実上支配し、管理する状態をいう。
甲は、夜にY宅に忍び込み、Yが管理する本件段ボール箱をY宅から持ち出しており、Yの占有を侵害していることから「窃取」に当たる。
⑶ 窃盗罪の故意は、他人の占有する財物を、占有者の意思に反してその占有を侵害し、自己又は第三者の占有に移すことの認識・認容をいう。
甲は、Yから100万円をゆすり取られないように、Yの占有する脱税の証拠である本件帳簿入りの本件段ボール箱を自己の占有下に戻す意思であることから、窃盗の故意が認められる。
⑷ 不法領得の意思とは、権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従い、これを利用し又は処分する意思をいう。
権利者排除意思は、窃盗既遂後の事情を考慮し、窃盗罪と違法性の乏しい一時使用窃盗を区別し、一時使用窃盗を不可罰にするために必要となる。
「その経済的用法に従い」とは、領得した財物自体から生み出される利用価値・交換価値を窃盗犯人が享受する使い方をいう。
利用処分意思は、「捨てる」という意味でなく「盗んだ物を売却する」「他人に譲り渡す」「自己使用する」などの処分行為を意味し、財物領得罪と器物損壊罪を区別するために必要となる。
甲に権利者排除意思があることは明らかである。
甲は、中に入っている脱税の証拠である本件帳簿を本件段ボール箱ごと自己の管理に戻すことで、Yから100万円をゆすり取られないようにするという本件段ボール箱の利用価値を享受する意思が認められる。
甲に本件段ボール箱を自己の管理下に置くという利用処分意思も認められる。
よって、不法領得の意思が認められる。
⑸ 以上より、窃盗罪の構成要件を満たす。
⑹ もっとも、甲の本件段ボール箱の窃取行為は取返し行為として自救行為が成立し、違法性が阻却されないか。
自救行為とは、国家に頼らず、自らの力で自分の権利を守ること(自力救済すること)をいう。
取返しという正当な目的のもと、正当性、緊急性、相当性が認められる場合には自救行為が成立し、違法性が阻却されると解する。
甲は、Yに預けていた脱税の証拠である本件帳簿を取り返すという目的であり、目的は正当ではない。
甲はYに「返してほしければ100万円を持ってこい。」と言われていることから、事件として警察に届け出て、警察に動いてもらうことが十分に可能だったのであるから、自力救済でなければならない緊急性も認められない。
取返しの方法は、夜にY宅に忍び込んで窃取するというものであり、相当性も認められない。
よって、自救行為は成立せず、違法性は阻却されない。
⑺ 以上より、甲に窃盗罪が成立する。
2 本件帳簿にライターで火を付けた行為につき、建造物等以外放火罪(刑法110条2項)が成立しないか。
⑴ 建造物等以外放火罪は、現住建造物等放火罪と非現住建造物等放火罪を補充するものである。
具体的には、現住建造物等放火罪及び非現住建造物等放火罪の客体以外の一切の客体に対する放火について規定するものである。
本件帳簿は、現住建造物等放火罪及び非現住建造物等放火罪の客体以外の物に該当するので、建造物等以外放火罪の客体に当たる。
⑶ 建造物等以外放火罪の実行行為は、火を放って目的物を焼損することである。
「焼損」とは、火勢が放火の媒介物を離れて目的物に移り、独立して燃焼作用を継続しうる状態に達したことをいうと解する(独立燃焼説)。
本件帳簿は、炎を上げて舞い、飛散し、油が付いた魚網に燃え移って延焼もさせていることから、「焼損」に当たる。
⑷ 建造物等以外放火罪は、具体的危険犯であり、公共の危険が具体的に発生したことを要件とする。
「公共の危険」とは、不特定又は多数の人の生命・身体・財産に対する侵害のおそれがある状況をいう。
本件帳簿から火が魚網に燃え広がり、5名の釣り人が煙に包まれた上、火が原動機付自転車に延焼するおそれが生じており、不特定又は多数の人の生命・身体・財産に対する侵害のおそれがある状況が認められることから、「公共の危険」の発生が認められる。
⑸ 建造物等以外放火罪の既遂時期は、公共の危険が具体的に発生した時点であることから、既遂が認められる。
⑹ 甲は、本件帳簿に火を付けたときは、周囲が暗く、魚網、原動機付自転車、釣り人5人の存在をいずれも認識していなかったため、故意が認められないのではないか。
建造物等以外放火罪の故意を認めるに当たり、対象物に火を放って焼損することの認識があれば足り、公共の危険の発生の認識は不要である。
刑法110条2項が「よって公共の危険を生じさせた」としていることから、建造物等以外放火罪は、結果的加重犯である。
そして、結果的加重犯は、基本犯の行為に加重結果発生の現実的危険性を有するために認められるものであるから、加重結果について故意は不要であり、因果関係があれば足りると解する。
そのため、本件において、甲が「公共の危険」を認識している必要はない。
甲は、本件帳簿を燃やすことを認識・容認している上、本件帳簿の焼損と魚網の延焼等したことによる公共の危険の発生の因果関係が認められる。
よって、甲に建造物等以外放火罪の故意が認められる。
⑺ 以上より、甲に建造物等以外放火罪が成立する。
なお、甲が放火した本件帳簿は、甲が所有するものなので、刑法110条2項により、科される刑罰は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金となる。
3 甲が乙を制止せずにそのまま立ち去った行為につき、殺人罪(刑法199条)の共同正犯(刑法60条)又は不作為による殺人罪の幇助犯(刑法62条1項)又は不作為による自殺幇助罪(刑法202条)の幇助犯が成立しないか。
⑴ 殺人罪の共同正犯は成立しないか。
共同正犯が成立するには、共謀、共同実行の事実があることが必要となるが、乙は甲の帰宅に気付いておらず共謀はない。
甲は殺人罪の実行行為を分担して行っていないので、共同実行の事実も求められない。
よって、殺人罪の共同正犯は成立しない。
⑵ では、不作為による殺人罪の幇助犯が成立しないか。
ア まず、不作為による殺人罪の成立要件を満たすか。
殺人罪は不作為によっても成立する不真正不作為犯である。
不真正不作為犯が成立するには、①法的作為義務の存在、②作為の可能性、③故意の実行行為としての不作為、④不作為と結果の因果関係の4つの要件が必要となる。
①「法的作為義務の存在」とは、行為者に結果の発生を防止すべき行動をする法律上の義務があることをいう。
②「作為の可能性」とは、行為者において作為義務を行うことで、結果の発生を防止できる可能性があったことをいう。
③「故意の実行行為としての不作為」とは、行為者が故意に作為義務を行わなかったことをいう。
④「不作為と結果の因果関係」とは、不作為者が期待された必要な行為をしたならば、結果が発生しなかったと認められる関係があることをいう。
甲はXの子であるから、法的に扶助義務(民法730条)を負っている上、乙の実行行為は甲宅内で行われており、これを阻止し得たのは甲のみであったことから、Xの生命の存続は、排他的に甲に依存しており、甲はこれを支配していたといえる。
よって、甲にXの生命を救護する措置をとるべき法律上の義務があったと認められる(①「法的作為義務の存在」充足)。
甲が直ちに乙の犯行を止めた上で救護治療を施せば確実にXは助かったのであるから、甲はXの殺害結果を防止することが容易にできた(②「作為の可能性」充足)。
甲は、Xが死を望んでいるならそのまま死なせてやろうと考え、乙を制止せずにそのまま立ち去っており、Xを助けることができたのに故意に行わなかった(③「故意の実行行為としての不作為」充足)。
甲がXを助けていれば、Xは乙に殺害されなかったのでから、甲が期待された救助行為をしていれば、結果が発生しなかったと認められる(④「不作為と結果の因果関係」充足)。
よって、殺人罪の不真正不作為犯の成立要件を満たす。
イ 次に、幇助犯の成立要件を満たすか。
「幇助」とは、正犯の実行行為を容易にし、促進することをいう。
幇助犯が成立するためには、①幇助の意思があること、②幇助された者が犯罪を実行することが必要となる。
「幇助の意思」があるといえるには、自分の幇助行為により、幇助された者の犯罪の実行が容易になることを認識・容認することが必要になる。
幇助行為があったいえるためには、幇助行為が正犯の行為を物理的・心理的に容易にし、促進したと認められれば足りる。
甲は、乙がXを殺害する状況にあることを認識したが、Xをそのまま死なせてやろうと考え、乙を制止せずに立ち去っていることから、自己が何もしないことで、乙の殺人の実行行為が容易に遂行されることの認識・容認があったといえ、「幇助の意思」が認められる。
そして、乙は、Xの殺人罪を実行している。
甲の幇助行為は、乙の殺人の実行行為を手助けするものであり、乙の犯行を物理的に容易にし、促進するものであったと認められる。
ウ もっとも、乙は甲が帰宅したことに気付いておらず、甲の幇助行為に気付いていない。
この点、正犯が幇助を認識していなくても、その実行行為を容易にすることは可能であるから、片面的幇助も成立する。
よって、乙が甲の幇助行為に気付いていなくても、幇助犯が成立する。
エ したがって、幇助犯の成立要件を満たす。
オ もっとも、甲はXが真意かつ任意に死を望んでいたと思っていたのであるから、自殺幇助罪(刑法202条)の故意であり、殺人罪の故意を有していない。
よって、甲に不作為による殺人罪の幇助犯は成立しない。
⑶ では、不作為による自殺幇助罪の幇助犯が成立しないか。
故意責任の本質は、反対動機形成可能性にあり、構成要件の範囲内の認識にずれがあっても、反対動機形成は可能である。
したがって、殺人罪と自殺幇助罪との間に重なり合いが認められれば、軽い限度で故意責任を問うことが可能である。
構成要件の重要部分は行為と結果であるから、行為態様及び保護法益の共通性により重なり合いを判断する。
検討すると、行為態様は、殺害であり、共通する。
保護法益は、人の生命であり、共通する。
よって、殺人罪と自殺幇助罪との間に重なり合いが認められる。
殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑」であるのに対し、自殺幇助罪の法定刑は「6月以上7年以下の拘禁刑」であることから、刑の軽重は、自殺幇助罪の方が軽い。
よって、刑が軽い自殺幇助罪の故意が認められる。
⑷ したがって、甲に不作為による自殺幇助罪の幇助犯が成立する。
なお、この場合、実際に行っていない自殺幇助罪を成立させることになるが、刑法38条2項がその成立を認めているので罪刑法定主義に反しない。
4 以上より、甲に、①窃盗罪、②刑法110条2項の建造物等以外放火罪、③不作為による自殺幇助罪の幇助犯が成立する。
①②③は、それぞれ別個の行為であるから併合罪(刑法45条前段)となる。
第2 乙の罪責
1 乙がXの首を両手で絞め続けた行為につき、殺人罪が成立しないか。
⑴ 「実行行為」とは、法益侵害(構成要件的結果)が発生する現実的危険を有する行為をいう。
乙がXの首を強く絞め付けて失神させ、その後も首を絞め続けた行為は、Xに生命の危険を生じさせる現実的危険を有する行為であり、殺人罪の実行行為であると認められる。
⑵ 「因果関係」とは、犯罪行為と犯罪結果との間にある原因と結果の関係をいう。
乙がXの首を締め続けたことによりXが窒息死しているので、乙の行為とXの死亡結果との間に因果関係が認められる。
⑶ 殺人罪の故意は、自己の行為によって、人の死という結果が生じることを予見・容認するこという。
乙は、Xが失神してもなお首を絞め続けており、自己の行為によってXの死という結果が生じることを予見・容認している。
また、Xは、乙から「あれはうそだ。やめてくれ。」と言われ、Xが死を望んでいないことを認識しているので、自殺幇助罪の故意ではない。
よって、殺人罪の故意が認められる。
2 以上より、乙に殺人罪が成立する。