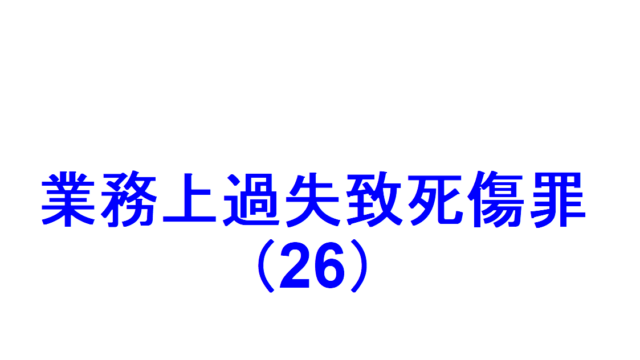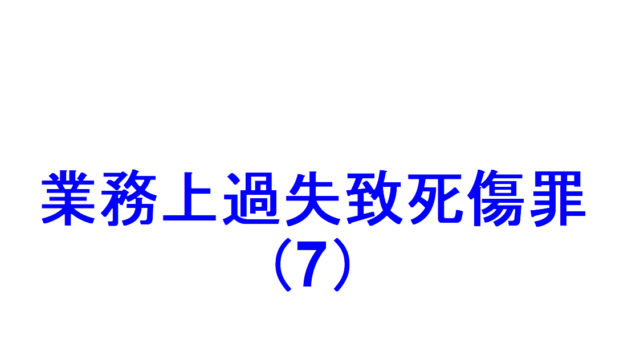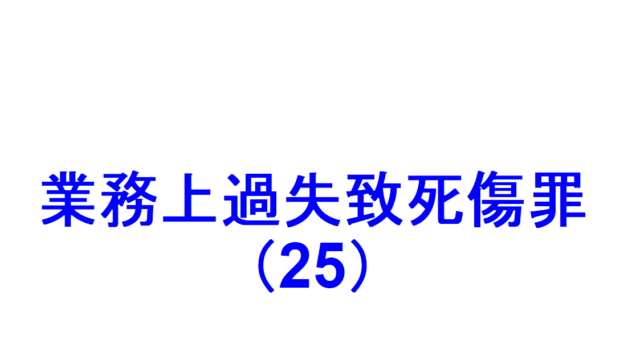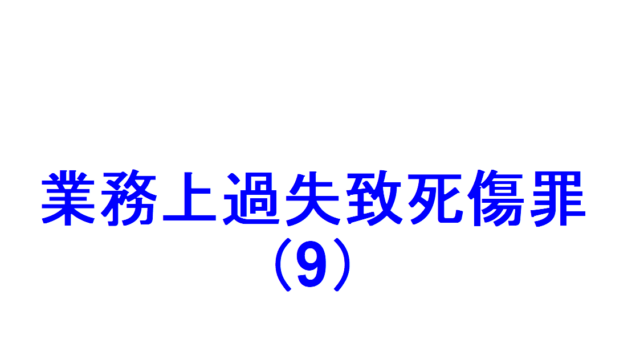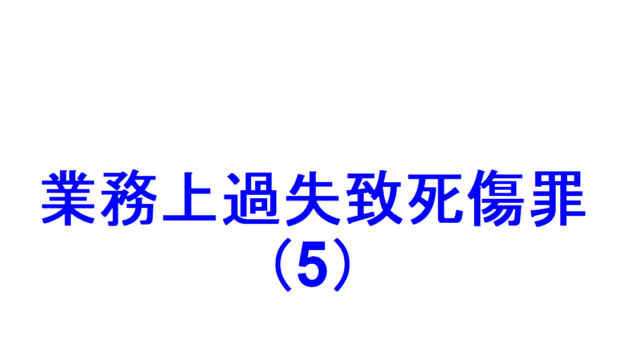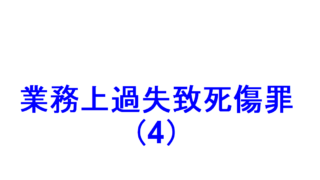信頼の原則とは?
「信頼の原則」とは、
行為者がある行為をなすに当たって、被害者あるいは第三者が適切な行動をすることを信頼するのが相当な場合に、被害者あるいは第三者の不適切な行動によって致傷の結果が発生したのであれば、それに対しては責任を負わない原則
をいいます。
「信頼の原則」の考え方を用いた主要判例は、以下の2つの判例です。
小型自動車を運転して交通整理の行われていない交通頻繁な交差点を右折しようとしたところ、交差点の中央付近でエンストを起こしてしまった被告人が、再びエンジンを始動し、左側方の安全のみを確認して時速約5キロメートルで右折進行を開始したとき、右側方から原動機付自転車が進行して来るのを約5メートルの距離まで接近して初めて気付き、直ちに停車したが間に合わず、両車が衝突し原動機付自転車の運転者に傷害を与えたという自動車事故による業務上過失傷害罪の事案です。
裁判官は、
- 自動車運転者としては、特別な事情のないかぎり、右側方からくる他の車両が交通法規を守り自車との衝突を回避するため適切な行動に出ることを信頼して運転すれば足りるのであって、 あえて交通法規に違反し、自車の前面を突破しようとする車両のありうることまでも予想して右側方に対する安全を確認し、もって事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務はないものと解するのが相当である
と判示し、被告人に過失(注意義務違反)はないとして、業務上過失傷害罪の成立を否定しました。
酒に酔った客が線路敷に落下して、電車に接触して死亡した業務上過失致死罪の事案です。
裁判官は、
- 乗客係がその業務に従事するに当たって、旅客のなかに泥酔者を認めたときは、その挙措態度等に周到な注意を払い、車両との接触、線路敷への転落などの危険を防止する義務を負うことはもちろんである
- しかし、他面鉄道を利用する一般公衆も、鉄道交通の社会的効用と危険性にかんがみ、みずからその危険を防止するよう心掛けるのが当然であって、飲酒者といえども、その例外ではない
- それ故、乗客係が酔客を下車させる場合においても、その者の酩酊の程度や歩行の姿勢、態度その他外部からたやすく観察できる徴表に照らし、電車との接触、線路敷への転落などの危険を惹起するものと認められるような特段の状況があるときは格別、さもないときは、一応その者が安全維持のために必要な行動をとるものと信頼して客扱いをすれば足りるものと解するのが相当である
と判示し、乗客係は、客が線路上に落下しない行動をとると信頼して客を取り扱えば足り、酒に酔った客が線路上に落下して電車に接触して死亡したことに対し、業務上の過失責任を認めることは酷であるとし、業務上過失致死罪の成立を否定しました。
上記判例のほか、信頼の原則の考え方を用いた判例として、以下のものがあります。
自動車事故の事案で、交通整理が行われていない左右の見通しがきかない交差点で、交差道路には一時停止の標識と停止線の表示がある場合、交差点に進入する自動車運転者としては、徐行し、停止線付近に交差点に入ろうとする車両が存在しないことを確かめた後、すみやかに交差点に進入すれば足り、あえて交通法規に違反して、高速度で、交差点を突破しようとする車両のあり得ることまで予想して、他の道路に対する安全を確認する注意義務はないとし、業務上過失傷害罪(現行法:過失運転致傷罪)の成立を否定しました。
信号が青色に変わった直後に発進した自動車が、赤色信号を無視して交差点に進行した疑いがある車両と衝突した事案について、特別な事情がない限り、そのような交通法規無視の車両のあり得ることまでを予想すべき業務上の注意義務はないとし、業務上過失傷害罪(現行法:過失運転致傷罪)の成立を否定しました。
自動車事故の事案で、交差点の入口で、私人の手旗による交通規制の行われている交差点に進入する自動車運転者としては、交差道路から進行して来る車両の運転者が私人の赤旗による停止の合図に従うものと信頼してよく、同運転者がその停止の合図を無視し同交差点に進入することまでを予想して徐行しなければならない業務上の注意義務はないとし、業務上過失傷害罪(現行法:過失運転致傷罪)の成立を否定しました。
自動車事故の事案で、自車と対面する信号機が黄色の灯火の点滅を表示し、交差道路上の信号機が赤色の灯火の点滅を表示している場合、交差点に進入する自動車運転者としては、特段の事情のない限り、交差道路から交差点に接近して来る車両の運転者においてもその信号に従い一時停止及び事故回避のための適切な行動をとるものと信頼して運転すれば足り、それ以上に、あえて法規に違反して一時停止することなく高速度で交差点を突破しようとする車両のあることまで予想した周到な安全運転をすべき業務上の注意義務はないとし、業務上過失致死傷害罪(現行法:過失運転致死傷罪)の成立を否定しました。
路面電車(市電)から降車した直後に信号を無視して道路を横断した歩行者を自動車で、被告人が運転する自動車が衝突し、歩行者にけがをさせた業務上過失致傷害罪(現行法:過失運転致死傷罪)の成立を否定しました。
この判例は、歩行者は交通規則の知識が限られており、容易に信頼の原則を適用すべきではないが、その行動について一定の信頼をおくことは可能であるとして、信頼の原則の適用を認めた事例です。
裁判官は、
- 当時、対向市電が右側安全地帯に停車して乗降客を取扱中であったのであるから、その乗降客が不注意に信号に違反して道路を横断しようとして、自動車の進路前方に進出してくることもないとはいえない
- しながら、本件交差点には信号機が設置されていて、当時、東西進めの信号を示していたのであるから、南北は止まれの信号を示していたはずであり、被害者の連れであって一緒に市電を降りたという証人Bの証言によっても、南北は止まれ(赤色の灯火)の信号を示していたことが明らかである
- このような場合、自動車を運転して西進する者は、交差点内にある右側安全地帯に停車中の市電の後方から、降客等が信号を無視して進路前方に進出して来ることがあることも全然予想しえないわけではないにしても、交差点に信号機を設置し、信号を表示している場合、信号に違反して進出してくる歩行者はほとんどないであろうこと、及び仮りにそのような歩行者があったとしても、他の側は進めの信号が表示され、自動車等の車両が走行している以上、歩行者またはその保護者において左右の安全を十分確認するなど自己防衛の手段を尽すであろうことを一応期待するのが通常であって、このように期待することを一概に非難することはできない
- 従って、自動車運転者としては、このような場合、どれほど無鉄砲な信号違反の歩行者が市電の後方から飛び出しても、事故の発生を完全に防止するに足りる措置を講ずべき必要はなく、信号違反の歩行者側の自己防衛手段と相俟って、事故の発生を防止しうる程度の措置を講ずれば足りるものと解するのが相当である
- もし、このような場合にまで、一方的に自動車運転者に事故の発生を未然にかつ完全に防止するに足りる措置を講ずべき義務を課するならば、信号違反の歩行者に比し、信号に従っている自動車運転者に甚だ酷であるばかりではなく、いつでも直ちに停車できる程度に減速徐行すべきものとすれば、最徐行運転による交通停滞の原因ともなり、かえって交通の安全と円滑を阻害し、自動車の高速度交通機関としての機能を奪うことになって、交差点に信号機を設置した意味を失わせることになるからである
- してみれば、このような場合、自動車運転者としては、安全地帯横に停車している市電のすぐ南側を進行するのであるから、一応市電の後方から信号違反の歩行者が進出してくることがあることも考慮して前方左右を注視しながら、時速を20キロメートル程度に減速して徐行すれば、仮りに右市電の後方安全地帯の西端(その西側に横断歩道がある)付近から道路を横断しようとする歩行者があっても、歩行者において急に飛び出すようなことのないかぎり歩行者側の停止、待避等自己防衛の措置と相俟って、衝突等の危険は一般に避けられるものと考えられるから、右の程度の注意義務を尽せば足りるものといわなければならない
- そして、被告人は安全を期して時速を約20キロメートルに減速して市電の南側を進行したところ、被害者Aが市電の後方から信号に違反し、左方へ進路を横断しようとして南に向かって小走りに進出して来るのを右前方約1.6メートルの地点に発見したので、急停車の措置をとったが(自動車は約4メートル進んで停車している)、間に合わなかったものであって、被告人には右以上に減速徐行しなかった点に過失があったとすることはできない
- また、被告人において被害者の早期発見及び急停車措置に欠けるところがあったことも証拠上認められないし、その他、記録を精査し、当審における事実取調の結果を参酌しても、本件事故が被告人の過失によって発生したことを認めることができないから、結局、本件公訴事実は犯罪の証明が十分でないというほかはない
と判示し、歩行者が信号無視をして進行してこないことを期待するのが通常である趣旨を述べ、被告人に過失(注意義務違反)はないとして、業務上過失致傷害罪(現行法:過失運転致死傷罪)の成立を否定し、無罪を言い渡しました。
「信頼の原則」が適用された交通事犯以外の判決として、以下のものがあります。
札幌高裁判決(昭和56年1月22日)
ボイラーマンの過失により病院が火災となり、入院患者ら6名が死傷した病院の火災事故の事案で、経営管理者である病院長の過失責任が追及され、病院長が業務上過失致死傷で起訴された事例です。
経営管理者である病院長の過失責任が問われましたが、現場にいた看護婦らが適切な救助活動を行っていれぱ死傷者が出なかったにもかかわらず、適切な行動に出なかったことについて、病院長には「信頼の原則」が適用されるとして過失責任を否定し、業務上過失致死罪の成立は成立しないとして無罪としました。
裁判官は、
- 被告人は、本件当時、本件病院の理事長兼病院長として、本件病院の経営及び管理部門全体を統括し、診療部門全体を監督する職責を担っており、旧館出火の場合に備えて新生児及び入院患者並びに付添人の救出や避難誘導に関する職責をも当然負担していたといわざるを得ない
- けれども、本件病院の理事長ないし病院長としての立場から考えるとき、当直看護婦や夜警員が当然果してくれるものと予想されるような出火通報、非常ロ開扉及び新生児搬出などの救出活動ないし避難誘導活動が現実に実行されないであろうという場合までも考慮に入れて火災発生に備えた対策を定めなければならないとまでいうのは行過ぎといわざるを得ない
- すなわち、検察官が本件死傷者6名の死傷事故につき、理事長兼病院長である被告人の過失として捉えている注意義務は、出火の際の救出活動や避難誘導活動について人員の質(対策の定立とこれに基づく訓練の実施が経由されていること)及び量(当直人員の増員)の拡充と物的設備の改善(非常ロ扉の改造又は右の扉の鍵の携行)とに尽きるところ、かかる拡充改善の措置をすることを刑法上の業務上の注意義務として要求するには、既存の当直人員の質及び量並びに既存の物的設備の下で、従業員が当然に果すであろう救出活動ないし避難誘導活動によってもなお回避不能とみられる死傷事故に対する関係においてはじめて肯定されるべきものに過ぎないというべきである
- そして、本件火災により発生した前記6名の死傷という結果については、当時の当直人員の質及び量並びに当時の物的設備の下で回避不能であったとは認められないから、被告人については、公訴事実で主張されているような結果回避措置をあらかじめ講じておかなければならないとすることの前提となるべき客観的予見可能性が欠落し、従って、被告人に前記6名の死傷という具体的結果に対する予見義務を負わせることができない道理である
- 結局、本件死傷事故につき、被告人には業務上過失致死傷の責を問うことはできないと判断される
- 以上の次第で、被告人に対する本件公訴事実中、業務上過失致死傷の点は、犯罪の証明がないことに帰するから、刑事訴訟法336条後段により、被告人に対し無罪の言渡しをする
と判示しました。
次回の記事に続く
次回の記事では、信頼の原則を以下の①~④の類型ごとに説明します。
- 加害者(被告人)が交通法規に違反している場合
- 信頼の原則を基礎付ける条件が整っていない場合
- 相手方の不適切な行動について、予測が可能な場合
- 相手方が泥酔者、幼児、老人などで通常の判断能力を期待し得ない場合
業務上過失致死傷罪、重過失致死傷罪、過失運転致死傷罪の記事まとめ一覧