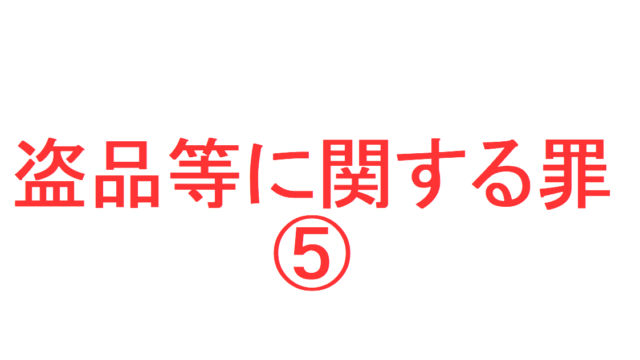盗品等に関する罪⑩ ~「故意の内容」「盗品であることの知情」「未必の故意」「知情の時期」「行為の認識」「不法領得の意思は不要」を判例で解説~
盗品等に関する罪は故意犯である
故意犯とは?
故意犯とは、犯罪を犯す意思をもって、故意に犯した犯罪をいいます。
過失犯とは、故意ではなく、不注意により犯した犯罪をいいます。
たとえば、自動車事故(過失運転致傷罪)、過失傷害罪などが過失犯です。
盗品等に関する罪における故意とは?
本題ですが、盗品等に関する罪(刑法256条)は、故意犯です。
盗品等に関する罪に、過失を処罰する規定はありません。
盗品等に関する罪が成立するためには、
故意(盗品等に関する罪を犯そうとする意思)
が必要になります。
この故意が認められなければ、盗品等に関する罪は成立しません。
ここで、故意の内容として重要になるが、
盗品等であることの知情
です。
盗品であることの知情
盗品であることの知情があると認めるためには、
目的となる財物(不動産を含む)が、財産に対する罪に当たる行為(窃盗罪など)によって、本犯(窃盗罪などの犯人)に領得されたものであることの認識
が必要になります。
「財産に対する罪に当たる行為により本犯に領得されたことの認識」の具体的内容
1⃣ 盗品であることの認識があればよく、本犯の犯罪の具体的内容の認識までは不要である
財産に対する罪に当たる行為(窃盗罪など)によって、本犯(窃盗などの犯人)が、当該財物を領得したものであることの認識があれば、それがいかなる犯罪によるものであるかの認識は不要です。
この点について、以下の判例があります。
大審院判決(大正3年3月14日)
この判例で、裁判官は、
- 贓物故買(盗品等有償譲受け)罪は、犯人の贓物(盗品等)すなわち他人の財産権を害し、不法に領得したる物なる情を知して、これを買取するをもって足り、それが何なる犯罪によりて取得したるものか知悉せざるも故買罪の成立に妨げなし
と判示し、盗品等に関する罪であることの認識として、盗品であることを分かっていればよく、どのような犯罪で入手された盗品なのかまで知る必要はないとしました。
この判例で、裁判官は、
- 贓物に関する罪(盗品等に関する罪)の成立に必要な贓物たることの知情は、財産罪により不法に領得された物であることを認識すれば足りるのであって、その物が何人のいかなる犯行によって不法に領得されたかの具体的事実までをも認識することを要するものではない
と判示しました。
もし、本犯の犯罪まで知る必要があるとすると、現実問題として、大半の盗品等に関する罪は犯罪が成立しなくなることから、判例の結論は妥当といえます。
本犯の犯罪が、いかなる犯罪かの認識を不要とする以上、本犯の犯罪が、どのような内容のものであったか、本犯の犯行年月日、被害者が誰かなどの犯罪の具体的内容についても、知る必要はありません。
この点について、以下の判例があります。
大審院判決(大正12年12月8日)
この判例で、裁判官は、
- 贓物(盗品等に関する)罪は、贓物(盗品等)犯人において取扱いたる物品が不法に領得せられたることの情を知れるをもって足れりとし、必しも本犯の犯行を詳細に熟知するを要せざるものとす
と判示しました。
2⃣ 盗品であることの認識は「未必の故意」で足りる
盗品等であることの知情は,未必的な認識(未必の故意)で足ります。
未必の故意とは、
犯罪結果の発生を確実なものとして認識・容認していないが、犯罪結果が発生しても構わないと考え、犯罪結果を発生させることが可能なものとして認識・容認している場合の故意
をいいます。
たとえば、相手にバカにされて頭にきたので、相手を木刀で殴った場合に、「相手は死ぬかもしれないが、それでも構わない」と思っていたのなら、殺人の未必の故意が認められ、殺人罪が成立することになります。
盗品等に関する罪における故意(盗品等であることの知情)も、未必的の故意で足りるとした判例として、以下のものがあります。
この判例で、裁判官は、
- 贓物故買罪(盗品等有償譲受け罪)は、贓物であることを知りなから、これを買い受けることによって成立するものである
- その故意が成立するためには、必すしも買い受くべき物が贓物であることを確定的に知っていることを必要としない、あるいは贓物であるかも知れないと思いながら、しかも敢えてこれを買い受ける意思(いわゆる未必の故意)があれば足りるものと解すべきである
- ゆえに、たとえ買受人が売渡人から贓物であることを明らかに告げられた事実がなくても、苛くも買受物品の性質、数量、売渡人の属性態度等諸般の事情から「あるいは贓物ではないか」との疑いを持ちながら、これを買受けた事実が認められれば、贓物故買罪(盗品等有償譲受罪)が成立する
と判示しました。
その他の未必の故意に関する判例として、以下の判例があります。
仙台高裁判決(昭和24年10月20日)
この判例で、裁判官は、
- 贓物牙保罪(盗品等有償処分あっせん罪)の成立には、犯人が贓物であるかも知れないものと思いながら、その売買の仲介周旋をした事実があれば足り、かつその程度の認識があれば「贓物たる情を知りながら」と判示して差し支えない
としました。
札幌高裁判決(昭和28年7月7日)
この判例で、裁判官は、
- 贓物運搬罪(盗品等有償処分あっせん罪)は、贓物であることを知りながら、これを運搬することによって成立するものであるが、その故意が成立するためには、必ずしも運搬すべきものが贓物であることを確定的に知っていることを必要としない
- あるいは贓物であるかも知れないと思いながら、しかも敢えてこれを運搬する意思(いわゆる未必の故意)があれば足りるものと解すべきである
- 被告人がAの依頼により、本件の物品を運搬したのは深夜であること、その際、Aから親に内緒の物を運んでくれと言われていること…等がうかがわれ、右事実は、十分人をして「贓物ではないか」、との推量をなしむるに足りる事情である
と判示しました。
【盗品であることの認識が途中で消えた場合】
いったん盗品であることの認識を持っても、盗品等に関する罪の犯罪行為の実行の時点で、その認識が消えている場合には、犯罪が成立しない可能性があります。
この点について、以下の判例があります。
高松高裁判決(昭和26年4月27日)
この判例で、裁判官は、
- 贓物故買罪(盗品等有償譲受け罪)の成立するためには、必ずしも買い受けるべき物が、贓物であることを確定的に知っていることを必要としない
- あるいは、贓物であるかも知れないと思いながら、しかも敢えてこれを買い受ける意思(いわゆる未必の故意)があれば足りる
- 被告人の自白と補強証拠と相まって、全体として犯罪構成要件たる贓物故買(盗品等有償譲受け)の事実を認定し得られる以上、必ずしも被告人の自白の各部分について、いちいち補強証拠を要するものではなく、贓物たる知情の点を被告人の自白のみによって認めても違法ではない
- しかしながら、一応はその物が「あるいは贓物ではないか」との疑念を持ったものの、この疑念が解消して、そのような不正品ではないとの信頼を生じたがゆえに、これを買い受けた場合には、贓物故買罪(盗品等有償譲受け罪)の犯意を認めることはできない
と判示しました。
3⃣ 知情の時期
【 行為時の知情 】
盗品であることの情を知らなければならない時期については、基本的には、
行為の時
に知情のあることを要します。
盗品の譲受け(盗品等無償譲受け罪、盗品等有償譲受け罪)のように、物の移転を要件とする場合についても、契約・約束などの時期ではなく、現実の物の移転時を、知情の時期の基準とします。
この点について、以下の判例があります。
盗品等有償譲受け罪について、盗品譲受けの取引後、盗品を運搬するときに初めて知情を生じた事案で、
- 現実に贓物の移転のある際に、贓物たるの情を知っていれば、贓物罪は成立するものといわなければならない
として、盗品の受け取り後、盗品の運搬時にその財物が盗品かもしれないと分かった場合でも、知情性を持って、盗品等有償譲受け罪に及んだとして、同罪の成立を認めています。
【運搬・保管開始後の知情】
継続犯とは、
犯罪の結果発生と同時に、犯罪は成立するが(既遂に達するが)、加害行為が継続する犯罪
をいいます。
たとえば、監禁罪です。
犯人の家に連れ込まれて、監禁された時点で監禁罪は成立します。
その後も解放されるまで、ずっと監禁(加害行為)が継続します。
継続犯である盗品等運搬罪、盗品等保管罪について、運搬・保管を開始した後に、知情が生じた場合には、その時以降、当該行為を継続する限り(やむを得ず継続する場合、例えば、運搬途中で気付き、そのまま盗品を放置できないような場合を除く)、各罪が成立します。
この点について、以下の判例があります。
この判例で、裁判官は、
- 贓物であることを知らずに物品の保管を開始した後、贓物であることを知るに至ったのに、なおも本犯のためにその保管を継続するときは、贓物の寄蔵(保管)にあたるものというべきである
と判示し、盗品等保管罪の成立を認めました。
行為についての認識を要する
盗品等に関する罪の故意の内容としては、盗品等であることの知情のほか、自己の行為についての認識を要します。
具体的には、盗品等に関する罪を犯した犯人が、譲受け、運搬、保管、処分のあっせんの各行為を行っていることの認識が必要になります。
もし、犯人に、譲受け、運搬、保管、処分のあっせんの各行為を行っている認識がなかったのであれば、盗品等に関する罪は成立しないことになります。
不法領得の意思は不要
窃盗罪、遺失物等横領罪、強盗罪、詐欺罪などの領得罪は、犯罪の成立要件として、不法領得の意思(権利者を排除して他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思)を必要とします。
これ対して、盗品等に関する罪については、不要領得の意思が犯罪の成立要件になっていいませ。
具体的には、窃盗罪などの領得罪については、窃盗などの犯人に、不法領得の意思がなければ、窃盗罪などの犯罪が成立しない結果になります。
しかし、盗品等に関する罪については、盗品等に関する罪の犯人に、不法領得の意思がなかったとしても、盗品等に関する罪は成立する結果になります。