そもそも占有とは?
占有とは、
人が財物を事実上支配し、管理する状態
をいいます。
そして、占有の主体は、
に限られます(たとえば、人ではない法人が占有の主体になることはできません)。
占有は、現実的な観念なので、物の事実上の支配をなしうるのは、自らの意思を持ち、行動できる自然人に限られるのです。
ここで、
自らの意思を失い、行動できなくなった死者
に財物の占有が認められるかが問題になります。
今回は、この問題点を解明すべく、死者の占有について説明します。
死者の占有
死者の占有について、理詰めで考えると、
自然人は、死亡と同時に占有の主体ではなくなり、死者が生前占有していた物は、占有離脱物となる
となります。
すると、死者が生前占有していた物を奪い取った場合、犯人を窃盗罪(法定刑10年以下の懲役)で処罰することができず、窃盗罪より軽い刑の占有離脱物罪(法定刑1年以下の懲役)でしか処罰できないことになります。
もしそうなってしまうと、
- ハンマーで殴って息絶えた人がしていた腕時計を奪った場合は、1年以下の懲役刑である占有離脱物横領罪が成立する
- ハンマーで殴ってまだギリギリ息がある人がしていた腕時計を奪った場合は、10年以下の刑である窃盗罪が成立する
という結論が導かれ、被害者が死んでいるか死んでいないかで、犯人に与えられる刑罰が大きく変わるという理不尽な結果になってしまいます。
そこで、法は、このような理不尽な結果にならないように、死者に対する占有を、以下の3つの類型に分けて解釈し、正当な判断が導かれるようにしています。
3つの類型
死者が生前占有していた物を、犯人が、その死後不法に奪う行為は、
- 財物強取の意思で人を殺し、財物を取得する場合
- 人を死亡させた後に、領得の意思が生じ財物を取得する場合
- 致死行為に関与していない者が死者の生前占有していた財物を取得する場合
の3つの類型に分けて考えます。
これから①~③の類型ごとに説明していきます。
① 財物強取の意思で人を殺し、財物を取得する場合
まず、死者が生前占有していた物を、犯人が、その死後不法に奪う行為の3つの類型のうち、『①財物強取の意思で人を殺し、財物を取得する場合』について説明します。
初めから人を殺害して財物を強取する意志で人を殺したときには、財物を取得したと否とにかかわらず、刑法240条の強盗殺人罪が成立します(大審院判例 昭和4年5月16日)。
しかしここで、殺害行為の後、殺された人が生前占有していた財物が欲しくなって財物を取得した場合、その財物取得行為は、強盗殺人罪を構成するかが問題になります。
結論として、人を殺した後に、財物を取得する意思を生じさせ、財物を取得したときでも、強盗殺人罪が成立します。
このように結論づける理論は、
- 強盗殺人罪は、被害者の財物に対する占有を「殺害・盗取の一連の行為」によって侵害し、自己の占有に移す行為を構成要件的行為として予定している
- 被害者が死亡した後に財物を取得する場合には、死亡によって被害者の占有が失われるから、殺害行為が同時に財物に対する被害者の占有の侵害行為としての性質を特に濃厚に持つ
- それゆえ、殺人行為の着手があれば、同時に占有侵害行為が開始されたといえる
- そのため、その後、被害者が死亡によってその占有を失い、財物取得行為によって行為者が占有を取得する一連の行為は、一体となって一個の強盗殺人行為をなす
- したがって、殺人行為の着手時に被害者の占有があればよく、財物取得行為時の被害者の占有がなくても、財物取得行為が強盗殺人行為の一部をなすとするのすることができる
というものです。
判例も上記の理論に沿う結論を導いています。
大審院判例(大正2年10月21日)において、裁判官は、
- 刑法240条後段の強盗殺人罪は、強盗か財物強取の行為によって、人を死に至らしめる事実があれば、致死の結果か財物強取の前にあるとその後にあるとによって、同罪の成立に消長を来すことなし
- 被告人が他人を殺して、その財物を強取しようと企図し、その目的を遂行したる場合において、財物を領得したる行為が、被害者の死後にあっても、財物は所有者の意思によらず、誤ってその占有を離れたる物件でないことはもちろんであって、遺失物領得の罪を構成する理由なく、強盗殺人の一罪中に、包含処罰されるべきものである
- したがって、財物強取の手段たる暴行によって他人を死に至らしめ、その占有に係る財物を自己の領得せる行為は、当然、強盗殺人罪の観念中に属するものである
旨述べています。
② 人を死亡させた後に領得の意思が生じ財物を取得する場合
次に、死者が生前占有していた物を、犯人が、その死後不法に奪う行為の3つの類型のうち、『②人を死亡させた後に領得の意思が生じ財物を取得する場合』について説明します。
人を死亡させた後に、財物を領得する意思が生じ、致死行為によって生じた占有侵害の結果を利用する意思で財物を取得したときは、占有離脱物横領罪(法定刑1年以下の懲役)でしか処罰できないのか、それとも、窃盗罪(法定刑10年以下の懲役)で処罰できるのかが問題になります。
やはり、この場合も、財物に対する被害者の占有が死亡と共に消滅し、財物取得行為時において、財物は占有離脱物になっていたとして、占有離脱物罪とするのではなく、より重い罪である窃盗罪で処罰できるとした方が、社会正義に合致します。
たとえば、被害者をハンマーで殴って傷害を負わせ、その時に被害者が落とした物を奪えば窃盗罪で処罰できるのに、被害者をハンマーで殴って殺し、その時に被害者が落とした物を奪った場合は占有離脱物横領罪でしか処罰できないとなれば不合理な結果となります。
そこで、人を死亡させた後に領得の意思が生じ、財物を取得する場合でも、 窃盗罪が成立するとする理論として、
- 致死行為が、結果として、被害者が持つ財物の占有侵害をなしている
- その占有侵害の結果を利用する意思に基づいて、財物取得行為を行っている
- 致死行為による占有侵害行為と、財物取得行為を一体のものと見なし、社会観念上1個の行為と捉える余地がある
という考え方が採用されます。
判例も、致死行為のうち、占有侵害部分と財物取得行為を1個の窃盗行為と捉え、それによって財物に対する被害者の生前の占有が侵害されたと解するのが妥当であるとし、窃盗罪が成立するという結論を出しています。
大審院判例(昭和16年11月11日)
野外で人を傷害して死に至らしめ、その場で懐から現金が入った財布を取得した事件について、裁判官は、
- 被告人は、自ら占有離脱の原因たる被害者の死亡を客観的に惹起せしめたるのみならず、更にその事実を主観的に認識している
- 被告人は、被害者を死亡させた事実に乗じ、その行為の結果を故意に利用して、自己が被害者からその占有を離脱させた物を、その直後に奪取したことも明白である
旨述べ、窃盗罪が成立するとしました。
被告人が、当初からは財物を領得する意思は有していなかったが、野外において、人を殺害した後に、領得の意思を生じ、その現場において、被害者が身につけていた時計を奪取した事件について、裁判官は、
- このような場合には、被害者が生前有していた財物の所持は、その死亡直後においても、なお継続して保護するのが法の目的にかなうものというべきである
- そうすると、被害者からその財物の占有を離脱させた自己の行為を利用して、財物を奪取した一連の被告人の行為は、これを全体的に考察して、他人の財物に対する所持を侵害したものというべきである
- よって、財物奪取行為は、占有離脱物横領ではなく、窃盗罪を構成するものと解するのが相当である
旨述べました。
どのような場合に、致死行為と財物取得行為が一体をなしているといえるか?
人を死亡させた後に領得の意思が生じ財物を取得する場合でも、窃盗罪が成立するといえるためには、
財物取得行為が、致死行為のうちの占有侵害行為の部分と一体となっている
と見なすことができる点がポイントになります。
なのでこれから、財物取得行為が、致死行為のうちの占有侵害行為の部分と一体をなしているといえるための要件について説明します。
財物取得行為が致死行為のうち、占有侵害行為の部分と一体となって一個の窃盗行為だといえるためには、第一として、
- 財物取得行為が致死行為後、直ちに(同一場所において時間的に接近して)行われていること
- そうではないときは、時間的・場所的に近接し、かつ、致死行為に付随または関連する行為や財物取得行為の準備ないし前提的行為が介在するなどして、両行為が同一の機会になされたといえる場合であること
が要件になります。
さらに、第二として、窃盗罪においては、占有侵害行為と財物取得行為を一個の「窃取」行為として捉え得るものであることを要求しているので、
- 致死行為によって被害者の財物の占有を喪失させ、行為者が致死行為に引き続いて、直接的に(第三者を介することなく)占有を取得すること
が要件となります。
さらに、第三として、
- 致死行為による占有侵害の結果を認識し、これを利用して財物を取得するという一個の意思にもとづいて財物取得行為が実行されたこと
が要件になります。
人を死亡させた後に財物を領得する意思が生じ、財物を取得した事件の判例
人を死亡させた後に財物を領得する意思が生じ、財物を取得した事件の判例を紹介します。
被告人が居宅で同棲中の愛人を殺害し、その2時間後に愛人の死体を車で海岸まで運んで遺棄し、再び居宅に戻って、
- 殺害の3時間後に愛人の指輪
- 殺害の86時間後に愛人の腕時計など
を取得した事件で、①②ともに窃盗罪が成立すると判示しました。
東京地裁判例(昭和37年12月3日)
被告人が愛人のアパートで愛人を殺害し、
- その1時間後に、領得の意思を生じ、同所で愛人が生前占有していたままの状態にあった現金を持ち出し
- その後、バーで飲酒し、旅館に宿泊して持ち出した現金を消費した後、愛人が郵便貯金通帳をもっていたのを思い出して、これを領得する意思を生じ、現金持ち出しから9時間後、同アパートに赴き、まだ何人の占有にも属さない状態にあった郵便貯金通帳を持ち出した
という事件で、①につき窃盗罪を認定し、②につき占有離脱物横領罪を認定しました。
新潟地裁判例(昭和60年7月2日)
被告人が愛人関係にあった一人暮らしの被害者を、被害者宅で殺害し、その後、領得の意思を生じ、
- その翌日に、被害者宅から現金、総合口座通帳を持ち去り、殺害から2日後、被害者の死体を同女宅でばらばらに解体して、その翌々日までにこれを持ち出して被告人方に隠匿し
- 殺害から5日後に現金を、10日後に整理ダンス等を持ち出し、なお、その後、①で取得した総合口座通帳を使用して預金引き出し行為を繰り返した
という事件で、①につき窃盗罪を認定し、②につき占有離脱物横領を認定しました。
③ 致死行為に関与していない者が死者の生前占有していた財物を取得する場合
最後に、死者が生前占有していた物を、犯人が、その死後不法に奪う行為の3つの類型のうち、『③致死行為に関与していない者が死者の生前占有していた財物を取得する場合』について説明します。
致死行為に関与していない者が、領得の意思をもって死者の生前占有していた財物を取得する場合は、それが家人その他の者の占有に属しているとみられる場合を除き、
致死行為が他人の行為であるから、行為者による窃取行為を認める余地がなく、占有離脱物横領罪が成立するに過ぎない
とされます。
占有に関する関連記事一覧
刑法上の占有とは?① ~「占有の要件(実力行使の可能性・排他性)」「占有の意思」を判例などで解説~
刑法上の占有とは?② ~「占有の主体 (法人は占有の主体になれない)」「幼児・精神病者・心神喪失者・死者の占有」「占有の機能(奪取罪と横領罪を区別する)」を解説~
占有が認められる判断基準① ~「現実的握持・監視」「機械・器具等による確保」を判例で解説~
占有が認められる判断基準② ~「包括的支配」などを判例で解説~
占有が認められる判断基準③ ~「現実的握持を離れて間がない」を判例で解説~
占有の帰属とは?① ~「財物が組織体(上位機関と下位機関)によって管理されている場合の占有」を判例で解説~
占有の帰属とは?② ~「財物の占有が移転するとき(委託・受託関係があるとき)」「梱包された荷物の占有」「客に提供された財物の占有」を判例などで解説~
死者の占有 ~「死者に占有は認められるのか」「死者の物を奪った場合、窃盗罪と占有離脱物横領罪のどちらが成立するのか」を判例などで解説~


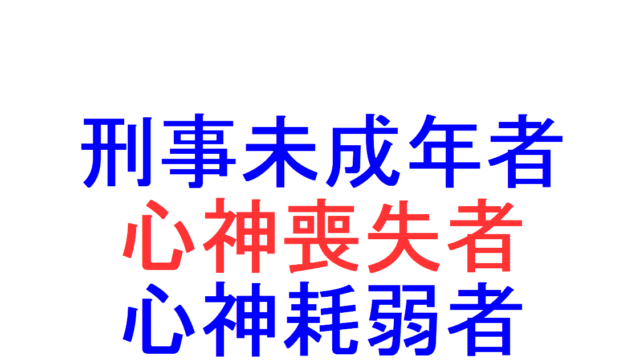


しても犯罪は成立する-640x360.png)

