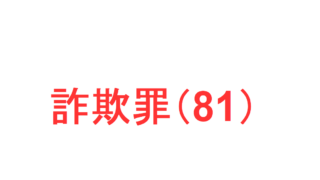詐取した財物を利用して、さらに財物を詐取した場合の詐欺罪の成立個数
詐取した財物を利用して、さらに財物を詐取した場合、2つの詐欺行為は、包括的に観察して1つの詐欺罪が成立する(言い換えると、詐欺罪は一罪となる・包括一罪となる)とした以下の判例があります。
一罪とされる場合
人を欺いて借用証書を詐取し、次いで、その証書に基づいて金員を交付させた事案で、判例は、包括的に観察して一罪として処断すべきで、後の金員取得を、前の証書詐取の結果の事後処分として不問に付すべきでないとしました。
大審院判決(明治44年6月13日)
この判例で、裁判官は、
と判示しました。
大審院判決(明治44年10月23日)
この判例で、裁判官は、
- 他人を欺罔して債権に関する公正証書を作成せしめ、これに基づき金員を騙取したる行為は、これを包括的に観察し、一罪をもって処断すべく、右金員騙取をもって、公正証書により得たる債権の結果なりとして、これを不問に付すべきものにあらず
と判示しました。
上記判例に対し、詐取した財物を利用して、さらに財物を詐取した場合、2つ(又は複数)の詐欺行為について、包括的に観察して1つの詐欺罪が成立するのではく、2つ(又は複数)の詐欺罪が成立するとした以下の判例があります。
数罪とされる場合
詐取した郵便貯金通帳を利用して、郵便局員を欺いて貯金を引き出した事案で、裁判官は、
- 騙取した郵便貯金通帳を利用して郵便局係員を欺罔し、真実名義人において貯金の払戻を請求するものと誤信せしめて貯金の払戻名義の下に金員を騙取することは、更に新法益を侵害する行為であるから、ここにまた犯罪の成立を認むべきであって、これをもって贓物(盗品等)の単なる事後処分と同視することはできないのである
- 然らば、原審が郵便貯金通帳を利用して預金を引出した行為に対し、詐欺罪をもって問擬(もんぎ)したことは正当である
と判示し、郵便通帳の詐取で1個の詐欺罪が成立し、その郵便通帳から現金を払い出した詐欺でさらにもう1個の詐欺罪が成立し、2つの詐欺罪は併合罪になるとしました。
米穀通帳を詐取し、これを配給所に提出して米穀を詐取した事案で、裁判官は、
- 騙取した米穀通帳を配給所へ提出して係員を欺罔して米穀を騙取することは、更に他の新法益を侵害する行為であるから、ここにまた犯罪の成立を認むべきこと理のまさに然るところであって、右の事実を目して、単に騙取した米穀通帳の事後処分たるに過ぎないと見るべきいわれはない
と判示し、米殻通帳の詐取で1個の詐欺罪が成立し、さらにその通帳を使って米を詐取した行為についてもう1個の詐欺罪が成立し、2つの詐欺罪は併合罪になるとしました。
Aから詐取した財物を貸金債権の担保としてBに差し入れた後、さらにBを欺いて財物の交付を受けた場合には、前の詐欺罪の被害法益とは別な新たな財産上の法益を侵害するとして、2個の詐欺罪が成立し、両罪は併合罪になるとしました。
裁判官は、
- 他人を欺罔して財物を騙取した後、他の第三者から金銭を借り受けるに際し、該貸金債権の担保に供するため、 右騙取した物件をその情を秘して貸主に交付する行為は、前の詐欺罪における贓物の処分行為として同罪のうちに包含され、新たに別罪を構成しないと解すべきことは、論を待たないところであるが、既に、右担保に供した後においては、該物件は、右貸金債権の担保物件として、貸主の占有に属するものであるから、更に、右貸主を欺罔して該物件の交付を受ける行為は、前の詐欺罪の被害法益とは別な新たな財産上の法益を侵害するものというべく、従って、前の詐欺罪とは別個に、新たな詐欺罪を構成するものと解するのが相当である
と判示しました。
偽造約束手形を交付して現金を詐取し、さらに別の偽造約束手形を交付して、前の偽造約束手形の支払を延期させた場合の詐欺罪の成立個数
偽造約束手形を交付して現金を詐取し、さらに別の偽造約束手形を交付して、前の偽造約束手形の支払を延期させた場合、2つの詐欺罪が成立するとしました。
偽造の約束手形を被害者に交付して受け取らせ、割引名下に金員を詐取した者が、その後、別の偽造約束手形を相手方に差し入れて、前の偽造の約束手形の支払を延期させた場合につき、前の金員詐取罪とは別個に詐欺利得罪(刑法246条2項の詐欺)が成立するとしました。
まず、被告人の弁護人は、
- 偽造約束手形によって現金を騙取したのちに、別の偽造約束手形を交付して前の約束手形の支払を延期させたのを前の騙取罪とは別に刑法第246条第2項の不法利得罪にあたるとしたのは罪とならない事実を有罪とした違法があるとし、その理由として、前の約束手形が偽造手形だとすればその振出は無効であり、手形所持人はいつでも裏書人に対し求債権を行使することができるわけであるから、支払期日の延期による利益なるものはありえず、その延期を承諾させても、なんら新たな利益も損害も生じないから、不法利得罪は成立しない
と主張しました。
この主張に対し、裁判官は、
- 刑法第246条第2項にいう「財産上の利益」は、法によって認められた権利ばかりでなく、事実上の経済的利益をも包含するものと解しなければならない
- そのことは、同条第1項が財物の交付を受けること、すなわち財物に対する事実上の支配を取得することによって詐欺罪が成立するとしていることと対応するのである
- ところで、原判示各約束手形は刑法上偽造されたものと解すべきことは前に説明したとおりであるが、刑法上の偽造と手形法上の偽造とはその範囲が必ずしも一致するとは限らず、したがって原判示各手形の振出行為の効力については、別に検討を要するところであるし、そのことを別としても、本件においては、当該約束手形に代えて新たな約束手形を差し入れ、その支払期日を延ばすことについて、G株式会社としては少なくとも経済上大きな利益を有していたとみなければならない
- すなわち、原判示各約束手形は原判示漁業組合を振出人として作成されたものであるが、これらはすべてG株式会社に金融を得させるための融通手形で、満期となれば当然同会社がその支払の責任を負担すべきものであり、現に同会社の責任において事実上その決済を行ないつつあったものである
- もし同会社がこれを怠れば、組合幹部に内密に行なっていたこれらの手形による金融の操作が直ちに発覚し、同会社に経済上の破局を来たすことは火を見るよりも明らかな状態にあったのであるから、同会社としては、原判示各約束手形の支払の時期が延長されることに至大の利益を有していたものである
- それゆえ、これらの約束手形の振出が手形法上有効であるかどうかにかかわらず、その支払いが延期されたことは、G株式会社にとってまさに刑法第246条第2項にいう「財産上の利益」にほかならず、この利益はもとの約束手形の割引による現金取得の利益とはまた別個のもので、しかも別個の新たな欺罔行為に基づくものであるから、原判決がこれを得た行為を同条項に該当するものとしたのはまことに正当で、論旨(弁護人の主張)は理由がない
と判示し、偽造手形を使って金員を詐取した行為で1個の詐欺罪が成立し、別の偽造約束手がを使って前の約束手形の支払を延期した行為で更にもう1個の詐欺罪が成立するとしました。
異なる被害者が複数いる場合の詐欺罪の成立個数
異なる被害者が複数いる場合、詐欺罪は、その被害者の数に応じた数だけ成立するとした以下の判例があります。
大審院判決(明治44年10月26日)
多数の応募者に対し、各別に人を欺く手段を施して、各人から加盟手数料及び醵金名下に金員を詐取した場合、各応募者の被害法益は個々独立で、これを包括的に観察して単一のものとみなすことができないから、応募者一人ごとに独立の詐欺罪が成立するとしました。
裁判官は、
- 詐欺の目的をもって、房総博愛会社なるものを設立し、多数応募者に対し、格別に詐欺手段を施し、よって各法益を侵害したる場合においては、各応募者の被害法益は、個々独立なるをもって、犯意の継続すると否とを問わず、応募者一人ごとに詐欺罪を構成すべきものとす
と判示しました。
虚偽誇大の広告宣伝と勧誘によって、被害者1348名を欺罔し、事務所等215か所やその他の場所において、出資金名目で、現金合計1億8343万7230円、株券5654枚(見積価格合計
3107万8200円)および投資信託証券301枚(見積価格合計838万2460円)を詐取した事実です。
被告人の弁護人は、この詐欺行為を
と主張しました。
この主張に対し、裁判官は、
- 犯罪の個数に関するいわゆる罪数論は、刑法上、併合罪の関係において、また刑事訴訟法上、判決の既判力、公訴不可分等の関係において、実益があり、重要な問題である
- 本件詐欺事犯は、いわゆる連続犯の規定(昭和22年法律124号によって削除された刑法55条)があった当時においては、当然「連続した数個の行為にして同一の罪名に触れる場合」として実質上数罪であるのにかかわらず、科刑上一罪として処断されるべき案件であるが、右連続犯の規定が削除されてなくなった現在において、当然、実質上の数罪として、刑法併合罪の規定によって処断すべきであるか、それともいわゆる包括的一罪という概念を適用し て、けつきょく一罪として処断すべきであるか、理論的解釈はきわめて困難なところである
- 連続犯の規定のあった当時においても、包括一罪の概念はあったが、それは、(一)犯罪の特別構成要件の内容たる行為が異種の行為を結合している場合 (例、強盗強姦罪、刑法241条)、(二)犯罪の特別構成要件たる行為がその性質上反復を予想せられる場合(例、常習賭博罪、刑法186条、わいせつ文書販売罪、刑法175条)、(三)犯罪の特別構成要件たる行為が同一法益侵害の諸種の態様を定めている場合(例、収賄罪の収受、要求、約束、刑法197条)等においてそれらの行為を一罪として取り扱う概念であって、明らかに連続犯として科刑上一罪とせられるものと区別された概念であった
- そして、右包括一罪の概念は、連続犯の規定の削除されたのちにおいても、当然に変ることのあるべきはずはなく、これを拡張すべき理論的根拠は見出されないのであるが、裁判の実務においては、右概念に含まれない連続犯的犯罪を包括一罪の名のもとに一罪として処断する傾向が生じていることは否定できない
- おそらくそれは、現行刑事訴訟法の下において、 犯罪個数の多い事件に関する捜査、公訴事実の訴因化、自白に関する補強証拠などすべての面について幾多の制約があるため、この種事犯を簡略処理するためその必要に迫られて生じた現象のようである
- それゆえに、それら判例の右包括一罪の理由づけにあたっては、講学上いわゆる、意思標準説、行為標準説、結果標準説、あるいは犯罪特別構成要件標準説等のそれぞれに基いてまちまちであり、統一的な理論的根拠は発見し得ないのである
- 連続犯の規定のなくなった現在において、連続犯的犯罪を常に必ず併合罪として処断すべきであるというのではなく、かかる犯罪を単に事務処理上の便宜のため包括一罪の概念を不当に拡張し、あたかも連続犯の規定の再現と同じように一罪として処断することは、他の犯罪との処断上の不均衡を伴い、社会通念ないし国民の法的感情からみても不合理といわざるを得ない結果が生ずることをおそれるのである
- しからば、連続犯的数個の犯罪を包括一罪として処断すべき要件をどう考うべきか甚だ困難を感ずるのであるが、前記学説または判例等を総合考察すると、その最少限度の要件として、(一)犯意が同一であるかまたは継続すること、(二)行為が同一犯罪の特別構成要件を一回ごと充足すること、(三)被害法益が同一性または単一性を有することの3つが必要であると解する
- はたして、この見解にして妥当であるとすれば、本件詐欺事犯は、犯意の継続性、行為の前記構成要件充足性は認められるが、全犯罪事実について被害法益の同一性または単一性を認めることはできないから(財産的被害法益でその数は多数であるが、同一被害者に対する数個の行為に限り被害法益の同一性ありとしてこれを包括一罪と認むべきである。)本件を包括一罪として処断することは許されないものといわなければならない
と判示し、被害者一人ごとに独立の複数の詐欺罪が成立するとしました。
福岡高裁宮崎支判決(昭和28年4月10日)
数人に対し、各別に人を欺く手段を施し、各別に財物を交付させれば、その交付の日時が近接し、場所が同一であり、その実害が同一人に帰する場合でも、各別に詐欺罪が成立し、併合罪となるとしました。
事案は、同一の飲食店において、女給Aを欺罔し、物品の交付を受け、次いで、その直後、女将Bを欺罔して財物を交付させたというものです。
裁判官は、
- 元来、詐欺罪は、他人を欺罔し、これを錯誤に陥れ、よって、財物を交付せしむれば成立するものである
- それで、もし、数人に対し、各別に欺罔手段を施し、これをそれぞれ錯誤に陥れ、よって、被欺罔者から格別に財物を交付せしむれば、その財物交付の日時が近接し、場所が同一であり、しかして、その実害が同一人に帰する場合でも、その犯意は単一ではないから、数罪が成立するものと解するのが相当である
- 被告人は、飲食店において、女給Aに対し、欺罔手段を施し、同女を錯誤に陥れ、よって、同女から物品の交付を受け、次いで、その直後、外出先から帰宅した女将Bに対し、虚構の事実を告げ、同女を錯誤に陥れ、よって、更に同女から物品の交付を受けたいきさつが窺い得られる
- 被告人の所為が、時間の近接した、同一飲食店内における階下、階上の一連の行為であり、その請求された代金が、右前後にわたる計算を一緒にしたものであったとしても、前説示するところにより、被告人の所為は、併合罪の関係にある2個の詐欺罪が成立するものといわざるを得ない
と判示しました。
2個の詐欺罪が牽連犯とされた判例
大審院判決(明治43年11月15)
株式売買の担保義務を免れるため、まずA銀行頭取名義の預金手形を偽造し、B銀行を欺き、B銀行がC銀行に対して有する預金をA銀行に振り替えさせた後(第一の詐欺罪)、A銀行頭取名義の小切手を偽造し、Dに交付して株式売買の証拠金に充て担保義務を免れた場合(第二の詐欺罪)、前の詐欺(第一の詐欺罪)は、偽造小切手を証拠金に代用して不法に利得を得た第二の詐欺罪の手段であるから、両者は牽連犯の関係に立つとしました。
裁判官は、
- 被告人が、株式売買の担保義務を不法に免除せんと企て、まずA銀行頭取名義の預金手形を偽造し、B銀行を欺き、同行がC銀行に対して有する預金をA銀行に振替へたる後、頭取名義の名義を冒して小切手を偽装し、これをD者い交付して売買の証拠金に代用したるときは、刑法第54条により一罪としてこれを処断せざるべからず
と判示しました。