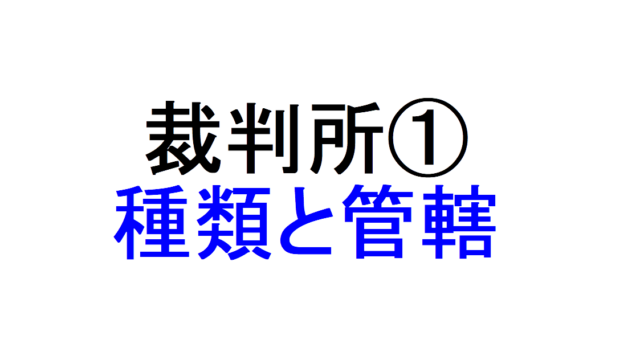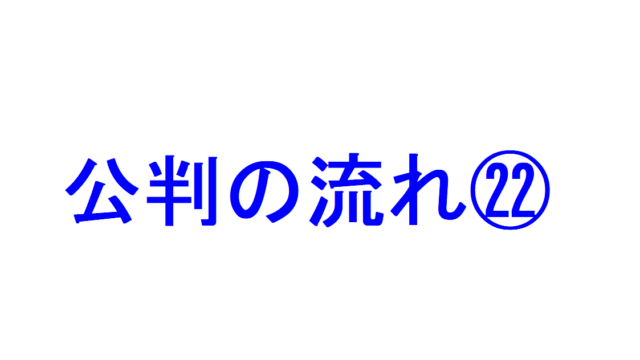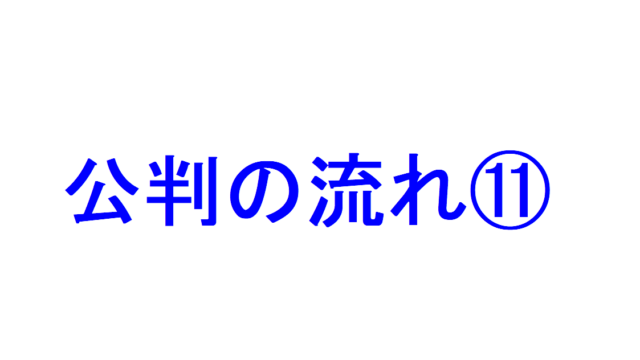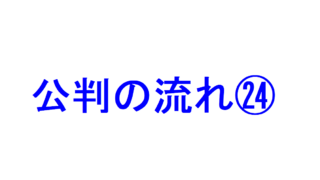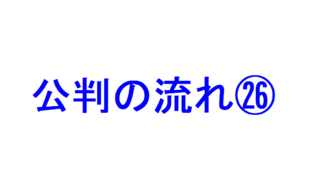公判の流れ㉕~「弁論の分離・併合・再開」「審判の併合」を説明
前回の記事の続きです。
弁論の分離・併合・再開とは?
裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により、又は職権で、決定をもって、弁論を分離、併合、再開することができる
と規定します。
刑訴法313条における「弁論」とは、「審理」や「公判手続」を意味します。
以下で、
- 弁論の分離
- 弁論の併合
- 弁論の再開
をそれぞれ説明します。
① 弁論の分離とは?
弁論の分離とは、
裁判所に起訴された数個の事件が併合され、1つの同じ裁判で審理されている状況において、数個の事件を分けて審理すること
をいいます。
例えば、被告人Aと被告人Bが共謀して窃盗罪を犯し、被告人Aに対する窃盗事件の裁判と、被告人Bに対する窃盗事件の裁判が併合されて1つの同じ裁判で審理されていたところ、被告人Aに対する窃盗事件の裁判と、被告人Bに対する窃盗事件の裁判を分けて、別々の裁判にすることを弁論の分離といいます。
弁論の分離は、
- 同一手続で審理を受けている数人の被告人(これを「共同被告人」といいます)の利益が相反しているため、利益の相反する被告人の審理を分離して、別々に審理する必要がある場合
- 共同被告人の一人が公訴事実を認め、証拠も全部同意し(刑訴法326条)、早期の裁判の終結を希望しているため、争っている共同被告人の審理と分離して審理する必要がある場合
- 共同被告人の1人を他の被告人の関係で証人として尋問する場合
などに行われます。
弁論を分離する状況の具体例を説明します。
例えば、互いに共犯者である暴力団組長の被告人Aと、暴力団組員の被告人Bが1つの同じ裁判を受ける状況であった場合に、暴力団組員の被告人Bは、暴力団組長の被告人Aをおそれて、法廷で真実の話ができない場合があります。
そのような場合には、事件の真相究明が阻害されたり、訴訟が遅延したりする場合があるので、裁判所は、弁論を分離する決定をし、被告人Aと被告人Bの審理を分けることをします。
そうすることで、暴力団組員の被告人Bは、暴力団組長の被告人Aがいない法廷で裁判を受けることができるようになり、法廷で真実の話ができるようになります。
弁論の分離が必須となる場合
刑訴法313条2項、刑訴法規則210条において、弁論の分離をしなければならない場合が定められており、
共同被告人の防御が互いに相反するなどして、被告人の権利を保護する必要があるときは、裁判所は、検察官・被告人若しくは弁護人の請求により、又は職権で、決定をもって弁論を分離しなけれはならない
とされます。
裁判員裁判における弁論の分離
裁判員裁判においては、裁判員の負担に関する事情を考慮し、特に必要があると認められるときは、併合事件の一部を1又は2以上の被告事件ごとに区分し、順次審理する「区分審理」によることができます(裁判員法71条1項)。
区分審理も弁論の分離の一種です。
※ 区分審理の詳しい説明は前の記事参照
② 弁論の併合とは?
弁論の併合とは、
数個の事件を同一手続で同時に審理すること
をいいます(弁論の分離の逆です)(刑訴法313条1項)。
弁論の併合は、一般的に、「併合審理」と呼ばれます。
弁論の併合は、事件が数個ある場合で、これを同時に審理した方が真相の究明、刑責の確定、量刑の統一、訴訟経済などに便宜である場合に行われます。
例えば、被告人Aが3個の窃盗罪を犯した場合で、その3個の窃盗罪が同じ裁判所に起訴された場合、3個の窃盗罪をそれぞれ1個ずつ別々の裁判(合計3つの裁判)で審理したのでは、量刑が統一されなかったり、訴訟経済が不経済となります。
なので、このような場合、弁論が併合され、3つの窃盗罪を1つの裁判で審理することになります。
審判の併合
弁論が併合されるのは、上記の刑訴法313条1項の「弁論の併合」による場合のほか、「審判の併合」による場合があります。
「審判の併合」は、主に、
1⃣ 刑訴法8条による「審判の併合」
2⃣ 刑訴法5条1項による「審判の併合」
を押さえておくとよいです。
1⃣ 刑訴法8条による「審判の併合」の説明
刑訴法313条1項の「弁論の併合」は、
数個の事件が同じ裁判所に起訴され、同じ裁判所内に別々に係属している事件を一つの裁判に併合する場合の措置
です。
例えば、A地方裁判所に係属している2つの窃盗事件を、A地方裁判所で行う一つの裁判に併合する場合です。
これに対し、刑訴法8条の「審判の併合」は、
数個の関連事件(刑訴法9条)が、事物管轄を同じくする数個の裁判所に別々に係属している事件を一つの裁判に併合する場合の措置
です。
例えば、A地方裁判所に係属している一つの窃盗事件と、B地方裁判所に係属している一つの窃盗事件をA地方裁判所で行う一つの裁判に併合する場合です。
審判の併合は、事物管轄を同じくする裁判所であることが条件なので、例えばA地方裁判所の窃盗事件とB簡易裁判所の窃盗事件を併合することはできません。
なお、刑訴法313条1項の「弁論の併合」は、もともと同一の裁判所に数個の事件が係属している場合に、これを併合するものなので、刑訴法8条の「審判の併合」の場合とは異なり、その数個の事件が刑訴法9条の「関連事件」である必要はないという違いもあります。
2⃣ 刑訴法5条1項による「審判の併合」の説明
刑訴法5条1項による「審判の併合」は、
A地方裁判所(上級裁判所)が、A簡易裁判所(下級裁判所)にある関連事件の裁判をA地方裁判所の裁判に併合して、A地方裁判所において一緒に審理する措置
をいいます。
例えば、A地方裁判所には被告人Xの詐欺事件が起訴されて公判中であり、A簡易裁判所には被告人Xの窃盗事件が起訴されて公判中であった場合、同一の被告人の事件であり公判を一つにまとめて審理すべきなので、A地方裁判所は、刑訴法5条1項による審判の併合決定を行い、A簡易裁判所の事件をA地方裁判所に併合することを行います。
刑訴法5条1項の条文である
「数個の関連事件が各別に上級の裁判所及び下級の裁判所に係属するときは、事物管轄にかかわらず、上級の裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる」
の意味について、
「地方裁判所は、簡易裁判所の固有の事物管轄にかかわらず、簡易裁判の事件を併せて審判することができる」
という意味で捉えればよいです。
つまり、刑訴法5条1項による審判の併合を行うことで、地方裁判所は簡易裁判所の専属管轄の事件であって審判をすることができます(刑訴法3条1項も参照)。
また、刑訴法5条1項は、複数の事件がいずれも第一審に属している場合に関する規定であり、上級の裁判所に控訴審事件が係属し、下級の裁判所に第一審事件が係属している場合には適用がありません(最高裁判決 昭和27年3月4日参照)。
審判の併合決定は、上級の裁判所が職権により決定をもって行います。
そして、この決定に対しては抗告をすることはできません(刑訴法420条1項)。
③ 弁論の再開とは?
弁論の再開とは、
一旦終結(結審)した弁論(審理、公判手続)を再び開くこと
をいいます。
「結審する」とは、公判手続が検察官の論告・弁護人の弁論・被告人の最終陳述まで終了し、最後に判決宣告を残すのみになった状態をいいます。
結審した後に、公判手続を追加で行いたいという場合が起こり得ます。
そのような場合に、弁論の再開がなされます。
例えば、
- 裁判所が事実認定や量刑の判断をする上で、更に証拠調べを必要とした場合
- 検察官において訴因変更の請求をする必要が生じた場合
- 被告人又は弁護人において被害弁償・示談立証をする必要が生じた場合
などに弁論の再開が行われます。
弁論が再開されると、手続は結審前の状態に戻ります。
そのため、証拠調べ終了後、もう一度、検察官の論告・弁護人の弁論・被告人の最終陳述が行われることになります。
次回の記事に続く
次回の記事では、
公判手続の停止
を説明します。