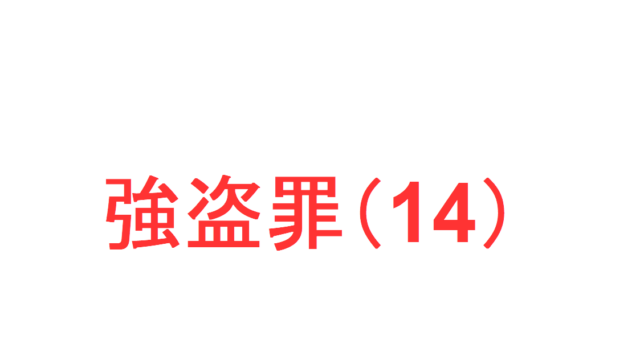前回記事の続きです。
暴行・脅迫により、現実に被害者が反抗を抑圧されていなくても強盗罪は成立する
強盗罪の成立を認めるに当たり、暴行・脅迫は、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることを要しますが、それによって、現実に被害者が反抗を抑圧される必要はありません。
この点について、以下の判例があります。
包丁を突き付け、「五千円を借せ」と申向けて脅迫し、金銭を強取しようとしたが、被害者が意思活動の自由を失わず、これに応じなかったため、目的を遂げなかったという強盗未遂の事案で、裁判官は、
- 被告人の脅迫の所為たるや、相手方たるAの意思の自由を抑圧するに足るものであったことが明かであるから、Aがたまたま被告人の要求に応ぜず、従って意思の自由を抑圧されなかったとしても、被告人の所為は強盗罪の実行をもって目さなければならない
と判示し、現実に相手が反抗を抑圧されていなくても、強盗罪(未遂)が成立するとしました。
この判例で、裁判官は、
- 強盗罪の成立には、被告人が社会通念上、被害者の反抗を抑圧するに足る暴行又は脅迫を加え、それによって被害者から財物を強取した事実が存すれば足りるのであって、被害者が、被告人の暴行脅迫によって、その精神及び身体の自由を完全に制圧されることを必要としない
- 被告人らが、草刈鎌やナイフを被害者に突き付け、「静にしろ」「金を出せ」等言って脅迫し、被害者を畏怖させ、その所有の現金3170円、腕時計、懐中時計、ライター等40点を強奪しと判示して、被告人らが、社会通念上被害者の反抗を抑圧するに足る脅迫を加え、これによって被害者が畏怖した事実をも明に説示して、手段たる脅迫と財物の強取との間に因果関係の存することをも認定しているから、これに対し、刑法第249条(恐喝罪)を適用せずに、刑法第236条第1項(強盗罪)を適用したのは正当である
と判示し、被害者が、被告人の暴行脅迫によって、その精神及び身体の自由を完全に制圧されなくても、強盗罪が成立するとしました。
広島高裁判決(昭和26年1月13日)
この判例で、裁判官は、
- 刑法第238条にいう暴行脅迫とは、相手方の反抗を抑圧する程度のものであることを要する
- その程度は、反抗を抑圧する手段として、一般的客観的に可能と認められる程度のものであれば足り、いかなる場合にも現実的に反抗を抑圧し得るものであること、又は現実的に反抗を抑圧したか否かは必要ではない
- 而して、被告人が逮捕を免れるため、Tの顔面を手挙で数回殴打し、よって治療約10日間を要する左上下門歯左上大歯が可動性となる程の口唇打撲傷を負わしめたことを認めることができ、その如き程度の暴行は、一般的観察上、Tの逮捕行為の遂行を抑圧する手段として功を奏する可能性があるものといはなければならぬ
- 従って、原審が、これに対し、刑法第238条を適用し、同法第240条前段をもって問擬したのは相当である
と判示しました。
仙台高裁判決(昭和40年2月19日)
この判例で、裁判官は、
- 強盗罪の成立に必要な暴行または脅迫は、犯行の時刻、場所その他の周囲の情況や被害者の年齢、性別その他、精神上、体力上の関係、犯人の態度、犯行の方法などを客観的に観察し、その暴行または脅迫が社会通念上、一般に被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものであるかどうかという客観的標準によって決定すべきものである
- 具体的事案における被害者の主観を基準として決すべきものでないことはもとより、被害者が犯人の暴行または脅迫により、その精神および身体の自由を完全に制圧されたことを必要としないものと解すべきである
と判示しました。
暴行・脅迫により、被害者が反抗を抑圧されていなくても、財物奪取との間に因果関係のあれば、強盗罪が成立する
被害者の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫があれば、それと財物奪取との間に因果関係のある限り、被害者が単に畏怖したにとどまったとしても、また、被害者自ら財物を交付したとしても、恐喝罪ではなく強盗罪が成立します。
この点について、以下の判例があります。
この判例で、裁判官は、
- 犯人によってなされた暴行又は脅迫が、社会通念上、相手方の反抗を抑圧する程度のものであって、右暴行又は脅迫と財物の奪取との間に因果関係がある以上は、被害者自身は、単に畏怖されたにとどまってたとしても、また被害者自ら財物を交付したとしても、強盗罪が成立するものであって、恐喝罪とはならない
と判示しました。
脅迫をした行為者が、現実にその脅迫どおりの実行をし得たかどうかは問わない
強盗罪の成立を認めるに当たり、脅迫をした行為者が、現実にその脅迫どおりの実行をし得たかどうかは問いません。
この点について、以下の判例があります。
大審院判決(明治43年4月22日)
所持していない刀を所持しているように装って、「抜くぞ、抜くぞ」と脅迫した事案で、裁判官は、
- 刑法第236条(強盗罪)・第238条(事後強盗罪)の脅迫手段としては、他人を畏怖せしむべき害悪の通知あるのみをもって足り、加害者が現実その通知したる害悪を加える能力を具有したるや否やは、脅迫手段の成立に何らの影響を及ぼすことなし
と判示しました。
もっとも、周囲の客観事情から、明らかに虚偽の脅しと分かる場合や、玩具の拳銃であることが一見して明白な場合は、反抗の抑圧があるといえません。
参考となる判例として、以下のものがあります。
大阪高裁判決(昭和32年3月22日)
この判例は、本物のナイフと玩具のピストルを用いて強盗を実行した事案で、ピストルについては、すぐに玩具と看破したものの、ナイフには畏怖したことを理由として、強盗罪の成立を認めました。