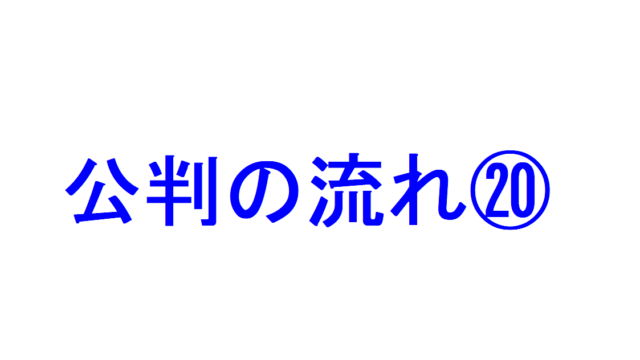訴因変更④~「訴因変更の要否の判断基準(被告人の防御に実質的な不利益が生じるかどうか)」を説明
前回の記事の続きです。
訴因変更の要否の判断基準(被告人の防御に実質的な不利益が生じるかどうか)
検察官に訴因を掲げさせるのは、審判の対象・範囲を明確にさせ、 被告人の防御に不利益を与えないようにするためです。
その結果、裁判所は、検察官の掲げた訴因に拘束されることになります。
公訴事実の同一性の範囲内にある事実であっても、訴因と異なる事実を認定することは許されないルールになっています。
裁判所は訴因に拘束されることから、訴因以外の犯罪事実を認定するには、訴因変更の手続が必要となります。
しかしながら、検察官の掲げた訴因と裁判所の認定しようとする事実とが食い違う場合でも、常に訴因変更を要するとすべき必要はなく、訴因変更をしなくても訴因と異なる事実を認定し得る場合があります(この場合を「訴因の同一性」がある場合といいます)。
訴因変更をしなくても訴因と異なる事実を認定できるか否かの判断基準(訴因の同一性の判断基準)は、
訴因の事実と裁判所の認定する事実との間に差異があるときであっても、被告人の防御に実質的な不利益を生じないものである場合には、訴因の変更を必要としない
という考え方が判断の基準になります。
被告人の防御に不利益がない場合は訴因変更を要しない
上記の「訴因の事実と裁判所の認定する事実との間に差異があるときであっても、被告人の防御に実質的な不利益を生じないものである場合には、訴因の変更を必要としない」ということの意味は、
被告人の防御に実質的な不利益を生じないのであれば、訴因の事実と裁判所の認定する事実との間に差異があっても、訴因変更をせずに裁判所が判決を言い渡しても問題がない
ということを意味します。
判例の立場は、事実の差異が犯罪の構成要件に変化を生じる場合は、被告人の防御に影響を及ぼすから、原則として訴因変更を要するが、裁判所の認定する事実が訴因の中に含まれている場合、例えば、傷害の訴因に対し、暴行の事実を認定するなど訴因を縮小的に認定する場合には、被告人の防御に不利益を生じないから、訴因の変更を要しないとします。
また、犯罪構成要件には変更がないものの、犯罪の日時・場所・被害金額などが変わる場合は、それがわずかの相違であって被告人の防御に不利益を生じないときは、訴因変更は必要としないとします。
しかし、犯行手段の大幅な違い、被害品・被害金額の大幅な増加のように、重要な事実が変わり、被告人の防御に不利益を生じる場合は、訴因変更を要するとします。
判例
判例は、訴因変更の要否の基準については、主として、訴因の事実と裁判所が認定する事実との差異が「被告人の防御に実質的不利益を生じるおそれ」のあるものであるかどうかによって判断しています。
見方を変えていうと、訴因の事実の裁判所が認定する事実の差異が、犯罪の構成要件に変化を生じる場合は、被告人の防御に影響を及ぼすから、原則として訴因変更を要することになります。
参考となる判例として以下のものがあります。
検察官が「強制わいせつ」(刑法176条、現行法:不同意わいせつ)の訴因で起訴した事件につき、裁判官が「公然わいせつ」(刑法174条)の事実を認定して判決を言い渡した事案です。
裁判所は、
- 審判の請求を受けない事件について判決をした違法がある
と判示しました。
このことから「強制わいせつ」の訴因を裁判官が「公然わいせつ」で認定する場合は、訴因変更の手続を要します。
検察官が「単純収賄」(刑法197条前段)の訴因で起訴した事件につき、裁判所が「請託収賄」(刑法197条後段)の事実を認定して判決を言い渡した事案です。
裁判所は、
- 本件起訴状記載の訴因はいわゆる単純収賄であるにかかわらず、第一審判決は、訴因変更の手続をふまず、いわゆる請託収賄と認定をしたことは所論の指摘(※弁護人の指摘)するとおりである
- このような場合、訴因変更の手続を定めた刑訴法の趣旨からいって、第一審がその手続をとらないで判決したことは違法たるを免れない
と判示しました。
このことから「単純収賄」の訴因を裁判官が「請託収賄」で認定する場合は、訴因変更の手続を要します。
「特別背任」(刑法247条)の訴因に対し、裁判官が「業務上横領」(刑法253条)の事実を認定して判決を言い渡した事案です。
裁判所は、
- 一審で当初起訴にかかる業務上横領の訴因につき被告人に防禦の機会が与えられていたとしても、既に特別背任の訴因に変更されている以上、事後における被告人側の防御は専ら特別背任の訴因についてなされていたものとみるべきであるから、これを再び業務上横領と認定するためには、更に訴因罰条の変更ないし追加手続をとり、改めて業務上横領の訴因につき防御の機会を与える必要があるといわなければならない
と判示しました。
このことから「特別背任」の訴因を裁判官が「業務上横領」で認定する場合は、訴因変更の手続を要します。
検察官が「収賄」(刑法197条)の共同正犯(共犯)の訴因で起訴した事件につき、裁判官が「贈賄」(刑法198条)の共同正犯の事実を認定して判決を言い渡した事案です。
裁判官は、
- 本件起訴状記載の訴因は、被告人がa町町長Aと共謀の上、A町長の職務に関し、2回にわたって賄賂金合計60万円を収受したという収賄の事実である
- しかるに、原判決(※控訴審の判決)は、第一審判決が公訴事実を収賄と認定したことが事実の誤認であるとして、これを破棄自判するに当たり、訴因罰条の変更手続をふまず、…原判決認定の事実は、被告人がDと共謀の上、a町町長Aに対し、A町長の職務に関し、2回にわたって賄賂金合計60万円を供与したという贈賄の事実である
- ところで、本件公訴事実(※収賄罪の公訴事実)と原判決認定の事実(※贈賄罪の事実)とは、基本的事実関係においては、同一であると認められるけれども、もともと収賄と贈賄とは、犯罪構成要件を異にするばかりでなく、一方は賄賂の収受であり、他方は賄賂の供与で
- あって、行為の態様が全く相反する犯罪であるから、収賄の犯行に加功したという訴因に対し、訴因罰条の変更手続をふまずに、贈賄の犯行に加功したという事実を認定することは、被告人に不当な不意打ちを加え、その防御に実質的な不利益を与えるおそれがあるといわなければならない
- 従って、本件の場合に、原審が訴因罰条の変更手続をふまずに、右のような判決(※収賄の事実の判決)をしたことは、その訴訟手続が違法であることを免れない
と判示しました。
このことから「収賄」の訴因を裁判官が「贈賄」で認定する場合は、訴因変更の手続を要します。
仙台高裁判決(昭和30年5月24日)
検察官が「重過失傷害」(刑法211条後段)の訴因で起訴した事件につき、裁判官が「業務上過失傷害」(刑法211条前段)の事実を認定して判決を言い渡した事案です。
裁判官は、
- 重過失傷害と業務上過失傷害とは、その犯罪構成要件を異にし、かつ前者に対する被告人の防御は当然に後者に対するそれを包含するものとは解されないから訴因の変更又は追加の手続なくして重過失傷害の公訴事実を業務上過失傷害と変更して認定することは許されないものである
と判示しました。
このことから「重過失傷害」の訴因を裁判官が「業務上過失傷害」で認定する場合は、訴因変更の手続を要します。
裁判所が訴因を縮小認定する場合は、被告人の防御に不利益を生じることがないから、訴因の変更を要しない
事実の差異が犯罪の構成要件に変化をもたらす場合であっても、裁判所の認定する事実が検察官の掲げた訴因の中に含まれている場合、言い換えると、
訴因を縮小的に認定する場合
には、
被告人の防御に不利益を生じることがない
ため、訴因の変更を要しません。
判例
検察官が「強盗」(刑法236条)の訴因で起訴した事件につき、裁判所が「恐喝」((刑法249条))の事実を認定して判決を言い渡した事案です。
裁判所は、
- 元来、訴因又は罰条の変更につき、一定の手続が要請されるゆえんは、裁判所が勝手に、訴因又は罰条を異にした事実を認定することによって、被告人に不当な不意打ちを加え、その防御権の行使を徒労に終わらしめることを防止するにあるから、かかるおそれのない場合、例えば、強盗の起訴に対し恐喝を認定する場合の如く、裁判所がその態様及び限度において訴因たる事実よりもいわば縮少された事実を認定するについては、敢えて訴因罰条の変更手続を経る必要がないものと解するのが相当である
と判示しました。
このことから「強盗」の訴因を裁判官が「恐喝」で認定する場合は、訴因変更の手続がなくても問題はありません。
最高裁判決(昭和35年12月13日)
検察官が「加重収賄」(刑法197条の3第1項・2項)の訴因で起訴した事件につき、裁判所が「単純収賄」(刑法197条)の事実を認定して判決を言い渡した事案です。
裁判所は、
- 公訴事実の同一性を害せず、かつ、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがない場合には、訴因の追加変更の手続を経ずして訴因と異る事実を認定しても違法でないことは当裁判所の判例とするところである
- これを本件について見るに、被告人は第一審第一回公判で本件金5万円を収受したことは認めたが、その趣旨を否認し儀礼的なものであったと弁解しており、その趣旨がいかなるものであったかについては、攻撃防御の方法が尽くされていると認められるばかりでなく、本件では起訴事実よりも縮少された軽い事実が認定されているのであるから、本件の如き認定が被告人の防御に実質的な不利益を生ぜしめるおそれがあったとはいえない
- 判決の認定事実が起訴事実と同一性のあるものであることは多言を要しない
と判示しました。
このことから「加重収賄」の訴因を裁判官が「単純収賄」で認定する場合は、訴因変更の手続がなくても問題はありません。
検察官が「殺人」(刑法199条)の訴因で起訴した事件につき、裁判所が「同意殺人」(刑法202条)の事実を認定して判決を言い渡した事案です。
裁判所は、
- 殺人の起訴に対し刑法38条2項を適用し同意殺人の責任を認めたからといって訴因、罰条の変更を必要とするものでないことは明らかである
と判示しました。
このことから「殺人」の訴因を裁判官が「同意殺人」で認定する場合は、訴因変更の手続がなくても問題はありません。
検察官が「殺人未遂」(刑法199条、203条)の訴因で起訴した事件につき、裁判所が「傷害」(刑法204条)の事実を認定して判決を言い渡した事案です。
裁判所は、
- 殺人未遂の起訴に対して訴因罰条の変更手続を経ないで傷害を認定することを是認した原審判断は正当である
旨判示しました。
このことから「殺人未遂」の訴因を裁判官が「傷害」で認定する場合は、訴因変更の手続がなくても問題はありません。
検察官が「業務上過失致死」(刑法211条前段)の訴因で起訴した事件につき、裁判所が「重過失致死」(刑法211条後段)の事実を認定して判決を言い渡した事案です。
裁判所は、
- 業務上過失致死の訴因に対し、訴因罰条の変更の手続を経ないで重過失致死罪を認定した一審判決を是認した原審の判断は正当である
と判示しました。
このことから「業務上過失致死」の訴因を裁判官が「重過失致死」で認定する場合は、訴因変更の手続がなくても問題はありません。
検察官が「強盗殺人の共同正犯(共犯)」(刑法199条)の訴因で起訴した事件につき、裁判官が「殺人の幇助」(刑法199条、62条)の事実を認定して判決を言い渡した事案です。
裁判所は、
- 当裁判所の判例(昭和29年1月21日判決)によれば、訴因は審判の対象を明確にして被告人の防御に不利益を与えないためであるから、被告人が幇助の主張をしているようなときに共同正犯の訴因で幇助を認定するのは妨げない旨判示しており、また共同正犯の訴因で幇助を認めても妨げない旨の判示(昭和28年3月5日決定)もあるのである
- 本件犯罪の外形的事実は全く同一であって、これについてどの程度の犯意があったと認定するかによって、強盗殺人の共同正犯ともなり、殺人の幇助ともなる事案である
- そして原審の認定(※殺人の幇助の認定)は、訴因よりもはるかに被告人に有利でありその防御を害したものとは認められないのである
と判示しました。
このことから「強盗殺人の共同正犯」の訴因を裁判官が「殺人の幇助」で認定する場合は、訴因変更の手続がなくても問題はありません。
最高裁決定(昭和30年10月19日)
検察官が「傷害」(刑法204条)の訴因で起訴した事件につき、裁判所が「暴行」(刑法208条)の事実を認定して判決を言い渡した事案です。
裁判所は、
- 「被告人両名は、共同して被害者の足を蹴り、顔面を殴打して同人に治療1週間を要する左眉毛部裂創並びに上下眼瞼皮下溢血腫脹の傷害を与えた」との公訴事実に対し、訴因変更手続を経ることなく「被告人は被害者の腰部を下駄ばきの足で蹴上げ、もって暴行した」との事実を認定することは違法でない
としました。
このことから「傷害」の訴因を裁判官が「暴行」で認定する場合は、訴因変更の手続がなくても問題はありません。
検察官が「酒酔い運転」(道交法117条の2第1号、道交法65条)の訴因で起訴した事件につき、裁判所が「酒気帯ひ運転」(道交法117条の2の2第1項3号、道交法65条)の事実を認定して判決を言い渡した事案で、裁判官は、
- 酒酔い運転も酒気帯び運転も基本的には道路交通法65条1項違反の行為である点で共通し、前者(※酒酔い運転)に対する被告人の防御は、通常の場合、後者(※酒気帯び運転)のそれを包含し、もとよりその法定刑も後者(※酒気帯び運転)は前者(※酒酔い運転)より軽い
- しかも本件においては運転開始前の飲酒量、飲酒の状況等ひいて運転当時の身体内のアルコール保有量の点につき被告人の防御は尽されていることが記録上明らかであるから、前者(※酒酔い運転)の訴因に対し、原判決が訴因変更の手続を経ずに後者(※酒気帯び運転)の罪を認定したからといって、これにより被告人の実質的防御権を不当に制限したものとは認められない
と判示しました。
このことから「酒酔い運転」の訴因を裁判官が「酒気帯ひ運転」で認定する場合は、訴因変更の手続がなくても問題はありません。
訴因を拡張的に認定する場合には、訴因変更を要する
上記のとおり、訴因の縮小的に認定する場合は、被告人の防御に不利益を生じることがないから、訴因変更を要しません。
しかし、被告人の訴因を拡張的に認定する場合には、被告人の防御に不利益を生じるおしれがあるので、訴因変更を要します。
参考となる判例として以下のものがあります。
法人税の脱税事件において、第一審判決が、検察官の主張しなかった仮払金・貸付金を新たに認定し、検察官の主張した借入金を削除して認定したことは違法であるとした事案です。
裁判所は、
- 第一審判決は、本件逋脱所得の内容として、検察官の主張しなかった仮払金175万円、貸付金5万円を新たに認定し、また、検察官の主張した借入金75万円を削除して認定しており、原判決は、訴因変更手続を経由することなく右のごとく認定した第一審判決が違法であるとはいえないと判示しているが、かような認定は、被告人側の防御に実質的な不利益を与えることもありうるのであるから、訴因変更の手続を要する
と判示しました。
犯行の手段・日時・場所・被害金額が変わる場合の訴因変更の要否
犯罪構成要件には変更がなく、犯行の手段・日時・場所・被害金額などが変わる場合は、それが
わずかの相違であって被告人の防御に不利益を生じない場合
は、訴因変更は必要としません。
しかし、犯行手段の大幅な違い、日時の大きなずれ、被害品・被害金額の大幅な増加のように、
重要な事実が変わり、被告人の防御に不利益を生じる場合
は、訴因変更が必要となります。
参考となる判例として以下のものがあります。
現住建造物等放火被告事件につき、「ガスコンロの点火スイッチを作動させて点火し、台所に充満したガスに引火、爆発させた。」との検察官の掲げた訴因に対し、訴因変更手続を経ることなく、「何らかの方法により上記ガスに引火、爆発させた。」と裁判所が事実を認定ことは、引火、爆発の原因が上記スイッチの作動以外の行為であるとした場合の被告人の刑事責任について検察官の予備的な主張がなく、そのような行為に関し求釈明や証拠調べにおける発問等もされていなかったなどの審理経過の下では、被告人に不意打ちを与えるものとして違法であるとしました。
次回の記事に続く
次回の記事では、
過失犯における訴因変更の判断基準
を説明します。