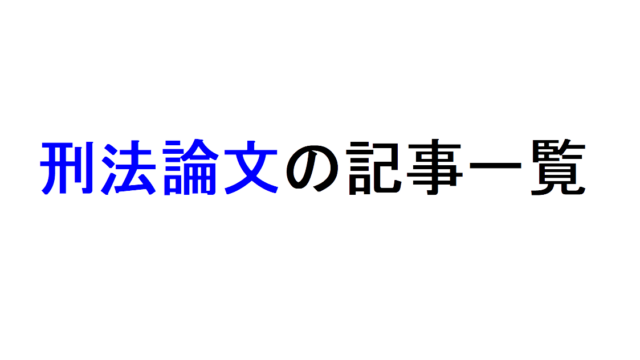刑法論文(6)~令和2年司法試験の刑法論文問題から学ぶ~
令和2年司法試験の刑法論文問題から学ぶ
令和2年司法試験の刑法論文問題の答案を作成してみました。
この論文からは以下のテーマが学べます。
5⃣ 刑法総論
因果関係、故意、占有(口座名義人は預金口座に預け入れた金銭に対する占有を有する)、事実の錯誤、因果関係の錯誤
問題
以下の【事例1】及び【事例2】を読んで、後記〔設問1〕から〔設問3〕について、答えなさい。
【事例1】
1⃣ AはBに対し、個人的に500万円を貸していた(この貸金債権を以下「本件債権」という。)。本件債権に係る弁済期限は到来していたが、BがAからの返済の督促に応じず、また、A自身忙しかったことから、Aは、知人の甲に本件債権の回収を依頼しようとして、甲に対し、「御礼はするから代わりにBから500万円を回収してきてくれないか。あんたに回収を頼むことは、Bには電話で伝えておく。」と申し向けた。甲は、その依頼を承諾し、Bの電話番号をAから教えてもらった。甲は、金融業者Cに多額の借金があったところ、上記依頼を受けた後、Cから、その返済を督促されたため、Bに対して、債権額についてうそをつくなどして水増しした額を請求し、その差額で少しでもCに対する自己の債務を弁済しようと考えた。
2⃣ 甲は、某月1日、Bに電話を掛け、Bに対し、自身が暴力団組員ではないのにそうであるかのように装い、「Aから債権の取立てを頼まれた。債権は600万円だとAから聞いている。その金を指定する口座に入金しろ。金を返さないのであれば、うちの組の若い者をあんたの家に行かせることになる。」などと言った。Bは、事前にAからの電話で本件債権の回収を甲に依頼したと聞いていたが、その額は500万円だと認識していた。しかし、Bは、甲が暴力団組員であると誤信し、甲の要求に応じなければ自身やその家族に危害を加えられるのでないかと畏怖した結果、甲に600万円を交付することとし、甲に対し、「分かりました。明日送金します。」と答えた。Bは、翌2日、自己名義の預金口座から甲の指定に係るD銀行E支店に開設された甲名義の預金口座(預金残高0円)に600万円を送金し、その結果、同口座の預金残高が600万円になった。
〔設問1〕
以下の①及び②の双方に言及した上で、【事例1】における甲のBに対する罪責について、論じなさい(特別法違反の点は除く。また、本件債権に係る利息及び遅延損害金については考慮する必要はない。)。
① 甲に成立する財産犯の被害額が600万円になるとの立場からは、どのような説明が考えられるか。
② 甲に成立する財産犯の被害額が100万円にとどまるとの立場からは、どのような説明が考えられるか。
【事例2】
(【事例1】の事実に続けて、以下の事実があったものとする。)
3⃣ 甲は、同日、前記口座にBから600万円の入金があったことを確認した。甲は、Cからの督促が予想以上に厳しいことから、600万円全額をCに対する弁済に充てようと決意し、同日中に、D銀行E支店の窓口係員Fに対して、同口座から600万円の払戻しを請求し、Fから同額の払戻しを受けた。甲は、同日、Cに対し、上記600万円を交付して自己の債務を弁済した。
甲は、同日、Aに対し、「昨日、Bに対して返済するようにきつく言った。Bは、反省した様子で『今度こそは必ず返す。返済を10日間だけ待ってほしい。』と言っていた。」などとうそをつき、それを信用したAは、「しょうがないな。あと少しだけ待ってやるか。」などと言い、同月11日まで、本件債権の回収状況に関して、甲に確認することはなかった。なお、本件債権について、その存在を証明する資料はなく、A、B及び甲以外に知っている者はいなかった。
4⃣ その後、同月12日になっても、甲からAに連絡がなかったため、Aが甲を追及したところ、甲は、本件債権に係るBからの返済金を自己の債務の弁済に充てたことを打ち明けた。これに憤慨したAは、甲に対して、直ちに500万円を返還するように厳しく申し向けた。その後、甲は、金策に努めたものの、返還に充てる金を工面できなかったことから、Aに相続人がいないことを奇貨として、その返還を免れる目的で、Aを殺害しようと決意した。
5⃣ 甲は、Aを殺害するため、その方法についてインターネットで調べたところ、市販されているX剤及びY剤を混合すると、致死性のある有毒ガスが発生することが分かった。そこで、甲は、以前に自身が病院で処方されていた睡眠薬をAに飲ませてAを眠らせた上で、当該有毒ガスを用いて自殺に見せ掛けてAを殺害することを計画した。甲の計画は、具体的には、犯行に必要な道具を全て自車に積み込んで、A方に隣接する駐車場まで自車で移動して同所に駐車し、A方に行き、ワインに混ぜた睡眠薬をAに飲ませてAを眠らせた後、直ちに自車に戻って車内に置いておいたX剤等を取った上で、再度A方に赴いて有毒ガスを発生させ、これをAに吸入させてAを殺害するというものであった。甲は、同月16日、ホームセンターでX剤及びY剤のほか、これらを混ぜるためのバケツを購入した。
6⃣ 甲は、前記計画を実行するため、翌17日、Aに電話を掛けて、Aに対し、「これまでのことをきちんと謝罪したい。」と言い、同日、計画していたとおり、前記駐車場に自車を駐車し、自車内にX剤、Y剤及びバケツを置いたまま、ワインと睡眠薬を持ってA方に行った。なお、甲が自車内に置いていたX剤及びY剤は、それらを混ぜ合わせれば致死量の有毒ガスが発生する程度の量であった。甲は、A方において、Aがトイレに行った隙に、睡眠薬をAのグラス内のワインに混入した。Aは、そのワインを飲み干し、間もなく、睡眠薬の影響で眠り込んだ。甲は、計画どおりX剤等を取りに行くために同駐車場に戻ろうとしたが、急にAを殺害することが怖くなり、有毒ガスを発生させることを止めた。
7⃣ 甲は、A方を去ろうとした際、机上にA所有の高級腕時計があることに気付き、遊興費を得るためにそれを換金しようと考え、同腕時計を自らの上着のポケットに入れて、A方から立ち去った。
8⃣ Aは、覚醒することなく、甲がA方から立ち去った数時間後に、急性心不全で死亡した。Aには、A自身も認識していなかった特殊な心臓疾患があり、Aは、睡眠薬の摂取によって同疾患が急激に悪化して、急性心不全に陥ったものであった。Aに同疾患があることについては、一般人は認識できず、甲もこれを知らなかった。
9⃣ 本件で甲がAのワインに混入した睡眠薬は、病院で処方される一般的な医薬品であった。その混入量は、確実に数時間は目を覚まさない程度ではあったが、Aの特殊な心臓疾患がなければ、生命に対する危険性は全くないものであった。また、甲も、本件で混入した量の睡眠薬を摂取しても、Aが死亡することはないと思っていた。
〔設問2〕
仮に【事例1】並びに【事例2】の3、4及び7の事実が認められず、【事例2】の5、6、8及び9の事実のみが認められた場合、Aが睡眠薬を摂取して死亡したことについて、甲に殺人既遂罪が成立しないという結論の根拠となり得る具体的な事実としては、どのようなものがあるか。考えられるものを3つ挙げた上で、上記の結論を導く理由を事実ごとに簡潔に述べなさい。
〔設問3〕
【事例2】における甲の行為について、その罪責を論じなさい(住居等侵入罪(刑法第130条)及び特別法違反の点は除く。)。なお、【事例1】における甲の罪責及び【事例1】で成立する犯罪との罪数については論じる必要はない。
答案
設問1
1 詐欺罪と恐喝罪のどちらが成立するか。
被害者から財物を領得する場合に、人を欺く行為と恐喝の両手段が併用された場合、詐欺罪(刑法246条)が成立するか、恐喝罪(刑法249条)が成立するかが問題となる。
このような場合、犯人の施用した手段の中に虚偽の部分があっても、その部分も被害者に畏怖の念を生ぜしめる一材料となり、その畏怖の結果として被害者が財物を交付するに至った場合は、詐欺罪ではなく恐喝罪となると解する。
甲は、Bに対し、自己が暴力団組員であると欺罔してBを畏怖させ、金員を領得している。
自己が暴力団組員であるという部分が虚偽であるが、この虚偽部分がBに畏怖を生じさせる一材料となり、その畏怖の結果として金員を甲に交付しているから、詐欺罪ではなく、恐喝罪が成立する。
よって、本件では恐喝罪が成立するとして検討を行う。
2 ①の立場
甲が暴力団組員であるかのように装い、600万円の支払を求めた行為に600万円の恐喝罪(刑法249条1項)が成立する。
⑴「恐喝」とは、財物・財産上の利益を供与させる手段として行われる脅迫又は暴行で、被害者の反抗を抑圧しない程度のものをいう。
恐喝罪における「脅迫」とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいう。
甲は、暴力団組員であることを装い、Bに対し「金を返さないのであれば、うちの若い者をあんたの家に行かせることになる。」などと言って600万円を支払うよう言っている。
これは、Bに財産上の利益を甲に供与させる手段としての人を畏怖させるに足りる害悪の告知であり、甲の犯行を抑圧しない程度のものであると認められることから恐喝に当たる。
そして、Bは、畏怖して600万円を甲名義の口座に振り込んでいることから、「交付させた」といえる。
⑵ もっとも、請求額のうち500万円については、Aから債権取立ての委託を受けていることから甲の財産上の損害が認められず、恐喝の被害額に含まれないのではないか。
恐喝罪における財産上の損害は、被害者が畏怖に陥らなければその財物又は財産上の利益を交付することはなかったのであるから、個々の財物又は財産上の利益の喪失自体を財産上の損害とみるべきである。
よって、恐喝罪の被害額は交付した財物又は財産上の利益全部に相当する価額であると解する。
したがって、恐喝犯人が、被害者から財物又は財産上の利益の交付を受けた場合、恐喝犯人が現に交付を受けた価額が被害額になると解する。
Bは債権が500万円だと認識していたが、甲の恐喝により畏怖したため600万円を甲名義の口座に振り込んだものであり、甲は畏怖に陥らなければ600万円を振り込まなかったといえる。
恐喝によりAの被った財産的損害は600万円である認められることから、600万円全額が被害額となる。
⑶ もっとも、500万円については、甲がAから取り立ての委託を受けた範囲内であることから違法性が阻却されないか。
恐喝罪において、被害者に対して権利を有する恐喝犯人が、恐喝手段を用いて権利の実現を図った場合、恐喝罪の成立を認めることができるかが問題となる。
この点につき、権利行使のため執った手段が、権利行使の方法として、社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱した恐喝手段である場合には、違法性は阻却されず、恐喝罪が成立すると解する。
甲の請求は、Aの債権額を100万円も超えるものである。
また、水増しした100万円を含む600万円全額を甲自身の債務の弁済に充てるという不正は目的に基づくものである。
Bから600万円を喝取しなければならない、緊急性、必要性、相当性は一切認めれらない。
その上で、暴力団組員を装うといった権利行使の方法として、社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱した恐喝手段を用いていることから、被害額500万円について違法性は阻却されない。
⑷ 以上より、恐喝罪が成立し、被害額は600万円全額となる。
3 ②の立場
上記恐喝行為に100万円の恐喝罪(刑法249条1項)が成立する。
500万円については、甲がAから取り立ての委託を受けた範囲内であり、Bは甲に500万円を交付することでAに対する500万円の債権が消滅する。
よって、Bに喝取された600万円のうち、500万円については財産上の損害は認められず、それを超える100万円の限度で財産上の損害が生じている。
したがって、恐喝の被害額は100万円にとどまる。
4 私見
⑴ Bの喝取行為は、喝取金を自身の債務の弁済に充てるという正当な権利行使ではなく、暴力団組員を装いBを畏怖させて金員を交付させていることから、恐喝である。
⑵ 恐喝罪は個別財産に対する罪であり、恐喝罪の被害額は交付した財物全部に相当する価額となるので、Bが甲に交付した600万円全額が財産上の損害に当たる。
500万円については、社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱した恐喝手段で喝取していることから、違法性は阻却されない。
⑶ 客体について、1項の恐喝罪は「財物」という物理的な物であるのに対し、2項の恐喝罪は「財産上の不法の利益」という有体物ではない無形の価値であることに違いがある。
口座を介した金銭の送金は、恐喝犯人が金銭を自由に処分できる状態に置くものなので、犯人に物理的に金銭を交付したことと同等に評価できる。
よって、財物を交付したといえ、1項の恐喝罪となる。
⑷ 以上より、甲に被害額600万円の恐喝罪(刑法249条1項)が成立する。
設問2
1 甲に殺人既遂罪が成立しないという根拠となり得る事実として、以下①~③の事実が考えられる。
2 ①Aのワインに混入した睡眠薬は一般的な医薬品であり、混入量はAの特殊な心臓疾患がなければ生命に対する危険性は全くないものであった事実
⑴ 「実行行為」とは、構成要件的結果が発生する現実的危険性を有する行為をいう。
現実的危険性を有し、実行行為性が認められるか否かの判断は、犯行の時点に立って、「一般人が認識し、予見できた事情」と「犯人が特に認識し、予見できた特別の事情」を基に判断すべきである。
⑵ 本件において、犯行の時点において、Aに特殊な心臓疾患があることは一般人は認識できず、甲も認識していなかったのであるから、実行行為性を認める基礎事情から除外される。
すると、上記睡眠薬を混入する行為に死亡結果発生の現実的危険性はないから、殺人罪(刑法199条)の実行行為性は認められない。
⑶ よって、殺人既遂罪が成立しないとの論拠になり得る。
3 ②Aは睡眠薬の摂取によって特殊な心臓疾患が急激に悪化して、急性心不全に陥り死亡した事実
⑴ 「因果関係」とは、犯罪行為と犯罪結果との間にある原因と結果の関係をいう。
因果関係は、偶発的な結果を排除して適正な帰責範囲を確定するものである。
よって、条件関係の存在を前提に、犯行の時点に立って、「一般人が認識し、予見できた事情」と「犯人が特に認識し、予見できた特別の事情」を基に、行為の危険性が結果へと現実化したといえるにより判断すべきである。
⑵ 本件において、「その行為がなかったならば、その結果は発生しなかったであろう」という条件関係は認められるものの、Aの特殊な心臓疾患は一般人には認識できず、甲も認識していなかったのであるから、睡眠薬の摂取と死亡結果発生の因果関係を認める基礎事情から除外される。
すると、睡眠薬の摂取の危険性が急性心不全という死亡結果へと現実化したとは評価できないから、因果関係が否定される。
よって、殺人既遂罪が成立しないという論拠となり得る。
4 ③甲は本件で混入した量の睡眠薬を摂取しても、Aは死亡することはないと思っていた事実
⑴ 「故意」とは、犯罪事実の認識・容認をいう。
因果関係が行為者の認識したとおりのものであれば、故意を認めることに問題はない。
しかし、因果関係が行為者の認識したとおりのものではなく、行為者の予期しない因果関係が生じ、その予期しない因果関係の基本部分が行為者が全く認識していないものであった場合は、故意が否定されると解する。
⑵ 本件について、甲はAをワインで眠らせた上で有毒ガスを吸引させて殺害しようと考えていたのであるから、Aの心臓疾患と相俟って急性心不全で死亡するという因果関係の基本部分につき認識がない。
よって、故意が否定される。
したがって、殺人既遂罪が成立しないという論拠となり得る。
設問3
1 甲名義の口座に入金された500万円を自己の債務の弁済に充てるため、引き出す行為につき、Aに対する横領罪(刑法252条)が成立しないか。
⑴ 横領罪は、委託信任関係に基づき他人の物を占有する者が、委託信任関係に背く権限逸脱行為を行い、不法領得の意思をもって、その物を横領した場合に成立する。
横領罪の成立を認めるには、横領の対象物が委託信任関係に基づき、犯人自身が占有している必要がある。
そして、金銭を預金口座から引き出して領得する行為について、横領罪を認めるには、預金口座に預け入れた金銭について、法的理解として、横領犯人の占有が認められる必要がある。
この点、預金口座の金銭に対する事実上の支配を有しているのは銀行なので、犯人に預金口座の金銭に対する占有が認めないのではないかとも思える。
しかし、預金契約に基づき、預金口座に預け入れた金銭は、口座の名義人が常時これを処分する権限を有するから、口座名義人は預金口座に預け入れた金銭に対する占有を有するものと解する。
したがって、横領犯人が自己の預金口座に預け入れた金銭が、委託信任関係に基づき預かっている金銭である場合において、その委託の任務に背いた権限逸脱行為を行う目的でその金銭を引き出せば、その時点で任務の委託者に対する横領罪が成立する。
本件につき、甲は、甲名義の口座に、Aから債権回収を依頼されて回収した500万円をAのために預かっていた。
甲名義の口座の金銭は甲の占有が認められる。
よって、甲は、委託信任関係に基づき他人の財物を占有する者に当たる。
そして、甲は、Aから委託された債権回収の任務に背き、甲名義の口座から500万円を自己の債務の弁済に充てる目的で引き出していることから、この時点で横領罪の実行行為があったといえ、横領罪の既遂が認められる。
⑶ 横領罪における不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思をいう。
甲には回収金500万円の処分権限がなく、500万円を自己の債務の弁済に充てるのはAからの委託の任務に背く行為であり、500万円の所有者でなければできない処分である。
よって、500万円を自己の債務の弁済のために領得した甲に不法領得の意思が認められる。
⑷ 以上より、500万円につき、Aに対する横領罪が成立する。
2 犯罪で得た金銭であることを秘して、Fに甲名義の口座から600万円の払戻しを請求し、払い戻した受けた行為につき、Fに対する詐欺罪(刑法246条1項)が成立しないか。
⑴ 詐欺罪が成立するには、①欺罔行為、②被害者の錯誤、③被害者の錯誤に基づく財産的処分行為、 ④財物又は財産上の不法の利益の取得、⑤財産上の損害の発生という因果的連鎖が必要となる。
「欺罔行為」とは、詐欺犯人の希望する財産的処分行為に向けて被害者を錯誤に陥らせる行為をいう。
欺罔行為は、交付の判断の基礎となる重要な事項について欺かなければならない。
口座の預金債権が犯罪行為により得た金銭であることは、交付の判断の基礎となる重要な事項である。
また、恐喝罪等の犯罪行為に利用した口座の預金債権は、銀行がその事実を知れば、口座凍結措置により払戻しを受けることができなくなる性質のものであり、口座の名義人は、その範囲で権利の行使に制約を受ける。
よって、口座の名義人は、犯罪行為に利用した口座の預金債権の払戻しを受ける正当な権限はないこととなり、これがあるように装って預金の払戻しを請求することは、欺罔行為に当たる。
甲は、600万円が恐喝で得た預金債権であること秘し、窓口係員Fに預金の払戻しを請求し(①充足)、Fにその払戻しが正当な払戻しであると錯誤に陥らせ(②充足)、Fに600万円を自己に交付させ(③充足)、600万円を取得している(④充足)。
銀行は、本来払い戻してはいけない預金を払い戻したことで、恐喝被害者のBから責任を問われるおそれがあり、財産上の損害が発生している(⑤充足)。
⑵ よって、上記①~⑤の因果的連鎖が認められ、甲にFに対する詐欺罪が成立する。
3 500万円の債務の弁済を免れるためにAを殺害した行為につき、強盗殺人罪(刑法240条後段、刑法236条2項)が成立しないか。
⑴ 甲の行為は強盗罪おける「暴行」といえるか。
強盜罪における「暴行」とは、財物を奪取する手段としての暴行であり、不法な有形力の行使のうち、被害者の犯行を抑圧するに足りる程度の行為であることを要する。
その判断は、社会通念に基づき客観的になされる。
確実に目を覚まさない程度の睡眠薬を入れたワインをAに飲ませ、睡眠させる行為は、被害者の犯行を抑圧するに足りる程度の行為であるとえるので、強盗罪における「暴行」に当たる。
⑵ 甲は、Aに睡眠薬入りのワインを飲ませてAを眠らせた上(以下、「第1行為」という。)、A方において有毒ガスを発生させて殺害する(以下、「第2行為」という。)計画であったことから、第1行為の時点で強盗殺人罪の実行の着手が認められるか。
「実行行為」とは、構成要件的結果が発生する現実的危険性を有する行為をいう。
よって、犯罪の結果発生の現実的危険性を発生させる行為の開始時点で実行の着手が認められる。
本件につき、①第1行為が第2行為を行うために必要不可欠な行為であること、②第1行為成功後に第2行為の遂行が容易になること、③第1行為と第2行為に時間的場所的接着性があり密接不可分であることがいえる場合には、第1行為の開始時点で犯罪の結果発生の現実的危険が認められるとして強盗殺人罪における「暴行」の実行の着手が認められると解する。
甲はAを自殺に見せかけて殺害しようとしていたのであるから、Aの抵抗を排除するために第1行為は第2行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠であった。
第1行為に成功した場合、Aは眠って抵抗できなくなるのだから、殺害計画を遂行する上で障害となる事情はなくなり、第2行為の遂行が容易になるものと認められる。
甲はAを眠らせた後、直ちに有毒ガスでAを殺害する計画なので、第1行為と第2行為との間の時間的場所的接着性が認められ、第1行為と第2行為は殺害計画を遂行する上で密接不可分といえる。
よって、第1行為の時点で、強盗殺人罪の実行着手があったと認められる。
⑶ 甲はAを毒ガスで殺害するつもりであったが、睡眠薬を飲ませることで殺害しているが、甲に強盗殺人罪の故意が認められるか。
これは事実の錯誤における因果関係の錯誤が問題となる。
「事実の錯誤」とは、犯罪の行為者が認識・容認していた犯罪事実と、実際に発生した犯罪事実とが食い違うことをいう。
「因果関係の錯誤」とは、犯罪行為者が認識していた「因果関係の経路」と、実際に発生した「因果関係の経路」との間に食い違いがあった場合の錯誤をいう。
事実の錯誤が起こった場合、犯罪の故意の存在を認め、犯罪の成立が認められるかどうかが問題となる。
故意責任の本質は、規範に直面し、犯行を思いとどまるという反対動機を形成できる状況にありながら、あえて犯罪行為に及んだことに対する道義的非難にあるから、因果関係の経路に錯誤があるなどの事実の錯誤を起こし、構成要件の範囲内で認識にずれがあっても、そのずれが構成要件の範囲内であれば故意を阻却しない。
Aを殺害したという点においては、甲の認識と現実に発生した事実は一致している。
Aが死亡するに至った因果関係が重要なのではなく、人を殺害したこと自体が強盗殺人罪の構成要件の重要部分である。
よって、甲の強盗殺人罪の故意は否定されない。
⑷ Aは睡眠薬の摂取によって特殊な心臓疾患が急激に悪化して、急性心不全に陥り死亡しているが、甲がAに睡眠薬を飲ませた行為とAが死亡した結果との間に因果関係が認められるか。
「因果関係」とは、犯罪行為と犯罪結果との間にある原因と結果の関係をいう。
因果関係は、偶発的な結果を排除して適正な帰責範囲を確定するものである。
よって、条件関係の存在を前提に、犯行の時点に立って、「一般人が認識し、予見できた事情」と「犯人が特に認識し、予見できた特別の事情」を基に、行為の危険性が結果へと現実化したといえるかにより判断すべきである。
Aが特殊な心臓疾患を有していたことは、犯行の時点に立って、一般人及び犯人が認識・予見できた事情とは言い難い。
しかし、睡眠薬を他人からひそかに摂取させられるという危険な行為をされれば、Aの体調に予期しない異常が発生する可能性があることは、一般人及び犯人が認識・予見できた事情といえる。
そのような事情を前提に、Aは体調に予期しない異常を来し、急性心不全に陥り死亡していることから、これは睡眠薬をひそかにAに摂取させる行為の危険性がA死亡の結果へと現実化したものといえる。
よって、甲がAに睡眠薬を飲ませた行為とAが死亡する結果との間に因果関係が認められる。
⑸ 財産上の不法の利益を得たといえるか。
2項強盗における「強取」とは、被害者の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を加えて、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させることをいう。
甲はAを殺害し、Aに対する500万円の返還を免れており、財産上の不法の利益を得ているので「強取」といえる。
Aには相続人がいない上、AがBに対して有する500万円の債権の存在を証明する資料はなかったことから、Aを殺害したことにより、事実上、甲はAへの500万円の返還を免れたといえることから、財産上の不法の利益を得たといえる。
⑹ 以上より、甲にAに対する強盗殺人罪が成立する。
4 甲がA所有の高級腕時計をポケットに入れた行為について窃盗罪(刑法235条)が成立しないか。
⑴ 強取ではなく、窃取といえるか。
暴行・脅迫が財物奪取の意図と無関係に行われた後で、財物領得の意思を生じて、相手の畏怖や昏酔の状態を利用して財物を領得した場合、これを強盗罪又は昏酔強盗罪(刑法239条)と認定するためには、財物領得の意思が生じた後に、新たな暴行・脅迫を行うことを必要とすると解する。
甲は、Aに睡眠薬を摂取させて眠らせるという暴行を加えてAが眠り込んだ後、Aを殺害することが怖くなり、Aを殺害せずにA方から立ち去る際に、高級腕時計を発見して領得している。
Aの上記暴行を行った意図は、Aに対する500万円の返還を免れるためであることから、高級腕時計を領得することとは無関係である。
高級腕時計を領得するにあたり、甲にAが眠り込んだ状態を利用する意図があったとも思えるが、甲はAを殺害することが怖くなってA方から立ち去ろうとしている状態であることから、強盗と評価できるほどのAが眠り込んだ状態を積極的に利用する意思があったとは認められない。
よって、Aの腕時計の領得は強取とはいえない。
⑵ では窃取といえるか。
「窃取」とは、目的物の占有者の意思に反して、その占有を侵害し、その物を自己または第三者の占有に移すことをいう。
「占有」とは、人が財物を事実上支配し、管理する状態をいう。
占有が認められるためには、①占有の意思を有すること、②物が占有者の実力的な支配下にあることを要する。
占有の意思は、必ずしも個々の財物に対する特定的・具体的意思であることを要せず、時間的・包括的なもので足りる。
これは、占有の意思の下に占有者の実力的支配にある物とそうでない物とでは、その物を領得する難易度、反対動機形成の心理的ハードルに差があり、その差が違法性の差に結び付くためである。
すなわち、占有者の実力的支配にある物の領得は、その難易度が高いため、犯行を思いとどまる反対動機も形成しやすいのだから、それでも犯行に及んだ場合は高い違法性が認められ、窃取として法定刑の重い窃盗罪で処罰される。
反対に、占有者の実力的支配にない物、つまり、占有離脱物・遺失物の領得は、その難易度は低いため、犯行を思いとどまる反対動機は形成しにくいことから、犯行に及んだ場合の違法性は低く、横領として法定刑の軽い占有離脱物横領罪・遺失物横領罪(刑法254条)で処罰される。
Aは睡眠薬の作用で眠らされていたため、高級腕時計の占有を失っていたのではいかとも思える。
しかし、占有の意思は、個々の財物に対する特定的・具体的意思であることを要せず、包括的に認められるので、Aが眠らされていたとしても、高級腕時計がAが支配する居宅内にあることをもって、Aの占有の意思が認められる。
さらに、腕時計が高価なものであることを考えれば、Aの占有の意思は強いものといえる。
また、高級腕時計は、Aが支配する居宅のAの机の上にあったのだから、Aの実力的な支配下にあったといえる。
よって、Aは高級腕時計の占有を失っておらず、高級腕時計にAの占有が認められる。
そして、それを領得した甲の行為は「窃取」といえる。
⑶ 甲は窃取した高級腕時計を換金して遊興費を得る目的で領得しているので、不法領得の意思も認められる。
⑷ よって、甲にAに対する窃盗罪が成立する。
5 以上より、甲には、①Aに対する横領罪、②Aに対する詐欺罪、③Aに対する刑法236条2項の強盗殺人罪、④Aに対する窃盗罪が成立する。
①②は、社会通念上1個の行為から生じているから観念的競合(刑法54条1項前段)となる。